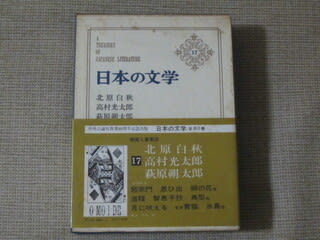唐澤平吉 一九九七年 晶文社
こないだ『明治タレント教授』を読んだときに、そのなかで「なかなかおもしろい本であった」って触れられていて、機会あったら読もうかと思っていたら、先月だったか地元の古本屋であっさり見つけられたので、さくっと買ってみた。
>花森安治は、昭和二十三年に雑誌『暮しの手帖』をおこし、同五十三年に死ぬまでその編集長だった人である。著者はその花森の晩年に、『暮しの手帖』編集部でしごかれた若い編集者。(『明治タレント教授』p.109)
ということであるが、ちなみに『明治タレント教授』のなかで紹介されてるエピソードのひとつは、花森編集長は「藏」って字にこだわるとこあって、「藏」は鍵かかってるものであり、「蔵」の字には鍵がない、って見解をもってたって話で、藏の字の左側のとこはべつにカギを意味してるわけぢゃないんだけど、「文字をデザインとして見る人らしくておもしろい」ってもの。
文字をデザインとして、ってのは、どういうことかというと、
>また、原稿を書くのに、なにより大事だったことは、字の書体でした。花森さん好みの書体がありました。花森安治はこう書いています。(略)
>いちばん読みやすいのは、原稿用紙なら、マス目に一字ずつきちっと入っていて、大きからず小さからず、あまりくずしてなくて、どちらかというと、活字にちかいような書体、ぼくの言葉でいうと「原稿体」といった感じの字が、いちばん読みやすいし、疲れも少ない。(p.238-239)
みたいな書体のこともあるようなんだけど、どうもそれだけではない。
>しかし、字はマネられても、どうしてもマネできないことがありました。それは、花森安治の文章の読みやすさを解くカギになるとおもいます。句読点の打ち方もさることながら、なんといっても特徴的なことは、漢字とひらかなの精妙な使いわけです。
>(略)おなじ文章のなかで、漢字にしていたり、ひらかなにしていたり、用字の統一がとれていません。気まぐれでしているのでは、ありません。花森さんは意識して使いわけています。まず漢字を使うのを、最小限度にとどめています。
>(略)ひらかなの文章の中に、漢字が群がらないようにポツリポツリとちりばめてあり、その漢字もなるべく画数の少ない字を選んでいます。(略)
>これは文章力だけでなく、文字の配列の美的センスによってささえられています。(p.240)
というように一文字ずつの形だけぢゃなくて、文章全体の見た目をデザインしようという意思がはたらいていたと。
しかも出版物になったときには隣あわせの行で漢字が並ばないようにとか句読点が並ばないようにとかって、行数や文字間のレイアウトまで見通して文章が書けたらしい。
もともと文章がどうこういうよりも美術の才能があったひとで、表紙の絵を描いたり、見出しとかの書き文字をデザインするのがうまく、だからたとえ原稿用紙に文章書いても出来上がりの作品としての掲載時の誌面での見映えが見通せてたんだろうが。
「暮しの手帖」って私は読んだことないと思うんだが、驚いたことに、なんでも隔月刊の表紙の誌名ロゴが毎号ちがってたんだという、ふつう出版物の顔なんだから一度決めたら動かさないと思うんだがロゴ、毎回花森編集長がそのたびにデザインしてたらしい、好きなんだろうね、そういうつくることが。
それと、私が本書を読もうと思ったのは、まえに丸谷才一さんの『ウナギと山芋』を読んだなかに、「暮しの手帖」のエピソードがあったのが、ずっと引っ掛かっておぼえてたからで。
>いつだつたか、大江健三郎さんと料理の本の話をしてゐましたら「暮しの手帖」の料理の本はいいですよ、と大江さんは言ふんですね。
>以前「週刊朝日」の書評欄を担当してゐたとき、大江さんに料理の本の書評が割当てられたことがあるんださうです。(略)さうして実地にやつてみると「暮しの手帖」の記事は、大江さんでも(略)きちんとやれるやうに書いてあるのださうです。(略)
>聞くところによると、暮しの手帖社は男であらうと女であらうと、新入社員にはまづ料理記事を担当させるんださうですね。これは先代の編集長である花森安治さんの方針だつたんですが、新入社員をしかるべき板前ないしコックのところに行かせる。目の前で作つてもらひながら教はる。帰つて来て作り方を文章にする。(略)わからないところは(略)新入社員につきつける。そこの文章を新入社員は直す。さういふことを何度かくりかえすうちに、完全な料理記事が書けるやうになる。それが新入社員の訓練法だといふのです。この花森さんの考へ方の基本には、散文といふもののいちばん大事な機能は伝達性だ、といふ認識がある。(『ウナギと山芋』p.284-285
ってとこですね、それで「暮しの手帖」ってのはどんなこと書いてあるんだろうかってのが気になってた。
その件についても、もちろん本書でも一章がさかれてる。
>丸谷さんが指摘しているように、『暮しの手帖』の料理記事は、作り方の説明がわかりやすく、また正確なことで定評があります。(略)
>料理というのは、作っただけでは料理ではありません。かんじんなことは食べてみてうまいかどうか。(略)まず、その見きわめから料理記事ははじまります。(略)
>(略)作った料理を、うまいかどうか判定するのが〈試食〉です。これは料理担当者がしますが、近くにいればだれでも食べてよろしい。(略)その結果、うまいと評価された料理がのこり、(略)記事に採用する料理としていました。これが第一の関門です。
>第二の関門は、丸谷さんの発言のとおり、料理担当者の書いた原稿を読んで、べつの編集者が作ります。これが〈試作〉です。(略)この試作を試食することによって、料理のでき具合、見ためや味が料理人の作ったとおりか、わかります。おかしければ、担当者の原稿が不明確だということになります。(略)
>このように、『暮しの手帖』の料理記事には二重のシカケがあり、原稿が何人もの編集者のからだを通って書かれています。作り方の説明をすなおに読めば、だれでも作れるのです。(p.135-136)
ってとこですね、プロの料理人が読んでも、内容が正確で勉強になるんだそうです。
でも、料理のできよりも、やっぱ文章いかに書くべきかってとこに戻って、私は興味をもつな。
>花森安治の『暮しの手帖』の文章の基調にあったのは、読者への気くばりです。文章やことばについての花森語録を、ここにあげてみます。
>「教えてやろう、というようなニオイのする文章がいちばんイヤラシイ。読者とおなじ眼線に立って、文章を書け」
>「やさしく書いたからといって、わかりやすいとはかぎらん。書いている本人がその意味を正しく理解していないと、わかりやすい文章にはならんのだ。一知半解の人間に、わかりやすい文章は書けん。一知半解、二歩後退というんだ」
>「ひらかなにすれば、やさしくなるわけじゃない。ひらかなで〈ひじょう〉と書かれたら、非常の意味か、非情の意味か、わからなくなる。それこそヒジョウシキだ」
>「改行が少ない文章はよみにくい。多くても十行が限度だ。だらだらと長くなるのは、なにを書くのか、頭の中できちんと整理されていないからだ」
>「いい文章にはムダがない。木で鼻をくくったような文章には情がない」
>「文章をやさしく、わかりやすく書くコツは、ひとに話すように書くことだ。眼で見なくてはわからないようなことばは、できるだけ使うな」(p.105-106)
といった薫陶があったそうです。
こうやって文字にされてみると、いいこと言ってるなという感じがするけど、実際には編集者たちは書いた原稿をチェックされるときに、なんだこれはバカヤロウってくらいの勢いで怒鳴られ叱られてたらしい、なんとかハラスメントみたいな言葉はない、古き良き時代だ。
本書の章立ては以下のとおり。
職人とよばれた天才ジャーナリスト
花森さんとの出会い
どぶねずみ色だっていい
弟子になるのもラクじゃない
暮しの手帖社の常識
わたしの商品テスト入門
負け犬になるな
お当番さんにあけくれる一日
研究室のみそ汁
三つのしごと
編集会議は会シテ議サズ
文章は話すように書け
カメラと標準レンズ
〈ある日本人の暮し〉余話
おいしい料理には詩がある
すばらしき日曜日
ドイツの緑、イギリスの茶色、日本の青
装釘にも一流のこだわり
オニ編集長も昔はホトケだった
ミステリーと春団治
チョンマゲ野郎への挑戦
眼は高く手は低く
紺のベレーと白いジャンパー
兵隊やくざと戦争を知らない子供たち
ナベさんの涙
字は編集者のいのち
波うちぎわに立つ一本の杭
みなさん、どうもありがとう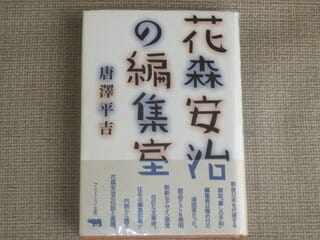
丸谷才一 2006年 講談社文庫版
これは去年のいまごろ古本まつりで買ったとおもう、一年ちかく放っておいて最近読んだ。
単行本は2000年の刊行らしいが、タイトルのとおり、夏目漱石論である、三章から成っていて、
「忘れられない小説のために」 は、『坊つちやん』
「三四郎と東京と富士山」 は、『三四郎』
「あの有名な名前のない猫」 は、『吾輩は猫である』
をそれぞれとりあげている、どれも読んだことあるので知らない話ぢゃなくてよかった。
でも、『坊つちやん』は、フィールディングの『トム・ジョーンズ』の影響下に書かれたのではないか、とか言われると、そっちは読んでないので、はあ、そーゆーものか、と説を承るだけなんだけど。
>つまり『坊つちやん』はイギリス十八世紀文学のことを考へつづけるかたはらに想を構へ、筆を執つた小説であつた。(略)念のために言ひ添へて置くならば、一般に文学作品は単なる個人の才能によつて出来あがるものではなく、まして個人の体験のみによつて成るものでなく、伝統の力による所が大きい。しかもそれが自国の文学の伝統と限らないことは言ふまでもないでせう。(p.23)
というのを読んだりすると、文学における伝統の力って、これまでも何度か丸谷さんの持論として出てきたことあったなあって気がする。
坊つちやんが、「ハイカラ野郎の、ペテン師の、イカサマ師の、猫被りの……」って罵り言葉を並べ立てるところは、日本文学の古来からの伝統で、枕草子をはじめとする「物尽くし」の技法だっていうんだけど。
海外文学にも列記とか列挙って呼んで、ちゃんとそういうレトリックはあったんだけど、十九世紀ころにはすっかり衰えてしまって、
>この原因もおそらく複合的なもので、(略)散文の発達と写実性の重視にともなつて位置を失つたせいもあるでせう。科学の影響を受けて、文学が真実の追求を主眼とするものとなり、祝祭的な性格が薄れたことも大きい。とにかく文学的趣味が大きく移り変つたせいで、エヌメラチオは往時のやうにかなり高い位置を占めるレトリック技法ではなくなつたのでした。(p.76)
ということらしいんだけど、二十世紀文学は十九世紀文学への反抗として、こういう伝統的なものを新しい色調でよみがえらせた、漱石もそういうモダニズム文学を書いたひとなんだって論を張ります。
>(略)こんなことを言ふと眉をひそめられるかもしれないが、漱石、特に初期の彼はモダニズムの小説家だつたし、とりわけその色調の強いのがあの都市小説『三四郎』であつた。一九二〇年代の末、横光利一や川端康成や伊藤整によつて日本のモダニズム小説がはじまつたと見るのは誤りなので、わが文学最初のモダニストは世紀初頭の漱石であつた。そして彼の栄光と悲劇のかなりの部分は、こんなふうに二十年も世にさきがけてゐたことにあると、わたしはかねがね思つてゐた。(p.119)
というように『三四郎』論のとこでも述べています、文学史とかそこでの位置づけとか、よう知らんからわからんけど、ふつうとは違った意見なんだそうで。
『三四郎』については、十九世紀なかばに「英国の状態小説」っていう文学が始まったそうなんだが、1910年の「英国の状態」小説の代表といえるフォースターの『ハワーズ・エンド』と比較して、
>(略)心のなかでじつと見くらべてゐると、『三四郎』には「日本の状態」小説とも呼ぶべき局面ないし性格があることに気がつくだらう。
>たとへば汽車のなかで、職工の妻の語る話を聞いて爺さんがする戦争批判と信心が大事だといふ説。同じく汽車のなかで髭の男が三四郎にする、西洋人は美しく、そして富士山しか自慢するもののない日本人はかはいさうだといふ説。日本は亡ぶといふ説。それらが彼らの立居振舞の描写をまじへて示されるとき、わたしたちはおのづから日本の全体を思ひ、その運命について考へることへと促される。(略)それをわたしは「日本の状態」小説への志と見るのだが、考へてみれば、彼がこんなふうに社会全体を展望しようといふ気持を見せたことは、これ以前にも以後にもなかつたのだ。その点で『三四郎』は例外的な作品であつた。(p.143-144)
というように論じています、ふーむ。
漱石がイギリス留学したころの、イギリスぢゃあ社会から小説が生まれ育つもんだっつーことについて、
>小説と社会との関係についてに日本人の認識は、今でもかなりその傾向があるが、戦前はもつと貧しいものだつた。一つにはロマンチックで個人主義的な文学観のせいで、小説はもつぱら個人の才能によつて書かれるとか、あるいはもつと極端に魂の叫びだとか、赤裸々な告白だとか思ひ込んでゐたし、それに加ふるに、もともと市民社会といふ概念が薄ぼんやりしてゐるから、市民社会のせいで小説が生れ、成長したといふ意識がなかつた。(略)さう言へばわたしは、これはもちろん戦後のことだが、イギリス小説について勉強をはじめたころ、「社会批評」(social criticism)が小説の大事な機能である、ただしこれはイデオロギー的政治批判のことではなく喜劇小説のことを意味する、とイギリスの批評家が淡々と書いてゐるのを読んで、ここまで言ひ切るのかと軽い衝撃を受けたことがあつた。(p.170)
というように書いてます。
小説ってのは、個人主義的な文学とか作者の自己表現とかってだけぢゃなくて、共同体の表現のようなことをするとか、文学はもっとカーニバル的なものであっていいのだとか、前にもなんかで読んだなと思ったんだけど、たぶん『ゴシップ的日本語論』でした。
高島俊男 2002年 文春文庫版
前に読んだ『お言葉ですが…』のシリーズの三冊目、昨年末ころに古本を買い求めた、読んだの最近。
初出は「週刊文春」の1997年から1998年ころで、単行本は1999年でそのときのタイトルは『せがれの凋落』だそうである。
収録されてるなかの一篇に、「せがれ」という言葉がいまや通じなくなっているって話があるんだけど。
そのなかで「せがれ」は漢字で書くと元来は「悴」であるのに、「伜」の字がよくあてられてる、こんな字は使わんほうがよい、と書いている。
そしたら読者からの反響におどろいて、「悴」という字を使えと言ってるんぢゃない、「せがれ」は純然たる日本語なんだから漢字を書く必要がないってのが言いたかった、って文庫版では追記している。
ということで、言葉の使い方おかしいよっていうのに、間違った漢字を使うなってのがメインぢゃなくて、なるべく漢字を使わないで文章を書きましょう、ってほうが言いたいことらしい。
よく見かける言葉でも、どうもわからない言葉があるって例として、
>小生思うのであるが、えらい学者さんがお使いになる「位相」なんてむずかしげなことば、一見いかにも厳密に、科学的に用いているようであるが、実はかなり情緒的なものなんじゃないかなあ。そう思いません?(略)
>「位相」というのは、学者さんが「おれ学者だもんね」といい気分になりたい時にもちいる、その場その場で「位置」とも「角度」とも「高さ」とも「向き」とも自由自在に変化するすこぶるアイマイなことば、ということでいいんじゃないでしょうか。(p.172-173)
みたいな具合に斬ってるとこなんかも、おんなじように、わかりやすい言葉使えよって主張に沿った一節だと思う。
それでも、やっぱ漢字の使い方のヘンなのには言いたいことあるようで。
たとえば、本来「銓衡会」であるものを「選考会」と書くようになっちゃったことについては、
>「銓衡」は重さをはかること。それが、人物や作品の価値をはかる意にもちいられる。その「銓」の字が戦後当用漢字からはじき出されたために、「選考」に吸収合併させられてしまった。
>本来「銓衡」は、はかりにかけて重さをはかるのであるから、かならずしも多数のなかから「選ぶ」のではない。(略)
>(略)「銓」の字は(略)使わないようにしましょう、というなら、それはそれでけっこう。ならば「銓衡会」のかわりに「審査会」と言ってもいいし、あるいはほかに適当な言いかたがあればそれでもいい。それを、「銓衡」はダメになった、しかしセンコウでないといけない、と視野のせまいところがあさはかなのである。(p.84)
というように戦後の国語改革のもたらしたものについてけちょんけちょんに言う。
同様に、
>「抽籤」ということばがあった。一見むつかしげだが実は何でもない。「抽」は「ひく」、「籤」は「くじ」、つまりくじびきのことである。
>この「籤」が当用漢字からはずれた。(略)ではどうするか。何でもない。「くじびき」と言えばよいのである。チュウセンなんてわかりにくいことばより「くじびき」のほうがよっぽど上等だ。
>ところがあきれたことに、「抽選」という新語をデッチあげた。「くじをひく」だから意味があるので、「選をひく」では意味をなさない。(p.84-85)
みたいな例もあげてるけど、これなんかは、正しい漢字を使えって言ってんぢゃない、純然たる日本語だから漢字あてなくていい、って路線に沿ったものなんぢゃないかと思う。
でも、やっぱ漢字は正字ってやつを使いたいらしく、原稿には必ず「藏」と書くんだけど活字になると「蔵」に変えられてるのはがっかりするそうで、「小生きらいな敗戦略字は「蔵」だけではない。」(p.110)と、戦後国語改革由来のことは敗戦略字って言いかたしてんのは、戦争に敗けておかしくなり自国の文化に誇りもてなくなってんぢゃねーよと言いたいのかも。
ことばとか漢字とかって以外にも、教わることは多い。
なんで国の役所、大蔵省とか文部省とか「省」って呼ぶのかとか。
>大蔵省も文部省もずいぶん古い名前で、奈良平安の昔からすでにある。どちらも、律令官制の「八省」の一つである。(略)
>奈良平安の官制は唐の官制のマネである。(略)
>朝廷の役所のことをなぜ「省」というのか。
>漢代に皇居のことを「禁中」と言った。「無用の者立入り禁止の場所」の意味である。ところが元帝の時に、皇后の父が禁という名だったのでこの字を避け、「省中」と言うようになった。省は、「ここに立入る者は一人一人とっくと調べる」という意味である。そういうことから朝廷の役所を「省」と称するようになったのだ。(p.73-74)
だなんてのは、知らなかった、「禁中」って言葉あるのは知ってたけど、ぢゃあ大昔の皇后の一族に「禁」って名前のひといなかったら、いまの日本で「外務禁」とか役所を呼んでたかもしれないと言われると、わからんもんだなと思わされる。
そうやって文献からの知識なんかを教えてくれることが多いのに、めずらしくというかご自身の心持ちによる意見を述べてるとこがあって気になった一節があった。
北朝鮮からの一時帰国者を空港で出迎えた親族が抱きあってたテレビ報道を見て、
>日本人はいつからああいうことをするようになったのだろう。
>敗戦後、何十万という日本人が戦地や外地から帰国したが、親やきょうだいといきなりガバ、というのは、まずなかっただろうと思う。(p.68)
と疑問を呈して、自身の親きょうだいの例をあげたうえで、
>わたしなどはむしろ、九死に一生を得て帰ってきた夫を空港に迎えた妻が黙って静かにおじぎをする姿や、あるいは、久しぶりに帰ってきた人が子供の頭をちょっとなでるしぐさなどに、深い感情を感じる。
>あのガバと抱きつくというのは、そんな感情が何もなくて、その何もないのがうしろめたく、人に見すかされるのがこわくて、あんなふうな派手な挙動に出るのではないかと思う。(p.72)
と分析するんだけど、うーん、どうなんだろうねえ。
コンテンツは以下のとおり。
青い顔してナンバ粉食うて
読みやすくこそあらまほしけれ
小股の切れあがった女
命短し恋せよ乙女
青い顔してナンバ粉食うて
緑色の天皇
教室と寝室
ジュライ、オーガストの不思議
院殿大居士一千万円
院殿大居士一千万円
墓誌銘と墓碑銘
肉親再会
消えた大蔵省
ワープロがもたらすもの
蟻の一穴「書きかえ語」
人は神代の昔から
カギのない蔵
月光最と澄み渡れり
本に小虫をはわせる
カギのない蔵
グッド・バイ
臥薪嘗胆
しっかりせんかい日本の辞書
文化輸入国の悲哀
赤い腰巻き
エンドレステープを憎む
三都気質論
鶴翼の陣
『アーロン収容所』
赤い腰巻き
「位相」ってなんだろね
五十をすぎたおばあさん
一割現象
せがれの凋落
開きなおって戦います!
「ゲキトバ」新説
千円からおあずかり
何もありませんけど……
せがれの凋落
細くない細君
「食う」の悲運
明治タレント教授
ゴのおはなし
テレビの「用心棒」
ホコトン博士の国会演説
国民学校一年生
明治タレント教授
二つの「イズム」
独狐将軍孤軍奮闘
「美しい国」と「腹のへった国」
なぜヨウダイなの?
独孤将軍孤軍奮闘
みどりみなぎる海原に
KWANSAI健闘
すむと濁るで大ちがい
赤穂にうつりました
ルース・スタイルス・ガネット作/ルース・クリスマン・ガネット画/渡辺茂男訳/子どもの本研究会編集 1963年 福音館書店
こないだじつにひさしぶりに『大どろぼうホッツェンプロッツ』を読んだあとしばらくして、やっぱり子どもんときに読んだもので、もうひとつどーしても読みたくなっちゃったのがあって、そいつがこれ。
先月リサイクルショップに中古を探しにいったさ、あったあった、複数あった、私が買ったやつは2003年で新版第111刷を重ねてる、時代移り変わってもみんな読んでんだねえ、ちょっと安心する。
原題「MY FATHER'S DRAGON」は1948年アメリカの出版だという。
そう、私の父の竜なんだよね、
>ぼくのとうさんのエルマーが小さかったときのこと、あるつめたい雨の日に、うちのきんじょのまちかどで、としとったのらねこにあいました。(p.1)
という始まりのものがたり、お父さんが子どもだったときの冒険談という体裁。
ひろって世話してやった年寄り猫は若いときは各地を旅行したんだけど、「どうぶつ島」ってとこで他の動物たちにつかまっている可哀そうな竜がいた、って話をエルマーにする。
(あー、猫とひとが話ができるのかとか、つまんないことは突っ込まないように、できるに決まってるぢゃないですか。)
それでエルマーがその竜を助けに行くってのが冒険のなかみなんだが、だいたいのところのストーリーはおぼえてたが、細かいことは当然のように忘れてた。
ちなみに、その首を綱でしばられて川を渡す仕事をさせられちゃってる竜は、
>りゅうは、ながいしっぽをしていて、からだにはきいろと、そらいろのしまがありましたよ。つのと、目と、足のうらは、目のさめるような赤でした。それからはねは金いろでした。(p15)
というカラフルな生き物である、むかしの恐竜想像図のような地味なのを想像してはいけない、まだ子どものときに空から落ちてしまったとこをつかまってしまったんだという。
かくして、エルマーは船に忍び込んで密航するんだけど、
>エルマーのもっていったものは、チューインガム、ももいろのぼうつきキャンデー二ダース、わゴム一はこ、くろいゴムながぐつ、じしゃくが一つ、はブラシとチューブいりはみがき、むしめがね六つ、さきのとがったよくきれるジャックナイフ一つ、くしとヘアブラシ、ちがったいろのリボン七本、『クランベリいき』とかいた大きなからのふくろ、きれいなきれをすこし、それから、ふねにのっているあいだのしょくりょうでした。(p.19)
というのがいい、物語のおもしろさは細部にやどるんだな、男の子の冒険の持ち物はこうでなくちゃいけない、まさに完全装備だ。
どうぶつ島のとなりの「みかん島」で船をおりたエルマーは、島と島とを結ぶ「ぴょんぴょこ岩」をつたっていくんだけど、いま読んだら、夜の海のうえで岩から岩へ跳んだりすべったりしたのが「七じかん」ってなってて驚いた、そんな長時間をタフだねえ。
どうぶつ島へ侵入したものは猛獣に食われてしまうと言われてんだけど、こっからエルマーは出会う動物たちを勇気と智略でかわしていく。
七匹のトラには、チューインガムを与えて、噛み続けてると色が変わるよとか言って、それに夢中にさせる。
年取ったらツノが黄色く汚れてしまったと嘆くサイには、歯ブラシとはみがきを与えて、磨けば白く戻るよとか言って、それに忙しくさせる。
黒イチゴの小枝がたてがみにからまってかんしゃくを起こしてるライオンには、ブラシとくしと七色のリボンを与えて、身だしなみに専念させる。
のみに悩まされてるゴリラには、子分の6匹の小猿たちに虫眼鏡を与えて、ゴリラを猿に取り囲ませてエルマーのことを忘れされてしまう。
そして川にいる十七匹のワニたちには、しっぽの先にキャンデーを輪ゴムでくくりつけて、前のワニのしっぽのキャンデーをしゃぶらせることで、ずらりと一列縦に並ばせて、川を渡るためのワニの橋をつくることに成功。
そして、川の向こう岸に渡ると、つかまってた竜のクビの綱をナイフで切って救出に成功、空を飛んで脱出する。
いいなあ、空を飛ぶってのは、夢がある。
魔法使いはホウキに乗って飛ぶのかなあ、絨毯に乗って飛ぶやつもいたよね。映画「アバター」ではなんか鳥みたいのに乗ってとんでたっけか。
でも空を飛ぶんなら、やっぱ、りゅうのせなかに乗りたいよね、できたら黄色と空色の縞のボディーだったら、最高。
日本の文学17 北原白秋・高村光太郎・萩原朔太郎 昭和40年 中央公論社
きっかけは『文学全集を立ちあげる』を読んだときに、この架空の日本文学全集に萩原朔太郎を一巻入れるとしたら、詩集はほどんど全部入るとしたあとで、
>鹿島 あと、アフォリズム集。あれは僕は大好きなんだなあ。芥川なんかと格が違いますよ。
>丸谷 そう、あれは大変いいもんだね。これぞ文学、という感じがするのね。
>三浦 芥川のほうが頭がよくて、理論的で、朔太郎のほうが感覚的で、頭が悪いと思われているけど、ぜんぜん違う。(略)書いているものを読むと、理が通っているのは朔太郎のほうでしょう。
>鹿島 少なくともアフォリズムに関する限り、朔太郎はボードレールを超えているんじゃないか、と思うぐらいすごい。
>丸谷 僕も朔太郎はすごいと思うよ。(『文学全集を立ちあげる』p.216)
って議論がなされてるのをみて、そんなすごいの、読んだことないよ、って思ったからで。
どこでどう探せばいいのかわかんないでいたら、この全集をみてみたらアフォリズムが入ってた。
私の生まれ育った家には、この「日本の文学」って全集がほぼ80巻(一つか二つ欠けてる)そろってあるんだが、夏目漱石も芥川龍之介もこのシリーズで読んだものさ。
でも興味ないものは、っていうかほとんど多くの日本文学は、読まないでいたんで、この巻も開いてみた記憶なんかない。
さてさて、問題のアフォリズムなんだけど、巻末解説によると、大正十一年に「新しき欲情」って人生哲学の書を出版して、それって「日本で珍しい芸術的思想の書」なんだそうである。
本書では、その「新しき欲情」と「虚妄の正義」(昭和四年)と「絶望の逃走」(昭和十年)というアフォリズム集または評論集ってものから、いくつか集めてあるようである。
で、読んでみたんだけど、なんか私にはあまりピンとこないんで、困ってしまう。
それでも、わかりやすそうなのをいくつか、抜いてみますか。
「帽子と求婚」
>帽子を買ふためにすら、人は遠方まで出かけて行き、数軒の店をひやかし、幾百の中からただ一箇を選ぶのである。それでも尚、じつに満足する品を得ることはむづかしい。(略)
>(略)いかにして諸君は結婚したか? いかに諸君の唯一の妻を(もしくは良人を)幾千人の異性の中から選定したか?(略)おそらくは無造作に、つい手近の所で、僅かに数人の中の一人を(略)見込んだにすぎないのだ。(略)
「芸術には上達がない」
>すべての技術は、練習によって上達する。ところで練習とは、筋肉または思惟の法則が、脳髄の中に溝をつくることである。(略)
>(略)然るに芸術が意義するところの、創作の本意は何だらうか? 創作の真の本意は、すべての習慣上の型を破って、不断に新しき世界を創るにある。(略)
>されば芸術家の修養は、技術家の勉強と反対である。後者にあっては、練習が上達の秘訣であるのに、前者にあっては、むしろ練習しないことが、平常の善き心掛けに属してゐる。(略)
>それ故に芸術は、それが単なる技芸――ヴァイオリンを巧みに弾くことなど――でなく、本当の意味の芸術ならば、芸術は練習すべきものでない。(略)
「日本の文学」
>日本の文学には、いつも二つの範疇しかない。「老人の文学」と、そして「少年の文学」である。(略)
>「日本人の特殊なことは」と、或る外国人が評して言った。「一般に早老であり、少年期から老年期へと、一足跳びに移って行き、早く年齢を取ってしまふ。」と。同様に我々の文学が、また少年期から老年期へと、一足跳びに変移していく。(略)
>日本の文壇と文学とは、人生の収穫すべき、最も重要な時期を通過しない。それからして文学が、いつも永遠の「稚態」と「老耄」との外、一の成熟をも見ないのである。
…うーん、なんかわかったようなわからんような、もっと若いときに読んで触れてたら、受ける印象ちがったのかもしれないけど。
コンテンツは以下のとおり。
読者への挨拶
危険人物!
輝かしい心像
良心! いみじき意匠
技芸家
賤民根性の人々
楽天的自然主義と悲観的自然主義
有神論のジレンマ
結婚の時期
帽子と求婚
或る野戦病院における美談
永世輪廻
門
芸術には上達がない
日本の文学
ポーの名言
友情の侵害区域
私が此処に居る
天才の鬼哭
女と厭世哲学
忘却への熱意
セザンヌの逆定義