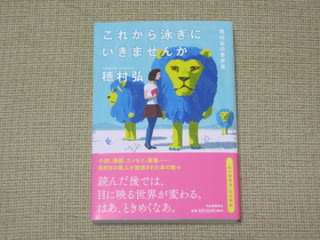穂村弘 2019年3月 KADOKAWA
前に読んだ『短歌ください』の続刊が出てたのを、つい最近知ったんで、読んでみた。
「ダ・ヴィンチ」の連載の2015年11月号~2018年4月号までをまとめたものだって。
それはいいけど、よくみたら、これ単行本第4弾だっていう、第3弾ってのを読んでないぞ私、そのうち読まなくては。
でも、まあ、順番飛ばしてても問題はないだろう、たぶん。この本のなかではお題が前後つながった章もあるようだけど。
短歌のよしあしがわかるってわけぢゃないから、サラサラと読んでくだけなんだけど、穂村さんの講評がやっぱおもしろい。
今回、とくに印象的だったのは、日常的なことをあらためてちょっと違う角度から見てみると意外な発見がある、って感じのこと。
言葉で世界を切りとるっていう短歌の魅力の解説になってんだと思う。
以下、いくつかの例、講評の一部とその短歌。
>見慣れた現象を言葉で組み立て直した時、まったく新しい風景が見えてくることがあります。
「ライターのどこかに炎は隠されて君は何回でも見つけ出す」 (p.137自由題)
>日常的な動作を敢えて言語化することで、根源的な何かが立ち上がってくるようです。
「眠る時ひとは躰を柔らかい布で(できれば羽毛で)覆う」(p.165自由題)
>客観的な事実を改めて言葉で組み立て直すと、奇妙な世界ができあがることがある。
「胃の内容物を全員同じにし眠気を誘う給食センター」(p.206自由題)
>そういうことは普通にある。でも、こんな風に言葉にされると不思議な感触が生まれます。
「こめかみの五メートル先は県道だ そう思いつつ静かに眠る」(p.247自由題)
穂村弘 2019年2月 文春文庫版
新しめの文庫なんだが、最近買った中古もの。
単行本は2011年のNHK出版で、「きょうの料理ビギナーズ」に連載されてたものらしい、読んだことないなー。
なかみは、そういうわけで、食べものに関して書いたものが集められている。
とはいえ、なんかめずらしいものとか特別うまいものとかのレポートや、素材や料理法に関するうんちくなんかぢゃない。
著者のエッセイにありがちな、世間のひとのようにふつうに対応することができなくて困っちゃう、といった感じのテイストがいっぱい。
お好み焼き屋にいくと、「混ぜが足りないよ」ってまわりから指摘されちゃうとか、ミスドで“D―ポップ”を頼むと女友達に「ださー」って言われちゃうとか、そういう経験にあふれた日常みたいな。
若い長身のきれいな男の子がホームパーティにお稲荷さんを持参したときの次のような感想とか笑う。
>日本男子はレベルアップしている、と実感した。
>きれいでおしゃれで若い男の子に漏れなく「お手製のおいなりさん」がついてくるのだ。
>きれいでもおしゃれでも若くもない私には「コンビニの菓子パン」がついてくる。
>比較の結果はあきらかだ。後者をパートナーに選びたい女性はいないだろう。
>私は未来における自分の孤独死をありありとイメージした。(p.57-58「苺のヘタをみたことがない」)
食べものの好みに関する話でも、ちょっとそんじょそこらのエッセイとはポイントがちがってたりしておもしろい。
>先日、或る編集者と御飯を食べながら打ち合わせをしていたときのこと。不意に彼女が云った。
>「カレーは温かいのがいいって云う人が多いけど、私は御飯かルウのどっちかが冷たい方が好きなんです」
>「おおっ、俺もです!」
>興奮のあまり、思わず一人称が「俺」になってしまった。だって、人生の四十五年目にして初めて出会ったのだ。(略)仲間だ。(p.99「「どっちかカレー」現象」)
この、自分だけがほかのひとと違うのか、みたいな感覚は、こと食べものについてってなると、ひときわ精彩を放つような気がする。
ある公開対談で、「ところてんを箸一本で食べる」と発言したら、会場に同意してくれるひとが誰もいなくてシーンとなってしまったとか。
それで家に帰ってからネット検索したら、自分の育った地域に特有の習慣だとわかって、ちょっとほっとしたなんて言いながら、そこからさらに妄想がすすむとこがおもしろい。
もし、夜通し検索して、ヒットしたのが一件だけだったなんてことになったら、
>自分以外にところてんを箸一本で食べる唯一人の人。
>充血した目でその画面をみつめながら、私は決意する。
>この人に会いに行こう。
>どこの誰かはわからない。
>でも、運命の人だ。(p.151「ところてんの謎」)
っていうんだけど、このおおげささがサイコー。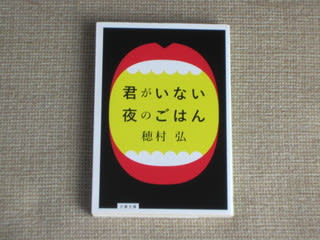
7月に書店で見かけて買った文庫、夏のあいだのどこかで通勤電車のなかで読んだ。
文庫新刊売り場でタイトル見て、あれ、これ持ってたっけ読んだっけって、ちょっと思い出せず困ったんだが、調査の結果2015年の単行本は読んでなかった。
「はじめに」によれば、本書は『群像』に連載中のエッセイ(なのかな?)をまとめたもの。
『はじめての短歌』って文庫は読んだんだけど、その元ネタの講義では本書でとりあげた歌を例として同じようにとりあげてるんだそうで。
与謝野晶子とか斎藤茂吉とかって古いものから、現代の歌でも新聞に投稿されたものまでも、いろいろとりあげて、わかりやすく解説してくれてる。
ときどき改悪した例文のようなものをつくって、ノーマルな表現だといかにつまんないかというのを具体的に示してくれるんで、そういうのがおもしろい。
ただねえ、たぶん私のほうに問題があるんだろうが、このテの本を以前読んだときのように、すごい歌にめぐりあって「オッ!」と思ったりするようなことがない。
なんかの感覚、言葉に対するアンテナのようなものが、鈍くなっちゃってるんぢゃないかと、ガラにもなく自分で不安になってしまう。
でもでも、油断してると、
>先日、久しぶりに岡崎京子の『リバーズ・エッジ』を読み返した。やっぱり凄い。この人が今を描いたらどうなるんだろう、と思う。(p.93「窓の外」)
なんて書いてあったりするんで、この歌人にはついていく気になる。
コンテンツは以下のとおり。
コップとパックの歌
賞味期限の詩
高齢者を詠った歌
ゼムクリップの詩
花的身体感覚
するときは球体関節
意味とリズム その1・その2
天然的傑作
内と外
画面のむこう側とこちら側 その1・その2
日付の歌
素直な歌
子供の言葉
窓の外
ちやらちやらてふてふ
今と永遠の通路
美のメカニズム
生殖を巡って
システムへの抵抗
感謝と肯定
身も蓋もない歌
ドラマ化の凄み
暗示
貼紙や看板の歌
ミクロの世界 空間編・時間編
永遠の顔
平仮名の歌
漢字の歌
繰り返しの歌
落ちているものの歌
デジタルな歌
動植物に呼びかける歌
我の歌
会社の人の歌
時計の歌
間違いのある歌 その1・その2
慎ましい愛の歌 その1・その2
ハイテンションな歌 現代短歌編・近代短歌編
殺意の歌

年明けに、こないだ読んだ『これから泳ぎにいきませんか』といっしょに買ったやつ。
同時刊行とやらだが、そう言われると、片っぽだけ買うのは手落ちな気がしてしまうので。
こっちのサブタイトルは「穂村弘の読書日記」、書評よりはちょっとくだけた感じか。
巻末初出をみれば、2010年から2011年に「週刊現代」に連載したものと、2013年から2017年に「週刊文春」に連載したもの、後者はホントに文中の区切りに「×月×日」って入れてる日記のかたち。
なかみは、短歌はもちろんだけど、マンガあり、ミステリーを多く含む小説ありで、いろいろ。
古いものもあり、新しいものもある、読んだことあるけどまた読んでみたみたいなのもある。
よく古本屋に行くらしい、いいなあ、古本屋の多い街に住みたい。私の生活圏内では、年々減ってってる。
ひとに薦められて読むことも多いみたい、「好きそうだよ」とか言われて、読んでみたらもちろん気に入ったようで。
そのなかで気になったひとつが、『オーブランの少女』ってミステリー。深い謎がありそう、見つけたら読んでみよう。
『宝石の国』ってマンガも気になってしまった。
>(略)とうとう読んだ。既刊の三巻分を一気にまとめ読み。ほっとした。これで自分も『宝石の国』を読んだ人の仲間入りだ。(p.150「本のおかず」)
って感じで書かれちゃうと、仲間入りしてみたくなる。
『翻訳できない世界のことば』ってのも気になる。
フィンランド語の「PORONKUSEMA(ポロンクセマ)」というのは「トナカイが休憩なしで、疲れず移動できる距離」って意味で、他言語ではニュアンスが説明できない。
うーむ、冷静に考えると、そういうものを集めて一冊の本にまとめられるひとというのは、どんな能力の持ち主なんだろう。
ところで、タイトルの「きっとあの人は眠っているんだよ」は、『新車の中の女』というミステリーのなかで、小さな子供が言うセリフらしい。
なんとも謎めいてていい、「私の大好きな作品だ」って言ってるんで、これまた読んでみたくなる。
そんなふうに著者のことを私が信用するのは、たとえば本書のなかにも、
>喫茶店や電車の中で、それを読んでいる人を見かけたら好感を持つ本は何か。そんな話をしたことがある。私が思いついた答は「諸星大二郎の本」だった。(p.215「「ダーク」の教え」)
みたいな、私にとってうれしいフレーズを書いてくれたりするからで。
べつに好感持ってもらいたいとまでは思わないけど。

年明けすぐごろだったか、書店でみかけて、おやと思った。
また不思議な響きのタイトルだなあ、エッセイ集かな、いつものようにちょっとした日常のなかでドキッとした言葉に出会った瞬間とかそういう系っぽい。
そんな印象を受けて、手にとってよくみたら、サブタイトルは「穂村弘の書評集」、そうなんだ、そういう仕事もありだったのか。
目次サラサラと見たら、知ってるマンガの名前なんかもあったんで、安心して買い。
巻末の初出みたら、第一部の書評集は、2000年代後半以降に、朝日新聞とかGOETHEに載ったものらしい。
第二部は、文庫本の解説とか集めたもの。
とりあげられてるなかみは、当然短歌に関係したものがわりと多いけど、マンガとか小説とかもあって、いろいろ。
表紙のタイトル見て、おっと思わされた「これから泳ぎにいきませんか」というのは、編集者だった二階堂奥歯さんという女性が、穂村さんと晩御飯たべながらの仕事の打ち合わせの終わりがけ、もう夜10時過ぎだというのに、突然言い出したことだと判明。
鋭敏な感覚と高度な認識をもったひとで、若くして亡くなってしまったらしいが、いまだに穂村さんをして「二階堂さんだったら、こんな時なんて云うだろう」と思わせる存在だったらしい。それ、ちょっと読んでみたいかも、本書収録されてるのは、『八本脚の蝶』という本への寄稿文。
どうでもいいけど、「まえがきにかえて」という冒頭のイチのイチの場所に、
>知り合いの青年に「本は読まないの?」と尋ねたら「ほむらさんはダンスしないんですか?」と聞き返されたことがあります。読書は人生の必修科目でダンスは選択科目、というのはもう古い感覚らしい。
とあって、つくりばなしかもしれないけど、かなりドキッとさせられた。