堀井憲一郎 2006年講談社現代新書
これ、いいっすよ。
世の中、いつの間にかヘン(←これは私の判断基準による)になってたんだけど、いつどっからヘンになったのか、わからせてくれる本。
たとえばクリスマス。
いつからクリスマスは、男と女で人気のレストラン行ったり、ホテル泊まったりっしなきゃいけない、「恋人たちの日」になっちゃったのかとか。
これは、1983年の12月のアンアン「クリスマス特集 今夜こそ彼の心(ハート)をつかまえる!」からだそうだ。内容は、“シティホテルに泊まって、朝、ルームサービスで彼と朝食をとろう”ということだそうだけど、それは“当時はおもいもつかなかった”記事だったらしい。
著者は例によって、テッテー的に調査・もの数えをする人なので、1970年代の雑誌を探した限りは、十年間で六つしかクリスマス・デートの記事は無いと言ってるんで、信用できる。
女性誌が先行して、男のほうはそれに遅れること数年、1987年やっとポパイが「クリスマス、今年こそ決めてやる」、翌88年ホットドッグプレスが「彼女へのプレゼントはこれをあげよう特集」を始める。
ここから、“クリスマス・ファシズムが始まった”んだそうだ。「クリスマスを恋人同士で」という動きが拡大の一途をたどることになる。みんな、おかしいと思いつつも止まらないファシズム。
ほかにも、開園した1983年の大みそかには何事もなかった東京ディズニーランドが、1987年の大みそかには“壊れるような混雑になっていた”こととか。ホイチョイが1985年に「ディズニーランドは、子供のものではなく、デートに使うべきだ」と主張した本を出して、そのすぐあとには“世界が、女の子の希望を優先”して、“80年代を通して、つねに女の子の希望が消費経済を誘導していった”さまが書かれている。
“家庭”を舞台にしたNHKの朝の連ドラが凋落して、恋愛を中心にした“空虚なドラマ”である月9が成功しはじめると、“自分らしい生き方は譲らない。女性であることも手放さない。どちらもかなえてくれる相手でないと恋愛しない。”と女性が恋愛のレートを上げてしまったこととか。ディズニーランドのときに“女の子の機嫌をうまくとらないと、相手にしてもらえなくなった”のに輪をかけて、遊びの場の賭け金を女性が高くしてしまった時代の流れがよくわかる。
そのへん、遊んでる本人たちが好きでやってるだけならかまわないが、実はオトナ、っていうか日本の社会が、「若者はこうするべきだ」という情報を流して、若者から金を巻き上げよう(カツアゲぢゃないんで、より正確には、資本を投じてその資本を回収するため若い人の行動を誘導した)と動きだしたというのが実際らしい。そういう社会につかまっちゃった若い人はどうしたらいいんだろうというのが本書の問いかけ。
どうやらバブルって1985年から89年くらいのあいだのことらしかったんだけど、そのころ私は高校から学生のころだったんで、可処分所得が少なかったから、経済的には踊らされるようにカネ使えって動きの実害を(恩恵もだけどね)受けてない。就職活動でキビしい思いをしなくて済んだっていうのが今となってはバブルの実感なんだけど、少し上の世代は大変だったんだなーって気がしないでもない。
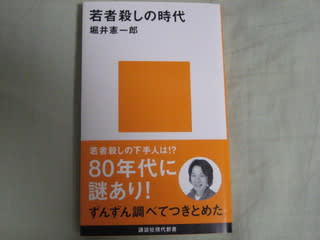
なにはともあれ、みなさん、よいクリスマスを!
これ、いいっすよ。
世の中、いつの間にかヘン(←これは私の判断基準による)になってたんだけど、いつどっからヘンになったのか、わからせてくれる本。
たとえばクリスマス。
いつからクリスマスは、男と女で人気のレストラン行ったり、ホテル泊まったりっしなきゃいけない、「恋人たちの日」になっちゃったのかとか。
これは、1983年の12月のアンアン「クリスマス特集 今夜こそ彼の心(ハート)をつかまえる!」からだそうだ。内容は、“シティホテルに泊まって、朝、ルームサービスで彼と朝食をとろう”ということだそうだけど、それは“当時はおもいもつかなかった”記事だったらしい。
著者は例によって、テッテー的に調査・もの数えをする人なので、1970年代の雑誌を探した限りは、十年間で六つしかクリスマス・デートの記事は無いと言ってるんで、信用できる。
女性誌が先行して、男のほうはそれに遅れること数年、1987年やっとポパイが「クリスマス、今年こそ決めてやる」、翌88年ホットドッグプレスが「彼女へのプレゼントはこれをあげよう特集」を始める。
ここから、“クリスマス・ファシズムが始まった”んだそうだ。「クリスマスを恋人同士で」という動きが拡大の一途をたどることになる。みんな、おかしいと思いつつも止まらないファシズム。
ほかにも、開園した1983年の大みそかには何事もなかった東京ディズニーランドが、1987年の大みそかには“壊れるような混雑になっていた”こととか。ホイチョイが1985年に「ディズニーランドは、子供のものではなく、デートに使うべきだ」と主張した本を出して、そのすぐあとには“世界が、女の子の希望を優先”して、“80年代を通して、つねに女の子の希望が消費経済を誘導していった”さまが書かれている。
“家庭”を舞台にしたNHKの朝の連ドラが凋落して、恋愛を中心にした“空虚なドラマ”である月9が成功しはじめると、“自分らしい生き方は譲らない。女性であることも手放さない。どちらもかなえてくれる相手でないと恋愛しない。”と女性が恋愛のレートを上げてしまったこととか。ディズニーランドのときに“女の子の機嫌をうまくとらないと、相手にしてもらえなくなった”のに輪をかけて、遊びの場の賭け金を女性が高くしてしまった時代の流れがよくわかる。
そのへん、遊んでる本人たちが好きでやってるだけならかまわないが、実はオトナ、っていうか日本の社会が、「若者はこうするべきだ」という情報を流して、若者から金を巻き上げよう(カツアゲぢゃないんで、より正確には、資本を投じてその資本を回収するため若い人の行動を誘導した)と動きだしたというのが実際らしい。そういう社会につかまっちゃった若い人はどうしたらいいんだろうというのが本書の問いかけ。
どうやらバブルって1985年から89年くらいのあいだのことらしかったんだけど、そのころ私は高校から学生のころだったんで、可処分所得が少なかったから、経済的には踊らされるようにカネ使えって動きの実害を(恩恵もだけどね)受けてない。就職活動でキビしい思いをしなくて済んだっていうのが今となってはバブルの実感なんだけど、少し上の世代は大変だったんだなーって気がしないでもない。
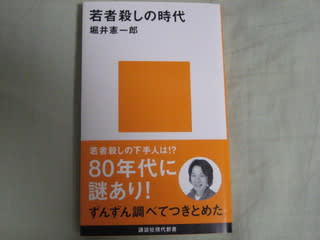
なにはともあれ、みなさん、よいクリスマスを!















