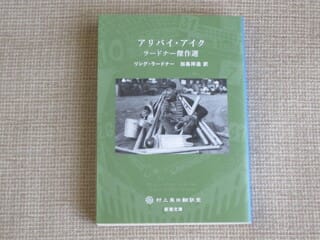リング・ラードナー/加島祥造訳 平成二十八年 新潮文庫版
リング・ラードナーはこのあいだ文庫の短篇集を読んだら、たいそうおもしろかったんで、ほかにも読んでみたくなった。
そしたら、この文庫は近年になって復刊されたらしく、中古を買うのもわりとたやすかった、「村上柴田翻訳堂」というシリーズのラインナップとして「ラードナー傑作選」という副題が付されてる。
どの短篇も登場人物たちがじつによくしゃべる、男も女もとにかくおしゃべり、またそれがおもしろいんだ。
解説セッションで柴田元幸さんが、「ほとんどお笑いの世界ですよね。純文学というよりは話芸といったほうがずっと近い」(p.453)って言ってるけど、まさに「語り」だけでできてる作品たち。
収録作は以下のとおり。
『アリバイ・アイク』 Alibi Ike
>「彼女って?」とアイクが言った。
>「晩飯を一緒に食べた彼女さ」
>「ああ、あれはただ偶然食堂へはいる時一緒になっただけなんだ。監督が一緒に坐れって言うもんだから」
>「彼女はお前がジョーの店で買ったのを指にはめてたなあ」
>「ああ、しばらく貸してくれって言うんでね、貸してやったんだ」
>「台を新しく作り直して貸してやった、というわけかい?」とおれが言った。
>「あれは彼女のだよ。石を落としたんだってさ」(p.40-41)
『チャンピオン』 Champion
>「今晩のあんたすごかったなあ。こてんぱんにやっつけた」
>酒が出た時ハーシュは言った。「殺しちまうのかと思ったぜ」
>「レフェリーが止めなきゃ殺したろうな」ミッジは答えた。「おれは誰でもみんな叩き殺すぜ」
>「とにかくあんたのパンチはすごい」ハーシュは惚れこんだ調子で言った。
>「おれのパンチだと?」とミッジ。「らばの蹴る力にだって負けやしないぜ。おれの肩の筋肉見たかい?」(p.60)
『この話もう聞かせたかね』 Stop Me,If You're Heard This One
>オズボーン氏は、こんな話ばかりで退屈させなかったかしら、と二人に言った。
>「とんでもない!」とブレイズ。
>「まったく聞きあきない話ばかりですよ」とガーナー。
>「ぜひ回想録をお書きになるべきですね」とブレイズが言った。
>「よく人にそう言われるんだが、一カ所にじっとしてないんで、落着いて書く暇がない。定期的に慢性の放浪癖が出る性質なんだねえ」(p.102)
『微笑みがいっぱい』 There Are Smiles
>ベンの部署である交差点では、たとえ交通違反があっても、よっぽど重大な事故にならぬかぎり、めったに罰せられなかった。いま話したような茶目っ気たっぷりなお叱りを受けるのが関の山で、それも言い方がすごくおだやかなものだから、叱られてかえって嬉しく感じるくらいだった。(p.122)
『金婚旅行』 The Golden Honeymoon
>わしという人間は喋りはじめたら止らんから困る、とかあさんは言うんだがね。しかしわしは言うんだ、だってわしが喋れるのはかあさんがそばにいない時だけなんだ、だからその機会にできるだけ稼ぐわけさとね。(p.150)
『ハーモニイ』 Harmony
>「さっき監督が話してくれたんだよ、あんたがウォルドロンを掘りだした話をね」
>「ああ、あれか」と彼は言った。「あんなこと、べつに話にはならんだろ」
>「ぼくにはすてきな話に思えたな」とぼくは言った。「凡フライを打った新米を見ただけで、これはタイ・カッブみたいな大選手だと見抜くなんて、誰にもできることじゃないものね」
>グレアムは微笑した。
>「そうさ」と彼は言った。「そういう目を持ってるやつは少ないだろうな」(p.195)
『ここではお静かに』 Zone of Quiet
>「あの先生、とてもいい人みたいだわね」とミス・ライオンズは言った。「それに医師としてもね。あたしあの先生につくのはこれがはじめて。彼は看護婦のすることを信用してくれるようね。たいていのお医者って、看護婦を顎で使う気持でいるんです。たとえばホランド先生なんかそう。先週、あの先生についたのよ。そしたら人をまるで自分の妾みたいに扱うの。しまいにあたし、言ってやったわ、こう言ったの――『あたし、見たほど薄のろじゃないんです』って。彼女、金曜日の晩に死んだわ」
>「誰が?」とベッドの男は訊いた。
>「あたしがついてた女の人」とミス・ライオンズは言った。(p.227-228)
『愛の巣』 The Love Nest
>「そこへ掛けたまえ」とふかふかする安楽椅子を指しながら、この家のあるじは言った。
>「さて、君の飲みもの、何にするかね? わしは本物の古い国産ウイスキーを持っとるんだ。それを君にも飲んでもらいたいな。ね、君、わしはシカゴ出身だろ、だからどうも外国物よりも国産のほうが口に合うんだ。言いかえると、わしには外国物よりも国産のほうがうまい、というわけだ。フォブズ」と彼は使用人を呼んだ。「一杯やることにした。その食器棚に口をあけたばかりのバーボンの瓶があるはずだ」(p.257)
『誰が配ったの?』 Who Dealt?
>あたし、パスにするわ。あら、ご免なさい、トム。あたし、きっと間違えるだろうと予感してたのよ。トム、ご免なさいね。でもいずれはあたしたちが勝つわ、そうでしょ、トム? 今度は誰がリードする番?
>ええ、あたし、お喋りやめて、もっとゲームに集中するわ。トム、そんな顔しなくてもいいじゃないの? あたし、その気になればお喋りやめることできてよ。でもねえ、気持がたかぶってると、落着いて物を考えることができないものよ。(p.289)
『散髪の間に』 Haircut
>お客さん、この町ははじめてでしょ、ええ? 見かけない顔だと思いましたもの。この町が気に入ってくれるといいですねえ。もちろん、さっき言ったように、ここはニューヨークやシカゴってわけにいきませんよ、でもね、けっこう面白いことがあるんでさあ。ただ、ジム・ケンドールが死んじまってからは、ちょっと淋しくなりましたね。ジムが生きてたころは、彼とホッド・メイヤーズの二人で、町じゅうをげらげら笑わせたもんです。(p.308)
『ハリー・ケーン』 Hurry Kane
>なかでもいちばん滑稽だったのは歩き方だったなあ。投げる番になって、はじめてピッチャー・プレートへ行った時の様子ときたら、まず忘れられないもんだったな。まるで自分がハダシでいてガラスでも踏んづけやしまいかとビクついてるみたいさ。片脚をあげ、それをしばらく空中に置いといて安全なとこを見つけてから、やっとおろす。それからもう一方の脚も同じようにやるんだ、だからベンチを出てからピッチャー・プレートに着くまで、半時間もかかったみたいだったぜ。もちろん監督はじきに彼のこの癖を直しちまった、いや、監督じゃなくてキッド・ファレルがやった、と言うべきかな。(p.338-339)
『相部屋の男』 My Roomy
>いいや、まだ来年の契約はしてないさ、しかしべつにトラブルはないんだ。金額の点は話がすっかりついてるからな。そのことでは監督との話も終っていて、向うが契約書を送ってくればすぐにサインするのさ、ただし一つだけ条件を出してるんだ、今後自分の相部屋になる男はおれが選ぶ、向うから押しつけられるのはご免だ、ということさ。(p.384)
『短編小説の書き方』 How to Write Short Stories
>たいていの場合、私が常にとる第一の手は、目立つ題名を見つけることです。たとえば、『バジル・ハーグレィヴの駆虫剤』とか、『焼却工場での悦楽』といったふうです。それから私は、どんな種類のでもいいがデスクかテーブルの前に坐り、三枚か四枚の紙を置き、できるだけ多くの色の色鉛筆をとりだし、それらを横目で数分間じっとにらみつけてから一本を選びだします。(p.435-436)