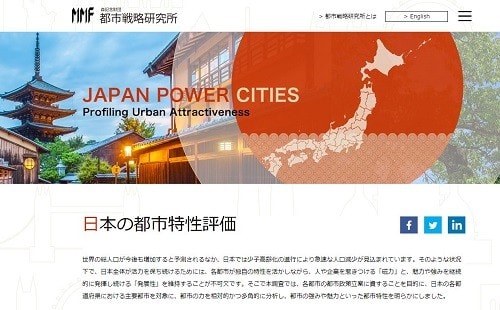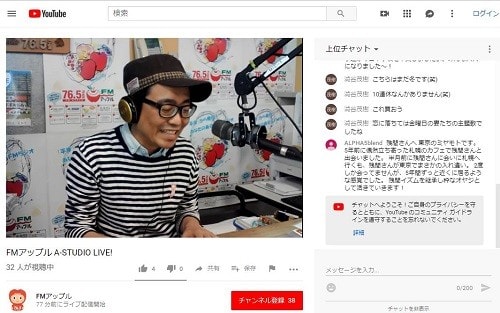札幌商工会議所が主催するまちづくり講演会に参加してきました。
今日の講演のテーマは、「日本の都市特性評価2018」で、日本の主要都市を客観的な指標で比較し、順位をつけて、それぞれの強みや弱みを明らかにした調査の2018版についてのお話。
講師はこの調査を行った、一般財団法人森記念財団都市戦略研究所 理事の市川宏雄先生です。
特に今回は、札幌で開催していただくということで「札幌市の強みと弱み」について説明をしてくださって、興味深いお話でした。
この調査については要約版をインターネットで入手することができますので、ぜひダウンロードされてください。
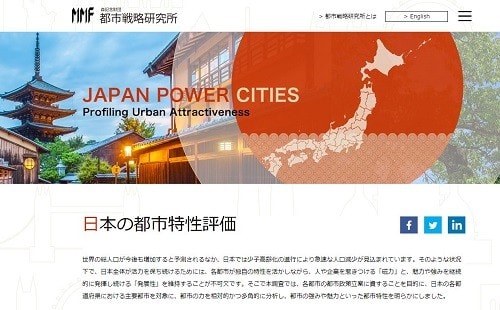

【日本の都市特性評価2018 概要版】
http://mori-m-foundation.or.jp/ius/jpc/
この調査は、世界の都市を対象に、"Global City Power Index"として都市間の優劣を2007年から行っており、2012年からは日本国内の都市の調査も行っています。
この調査の特徴は、
① 6分野26指標グループ83指標による分析で都市特性を客観的に評価し、
② レーダーチャートなどを用いて都市の強みや魅力を視覚化して、
③ 定量データを主に使った都市戦略立案・検証に活用しやすいデータになっているということ。
対象都市は、21の政令市と、それ以外の31の県庁所在地、さらに各道府県で人口規模で2番目と3番目の都市を加えた、全部で72都市。ちなみに、東京23区は別扱いでの調査となっています。

北海道では、札幌と函館と旭川がエントリーされていますよ。
さて、上の①で述べた「6分野」とは、
(1)経済・ビジネス
(2)研究・開発
(3)文化・交流
(4)生活・居住
(5)環境
(6)交通・アクセス という6つで、それぞれにその下にいくつもの指標があります。
調査は、できるだけ各種の客観的なデータを用いてトップからビリまで順位をつけて都市ごとに得点化してゆく、というものです。

最終的な結論を言うと、札幌市は全国で7位と上位にあって、一言でいうと、「ハード・ソフト両方の資源を併せ持つ観光都市」と表現されました。
ちなみに全国順位を言うと、1位京都、2位福岡市、3位大阪市、4位名古屋市、5位横浜市、6位神戸、そして7位が札幌。
札幌の後ろには、8位仙台市、9位つくば市、10位浜松市と続きます。
札幌の6分野ごとの成績表を見ると、高い順から、文化・交流が72都市中(以下同じ)の6位、研究・開発が9位、経済・ビジネスが11位、交通・アクセスが15位、環境40位、生活・居住54位となりました。

市川先生は、最後に札幌に対するアドバイスとして、「MICE対応が同レベルの都市の中では特に弱いので、このジャンルは強化するとよい」、「北大などのトップ大学があるので、大学と企業、研究機関の連携で、地場産業の高度化を図るべき」、また「外国人や高齢者などの多様な人材活用をもっと進めたほうが良い」といったまとめをしてくださいました。
指標そのものの是非には、いろいろと突っ込みたくなることもあるかもしれませんが、まずは共通の指標で全国の都市を比較すると、こうなると、という話としては面白いものでした。
講演の後の質疑応答コーナーで、私から、「災害のリスクや被災した過去などは評価の対象にならないのか、また雪が降るということはメリット・デメリットがあるが評価としてどうか」と質問をしました。
市川先生の答えは、「確かにその辺は議論もあったけれど、災害のリスクや、過去の災害履歴を加えると、生々しくガクッと評価が上下するので、まずそこは判断から外そうということにした。また雪もデメリットとすると、日本海側が一様に不利になるということもあり、それも考えない指標になっている」とのことでした。
全国7位という順位を「思ったより高い」とみるか、それとも「馬鹿にするな、もっと高くても良いはずだ」と思うでしょうか。
市川先生は、「各都市には地理的特性や位置などどうしようもないポテンシャルもあるけれど、環境政策や居住政策、福祉政策など、各都市の意思が示される評価軸も多いので、都市ごとにどんな政策に力を入れているのか、ということも浮き彫りになるので、そういう視点で眺めてみてもらうとよいのではないか」とおっしゃっていました。
札幌が環境政策の中でも再生エネルギーに対する取り組みが弱かったり、案外福祉政策も順位が上がっていないということでしたし、最後に指摘があったように、「MICE政策がまったく脆弱」という点は大いに改良に向けて力を注ぐべきと思いました。
国内のライバル都市に負けないような、都市政策をやりたいですね。
興味深いお話でした。