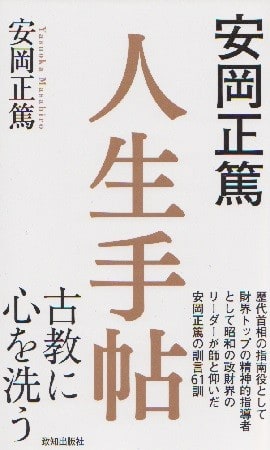前回は「民泊の勉強」と言いながら、ゲストハウスについてのレポートを書きましたが、今回は江別市で事業が始まろうとしている小規模のゲストハウスを訪問しました。
今回訪問したのは「ゲニウスロキが旅をした」という名のゲストハウス。
何やら哲学的な名前ですが、「ゲニウスロキ」というのはローマ神話の土地の主語精霊のことだそうで、土地の魂を大事にしたいという意味が込められているそうです。
こちらはコモンズファン代表の林匡宏さんがプランニング中のゲストハウスですが、林さん自身はデザイナー、イラストレーター、景観アドバイザー、公園整備アドバイザー、ランドスケープアーキテクトなどなど、いくつもの顔を持つ方。
一言でいうと、行政や地域にコミットしながら理想の形を実現するプランナー、という印象の、とても魅力的な若者です。
ゲストハウスの場所は、江別市大麻東町にある大麻銀座通りという200mほどの商店街の一角で、林さんはここでこれから13人が宿泊できるゲストハウスを開きたいと、店舗を一店買い取って現在はここを改装中。
しかしこちらの商店街は、一本北側には道道の太い道路があって、そちらには24時間のディスカウントショップがあったり大手の薬局チェーン店があり、ご多分に漏れずシャッターのしまったお店の多い商店街になってしまっています。
どうしてこの場所を選んだのか、と林さんに聞いてみると、「もともとは大手の建築コンサルタントに務めていたのですが、北海道勤務になったときに札幌の大学院で勉強をすることになり、その時に選んだフィールドが江別市の商店街でした。それで人の縁ができて、『こういう商店街をなんとかしてみたい』と思い立ったのだそうですが、やがて、江別のまちづくりを考える仲間や外の若者が次々と起業していた大麻銀座伊商店街さんと縁ができて、丁度良い物件も出るということでこちらにやってきました」とのこと。
林さんに、「なぜここでゲストハウスをしようと思ったのですか」と訊いてみると、「僕は地域が元気になるモデルを見つけてみたいと思っているんです。でもそれは理屈ではないので、まずは実際にやってみてそこからいろいろな学んで見たいと思っています」という答えが返ってきました。
「実は札幌市内南部の商店街でも、そこをフィールドにして地元の高校生と大学生を対象にセミナーをしているんですが、そこは高校生の反応が良くて、空き店舗を使って起業してみたい、という子が出始めています」
こういうところから、地方の知恵が出てくるのかもしれません。
◆
ゲストハウスの建物は、もともとは呉服屋さんだったという建物は一階が広いスペースになっていて、ゲストが寝泊まりするのは二階です。
林さんは、「この一階のスペースは地域の出会いの拠点にしたいと思っています。この界隈のお母さんたちに就業とのマッチングをしてもいいかな、と。例えばちょっとしたプログラミングを覚えてもらったり、エクセルに慣れてもらえれば、『ネットで2~3時間手伝ってほしい』というような細々した仕事をネット経由で手伝えるんじゃないかと。そうすれば、母親が正規に雇用されて一日を拘束されるのは無理だけれど、やりたいときにやれる範囲で社会の手助けをするという労働もあるのだと思います」とおっしゃいます。
新しい社会の到来を感じますね。
二階の寝泊まりスペースは、一人部屋、二人部屋、三人部屋がありますが、基本は和室で布団を敷くタイプで、仕切りはせいぜいカーテンがあるだけ。
トイレとシャワー室、お風呂はユニットタイプに入れ替えてあります。
「水周りだけは清潔感を出そうと思いました。でもやってみて気が付いたのは、古い家のために水周りの管を交換しないといけなかったことで、これは予想外の出費でした」
「仮オープンということですが、もう宿泊者はいるのですか?」
「まだネットでの募集もしていないのですが、ゲストハウスを始めたことを聞きつけた地域の方たちから『泊めてほしい』という要望があるんです。例えば、『親戚が来るので泊めてほしい』とかね。先日はお母さんたちの集まりがあって、夜遅くまでにぎやかに飲んで語って泊まっていきました。これなんかもやってみて初めて分かったことでした」
日本国内の若者の旅人や外国人観光客がターゲットなのかと思いきや、実は地域の中にも家から離れる宿泊需要があるとは思いませんでした。
大きな流れだけを追うのではなく、小さな需要をコツコツ拾うのもまた地域の中の拠点のあり方なのかもしれません。
実は林さんは、東京でも渋谷区の公園利用アドバイザーという嘱託職員でもあるのですが、会議などはリモート参加を認めてもらったので、札幌や江別市で仕事をすることと何とか折り合いがついている、と言います。
「ネットで会議に参加しながら、ゲストハウスのシーツにアイロンをかけたりしています(笑)。こういう働き方ももっと開放されて良いように思います」
林さんは今は札幌に住んでおられるということなので、こういう地域でのトライアルを重ねてゆくのでしょう。
一つの場所でずっと暮らして一つの仕事に邁進するという生き方が刷り込まれている昭和生まれの自分には、こうした場所を変え、移動しながら数多くのビジネスに携わるという生き方が正直言ってなかなか理解できません。
しかしネット環境の深化などで、自分の才能を生かして細々した時間をつなぎ合わせながら、今を渡り歩いて夢を実現していくような生き方がこれから増えてゆくのかもしれないと感じました。
「ところでなぜまだ仮オープンなのですか」と訊くと、「ネットのWifi環境が整っていなかったので仮にしていました。ようやくそれも揃いつつあるので、9月末を目指して本格オープンする予定です」
札幌市内でもなく、周辺都市の商店街の店舗活用のゲストハウス「ゲニウスロキが旅をした」。
林さんのこれからの活躍も含めて、フォローしておきたいと思います。