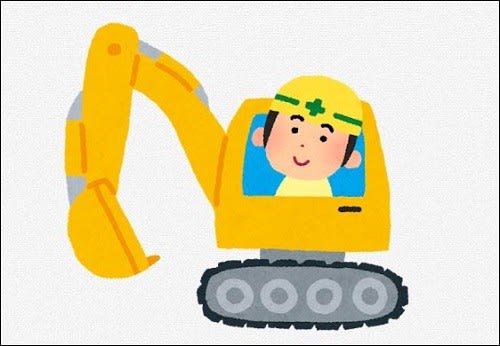先日職場の給与担当の女性と話をしていて、介護保険料の話題になりました。
介護保険は40歳から保険料の徴収が始まってこれはずっと支払いが続くのですが、一方で65歳になる前と後で大きく立場が変わります。
65歳以上になると、介護サービスが受けられるようになり「1号被保険者」と呼ばれます。
仕事勤めをしていようがいまいがそれは関係なく、年齢で立場が変わるのです。
そこで私が勘違いをしていたのが、「職場勤めをしていれば、介護保険料は給与からずっと天引きで引き去りされているのだろう」と思っていたことです。
それが給与担当の女性と話をしていて、私の介護保険料は昨年秋の誕生日で65歳になってからは職場はノータッチだったということが分かったのです。
改めて調べてみると、65歳以降は各個人で支払いを行うことになり、年金を受給していれば年金から天引きで引き去られるということになるのですが、年金を受け取っていなければ自分で支払い手続きをしなくてはなりません。
妻に「去年の秋からの介護保険料って支払った記憶があるかい?」と訊くと、「え~、覚えてない…」とのことで自信が持てない様子。
そこで昨年秋に届いた介護保険の保険証を開いて、区役所の担当者に介護保険料の支払い実績について問い合わせてみました。
電話に出てくれた担当者は、私の介護保険番号を聞き取ってから調べてくれて、「小松さんは3月分までを一括で納付されていますね」と教えてくれました。
「妻も同い年なのですが」と言うとそちらも調べてくれて、「はい、奥様も支払いは完了しています」とのことで、ホッとしました。
後で問い合わせた結果を妻に告げると「そういえば支払通知書が来て支払ったような気がしてきた」とのことで、まずは安心です。
保険料の額は、毎年6月の今頃に決まって通知書が届く形になるので、今後支払額のお知らせと納付書が届くはずですが、口座からの引き落としにもできるのでそれも検討項目です。
改めてですが年金を受け取れば、そこから差し引かれることになり、自分で何かをすることはなくなるというシステムはできあがっているとのことで、なるほどうまくできていますね。
会社勤めをしているとなんでも会社の事務方がやってくれているような気がしていましたが、少しずつそこから離れてやがて会社を離れれば、個人の立場で生きていかなくてはならないことも増えてきます。
新しい技術や制度についてゆくという生涯学習が必要な理由はこういうところにもあると言えますね。
強い個人になるように生涯学習を重ねましょう。
介護保険は40歳から保険料の徴収が始まってこれはずっと支払いが続くのですが、一方で65歳になる前と後で大きく立場が変わります。
65歳以上になると、介護サービスが受けられるようになり「1号被保険者」と呼ばれます。
仕事勤めをしていようがいまいがそれは関係なく、年齢で立場が変わるのです。
そこで私が勘違いをしていたのが、「職場勤めをしていれば、介護保険料は給与からずっと天引きで引き去りされているのだろう」と思っていたことです。
それが給与担当の女性と話をしていて、私の介護保険料は昨年秋の誕生日で65歳になってからは職場はノータッチだったということが分かったのです。
改めて調べてみると、65歳以降は各個人で支払いを行うことになり、年金を受給していれば年金から天引きで引き去られるということになるのですが、年金を受け取っていなければ自分で支払い手続きをしなくてはなりません。
妻に「去年の秋からの介護保険料って支払った記憶があるかい?」と訊くと、「え~、覚えてない…」とのことで自信が持てない様子。
そこで昨年秋に届いた介護保険の保険証を開いて、区役所の担当者に介護保険料の支払い実績について問い合わせてみました。
電話に出てくれた担当者は、私の介護保険番号を聞き取ってから調べてくれて、「小松さんは3月分までを一括で納付されていますね」と教えてくれました。
「妻も同い年なのですが」と言うとそちらも調べてくれて、「はい、奥様も支払いは完了しています」とのことで、ホッとしました。
後で問い合わせた結果を妻に告げると「そういえば支払通知書が来て支払ったような気がしてきた」とのことで、まずは安心です。
保険料の額は、毎年6月の今頃に決まって通知書が届く形になるので、今後支払額のお知らせと納付書が届くはずですが、口座からの引き落としにもできるのでそれも検討項目です。
改めてですが年金を受け取れば、そこから差し引かれることになり、自分で何かをすることはなくなるというシステムはできあがっているとのことで、なるほどうまくできていますね。
会社勤めをしているとなんでも会社の事務方がやってくれているような気がしていましたが、少しずつそこから離れてやがて会社を離れれば、個人の立場で生きていかなくてはならないことも増えてきます。
新しい技術や制度についてゆくという生涯学習が必要な理由はこういうところにもあると言えますね。
強い個人になるように生涯学習を重ねましょう。