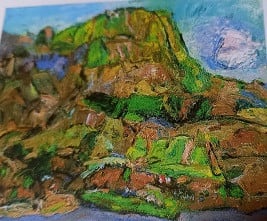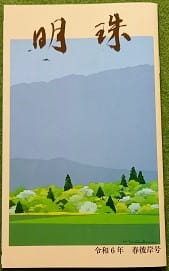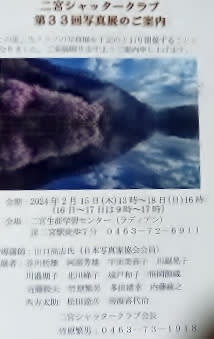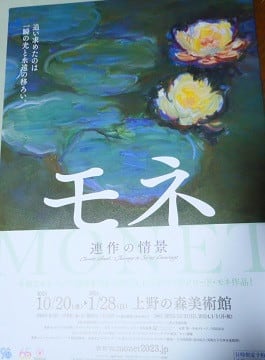明日からは旧暦のお盆~。
厳しい暑さの続く日々ですが、それなりの準備はしなくてはなりません。
長男から「日中の暑さの中で動き回るのは危険なので、なるべく早いうちに行動
しましょう」と、言われた「年より夫婦なのに朝寝坊」の私たち~(苦笑)
まずは、私の実家のお墓参りへ。
三連休&お盆休みの人たちが多いとみえて、たくさんのご家族連れの人たちがお墓参りをしていました。
次に、我が家の菩提寺へ。
ここは、7月の新暦のお盆ですので、お墓参りに見えるのは帰省されている方たたちのみと思われますので、お墓参りの人は少ない・・・。
我が家の墓地は、高い~場所!
こんな坂道を100m以上上ります(苦笑)

肺気腫で、坂道や階段は呼吸が苦しくなる夫は、何度も何度も休みながら・・・頑張りました。
「水桶」「掃除道具」「お施餓鬼のお塔婆」「お花やお線香」、いろいろのものは長男が持ってくれて、本当に助かりました。
もうかなり太陽がギラギラでしたが、我が家の墓地は周囲の木が日陰を作ってくれていて、ほっ~♪
それでも、汗はびっしょり、水分補給をしながら「草むしり」「墓石の掃除」「お花とお線香を手向けて」~、気持ちもスッキリしました。
帰りの坂の途中にある墓地・・・イノシシに掘り返されていて、すごいことになっていました!

後始末・・・どうするんでしょうかね・・・。
多分、7月のお盆にお墓参りにみえた時は何でもなかったんだと思います。
9月のお彼岸に見えた時には、唖然とされることでしょう・・・。
イノシシ被害・・・町全体でなんとか対策をして下さらないと、本当に困りますね!
帰宅後、一休みしてから「盆棚」を作りました。
夫と私は、疲れたので、30分ほどウトウトしていたのですが(笑)、長男が必要なものを天袋から出して、いろいろ準備をしてくくれていました。
「盆旗」を張って、

お掃除を済ませた仏壇の前に、テーブルを広げて「真菰」を敷いて、お位牌や盆用のグッズを並べましたが、まだ完成ではありません。
ご先祖さまや餓鬼のためのお供え物とか、いろいろ揃えるのですが、今日は何だか疲れたので、明日の朝にします(苦笑)。