日本経済新聞の記事です。
「独立行政法人や国立大学法人が保有する特許の収支状況を会計検査院が調べたところ、研究開発などで得た特許権の収入を出願料や維持費用が上回る法人が8割を超え、2013年度は全体で計約22億円の赤字だったことが10日分かった。検査院は事業化が見込めない特許を放棄するなど管理を見直すよう求めた。」そうです。
「検査院は2009~13年度の独法(55法人)と国立大(83法人)の特許の状況を調べた。5年間の平均収支は独法が毎年度10億~15億円、国立大が6億~13億円の赤字。13年度に特許収入が黒字だったのは計22法人にとどまった。
13年度末時点で、独法と国立大が保有する特許は計約4万8300件。このうち10年以上利用されていない特許が計約1万2800件あり、全体の26%を占めた。法人化前に国が登録した特許は維持費が免除されるが、独法に組織再編されるまで民間だった機関が登録したり、近年登録したりした特許は免除されず、維持費がかさんでいた。」とあります。
民間企業でもライセンス収入で黒字化するのは至難の業で、ライセンス収入に、関連会社からのライセンス収入(所謂上納金ですね)に特許を使用した製品・サービスの排他的権利の効力による貢献度を算出して(子の算定方法もかなり無理のあるものですが)、何とか黒字になるようにしているのが実情です。
私も企業と大学との共同研究のコンサルティングをしていますが、大学側の実施料収入に対する硬直的な考え方にも原因の一つがあるのではないでしょうか。
最近、柔軟な契約を締結する大学も増えてきていますが、依然として少数派ですね。
成功報酬を中心の、企業が活動し易い契約を締結するように大学関係者に話していますが、理解してくれるのは少ないですね。
成功実績を積み上げていくことが近道かもしれません。
ブログランキングに参加しています。よろしければ、以下のURLから投票して下さい。
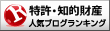
特許・知的財産 ブログランキングへ
 弁理士 ブログランキングへ
弁理士 ブログランキングへ
「独立行政法人や国立大学法人が保有する特許の収支状況を会計検査院が調べたところ、研究開発などで得た特許権の収入を出願料や維持費用が上回る法人が8割を超え、2013年度は全体で計約22億円の赤字だったことが10日分かった。検査院は事業化が見込めない特許を放棄するなど管理を見直すよう求めた。」そうです。
「検査院は2009~13年度の独法(55法人)と国立大(83法人)の特許の状況を調べた。5年間の平均収支は独法が毎年度10億~15億円、国立大が6億~13億円の赤字。13年度に特許収入が黒字だったのは計22法人にとどまった。
13年度末時点で、独法と国立大が保有する特許は計約4万8300件。このうち10年以上利用されていない特許が計約1万2800件あり、全体の26%を占めた。法人化前に国が登録した特許は維持費が免除されるが、独法に組織再編されるまで民間だった機関が登録したり、近年登録したりした特許は免除されず、維持費がかさんでいた。」とあります。
民間企業でもライセンス収入で黒字化するのは至難の業で、ライセンス収入に、関連会社からのライセンス収入(所謂上納金ですね)に特許を使用した製品・サービスの排他的権利の効力による貢献度を算出して(子の算定方法もかなり無理のあるものですが)、何とか黒字になるようにしているのが実情です。
私も企業と大学との共同研究のコンサルティングをしていますが、大学側の実施料収入に対する硬直的な考え方にも原因の一つがあるのではないでしょうか。
最近、柔軟な契約を締結する大学も増えてきていますが、依然として少数派ですね。
成功報酬を中心の、企業が活動し易い契約を締結するように大学関係者に話していますが、理解してくれるのは少ないですね。
成功実績を積み上げていくことが近道かもしれません。
ブログランキングに参加しています。よろしければ、以下のURLから投票して下さい。
特許・知的財産 ブログランキングへ















