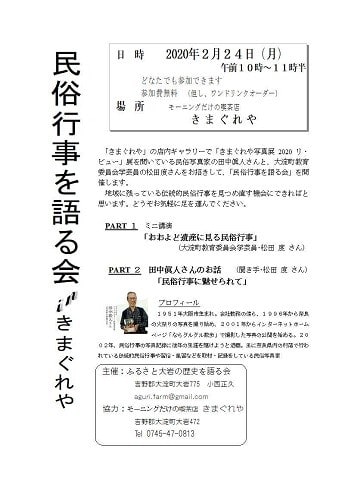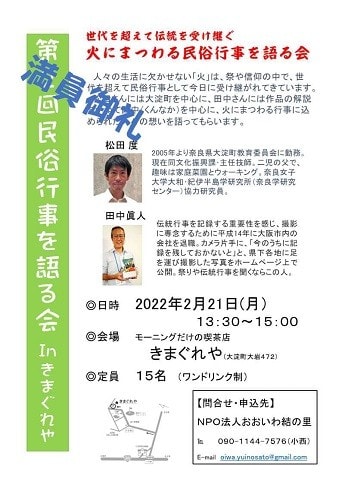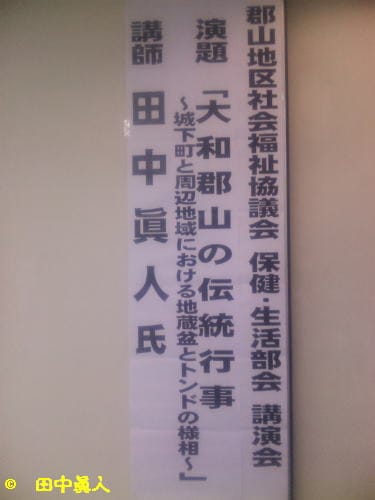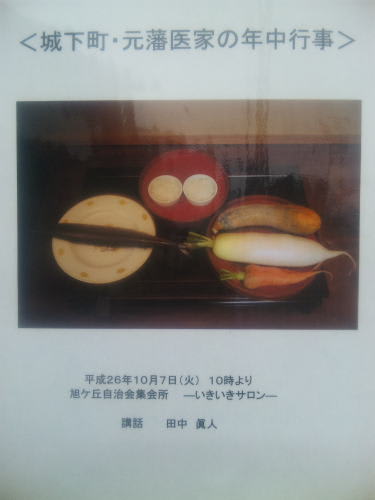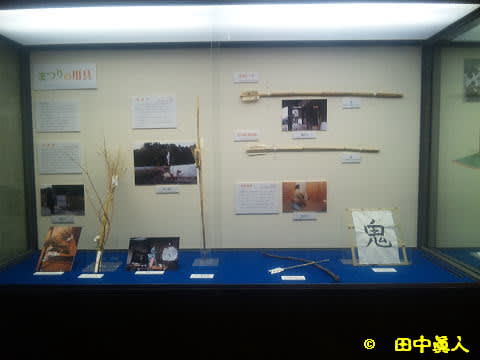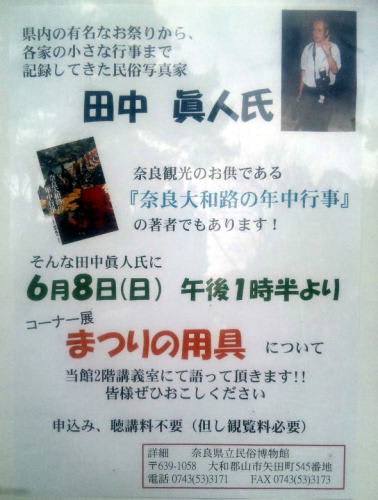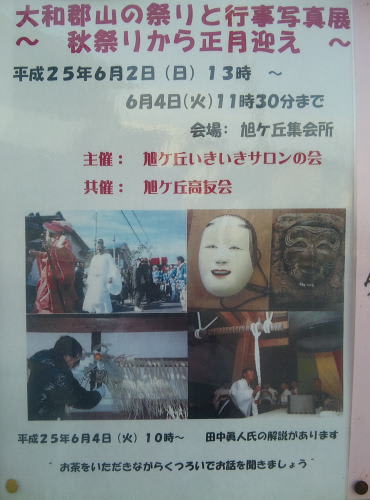今日も、県立民俗博物館併設大和民俗公園内施設の古民家を活用し、「私がとらえた大和の民俗」写真展を開催している。
県立民俗博物館の意向により、今回が最後になった、「私がとらえた大和の民俗」写真展。
当番日以外もできる限り、立ち寄り、来訪者に解説をしていきたい、と思っている。
午後1時から午後4時までが当番枠だが、たいがいは蛍の光が流れるまで、ぎりぎり滞在してきた。

会場近くまで来たとき、学芸主任のYさんに出逢った。
定年後は再任用勤め。
今月いっぱいで退職される。
十数年前、初めて県立民俗博物館に来館した。
調べたい大和郡山市の地域に子供たちが主役の行事を教わりたく門を叩いた。
地区は、椎木町。
行事名はショウブデンボ。
ショウブは植物の菖蒲。
漢字は、菖蒲であってもアヤメ。
ショウブとアヤメの違いは、わかり難い。
尋ねた結果は、調査したが最後になった、という。
対象とする子どもが村にいない。
誕生の報せもなかった旧村地域。
場所だけでも見ておきたいと、思って訪れた平成19年の5月26日。
そこでお逢いした椎木の住民。
ずいぶん昔になるが、子どものときに体験した詞章は、「ネーサン ネテルカ オキテルカ ショーブデンボデ イオタロケ」の囃子詞だった。
囃子の内容といい、節回しがさも似ている「わらべ歌」のような・・・
子どもの、今は・・に期待し、翌年の平成20年にも再訪した。
ショウブデンボは、6月6日にしていた、と資料にあったから、その日に合わせて出かけたが・・・
Yさんは、さまざまな民俗を教えてくれた一人。
逆に、学芸員でもわからないことがあり、その際に反応した行事は、私が取材、或いは見聞きした範囲内で協力していた。
DVD化に旧い映像を私に見せて、ここはどこ?何をしているのか・・・にも対応したことがある。
ところで、教えてほしいことが1件ある。
それは、令和4年の企画。
「博物館でひなまつり」に展示していた”陶器製の立ち雛”である。
室生の毛原に住む知人のFさんが、FBにコメントしてくれた「京都・立雛の作り手の名前を揚げてほしい・・」、一件である。
展示上では「回答のできない明治期になっているが、実際は江戸期。たぶんに集団工房で造りこんだものと推定している」、という。
集団による工房造りであれば作者の名は表に出ない。
実は。展示した立雛はYさんが個人的にあるところから買ってきたもの。
大阪のある文化施設に展示していた立雛の出里は奈良橿原の豪商であったようだ。
その豪商がどのような形で入手したかは、謎であるが、どうやら当時は大量に買い付けて、なんらかの祝い事に配ったようだと推定されている。
大阪の展示でわかった大量にある同形の立雛。
つまり大量生産する工房があったからこそ、それが可能だったことと、配る風習があったことによる立雛の生い立ち・・・に、だから作者の名はわかりようなく、答えられないものであった。
そのことは、私はある程度、推定はしていたが、まさかの豪商が購入。
金持ちだからこそできる手段であり、それが配る風習も絡んでいたとは・・・民俗って奥深い。
謎解きが、博物館学芸員の役目。
さまざまなことを調べて推論をたて、立証する素晴らしい職業を失った3人の学芸員。
大波乱であるが、根にあるのは、すべて県予算。
民俗調査、報告、展示に予算が組み込めない事態。
組織というか、民俗に知見どころか、見識のない人たちの怠慢が問題の根であろう。
立ち話に、もっと時間は必要だが、今日の古民家写真展は私の当番日。
早速、訪問された数名の男性。
名前を告げられて、はっとした。
そう、FBに度々訪れ、民俗に関心を持たれている川西町結崎にある大念仏・融通念仏衆 萬福山超圓寺の執事・徳野良裕氏であった。
展示見学に、わざわざお越しいただいた人たち。
徳野良裕氏は、六斎念仏鉦を調べている私を先生と呼ぶ。
まさかの先生呼びであるが、論文を執筆しているワケでもない、あくまで肩書は民俗写真家。
あるていど、というか。
ひとさま(※他人さま)より、ほんのちょっとは知しっているというレベルの私に、なんと手土産持参で来られた。

過去、何度か、同様に手土産をいただいたことがある。
お返しは、民俗行事の解説に替えて・・・
写真家たちが、それぞれ展示されている作品に一つ、一つ、作者の思いも含めて、丁寧(※にしたつもり)にさせていただいた。
順に、解説したラスト映像は、動画も収録された安堵町・寺垣内で行われた最後の営み。
映像にかつて取材させていただいた東安堵の大寶寺六斎講。
取材当時の代表のお顔もあった作品は「最後の営み」。
収録後に解散された念仏講の人たちの姿をとらえていた作品の出展者は、當麻武氏。
初の展示に、初の動画作品も写真展に華を飾った。
その解散話題から、話してくれた。
実は、私たちは川西町上吐田に住まいしているが、世話になっている寺院は、大念仏・融通念仏衆 萬福山超圓寺ですが、まったく別の組織である講が、今度の営みが最後、と伝えられた。
お逢いした講中のUさんの話しによれば、6軒で営みをしているそうだ。
その講は「センゲンサン」。
富士の山こと、浅間(※せんげん)さんを崇敬する講。
同一名称のセンゲンサン。
奈良市古市の講の営みを取材したことがある。
いつからはじまったのか、わからないが、上吐田のセンゲンサン行事は、最後の営み。
二日後の3月13日に行われる。
集まる場は、講中のお家。
まわりの家にきてもらうが、所在地がわかり難いから上吐田の春日神社に来てもらいたい、といわれた。
春日神社の行事といえば、春祭りがある。
たまたまのご縁に、取材させていただいた平成25年の3月17日。
また、上吐田のとんど行事も・・・
たぶんに、奈良ではいちばん遅いニノ正月のとんど。
春祭りの1カ月前の平成25年2月15日。
雨天決行の情景が印象に残っているだけに、承諾を得て最後のセンゲンサン行事に伺うことにした。
ちなみに、本日ご一緒された、もう一人の方もご住職。
なんと、立地する場は存じている大和郡山市小泉町・融通念仏衆維摩寺(※ゆいまじ)のH住職。

ご縁が広がる当番日。
午後2時15分。
今、駐車場に着いた、と電話をかけてくれた方は、これまたなんと神社の宮司。
今から写真展を拝見するから、と伝えてくれた。
宮司は、父親の代からご縁繋がりの奈良市阪原町にお住いの太田和秀宮司。
平成30年3月4日、山添村大西で行われた稲荷神社の初午行事以来、しばらくご無沙汰している。
古民家写真展に合流することになったお二人。
正式衣装で並んだら僧侶と神職。
神仏混合のお二方が、同時に観てくださる。
こんな嬉しいことは二度もないでしょ、と伝えて、解説した私のテーマ「コロナ禍、そのときのT家は・・」。

それぞれの写真家たちがとらえた大和の民俗情景も、その撮影主旨や、見方のポイントを語った。
所用がある、と先に帰られた僧侶と講中にありがとうございました、と見送った。
ところで、と話し出した宮司は、撮影協力を願われた。
行事は、現在、コロナ禍で中断しているから、それではない。
撮影対象は、現在奈良県美術館に寄託保管していただいている五枚(※実際は六面であった)の古い能面(※文化財一覧によれば室町、桃山、江戸時代)である。
撮影は、当初、村の人が所有するデジタルカメラで収めようと、していたそうだ。
簡単に撮れると判断したが、素人では、えー写真にならん、と判断。
その代わりのお鉢に私の名前があがった。
指名したのは太田和秀宮司。
ありがたく受け止めたが、能面は極力移動させず、美術館内のある一角で撮影するらしい。
撮影は、本来ならスタジオ撮影。
影を出さないよう、細心の注意が要るどころか、ラインティングは少なくとも2台か、3台。
数台のストロボ装置に同期も要る。
なんせ、ちゃちゃっと撮れるものでもない。
しかも、撮った写真データは、村に寄託している奈良県美術館も提供。
保管され、展示する場合があれば、使用したい、という。
では、村ではどのように、である。
能面は、普段見ることはない。
ないが、手元(村および神社)に置いておかない、と代々が失念することも考えられる。
また、観光などで神社に来訪される人たちに、昭和30年に県指定された村の貴重な有形指定文化財の能面も伝えたい。
掲示する立て看板も新しくしたい、と・・・
撮影日も時間も、既に決まっていた有形指定文化財の撮影。
宮司は、2本のUSBを持参されるので、撮影後の当日預かり。
撮影すべてのデータと選択したデータをそれぞれのフォルダごとに収めて提出することにした。
とにかく、急ぐ撮影。
一日、一発でできあがるかどうか、心配はするが、美術館の学芸員とともにする作業だけに、ま、なんとかなるだろう。
なお、駐車場は、県警東側の駐車場に停めてください、とこれも指示があった。
(R4. 3.11 SB805SH 撮影)
県立民俗博物館の意向により、今回が最後になった、「私がとらえた大和の民俗」写真展。
当番日以外もできる限り、立ち寄り、来訪者に解説をしていきたい、と思っている。
午後1時から午後4時までが当番枠だが、たいがいは蛍の光が流れるまで、ぎりぎり滞在してきた。

会場近くまで来たとき、学芸主任のYさんに出逢った。
定年後は再任用勤め。
今月いっぱいで退職される。
十数年前、初めて県立民俗博物館に来館した。
調べたい大和郡山市の地域に子供たちが主役の行事を教わりたく門を叩いた。
地区は、椎木町。
行事名はショウブデンボ。
ショウブは植物の菖蒲。
漢字は、菖蒲であってもアヤメ。
ショウブとアヤメの違いは、わかり難い。
尋ねた結果は、調査したが最後になった、という。
対象とする子どもが村にいない。
誕生の報せもなかった旧村地域。
場所だけでも見ておきたいと、思って訪れた平成19年の5月26日。
そこでお逢いした椎木の住民。
ずいぶん昔になるが、子どものときに体験した詞章は、「ネーサン ネテルカ オキテルカ ショーブデンボデ イオタロケ」の囃子詞だった。
囃子の内容といい、節回しがさも似ている「わらべ歌」のような・・・
子どもの、今は・・に期待し、翌年の平成20年にも再訪した。
ショウブデンボは、6月6日にしていた、と資料にあったから、その日に合わせて出かけたが・・・
Yさんは、さまざまな民俗を教えてくれた一人。
逆に、学芸員でもわからないことがあり、その際に反応した行事は、私が取材、或いは見聞きした範囲内で協力していた。
DVD化に旧い映像を私に見せて、ここはどこ?何をしているのか・・・にも対応したことがある。
ところで、教えてほしいことが1件ある。
それは、令和4年の企画。
「博物館でひなまつり」に展示していた”陶器製の立ち雛”である。
室生の毛原に住む知人のFさんが、FBにコメントしてくれた「京都・立雛の作り手の名前を揚げてほしい・・」、一件である。
展示上では「回答のできない明治期になっているが、実際は江戸期。たぶんに集団工房で造りこんだものと推定している」、という。
集団による工房造りであれば作者の名は表に出ない。
実は。展示した立雛はYさんが個人的にあるところから買ってきたもの。
大阪のある文化施設に展示していた立雛の出里は奈良橿原の豪商であったようだ。
その豪商がどのような形で入手したかは、謎であるが、どうやら当時は大量に買い付けて、なんらかの祝い事に配ったようだと推定されている。
大阪の展示でわかった大量にある同形の立雛。
つまり大量生産する工房があったからこそ、それが可能だったことと、配る風習があったことによる立雛の生い立ち・・・に、だから作者の名はわかりようなく、答えられないものであった。
そのことは、私はある程度、推定はしていたが、まさかの豪商が購入。
金持ちだからこそできる手段であり、それが配る風習も絡んでいたとは・・・民俗って奥深い。
謎解きが、博物館学芸員の役目。
さまざまなことを調べて推論をたて、立証する素晴らしい職業を失った3人の学芸員。
大波乱であるが、根にあるのは、すべて県予算。
民俗調査、報告、展示に予算が組み込めない事態。
組織というか、民俗に知見どころか、見識のない人たちの怠慢が問題の根であろう。
立ち話に、もっと時間は必要だが、今日の古民家写真展は私の当番日。
早速、訪問された数名の男性。
名前を告げられて、はっとした。
そう、FBに度々訪れ、民俗に関心を持たれている川西町結崎にある大念仏・融通念仏衆 萬福山超圓寺の執事・徳野良裕氏であった。
展示見学に、わざわざお越しいただいた人たち。
徳野良裕氏は、六斎念仏鉦を調べている私を先生と呼ぶ。
まさかの先生呼びであるが、論文を執筆しているワケでもない、あくまで肩書は民俗写真家。
あるていど、というか。
ひとさま(※他人さま)より、ほんのちょっとは知しっているというレベルの私に、なんと手土産持参で来られた。

過去、何度か、同様に手土産をいただいたことがある。
お返しは、民俗行事の解説に替えて・・・
写真家たちが、それぞれ展示されている作品に一つ、一つ、作者の思いも含めて、丁寧(※にしたつもり)にさせていただいた。
順に、解説したラスト映像は、動画も収録された安堵町・寺垣内で行われた最後の営み。
映像にかつて取材させていただいた東安堵の大寶寺六斎講。
取材当時の代表のお顔もあった作品は「最後の営み」。
収録後に解散された念仏講の人たちの姿をとらえていた作品の出展者は、當麻武氏。
初の展示に、初の動画作品も写真展に華を飾った。
その解散話題から、話してくれた。
実は、私たちは川西町上吐田に住まいしているが、世話になっている寺院は、大念仏・融通念仏衆 萬福山超圓寺ですが、まったく別の組織である講が、今度の営みが最後、と伝えられた。
お逢いした講中のUさんの話しによれば、6軒で営みをしているそうだ。
その講は「センゲンサン」。
富士の山こと、浅間(※せんげん)さんを崇敬する講。
同一名称のセンゲンサン。
奈良市古市の講の営みを取材したことがある。
いつからはじまったのか、わからないが、上吐田のセンゲンサン行事は、最後の営み。
二日後の3月13日に行われる。
集まる場は、講中のお家。
まわりの家にきてもらうが、所在地がわかり難いから上吐田の春日神社に来てもらいたい、といわれた。
春日神社の行事といえば、春祭りがある。
たまたまのご縁に、取材させていただいた平成25年の3月17日。
また、上吐田のとんど行事も・・・
たぶんに、奈良ではいちばん遅いニノ正月のとんど。
春祭りの1カ月前の平成25年2月15日。
雨天決行の情景が印象に残っているだけに、承諾を得て最後のセンゲンサン行事に伺うことにした。
ちなみに、本日ご一緒された、もう一人の方もご住職。
なんと、立地する場は存じている大和郡山市小泉町・融通念仏衆維摩寺(※ゆいまじ)のH住職。

ご縁が広がる当番日。
午後2時15分。
今、駐車場に着いた、と電話をかけてくれた方は、これまたなんと神社の宮司。
今から写真展を拝見するから、と伝えてくれた。
宮司は、父親の代からご縁繋がりの奈良市阪原町にお住いの太田和秀宮司。
平成30年3月4日、山添村大西で行われた稲荷神社の初午行事以来、しばらくご無沙汰している。
古民家写真展に合流することになったお二人。
正式衣装で並んだら僧侶と神職。
神仏混合のお二方が、同時に観てくださる。
こんな嬉しいことは二度もないでしょ、と伝えて、解説した私のテーマ「コロナ禍、そのときのT家は・・」。

それぞれの写真家たちがとらえた大和の民俗情景も、その撮影主旨や、見方のポイントを語った。
所用がある、と先に帰られた僧侶と講中にありがとうございました、と見送った。
ところで、と話し出した宮司は、撮影協力を願われた。
行事は、現在、コロナ禍で中断しているから、それではない。
撮影対象は、現在奈良県美術館に寄託保管していただいている五枚(※実際は六面であった)の古い能面(※文化財一覧によれば室町、桃山、江戸時代)である。
撮影は、当初、村の人が所有するデジタルカメラで収めようと、していたそうだ。
簡単に撮れると判断したが、素人では、えー写真にならん、と判断。
その代わりのお鉢に私の名前があがった。
指名したのは太田和秀宮司。
ありがたく受け止めたが、能面は極力移動させず、美術館内のある一角で撮影するらしい。
撮影は、本来ならスタジオ撮影。
影を出さないよう、細心の注意が要るどころか、ラインティングは少なくとも2台か、3台。
数台のストロボ装置に同期も要る。
なんせ、ちゃちゃっと撮れるものでもない。
しかも、撮った写真データは、村に寄託している奈良県美術館も提供。
保管され、展示する場合があれば、使用したい、という。
では、村ではどのように、である。
能面は、普段見ることはない。
ないが、手元(村および神社)に置いておかない、と代々が失念することも考えられる。
また、観光などで神社に来訪される人たちに、昭和30年に県指定された村の貴重な有形指定文化財の能面も伝えたい。
掲示する立て看板も新しくしたい、と・・・
撮影日も時間も、既に決まっていた有形指定文化財の撮影。
宮司は、2本のUSBを持参されるので、撮影後の当日預かり。
撮影すべてのデータと選択したデータをそれぞれのフォルダごとに収めて提出することにした。
とにかく、急ぐ撮影。
一日、一発でできあがるかどうか、心配はするが、美術館の学芸員とともにする作業だけに、ま、なんとかなるだろう。
なお、駐車場は、県警東側の駐車場に停めてください、とこれも指示があった。
(R4. 3.11 SB805SH 撮影)