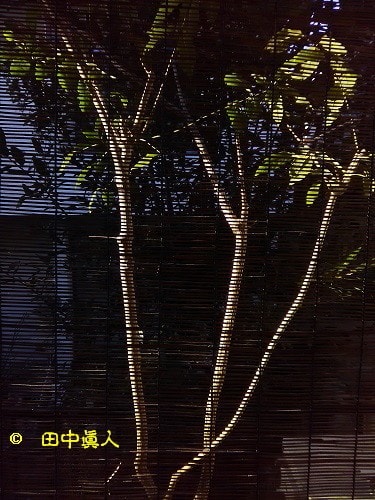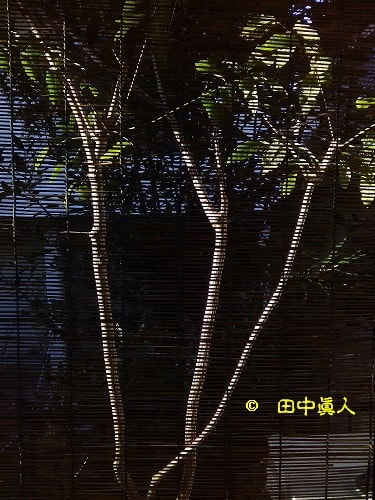冬のセンリョウ(※千両)の実は、赤い色。
6月初旬に淡く薄い緑色の蕾をつけ、初夏にはちっちゃい粒のような淡いピンク色の花が咲く。
それから数週間後。
7月半ばの状態は、数珠のような緑色の実に変化する。
10月半ばになって、緑色だった実は、色づきはじめ、見ごろの赤い実になる。
大晦日になれば、赤い実をつけたセンリョウを、わが家のしめ縄に飾る。
例年のこの頃ともなれば、中庭に植えているセンリョウ(※千両)は、すっかり赤い実を落としているはず。
ずいぶん少なくなったが、まだまだ落下もせずに実つけているセンリョウ(※千両)。
いつもなら、あっちこちから飛んでくる野鳥が、啄んで、すっかり消えているはずなのに・・
今年のセンリョウ(※千両)は、いつもと様相が違う。
ある年なんか、酷かった。
しめ縄に飾ろうと思っていたセンリョウが、晦日の日に全滅。
なーんもない、常緑樹の葉っぱばかりのセンリョウ。
こんな状態になるなら、ちょっと前にでも伐ってあげて一輪挿しにでもしてたら・・・と、悔やんでも仕方ない。

この一輪挿しのセンリョウは、大晦日のしめ縄に飾った余りもの。
赤い実がついた状態のセンリョウ、もったいないから、トイレを飾ってもらった。

正月を迎え、年明け後。
3週間以上にもなる赤い実付きのセンリョウ。
過去にもトイレ飾りにセンリョウを挿したことはあるが、この時期くらいになれば、ポロッ、ポロッ、ポロッと、毎日のように落実する状態だった。
妙なことに、萎れも、落実もしない赤い実。
いつまでもつんだろうか、と思い赤い実付きのセンリョウを観察することにした。
あれから3カ月も経ったトイレの花一輪。
いや、違った赤い実。
やや衰えたようにも見えるが、これらどれ一つも落実せずに生き残ってきた。
不思議なセンリョウだ。

ところが、この日の朝になって、やっと一つが、ポロリと落ちていた。
さらに1カ月を経たセンリョウ。
そろそろ終焉を迎える時期がきた。
毎日に用足しするトイレ。

その都度、観察してきたセンリョウ。
数週間前からは赤い実がポロポロ落ちるようになった。
右の実は、黒ずみ、少し萎んだような・・。
ただ、葉っぱの形容はほとんど変わり映えしない。
ここ数日の間に、すべてが落ちた奇跡のセンリョウ。
昨年の晦日から数えること半年間も、愉しませてくれたセンリョウを見送った。
(R3.12.29 SB805SH 撮影)
(R4. 1.21 SB805SH 撮影)
(R4. 4.19 SB805SH 撮影)
(R4. 5. 6 SB805SH 撮影)