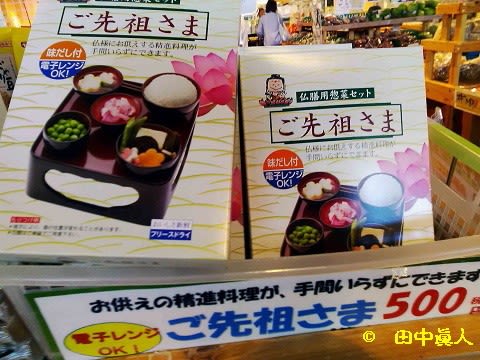民俗調査に訪れた三重県名張市。
お目当ての行事は変貌しいていた。
その代わりではないが、お家に祀っているえべっさんに干し鯛をかけると話してくださった。
その姿は、カラカラに乾いた二尾の干し鯛。
これまで拝見してきた事例から推測できる、それはカケダイ。
在所の情景にある民家は旧家が多いように思えた地区。
その帰りに立ち寄った大手スーパーはイオン。
そのイオングループにあるザ・ビックエクスプレス夏見橋店。
ひと通り巡って今夜のおかずを買った。
レジ支払いに済ませた店舗の壁にかけていた藁つくりのしめ縄。
この形はみたことがある。
著者の森須磨子氏が出版された『しめかざり』に載っている脚がある馬型しめ縄が、まさか、この店で売っていたとは・・。
奇遇な出会いに感動を覚えたえびす馬型しめ縄。
お家に飾るしめ飾り。
実は、平成29年5月11日にふきだわら御供の民俗取材に訪れた三重県伊賀市・下阿波のM家に祭っていた。
1カ所でも見つかれば、その地域にしている、と考えられる馬型しめ縄。
大晦日から正月三が日にかけて調査したいものだ。
(R3.12. 8 SB805SH 撮影)
お目当ての行事は変貌しいていた。
その代わりではないが、お家に祀っているえべっさんに干し鯛をかけると話してくださった。
その姿は、カラカラに乾いた二尾の干し鯛。
これまで拝見してきた事例から推測できる、それはカケダイ。
在所の情景にある民家は旧家が多いように思えた地区。
その帰りに立ち寄った大手スーパーはイオン。
そのイオングループにあるザ・ビックエクスプレス夏見橋店。
ひと通り巡って今夜のおかずを買った。
レジ支払いに済ませた店舗の壁にかけていた藁つくりのしめ縄。
この形はみたことがある。
著者の森須磨子氏が出版された『しめかざり』に載っている脚がある馬型しめ縄が、まさか、この店で売っていたとは・・。
奇遇な出会いに感動を覚えたえびす馬型しめ縄。
お家に飾るしめ飾り。
実は、平成29年5月11日にふきだわら御供の民俗取材に訪れた三重県伊賀市・下阿波のM家に祭っていた。
1カ所でも見つかれば、その地域にしている、と考えられる馬型しめ縄。
大晦日から正月三が日にかけて調査したいものだ。
(R3.12. 8 SB805SH 撮影)