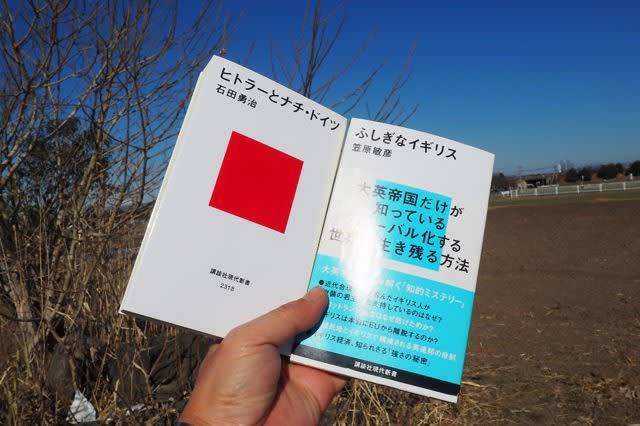
(知の空間を少し拡げるための読書がつづき、こういった領域へも関心がのびている)
■岩井克人「二十一世紀の資本主義論」ちくま学芸文庫2006年刊
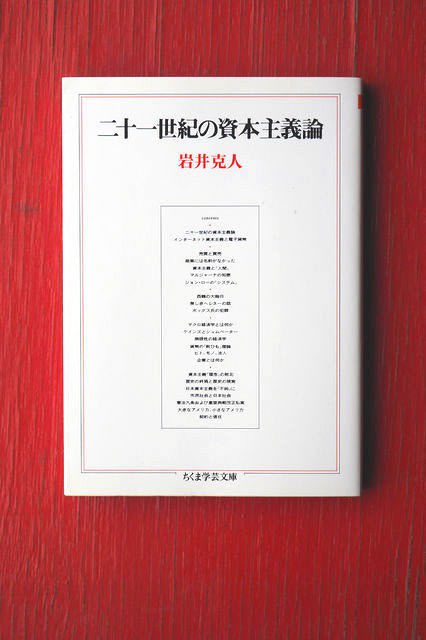
刊行された直後に読んでいたら、いまより遙かにインパクトがあったろう。いや、いまでも十分インパクトをもっている。
本書を読んでから、世の中に対する見方が変わった。経済学にかんして無知な人なら、こういった分析に驚きを隠せないだろう。
理路整然とした、説得力のある秀逸な論攷である。
わたしが手に入れたのは第7刷りなので、この手のお堅い本としてはけっこう読まれている。無知なヤカラたるわたしは、岩井克人さんがどういう方なのか、数ページ読んでから、あわててWebを検索した(^^;)
裏表紙にある本書の内容紹介は、つぎのようなもの。
《グローバル市場経済にとっての真の危機とは、金融危機や恐慌ではない。基軸通貨ドルの価値が暴落してしまうグローバルなハイパー・インフレーションである。しかし、自由を知ってしまった人類は好むと好まざるとにかかわらず、資本主義の中で生きていかざるをえない。21世紀の資本主義の中で、何が可能であり、何をなすべきかを考察し、法人制度や市民社会のあり方までを問う先鋭的論考。》
このほかに「ヴェニスの商人の資本論」「貨幣論」があり、いずれもちくま学芸文庫に収録されている。
資本主義の根幹には貨幣がある。有無をいわさず、何もかもが、貨幣に換算される。そんなことはだれでも知っている。しかし、このように貨幣の本質を明快かつ論理的に解き明かした人は、ほかにいないのではないか?
本論たる「二十一世紀の資本主義論 –グローバル市場経済の危機」のほか、「西鶴の大晦(おおつごもり)」「美しきヘレネーの話」等の二十を超えるエッセイからなっているがわたしにとっては「目からウロコ」の連続だった。
資本主義の究極の論理を突きつめていくいと、そこに商品が、そして貨幣がある。マルクスの思想やケインズの想定を超えた、21世紀を見据えた貨幣論の白眉、疑いない秀作である。
■水野和夫「過剰な資本の末路と、大転換の未来」徳間書店2016年刊
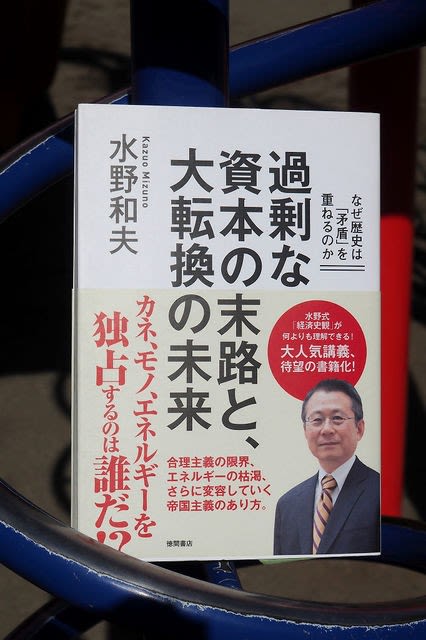
水野さんの本は、対談までふくめると、これが4冊目となる。水野さんの考え方がわかってきたため、ページをめくるのがもどかしいほどスリリングでおもしろい。
本書は東洋英和女学院大学院でおこなわれた連続講演がもとになっているという。
表紙には水野式「経済史観」の見出しがある。
全8章からなっているので、そのINDEXを引用しよう。
1.先進国の過剰と途上国の欠乏
2.近代以降における合理主義の確立と限界
3.科学革命が引き起した株式資本主義の誕生
4.なぜ先進国は集中的に富を得ることができたのか
5.白日のもとに露呈する近代の限界と矛盾
6.帝国のイデオロギーであるグローバリゼーション
7.利潤率の上昇につながらない二十一世紀の帝国
8.超低金利時代は成長が終った証
学術論文ではなく、大学院での講演記録に加筆・修正をくわえたものだけに、ビギナーにはたいへんわかりやすい(^^)/
本書を読んで、わたしはますます水野さんのファンになった。肩書きはエコノミストだが、どうやったらお金がもうかるか、損をしないかを教えてくれる俗流エコノミストではない。
非常に広い視野から、現代という時代を鋭く分析。そのメスさばきに、わたしはしびれた。
しかも、“近未来を見据えるための現状分析”であるところが、この人の身上。
資本主義は今後百年あるいはもっと長い過渡期をへて、終焉を迎えることになるのか?
水野さんの豊富な学識をバックにした思考には、読者を深くうなずかせるものがある。
枠組みが大きすぎて、肌理の粗い観念論に陥る危険がありそうだが、そのあたりの手際がじつにうまくいっている。
かつては民主党政権のブレーンのお一人だったようだが、水野さんの持論に耳を傾けていると、資本主義の限界と、そのさきの世界が何となく透かし見えてくる。
「そうか、そうなのか!?」
温厚篤実な印象をあたえるこの人の思想の核心には、いわばラディカルなヒューマニストが潜んでいるのではないか・・・。
それほど著作は多くはないようだが、とりあえず、このあと、二冊の本をスタンバイさせてある。水野さんからは今後も眼が離せないという意味で、本書を読むことで、わたしの重要なキーワードにランクインした。
こういう経済学者が存在することに、なぜもっと早く気が付かなかったのか(*_*)
■池田清彦「進化論の最前線」インターナショナル新書(集英社)2017年刊
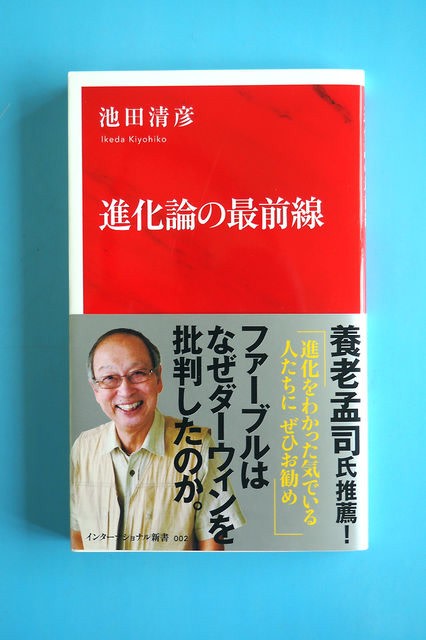
池田さんのお名前は以前から存じ上げていた。養老孟司さん、奥本大三郎さんとの鼎談「三人寄れば虫の智恵」を斜め読みした記憶がある。
本書は「進化論の最前線」というタイトルにとても忠実な内容になっている。
全7章の表題を掲げよう。
1.ダーウィンとファーブル
2.進化論の歴史
3.STAP細胞は何が問題だったのか
4.ゲノム編集がもたらす未来
5.生物のボディプラン
6.DNAを失うことでヒトの脳は大きくなった
7.人類の進化
“あとがき”をくわえ、189ページの小冊子みたいな本。しかし、押さえるべきところはきっちりと押さえてあり、遺伝子の最新研究までカヴァーし、iPS細胞とSTAP細胞をめぐる初歩的な知識まで易しく説いているので、進化論に興味のある人なら、学ぶべきことがこの小冊子の中に集約されているといえる。
生物とはなにか、生命現象の本質とは?
こういう疑問にまったく関心がないという人はいないはずである。小難しい議論に終始しているのではない。
《1953年にジェームズ・ワトソンとフランシス・クリックの二人によって、「DNAの二重らせん構造」が発見されて以来、人類はDNAに関連づけて進化の研究を発展させてきました。しかし、「なぜ進化は起こるのか」といった原因を突きとめるまでには至っておらず、もちろん科学の力で生物を別の種に進化させるという技術も開発できてはいません。進化に関しては、いまだ解明できていない謎が数多く残っているのです。》(本書89ページ)
高校時代以来、はじめて「生物進化」に関心をもったという人が読んでもわかるように書いてある。分厚いハードカバーの本ではなく、一般のビジネスマンが読んでも理解可能なレベル・・・それが、おそらく新書という形式の最大の効用といえるだろう。興味がわいたら、つぎのステップ、つぎの本へとすすめばいいのである。日本では山中伸弥さんがiPS細胞研究でノーベル賞を受賞したことによって、また世間を騒がせたSTAP細胞の論文捏造問題によって、この分野への一般の関心が高まっている。
地球環境は、なぜ人間=現世人類を生み出すにいたったのか? わたしは高校生のころから、それが不思議で仕方なかった。
簡単にいえば、人類はたまたま無数の偶然が重なった結果この地球に誕生したのか、それとも生命進化の必然として誕生したのか、ということである。
ミトコンドリアDNAの塩基配列を解析して、約20万年前、ミトコンドリア・イヴがアフリカで誕生したという仮説が発表されたときは多くの反響を呼んだ。
何かがわかると、つぎにまた新たな謎が生まれる。人間の胎児が系統発生をたどるということも、わたしにとっては、ワクワクするような“大いなる謎”であった。
この本は、現代科学が解き明かしてきたこと、解き明かせないことを・・・その境界線がいまどこにあるかを教えてくれる(^^)/
ゲノム編集というテクノロジーを手にした人間は、いわば「神の領域」へと挑戦しつつあるのだ。
そういったテクノロジーが、遺伝子組み換えをやって、新しい農産物を創生したり、遺伝子治療をおこなったりしているあいだはさしたる不都合はない。
しかし、核エネルギーをめぐる歴史的な推移を視ていると、人間は一度手にしたテクノロジーは決して手放すことがないのをみればわかるように、いずれ生命現象をコントロールし、いきつくところまでいくだろう、たとえその先にカタストロフィーが待っているとしても。
わたしが見つくろったこの三冊は、どれも“大当たり”の籤・・・みたいなものであった。
むろん、ハズレがあるから、大当たりもある。羊頭狗肉もある(^^;) それはそれで仕方ないことである。日本語だけに限定したとしても、何しろ、毎年気が遠くなるような膨大な本が出版されている。
選んだものが意に満たないものであっても、文句はいわないことにしよう、と自分にいいきかせているが・・・。
■岩井克人「二十一世紀の資本主義論」ちくま学芸文庫2006年刊
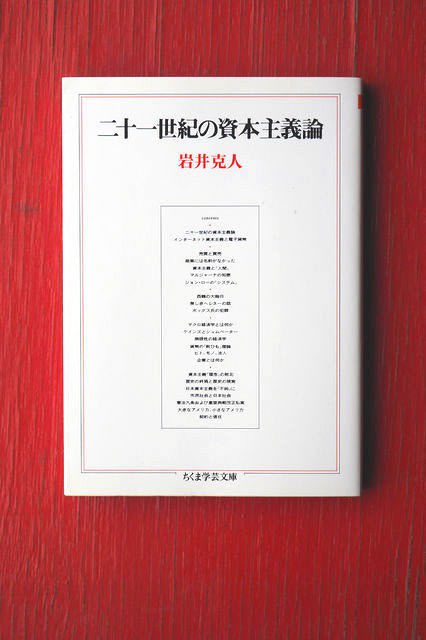
刊行された直後に読んでいたら、いまより遙かにインパクトがあったろう。いや、いまでも十分インパクトをもっている。
本書を読んでから、世の中に対する見方が変わった。経済学にかんして無知な人なら、こういった分析に驚きを隠せないだろう。
理路整然とした、説得力のある秀逸な論攷である。
わたしが手に入れたのは第7刷りなので、この手のお堅い本としてはけっこう読まれている。無知なヤカラたるわたしは、岩井克人さんがどういう方なのか、数ページ読んでから、あわててWebを検索した(^^;)
裏表紙にある本書の内容紹介は、つぎのようなもの。
《グローバル市場経済にとっての真の危機とは、金融危機や恐慌ではない。基軸通貨ドルの価値が暴落してしまうグローバルなハイパー・インフレーションである。しかし、自由を知ってしまった人類は好むと好まざるとにかかわらず、資本主義の中で生きていかざるをえない。21世紀の資本主義の中で、何が可能であり、何をなすべきかを考察し、法人制度や市民社会のあり方までを問う先鋭的論考。》
このほかに「ヴェニスの商人の資本論」「貨幣論」があり、いずれもちくま学芸文庫に収録されている。
資本主義の根幹には貨幣がある。有無をいわさず、何もかもが、貨幣に換算される。そんなことはだれでも知っている。しかし、このように貨幣の本質を明快かつ論理的に解き明かした人は、ほかにいないのではないか?
本論たる「二十一世紀の資本主義論 –グローバル市場経済の危機」のほか、「西鶴の大晦(おおつごもり)」「美しきヘレネーの話」等の二十を超えるエッセイからなっているがわたしにとっては「目からウロコ」の連続だった。
資本主義の究極の論理を突きつめていくいと、そこに商品が、そして貨幣がある。マルクスの思想やケインズの想定を超えた、21世紀を見据えた貨幣論の白眉、疑いない秀作である。
■水野和夫「過剰な資本の末路と、大転換の未来」徳間書店2016年刊
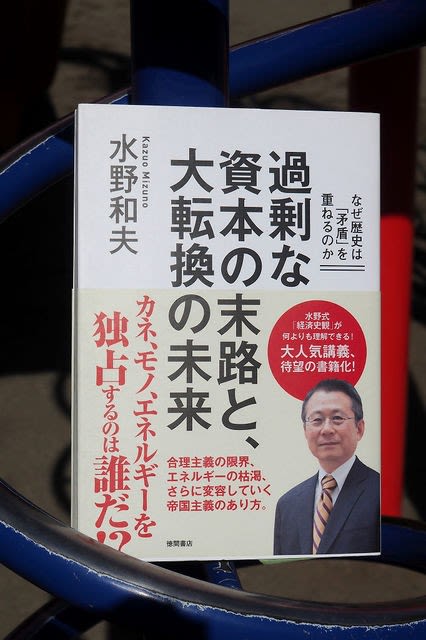
水野さんの本は、対談までふくめると、これが4冊目となる。水野さんの考え方がわかってきたため、ページをめくるのがもどかしいほどスリリングでおもしろい。
本書は東洋英和女学院大学院でおこなわれた連続講演がもとになっているという。
表紙には水野式「経済史観」の見出しがある。
全8章からなっているので、そのINDEXを引用しよう。
1.先進国の過剰と途上国の欠乏
2.近代以降における合理主義の確立と限界
3.科学革命が引き起した株式資本主義の誕生
4.なぜ先進国は集中的に富を得ることができたのか
5.白日のもとに露呈する近代の限界と矛盾
6.帝国のイデオロギーであるグローバリゼーション
7.利潤率の上昇につながらない二十一世紀の帝国
8.超低金利時代は成長が終った証
学術論文ではなく、大学院での講演記録に加筆・修正をくわえたものだけに、ビギナーにはたいへんわかりやすい(^^)/
本書を読んで、わたしはますます水野さんのファンになった。肩書きはエコノミストだが、どうやったらお金がもうかるか、損をしないかを教えてくれる俗流エコノミストではない。
非常に広い視野から、現代という時代を鋭く分析。そのメスさばきに、わたしはしびれた。
しかも、“近未来を見据えるための現状分析”であるところが、この人の身上。
資本主義は今後百年あるいはもっと長い過渡期をへて、終焉を迎えることになるのか?
水野さんの豊富な学識をバックにした思考には、読者を深くうなずかせるものがある。
枠組みが大きすぎて、肌理の粗い観念論に陥る危険がありそうだが、そのあたりの手際がじつにうまくいっている。
かつては民主党政権のブレーンのお一人だったようだが、水野さんの持論に耳を傾けていると、資本主義の限界と、そのさきの世界が何となく透かし見えてくる。
「そうか、そうなのか!?」
温厚篤実な印象をあたえるこの人の思想の核心には、いわばラディカルなヒューマニストが潜んでいるのではないか・・・。
それほど著作は多くはないようだが、とりあえず、このあと、二冊の本をスタンバイさせてある。水野さんからは今後も眼が離せないという意味で、本書を読むことで、わたしの重要なキーワードにランクインした。
こういう経済学者が存在することに、なぜもっと早く気が付かなかったのか(*_*)
■池田清彦「進化論の最前線」インターナショナル新書(集英社)2017年刊
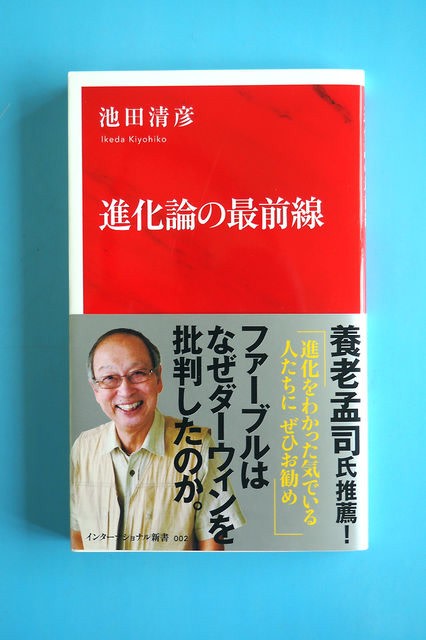
池田さんのお名前は以前から存じ上げていた。養老孟司さん、奥本大三郎さんとの鼎談「三人寄れば虫の智恵」を斜め読みした記憶がある。
本書は「進化論の最前線」というタイトルにとても忠実な内容になっている。
全7章の表題を掲げよう。
1.ダーウィンとファーブル
2.進化論の歴史
3.STAP細胞は何が問題だったのか
4.ゲノム編集がもたらす未来
5.生物のボディプラン
6.DNAを失うことでヒトの脳は大きくなった
7.人類の進化
“あとがき”をくわえ、189ページの小冊子みたいな本。しかし、押さえるべきところはきっちりと押さえてあり、遺伝子の最新研究までカヴァーし、iPS細胞とSTAP細胞をめぐる初歩的な知識まで易しく説いているので、進化論に興味のある人なら、学ぶべきことがこの小冊子の中に集約されているといえる。
生物とはなにか、生命現象の本質とは?
こういう疑問にまったく関心がないという人はいないはずである。小難しい議論に終始しているのではない。
《1953年にジェームズ・ワトソンとフランシス・クリックの二人によって、「DNAの二重らせん構造」が発見されて以来、人類はDNAに関連づけて進化の研究を発展させてきました。しかし、「なぜ進化は起こるのか」といった原因を突きとめるまでには至っておらず、もちろん科学の力で生物を別の種に進化させるという技術も開発できてはいません。進化に関しては、いまだ解明できていない謎が数多く残っているのです。》(本書89ページ)
高校時代以来、はじめて「生物進化」に関心をもったという人が読んでもわかるように書いてある。分厚いハードカバーの本ではなく、一般のビジネスマンが読んでも理解可能なレベル・・・それが、おそらく新書という形式の最大の効用といえるだろう。興味がわいたら、つぎのステップ、つぎの本へとすすめばいいのである。日本では山中伸弥さんがiPS細胞研究でノーベル賞を受賞したことによって、また世間を騒がせたSTAP細胞の論文捏造問題によって、この分野への一般の関心が高まっている。
地球環境は、なぜ人間=現世人類を生み出すにいたったのか? わたしは高校生のころから、それが不思議で仕方なかった。
簡単にいえば、人類はたまたま無数の偶然が重なった結果この地球に誕生したのか、それとも生命進化の必然として誕生したのか、ということである。
ミトコンドリアDNAの塩基配列を解析して、約20万年前、ミトコンドリア・イヴがアフリカで誕生したという仮説が発表されたときは多くの反響を呼んだ。
何かがわかると、つぎにまた新たな謎が生まれる。人間の胎児が系統発生をたどるということも、わたしにとっては、ワクワクするような“大いなる謎”であった。
この本は、現代科学が解き明かしてきたこと、解き明かせないことを・・・その境界線がいまどこにあるかを教えてくれる(^^)/
ゲノム編集というテクノロジーを手にした人間は、いわば「神の領域」へと挑戦しつつあるのだ。
そういったテクノロジーが、遺伝子組み換えをやって、新しい農産物を創生したり、遺伝子治療をおこなったりしているあいだはさしたる不都合はない。
しかし、核エネルギーをめぐる歴史的な推移を視ていると、人間は一度手にしたテクノロジーは決して手放すことがないのをみればわかるように、いずれ生命現象をコントロールし、いきつくところまでいくだろう、たとえその先にカタストロフィーが待っているとしても。
わたしが見つくろったこの三冊は、どれも“大当たり”の籤・・・みたいなものであった。
むろん、ハズレがあるから、大当たりもある。羊頭狗肉もある(^^;) それはそれで仕方ないことである。日本語だけに限定したとしても、何しろ、毎年気が遠くなるような膨大な本が出版されている。
選んだものが意に満たないものであっても、文句はいわないことにしよう、と自分にいいきかせているが・・・。



























