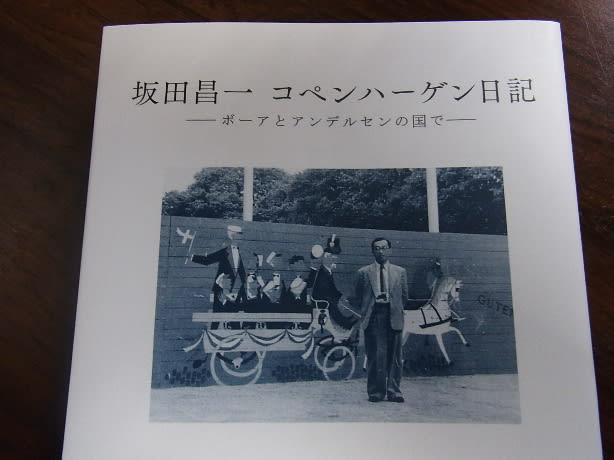8時、起床。昨日の風雨が嘘のようによく晴れている。ブログを更新してから、TSUTAYAにDVD(『SP 革命篇』を昨夜観た)を開店前に返却に行き、帰りに東口のドトールでモーニングセット(ジャーマンドッグとブレンド)の朝食。
妻と吉祥寺に出かける。娘の属してる「ドラマチック・カンパニー・インハイス」の公演を観るためである。12時に吉祥寺に着き、差し入れ用のおこわご飯などを購入し、ぶらぶら歩きながら、「櫂スタジオ」に12時半頃到着。


「灰」(作・演出 左観哉子)は3人芝居である。ジ・エンド・オブ・ザ・ワールドの物語である。空間的には世界の果て。舞台はどこかの島である。本土との連絡船はもうない。時間的には世界の終り。
西の本土から真っ黒な煙があがった
翌朝、冷たい雨が降って島中を濡らした
煙と同じ真っ黒な雨、・・・
それは世界を終らせる雨だと誰かが言った
雨に打たれたものは、遠からず、身体が腐って死ぬといいました
島の人は、最初は、笑っていた。そんなことあるもんか、どうせたいしてことないといって、・・・
だけどあの煙から一年が過ぎた頃、みんながあの煙を忘れ始めた頃に、ひとり、またひとり・・・、島人はバタバタと倒れて行きました
最初、目から腐るんです
目は、柔らかいからね、
じょじょに皮膚が腐って、苦しんで、異臭が放って、・・・
若い女の子たちは儚んで、岬から身を投げました
逃げ出す人、自殺する人、島人はそのふたつにわかれました
そしてついにこのように、島には私たちだけとなりました、・・・
『灰』が今回の原発事故を踏まえた作品であることは明らかだ。核爆発による世界の終りを描いた作品は多い。ただ、その多くは核爆発=核戦争であった。そして核戦争による世界の終わりの後には、生き残った人々や新種の人類(ミュータント)による世界の再生が待っている。第一幕の終り、第二幕が始まるのだ。しかし、『灰』にはそうした再生がない。世界はただ終るのである。静かに終るのである。ここで語られるのは未来ではなく、過去である。
月が出る。雲が薄れて、月が、・・・
思い出話をしよう
愛し合ったひとたちのように
遠い日の思い出を
世界は終ったというのに、どうして私たちは立っているのでしょう、・・・
男は女を殺した。愛する女の片目が腐り始めたからだ。
痛い
痛い?
目が、目が痛い
ナギ
溶けた、あたしの目がとけたあ! いやだ、あたし死ぬんだ、腐って死ぬんだ、殺して、殺して、いやよ腐って死ぬなんていや、あんたが殺して、殺して、・・・!
ナギ
この場面は三度現われる。愛し合った者たちの間に起こった悲しい出来事が三度語られる。物語の時間は前には進まず、現在と過去の間を反復する。
どうして私は生きているのか
世界は終ったというのに、・・・
どうして私は生きているか、・・・
彼らが本当に生きているのかは定かではない。もしかしたら、すでに死んでいて、思念だけが残っているのかもしれない。いや、やはり、彼らは生きているのだろう。打ちのめされて、未来の時間を奪われたまま、生きているのだろう。私の頭の中には、増田常徳の「黒い海」があった。彼も今回の震災をモチーフにして絵を何枚も書いている。暗く、重く、救いのないような絵である。しかし、絵の中の人間は生きている。絶望に打ちのめされているが、生きている。果たして再生があるのかどうか、定かでないが、もし再生があるとすれば、とことん絶望に打ちのめされた、その先にしか、それはないのだろう。安易な再生の物語を拒否する強い(そう、強いのだ)意志がそこには感じられる。『灰』もまた観る者をとことん打ちのめす。かけがえのものを失ってしまった人間の悲しみをこれでもかこれでもかと訴える。観客は、「もうわかった。やめてくれ」とjは言わずに、黙って舞台を観ていた。再生を期待できないことはわかっているが、黙って舞台を観ていた。レクイエムのような役者たちの言葉にじっと耳を傾けていた。芝居が終ったとき、誰もが心からの拍手を送った。

芝居の後に、朗読があった。それは一転して、祈りに似ていた。
わたしたちが、わたしたちにより汚した空気を吸っても、わたしたちが吐く息がきよくさえていることを わたしたちが わたしたちにより汚した水を飲んでも わたしたちのこの声がきよらかに かなしみをみそいでいくことを わたしたちが わたしたちにより汚れた心にふれたとしても わたしのあなたへの想いがいつもうるわしくあるように 愛といつくしみを 愛といつくしみを、・・・わたしのいのりがあなたに届きますように
それにしてもだ・・・、普通の父親は娘のラブシーンを見る機会はないであろう。私は、今日、三度、娘のラブシーンを見た。それも、おでこにチュとかのかわいらしいものではない。吉祥寺の駅に戻る途中、「はらドーナツ」で一服した。妻も、「三度はきつかったわね」と言った。「うん」と私は答えた。ジ・エンド・オブ・ザ・ワールド。子供期の終り。