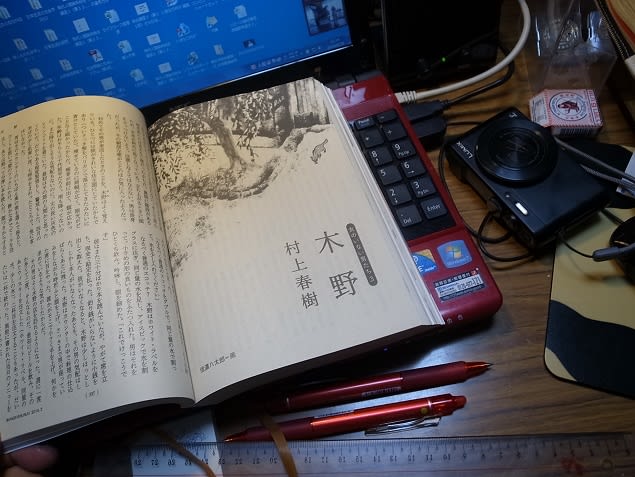7時半、起床。
スコッチエッグ(大野屋)、クリームパン(金谷ホテルベーカリー)、豆乳入りロールパン、スープ(昨夜の鶏団子汁の残り)、紅茶の朝食。朝から高カロリーの食事なり。


昼から大学へ。
有楽町で途中下車して、「竹葉亭」で昼食をとる。この店の鯛茶漬けをときどき食べたくなる。


最初、1階のテーブル席に案内されたが、2階の畳席を所望する。外から窓際の席が空いているのが見て取れたからである。ここが「竹葉亭」(銀座店)の特等席である。


ご飯は小ぶりの茶碗で3杯は食べられる。
一杯目はお茶漬けにしないで、鯛の刺身そのもので。

二杯目は鯛茶漬けで。

三杯目はお新香のお茶漬けで。

デザートは柚子のシャーベット。ごちそうさまでした。

研究室で夕方までレポートの採点作業。
夕方から「カフェ・ゴトー」で句会(第三回)。 今回はいままでで最多の7名が参加。主宰の紀本さん、私、校正者のT氏、文化構想学部の助手のMさん、コピーライターのMさん、初参加で私の教え子(一文の卒業生)のTさん、同じく初参加でMさんの小学校以来の友人のKさん。
あらかじめ参加者は紀本さんにメールで俳句(3句)を送っている。それを紀本さんが一枚の紙にまとめて、人数分コピーしてくれていた。さっそく選考が始まる。21作品の中から各人が順位(天・地・人)を付けて3句を選ぶ。天=5点、地=3点、人=1点として、全員の合計点を出す。仮に7人全員が同じ作品を天に選んだとしたら、5点×7人=35点となるわけであるが、今回は分散した。


入選作品(誰か一人でも選んだもの)は以下の13句(作者は選・講評が済んだ時点で明らかにされる)。
10点 生きる意味を問うこともなく冬銀河 (私)
冬苺二人の姪の手から手へ (助手のMさん)
8点 シュプールの正弦曲線消えやらず (校正者のTさん)
6点 はずかしくとけたくしろくあわいゆき (紀本さん)
寒鰤(かんぶり)の一点盛りの潔さ (私)
5点 猫眠るもういくつめの除夜の鐘 (助手のMさん)
我が孫の顔思い出すふくわらい (コピーライターのMさん)
4点 冬晴れの思いもかけぬ別れかな (私)
3点 寒空(さむぞら)割るはだかの血管落葉樹 (卒業生のTさん)
ランナーの数だけ走る冬木立 (助手のMさん)
1点 厚さみて幸数えてる年賀状 (Kさん)
吐く息のかおりに溶ける白雑煮 (Kさん)
丸文字の絵馬に祈る初受験 (コピーライターのMさん)
私と助手のTさんが特選となる。
私自身は、「冬苺・・・」を天、「はずかしく・・・」を地、「猫眠る・・・」を人に選んだ。3句中2句が助手のMさんの句だったわけだ。波長が合ったということだろう。「冬苺・・・」を評価したのは動きのある句だったから。一般に俳句はスナップショット的というか、一瞬を切り取った静止画的なものが多いわけだが、この句は「手から手へ」というところに動画的な印象を受けた。「はずかしく・・・」はたぶん紀本さんの句だろうと思ったが(実際そうだった)、「はずかしく」「とけたく」「しろく」と「く」が連続して韻を踏んでいて、最後の「あわいゆき」の「き」も同じくカ行の音だから、声に出して読むと心地いい。「猫眠る・・・」は谷内六郎の絵のような郷愁を感じさせる情景で大晦日の句としてふさわしいと思った。
自作解説をすると、「生きる意味を・・・」の句は、最初、「冬銀河」ではなく「冬の月」としていた。しかし、「冬の月」だと孤高の気分が強くなりすぎると思ったので、大きな宇宙を感じさせる「冬銀河」という言葉があることを歳時記を読んでいて知って、差し替えた。「生きる意味を問いかけてくる」という表現もチラリと考えたが、「意味」というものはもともと自然の中には存在しない要素で、むしろそういうものから人は解放される瞬間が必要なのではないかと思い、「問うこともなく」とした。「冬晴れの・・・」の句は、ある冬の晴れた日に突然に訪れた別れを読んだものだが、この別れは、離別と死別の二通りの解釈がありえると思っていたが、感想を聞いていると、やはり(男女の)離別ととらえた方と死別ととらえた方に分かれていた。私としてはどちらでもよいと思って作った。「寒鰤の・・・」は「たかはし」で実際に寒鰤の刺身定食を食べたときの情景を詠んだもの。寒鰤の刺身が好きな方には受けたようであるが、「一点盛り」の意味が通じなかった方もいたようである。
結果的に、 私の3句は全部が入選したわけだが、たぶん私の作風は短時間の(15分から20分程度)の選考には有利に働いているのではないかと思う。つまり、印象に残りやすい語句や言い回しが含まれているからというのが私なりの自己分析である。また、今回は安住敦を気取って、人生の感慨を句に込めてみたわけだが、それが共感を呼んだということだろう。元来、こうした趣向は短歌向きであって、俳句向きではないと思われている。それは安住敦の人気の理由でもあり、同時に、通俗的というか、歌謡曲の一節のようだと批判的に評される理由でもある。
主宰の紀本さんの感想では、句会も三回目になって、みなさん手練れてきましたねとのこと。これは正岡子規の言い方では、「月並み」な句が多くなったということである。「月並み」の「月」は「月例の句会」の意味で、それなりに上手ではあるが新味に欠けるということである。初心忘るべからず。
句回は1時間半ほどで終わって、場所を「五郎八」に移して食事会。
偶然だが、今夜の「五郎八」には長谷先生とそのお仲間の社会学者、那須先生のお弟子さんたち、と社会学者の占める割合が異様に高かった。早稲田社会学会「五郎八」部会か(笑)。




食事会が終わって、店の前=地下鉄の入口で解散したあと、卒業生のTさんと二人で「カフェゴト―」に食後のコーヒーを飲みに戻る。句会初参加の感想などを聞く(彼女がさっそく自身のブログで感想を書いているので、そちらを参照されたい)。
Tさんは私の研究室の掛け軸「単純な生活」を書いてくれた書家であるが、書と俳句というのは親和性がある。ブログを読んでもわかるとおり、言葉の感覚が研ぎ澄まされた人であるから、きっと俳句は向いていると思って、句会に誘ったわけだが、楽しんでもらえたようでよかった。今回は「寒空割るはだかの血管落葉樹」の一句が入選した。三句の中で一番思い入れが強い句だったそうだから、それが選ばれたのは嬉しかったに違いない。私はたぶんこの句はTさんの句だろうと思っていた。「寒空割る」も「はだかの血管」も強い表現の言葉で、私であれば一つの句に強い表現は重ねない(一つにしておく)ところだが、そうした抑制をしないところがTさんらしいと思った。ただし、TさんもTさんなりに抑制はしているので、それは「裸」を漢字でなく「はだか」と平仮名で表記した点である。はだかの(=本当の)自分を探究し、呈示することは、彼女の日々の生活のテーマなのである。

「カフェゴト―」には閉店の9時50分までいた。次回の句会は4月20日の日曜日である。春の俳句を作ることになる。