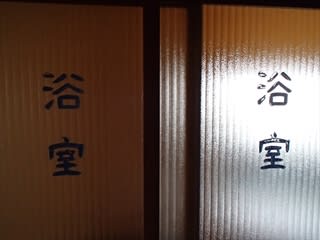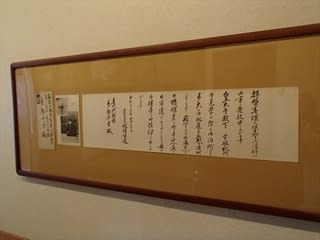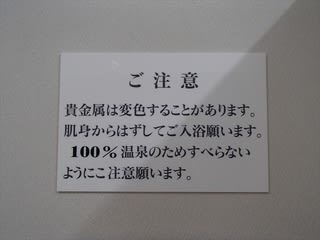前回記事では三重県熊野市の湯ノ口温泉を取り上げましたが、今回はその湯ノ口温泉へ向かうトロッコ列車について、もう少し細かく見ていきます。前回でも申し上げましたが、当地はかつて紀州鉱山として銅が採掘されており、鉱石運搬のための専用鉄道も運行されていたのですが、昭和53年に閉山されると鉱山鉄道も用済みになってしまいます。しかしながら、風光明媚な土地であることや、湯ノ口地区で温泉湧出が復活したこと等が機運になったのか、1987年に行われたイベントで奇跡的に復活し、1989年から通年運行されるようになったんだそうです。といっても復活したのは全区間ではなく、旧小口谷駅に位置する入鹿温泉「瀞流荘」と湯ノ口温泉駅(旧湯ノ口駅)の一区間のみですが、当時の線路をそのまま転用しているトロッコ列車は、そんじょそこらのお猿の電車とは一線を画する本格派であり、当時の様子に思いを馳せるには十分かと思います。
ま、そんな屁理屈はさておき、まずはスタート地点となる瀞流荘駅へ向かいましょう。
●瀞流荘駅


旧小口谷駅構内に設けられた瀞流荘駅は、その名の通り、入鹿温泉の旅館「瀞流荘」の目の前に位置しており、ここは鉱山鉄道の現役時代は広大なヤードであったため、山間にもかかわらず広大な敷地が広がっています。そんな広々とした中で、公園の休憩所みたいな木造の駅舎がポツンと佇んでいました。


とってもウッディーな建物でして、うららかな陽気に恵まれたこの日はドアや窓が全開放されていましたが、天井には天カセのエアコンが取り付けられていますので、季節に応じて空調管理されるようです。前回記事でも申し上げましたが、トロッコ列車で湯ノ口温泉へ向かうには、往復の乗車券と入浴料金がセットになっている「温泉・トロッコ電車セット券」がお得ですので、駅舎の窓口でその券を購入し、トロッコ列車の出発時間を待ちます。
なおトロッコ列車にはちゃんとダイヤがあり、本数も1日6往復と限られていますので、乗車希望の方は予め
公式HPで時刻表を調べておいた方が良いでしょう。


瀞流荘駅のホームは、小柄なトロッコ列車には不釣り合いな、妙に頑丈な上屋で覆われています。ホームには既に出発を待つ列車が入線しており、任意の車両に乗車できます。私は11:15発の列車に乗り込んだのですが、その列車の客は寂しい哉、私一人だけ。時間になると、先程チケットを発券してくださった係員の方が駅舎の窓口から出てきて、バッテリーロコのキャブに座ってマスコンを動かしました。


湯ノ口温泉駅までの約1kmは、中間の僅かな明かり区間を除けば、ほぼ全区間トンネル。出発して道路を横切ると、すぐにトンネルに入ってしまい、ひたすら真っ暗な車窓が続きます。軌間は日本の鉱山鉄道では一般的な610mmであり、現役時代の線路敷をそのまま転用しているためトンネル内は複線なのですが、現在は1本のトロッコが単純往復しているだけですので、片方の線路のみを単線使用しています。
トロッコはジョギングと大して変わらないほどのんびり走るのですが、プリミティブな車体構造と足回りのおかげで、振動と走行音が凄まじく、その大音響が背の低いトンネル内で反響するので、会話できないほどの轟音に包まれちゃいます。でもその振動と音こそが、鉱山鉄道のリアリティなんですね。メカ好きや乗り物好きの男子にとって、その大音響は興奮要素となるはずです。
●湯ノ口温泉駅

約8分の乗車で湯ノ口温泉駅に到着です。


湯ノ口温泉駅は橋の上に設けられており、立派な駅名標も取り付けられております。その駅名標にはかつての駅名である「小口谷」の名前が残っていますね。

更に奥にも線路が伸びており、デルタ状の配線を収束した直後に再びトンネルへと入ってゆくのですが、坑口から僅か数十メートルのところにフェンスが立ちはだかっているため、その奥には行けません。


上画像は湯ノ口温泉駅から瀞流荘駅を望んだ様子です。
さすがに現役の線路だけあって、坑道内の壁面は綺麗に整備されていますね。
●車窓の様子
湯ノ口温泉駅を出発してから瀞流荘駅に到着するまで、その全区間の車窓を録画しました。
ほとんどの区間がトンネルなので、正直車窓としては退屈なのですが、出発早々に辺りに響き渡る音と、線路の振動をモロに受ける車体の揺れを、おわかりいただけるかと思います。動画よりも実際に乗った方が、はるかにはるかに面白いんですけどね。
●機回し

トロッコ列車は機関車が客車を牽引して、一本の線路上を単純にピストン往復しているわけですが、列車が駅に着いたら折り返して元の駅へ戻るため、先頭の機関車を切り離して、最後尾へ付け替える必要があります。この作業のことを鉄道の世界では「機回し」と呼んでおり、某無料百科事典では動くイラスト付きでわかりやすく解説されていますが(
こちらを参照)、このトロッコ列車でもそれぞれの駅で機回しが行われております。
瀞流荘駅では複線の線路に渡り線(ポイント)を設け、普段客扱いしていない線路を機回し線にして、
某無料百科事典の動くgif画像で解説されているのと同じパターンで機回しが実施されています。
一方、湯ノ口温泉駅では、複線の線路敷があるにもかかわらず、すぐ先の線路が使えない状態であるため、ちょっと変わった方法で機回しをしています。その手順とは・・・
(1)駅に着いてお客さんを降ろした後、一旦瀞流荘駅へバック(推進運転)する。
(2)瀞流荘駅側のトンネルにトロッコ全体がすっぽり入ったあたりで停車。
(3)客車と機関車が切り離されると、機関車の目の前にあるポイントが側線側へ切り替えられ、機関車だけがその側線に入る。そして直後にポイントが正位(本線側)へ戻る。
(4)線路が緩やかな下りになっているため、客車は自然に(あるいはスタッフの手押しにより)駅のホームへと転がってゆき、これまた勾配の関係で、客車はホームで勝手に止まる(あるいはスタッフが腰にグイッと力を入れて車を停める)。
(5)側線にいた機関車は本線に戻り、ホームの方へ走っていって、客車と連結する。
こんな感じとなっています。機関者を側線に避けさせるのはわかるとしても、客車を自然の重力あるいは人力で動かすだなんて、とってもユニークです。
ご参考までに、これら2駅の機回しの様子を録画しました。もしよろしければご覧ください。
●バッテリー機関車


トロッコを牽引する機関車はバッテリーによって動くタイプのもので、鉱山鉄道が稼働していた時代から活躍している昭和46年・ニチユ(日本輸送機)製です。鉱山鉄道時代は全線電化されており、当時はパンタグラフで集電する機関車が働いていましたが、現在は架線が撤去されていますし、延々と低いトンネルが続く区間なのにディーゼル機関車を導入したら排ガスでお客さんが参っちゃいますから、復活に際しては当時のバッテリーロコに白羽の矢が立ったのでしょうね。


キャブに積まれているマスコンは一般的な電車と同じような立派なスタイルです。正面のボンネットっぽい部分にはバッテリー(GS蓄電池)が48個も積まれているんだとか。個人的には、ブレーキが丸ハンドルの手ブレーキである点に興味が惹かれました。自動車のような油圧でもなく、一般的な鉄道のように圧縮空気でも回生制動でもなく、人力によってハンドルをグルグル回して制動力を得るんですから、21世紀とは思えないほどローテクです。

キャブからの前方視界はこんな感じ。意外とスッキリしているじゃありませんか。
●客車


客車は復活に際して新たに製造されたんだそうですが、当時の鉱山列車風に再現されており、かまぼこ型の屋根を戴く客車の躯体は木造です。後部には黒いゴムの緩衝器が2つ取り付けられており、また車内照明のため、電線が引き通されています。


トロッコ車内の様子です。軌間が610mmしかありませんから、かなり狭く感じられます。車内の壁面は木目がむき出しになっており、ベンチには座布団が載せられ、窓にはガラスが嵌められています(窓はちゃんと開けられます)。木造ですから走行中は線路から伝わる振動をモロに受けてしまい、あちこちガタピシ鳴ってとっても賑やかでした。
●紀和鉱山資料館の展示車両

鉱山鉄道の起点であった板屋地区には紀州鉱山が稼働していた当時の様子を今に伝える「紀和鉱山資料館」があります。


入口に立つ看板の上には、鎚を振り上げる鉱山夫のモニュメントが立っていました。今回は時間の都合で資料館の内部を見学することができなかったのですが、屋外には当時の鉱山鉄道の車両が保存されているので、それらだけをササッと簡単に見学することに。


610とナンバリングされているこの車両は、電気機関車610号なのでしょう。車体と同じくらいに大きなパンタグラフが目を引きますが、上述のように紀州鉱山が稼働していた当時の鉱山鉄道は全線電化されていたので、このパンタで集電していたわけです。


610号キャブを覗いてみます。低い屋根で囲われたキャブは、右側と後方に窓が開けているものの、左側は完全に遮蔽されており、上下左右ともにスペースが限られているため、相当狭苦しそうです。マスコンは日立製で、その上に開閉器や各種スイッチが並んでいます。手ブレーキで制動するのは現在のバッテリーロコとほぼ同様のようですね。


軌間者の後ろには木造の客車と鉱石運搬用のかわいらしい貨車が並んでいました。運搬用索道も展示されていますね。現在の客車のモデルになった当時の客車も木造で、現在の車両以上にコンパクトであり、一見するとワム(有蓋貨車)のようでもあります。客車内には木のベンチが取り付けられていますが、とても狭いので、向かい合わせに座ると、膝が触れ合うどころか密着しちゃいそうです。現在のトロッコは窓にガラスが嵌め込まれていますが、当時は格子窓の吹きさらしだったんですね。


黄色いテントの下にはスイッチャーと思しき小さなバッテリーロコとレールバイクが前後に並んでおり、その後ろには小さなターンテーブルも設けられていました。ターンテーブルの先は資料館と一体になっている格納庫へ伸びているのですが、これが回転する機会ってあるのかな?
・トロッコ列車問い合わせ先
熊野市ふるさと振興公社
三重県熊野市紀和町湯ノ口10
0597-97-1126
湯ノ口温泉ホームページ
・熊野市紀和鉱山資料館
三重県熊野市紀和町板屋110-1
0597-97-1000
紀和鉱山資料館ホームページ