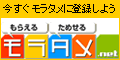8月3日(木)晴れ
昨日は娘と一緒にお台場へ。
音楽映画の『セッション』一夜限りのライヴ絶響上映の招待券が当たったから。
以前にこの映画を見て「よかったよ!」と言ってた娘は大喜び。
母はこの「ライヴ絶響上映」というものに一抹の不安を感じる。
説明書きによると・・・
スタンディングも歓声もOK。
ライヴハウスの音響で、通常の音楽ライヴと同様に楽しんでいただく上映スタイル
とあります。
マサラ上映のようなもの?
ま、何事も経験経験!
午前中ボランティア活動の例会を済ませから、お台場へ向かう。
以前は、「近いのに遠いお台場」というイメージだったが、バスという手段に気づいてから気持ちがぐんと楽になった。
「金子半之助」の天丼なぞを食してから会場へ。

スタンディング席の後ろに椅子席があり、そこの中央最前列に座る。
通常はライブ会場だからか仕方ないのか、スタンディングと椅子席の境が30センチほどの段になっており、
暗いせいもあり、ワタクシたちの前を通る人がその段差を踏み外す。
お一人の方は手にしていた飲み物を盛大にぶちまけておられたし、少々お年を召したおぢさまは「ををっっ!」と叫ばれた。
ワタクシはもう、みんなが着席するまで気もそぞろ。
なぜスタッフ一人くらい立って「こちら段差になっております!」と叫ばないのだ!?
あるいは、境目に柵を持ってきても良いではないか。
と、ひとしきり会場について母娘で語り合う。
ライヴ会場だからかよくわからんが、映画始まる前にMCの人が出てきて「ジンライム」だったかなんかを一気飲みするというよくわからんパフォーマンスと、絶響上映について説明した後、映画が始まる。
簡単に説明しますと・・・
世界的なジャズ・ドラマーを目指すニーマンと、名門音楽学校の伝説の鬼教師フレッチャーの壮絶なレッスンの日々を描いたものです。
どちらも、音楽に対する情熱が驚異的というか狂気的というか。
ワタクシ、自分がつくづく凡人で、性善説論者で、音楽家にも脚本家にもなれないということを痛感。
あ、ネタバレしますからね、見たいと思ってる方はここからは読まないでね。
フレッチャーの狂気じみた体罰バンバン精神的なダメージガンガン浴びせられながらのレッスンで、
ニーマンの精神も頂点まで張り詰めており、身心ともにボロボロになり退学。
教え子の自殺やらをリークされたフレッチャーも学校を辞めされられる。
ひょんなところで再会した二人は、和解し、フレッチャーはニーマンを自分のバンドのドラムに引き入れる。
そして、そのバンドで出た音楽祭で、フレッチャーはニーマンにだけ嘘の演目をいい、実際は違う曲をやる。
ここで性善説論者nは「これはおそらくフレッチャーの『お前なら入ってこられるだろう?』という期待によるものだろうと予想する。
だって、ジャズって自由なんでしょ?
ワタクシが脚本家ならそうする。
それゆえの、タイトル「セッション」だーーーっ!(駄作、間違いなし!)
しかし、そんな甘っちょろいワタクシの予想を裏切るように最後までニーマンはヘボ演奏を続ける。
そして、これはフレッチャーの、ニーマンにリークされた恨みを晴らすための復讐だったのだ。
一度はステージを去りかけるニーマンだったが、またドラムに戻って、フレッチャーを無視し「キャラバン」を演奏せざる得ない状況に持って行く。
驚き、戸惑い、苛立ちながらも指揮をするフレッチャー。
しかし、異常なスタートからかメンバーもすんごい演奏をする。
いや、わたしゃジャズは全くわからんが、おそらくすんごい演奏だと思う。
それまでは、この絶響上映の良さがわからず、ちょっと音、大き過ぎ!(「あなたを招待したのは間違いでした」主催者心の声)と思っていたが、
このラストの曲をここでこの音量で聞けたのはラッキーだったと思った。
しかし・・・いかんせん長い。
ドラム、長過ぎ!(ことごとく製作者の意に反している。ここが一番の見せ場なんだよっ!!!)
ワタクシ的には、すんごい演奏を作り上げたねっ!ってことでめでたしめでたし、で良いではないかと思ったのだが、
延々とドラムの演奏が続き、それまで怒り狂いながら、戸惑いながら指揮を振っていたフレッチャーが、だんだんと歓びへの表情へと変わっていく。
音楽に限らず、芸術家、いや、何かにのめり込む人たちのことがわからない。
つくづくワタクシは凡人。
そんなことを思い知らされながら見た映画だった。
そして、娘が小学生の頃に入ってた金管バンドのこととか思い出したりした。
彼女の所属してたバンドは、まあそれなりのレベルだったが、出場したコンクールで圧倒的な演奏を聴かせたジャズバンドには驚愕した。
聞くに、もうそのバンドは同じ土俵ではなく『ゲスト』として招かれており、
演奏といいパフォーマンスといい群を抜いていた。
アメリカに遠征にも行くとのこと。
その、有名な指導者のことを思い出した。
そのジャズバンドに入るには念書のようなものがあるとか、鬼のように怖い指導だとか、それはそれは恐ろしい噂が流れていた。
確かに、音楽にせよスポーツにせよ、指導者とか監督ってのはホント大事なんだろう。
実際、娘の金管バンドは、娘が入る前年度までは全く音楽に興味のない顧問がいて、破綻しかけていた。
しかし、新しい音楽の先生が赴任してきて、みるみる見違えるようになった。
この女の先生、やはり芸術畑の人らしく、もう、音楽のことしか考えていないようなところがあり、コンクールの前になると運転しながら指揮の練習するとおっしゃり凡人な母たちを驚愕させた。
音楽以外のトラブルには無頓着。
とはいえ、子供達が楽しそうだから、親たちも協力的に、「不思議ちゃん」な先生をサポートしていた。
よって、それまで金賞なんて無縁だったのに、九州大会にも出られたのよね〜
芸術は極めれば極めるほど狂気じみてくる。
その域に達した人でなければわからないことがあるのだろう。
凡人なワタクシは、身近にそんな人がいないことを嬉しく思うほど、怖く苦しい映画でありました。
昨日は娘と一緒にお台場へ。
音楽映画の『セッション』一夜限りのライヴ絶響上映の招待券が当たったから。
以前にこの映画を見て「よかったよ!」と言ってた娘は大喜び。
母はこの「ライヴ絶響上映」というものに一抹の不安を感じる。
説明書きによると・・・
スタンディングも歓声もOK。
ライヴハウスの音響で、通常の音楽ライヴと同様に楽しんでいただく上映スタイル
とあります。
マサラ上映のようなもの?
ま、何事も経験経験!
午前中ボランティア活動の例会を済ませから、お台場へ向かう。
以前は、「近いのに遠いお台場」というイメージだったが、バスという手段に気づいてから気持ちがぐんと楽になった。
「金子半之助」の天丼なぞを食してから会場へ。

スタンディング席の後ろに椅子席があり、そこの中央最前列に座る。
通常はライブ会場だからか仕方ないのか、スタンディングと椅子席の境が30センチほどの段になっており、
暗いせいもあり、ワタクシたちの前を通る人がその段差を踏み外す。
お一人の方は手にしていた飲み物を盛大にぶちまけておられたし、少々お年を召したおぢさまは「ををっっ!」と叫ばれた。
ワタクシはもう、みんなが着席するまで気もそぞろ。
なぜスタッフ一人くらい立って「こちら段差になっております!」と叫ばないのだ!?
あるいは、境目に柵を持ってきても良いではないか。
と、ひとしきり会場について母娘で語り合う。
ライヴ会場だからかよくわからんが、映画始まる前にMCの人が出てきて「ジンライム」だったかなんかを一気飲みするというよくわからんパフォーマンスと、絶響上映について説明した後、映画が始まる。
簡単に説明しますと・・・
世界的なジャズ・ドラマーを目指すニーマンと、名門音楽学校の伝説の鬼教師フレッチャーの壮絶なレッスンの日々を描いたものです。
どちらも、音楽に対する情熱が驚異的というか狂気的というか。
ワタクシ、自分がつくづく凡人で、性善説論者で、音楽家にも脚本家にもなれないということを痛感。
あ、ネタバレしますからね、見たいと思ってる方はここからは読まないでね。
フレッチャーの狂気じみた体罰バンバン精神的なダメージガンガン浴びせられながらのレッスンで、
ニーマンの精神も頂点まで張り詰めており、身心ともにボロボロになり退学。
教え子の自殺やらをリークされたフレッチャーも学校を辞めされられる。
ひょんなところで再会した二人は、和解し、フレッチャーはニーマンを自分のバンドのドラムに引き入れる。
そして、そのバンドで出た音楽祭で、フレッチャーはニーマンにだけ嘘の演目をいい、実際は違う曲をやる。
ここで性善説論者nは「これはおそらくフレッチャーの『お前なら入ってこられるだろう?』という期待によるものだろうと予想する。
だって、ジャズって自由なんでしょ?
ワタクシが脚本家ならそうする。
それゆえの、タイトル「セッション」だーーーっ!(駄作、間違いなし!)
しかし、そんな甘っちょろいワタクシの予想を裏切るように最後までニーマンはヘボ演奏を続ける。
そして、これはフレッチャーの、ニーマンにリークされた恨みを晴らすための復讐だったのだ。
一度はステージを去りかけるニーマンだったが、またドラムに戻って、フレッチャーを無視し「キャラバン」を演奏せざる得ない状況に持って行く。
驚き、戸惑い、苛立ちながらも指揮をするフレッチャー。
しかし、異常なスタートからかメンバーもすんごい演奏をする。
いや、わたしゃジャズは全くわからんが、おそらくすんごい演奏だと思う。
それまでは、この絶響上映の良さがわからず、ちょっと音、大き過ぎ!(「あなたを招待したのは間違いでした」主催者心の声)と思っていたが、
このラストの曲をここでこの音量で聞けたのはラッキーだったと思った。
しかし・・・いかんせん長い。
ドラム、長過ぎ!(ことごとく製作者の意に反している。ここが一番の見せ場なんだよっ!!!)
ワタクシ的には、すんごい演奏を作り上げたねっ!ってことでめでたしめでたし、で良いではないかと思ったのだが、
延々とドラムの演奏が続き、それまで怒り狂いながら、戸惑いながら指揮を振っていたフレッチャーが、だんだんと歓びへの表情へと変わっていく。
音楽に限らず、芸術家、いや、何かにのめり込む人たちのことがわからない。
つくづくワタクシは凡人。
そんなことを思い知らされながら見た映画だった。
そして、娘が小学生の頃に入ってた金管バンドのこととか思い出したりした。
彼女の所属してたバンドは、まあそれなりのレベルだったが、出場したコンクールで圧倒的な演奏を聴かせたジャズバンドには驚愕した。
聞くに、もうそのバンドは同じ土俵ではなく『ゲスト』として招かれており、
演奏といいパフォーマンスといい群を抜いていた。
アメリカに遠征にも行くとのこと。
その、有名な指導者のことを思い出した。
そのジャズバンドに入るには念書のようなものがあるとか、鬼のように怖い指導だとか、それはそれは恐ろしい噂が流れていた。
確かに、音楽にせよスポーツにせよ、指導者とか監督ってのはホント大事なんだろう。
実際、娘の金管バンドは、娘が入る前年度までは全く音楽に興味のない顧問がいて、破綻しかけていた。
しかし、新しい音楽の先生が赴任してきて、みるみる見違えるようになった。
この女の先生、やはり芸術畑の人らしく、もう、音楽のことしか考えていないようなところがあり、コンクールの前になると運転しながら指揮の練習するとおっしゃり凡人な母たちを驚愕させた。
音楽以外のトラブルには無頓着。
とはいえ、子供達が楽しそうだから、親たちも協力的に、「不思議ちゃん」な先生をサポートしていた。
よって、それまで金賞なんて無縁だったのに、九州大会にも出られたのよね〜
芸術は極めれば極めるほど狂気じみてくる。
その域に達した人でなければわからないことがあるのだろう。
凡人なワタクシは、身近にそんな人がいないことを嬉しく思うほど、怖く苦しい映画でありました。