先日の園芸友の会での話題から・・・。
四君子と楷の木のお話です。
四君子(しくんし)とは、ラン、タケ、キク、ウメの4種を草木の中の君子として称
えた言葉。また、それらを全て使った図柄、模様をいう・・とある。
それぞれの気品の高い美しさから、中国宋代より東洋画の画題としてよく用い
られ、春は蘭、夏は竹、秋は菊、冬は梅と、四季を通じての題材となる。 また、
これら4つの草木を描くにあたって基本的な筆遣いを全て学べるため、書を学ぶ場合
の永字八法と同じように、画法を学ぶ重要な素材となっている。(ネットから)
春蘭(シュンラン)
(ネットより)
話は、友の会会員の発表として、自宅の庭に咲く花にちなんで読んだ俳句のご披
露があり、その中の一句、春蘭を読んだ句があり、その解説に、自分の庭に地植えし
た蘭はこの20年ほどの間にかなり増えていて、香りもあまり感じられず、さほど美
しいとも思っていないが、貴重な花として昔から四君子の一つに挙げられている・・。
そんな、くだりで出てきた言葉でした。
少し調べていくうちに、日本では見られないが中国製の麻雀パイの花牌には、
この四君子が彫られており、ゲームの「上海」でもこの四君子の花牌があるという。
(ネットより)
もう一つの話題は、楷の木 です。
楷(かい) とは、木の名前で、その昔、紀元前550年、今から2500年ほど前、
儒学の祖、孔子が世を去った時に多くの子弟たちがその廟の周りに植えた木の中の
一つだそうで、それを大正4年、当時の農商務省林業試験場長だった白沢保美
博士が、中国山東省曲阜にある孔子廟から持ち帰って育て、大正14年、閑谷学校
、東京・聖堂、栃木・足利学校、佐賀・多久聖廟など孔子ゆかりの地に植えま
した・・とあります。
楷は、漢和辞典で引くと木の名前とあり、「まっすぐな」「手本」などの意味が
あり楷書などの例がる。 その後、日本国憲法施行50周年記念樹として、
国会議事堂前庭に2本植樹されたとも・・。
なぜ、「楷」の話題になったかというと、会員の一人が書道の会員でもあり、
たまたまこの字が出て、この「楷」というのは木の名前で、乃木神社に雌雄一対が
植えられているが、どちらか一方だと枯れてしまうという・・それは本当か?
と、園芸友の会員であるS氏に質問された・・このことが、話題になった。
楷は、中国原産、ウルシ科、ピスタシア属。和名は「ナンバンハゼノキ」、
「トネリバハゼノキ」といい、秋には美しく紅葉する。銀杏などと同じ雌雄があり
、一方だけだと実がならない。
楷の紅葉
(ネットから)
楷の葉
(こちらもネットから)
小さな葉っぱがたくさん出ているように見えるが、これは複葉といって、この小
さな葉っぱみたいなのを全部含んだ全体が一枚の葉っぱなんですね。へえ~。
つまり、この小さな葉っぱ見たいな付け根からは、一切芽が出ないのですね。
園芸友の会では、園芸の話ばかりでなくいろんな話題が出ますが、この日は、
俳句や書道に関連した話題でしたが、この他、1999年からずっと継続して観測され
てきた三貫清水のホタル(ヘイケボタル)の観察数の報告もありました。毎年、6月
下旬から9月中旬までの毎日20時前後のホタルの観察記録です。毎年、400~1200匹
くらいが観察されていました。
曲は ドビュッシーから・・・
VIDEO

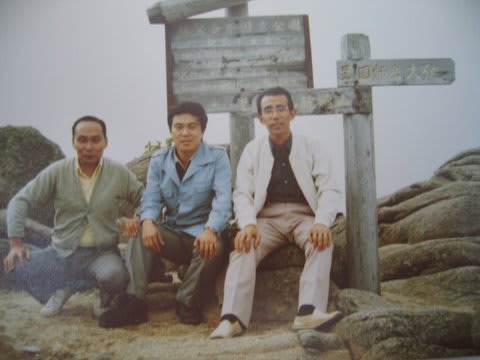

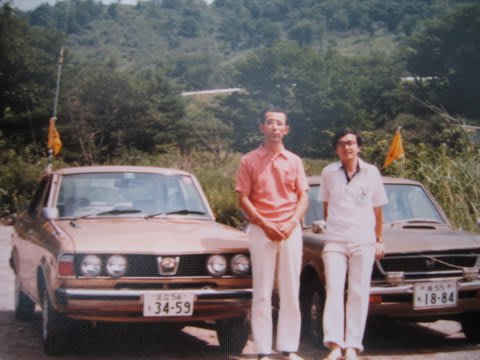











































 (ネットから借用、写真は回転しました。)
(ネットから借用、写真は回転しました。)









 (ネットより)
(ネットより)


 (ネットより)
(ネットより) (ネットから)
(ネットから) (こちらもネットから)
(こちらもネットから)


 (ネットから)
(ネットから)











