いよいよ8月もあと1日を残すばかりになりました。 巣ごもり老人のくせに、
やたら日の過ぎる速さに驚いています。 まぁ、何もすることがないのに、暇な
はずなのに早く日が過ぎているのは、ある意味ありがたいことなのかもしれません。
ところで、想い出というのは、優れモノなんですね。たくさん持っていても重
くはないし、どこへでも持ってゆくことが出来る、若干風化はあるかもしれないが
いつまでも残っている、ひょっとすぐに思い出す、維持費がかからない・・
しかし、想い出ばかりに耽る恍惚老人ではしかたがありません。 新しい思い出
作りも大切ですね。
では、不思議な日本語(28)に入ります。
 (ネット画像より)
(ネット画像より)
・台風 今年も台風の季節がやってきます。27日午後、南鳥島付近で台風11号
が発生し、小笠原で大暴れし沖縄に向かって西に進んでいるそうです。熱帯低気圧
がさらに発達して、暴風雨をもたらすあれをなぜ台風というのでしょうか?
まず、台風というのは、熱帯低気圧のうち北西太平洋または南シナ海にあって、
最大風速が17.2m/s以上に発達したものを指し、颱風、英語ではTyphoonというと
あります。これが北インド洋にあるものはサイクロンといい、南・北太平洋およ
び北大西洋にあって、最大風速33m/s以上のものはハリケーンと呼ばれています。
日本では、古くは野分(のわき、のわけ)といわれていますが、これは暴風そ
のものを指す言葉だそうで、厳密には気象学上の台風とは概念が異なるそうです。
難しいですね。
江戸時代には清国にならって颶風(ぐふう)と訳した文献があるそうですが、
明治にはタイフーンまたは大風(おおかぜ)などと呼ばれていたそうです。しか
し、末期頃には、颱風となったようだとあります。
で、なぜ「台風」というのか?については諸説あるようですが、タイフーンの
音にあてて台風というのがもっともらしいと思われます。
つまり、ギリシャ神話に登場する怪物ヂュポン(Typhon)に由来する、アラビア
語の風を意味するTufanが颱風およびtyphoonとなったなどの説がありました。
で、どうして、「台」の字が使われているかといえば、その昔、台湾や中国福
建省あたりから吹く強い風のことを颱風と呼ばれていたことから、台風と呼ばれ
ることになったとあり、時間をかけて調べた割には、あまり面白くない結果とな
りました。
・口実 意味は、言い逃れや言いがかりの材料、その言葉あるいは言い訳を指
しますが 、どうしてそのような意味になったのでしょうか? 語源由来辞典に
よれば、漢語で「口実」とは、口の中に満ちることを意味する とあり、口の中に
満ちるものには「飲食物」と「言葉」があり、「言葉(言い草)」の意味として
平安時代から使われるようになったそうです。その後、明治時代以降、中身のない
言葉に無理に実を込めようとするところから、「口実」が言い訳や言い掛かりの
材料を意味するようになった とあります。
 (ネット画像より
(ネット画像より
つまりは、口(言葉)の中にムリムリ弁解のための理由を詰め込むということ
なんですね。 #病気を口実に欠席する。
・マッチ(燐寸) 火は人間の生活になくてはならないものですが、火を起こ
す方法は簡単ではなかったのです。木を摩擦させたり、火打石を使ったり大変で
したね。私も、蓼科の縄文考古館にある木をこすって火を起こす『もみぎり』で、
懸命に手でもみ切りしましたがうまくつきませんでした。
1827年にイギリスで現在のような摩擦燐寸を発明しますが、火付きが悪かった
ようです。その3年後、今度はフランスで、頭薬(マッチ棒の先端)を黄燐にした
マッチを発明しました。これはどんなものに擦りつけても発火するので便利で普及
するのですが、逆に発火しやすいことや、黄燐が健康に良くないため、1891年には、
赤燐によるマッチが考案されたのです。
これは、頭薬にはリンを用いず、塩素酸かリウム、硫黄、ガラス粉などを使い、
側薬(マッチ箱)に赤燐、硫化アンチモンなどを使ったタイプのもので現在のも
のに近いものです。
 (ネット画像より
(ネット画像より
日本にも割と早く入ってきて、1875年(明治8年)には黄燐タイプのものが普及
するのですが、やはり健康上などの問題が発生し、しばらくたって、側薬の赤燐を
使ったいわゆる「安全マッチ」が普及することになったとあります。
なぜマッチを燐寸と書くか? そもそも、イギリスで発明された時にはラテン語
でろうそくの芯を意味する「XYXA」という名前が付けられ、それが英語で「MTCH」
という言葉になり日本に伝えられ「マッチ」とよばれたそうです。燐寸は、リン
がちょっとだけ使われているという意味から「燐寸」が与えられ、熟字訓の読み方
でマッチと読まれているのです。燐寸になるまでは、「早付木」「擦付木」など
と訳されていたそうですが、明治20年に燐寸に統一されたようです。
長くなりますが、7/18の読売新聞のコラムに燐寸のことが出ていて、つい最近
まであれほど身近に普及していた燐寸のことが書かれていました。 隆盛期には、
生産量を数えるための固有の単位「マッチトン」があったそうで、1マッチトンは、
約40本入りの小箱7200個を指すとありました。 また、私らにもお馴染みのあの
「ブックマッチ」を製造していた最後の兵庫県の企業が製造を終えるのだそうです。
ブックマッチは、二つ折りの紙製で出来たマッチで、喫茶や居酒屋、ホテルなどの
広告用として広く普及しましたね。私のところにもまだいくつか残っています。
懐かしいですね。
 (ネット画像より)
(ネット画像より)
・よそう ここでは、「予想」ではなく「装う」を取りあげました。もっと
言えば、「ご飯をよそう」の「よそう」です。 で、「よそう」は、「装う」の
意味から由来していると分かりました。 つまり、装うは、1、よそおう。2、
飯や汁等を食器にもる。の意味から、ご飯などを入れることの意味だとありました。
 (ネット画像より)
(ネット画像より)
「装う」は、「支度をする」「身なりを整える」 つまり服装や用具などを整え
て身支度をするという意味が原義であり、現代語では衣服などの場合は「よそう」
が変化した「よそおう」を使うことが多く、そして、「よそう」は、飲食物を整え、
用意するという意味から、飲食物を器に整えて盛るという意味になり、さらに飲食
物を器に盛るという意味に変化して、現代語の意味になっていったそうです。
言葉というのは不思議ですね。
「よそる」という人がいるようですが、これは、よそう と 盛るを合わせた
言葉として使われているフシがありますが、間違いであるそうです。 よそう の他、
盛る、つぐ などの表現もあります。「ご飯を盛る」「ご飯をつぐ」などは地域
によって優勢劣勢が分かれ、「盛る」は北海道・東北で優勢、「つぐ」は中国・
四国・九州で優勢とされているそうです。 また、「よそう」は関西および東京・
千葉、「よそる」はそれ以外の関東で優勢とありました。
 (ネット画像より)
(ネット画像より)
・毛嫌い なぜ、「毛」なんでしょうか? goo辞書には、(鳥獣が、相手の
毛並みによって好き嫌いをするところから)これという理由もなく、感情的に嫌う
こと。わけもなく嫌うこととありました。 言語由来辞典にも、毛嫌いの語源は、
鳥獣が相手の毛並みによって好き嫌いをすることからといわれるとあります。
闘鶏で相手の鶏の毛並みを嫌って戦わないことから出たとする説や、雌馬が雄
馬の毛並みを嫌って馬の種付けがうまくいかないことから出た言葉などの説がある
ようですが、後から付け加えられたものと考えられるともありました。
これといった訳もなく、感情的に嫌うのが「毛嫌い」ですから、嫌う理由がある
場合は毛嫌いではないのですね。 もし、あなたが毛嫌いしているものは?と聞
かれて、毛虫と答えた方がいるとしたらどうでしょう。 見た目が気持ち悪いから
や毒を持っていることが多いからという理由であれば、それは「訳もなく」では
ないので、厳密には毛嫌いではないのですね。この場合は、本当に嫌いであって、
毛嫌いには入らないのですね。 #演歌を毛嫌いする。
「Broken Promises/黒い傷痕のブルース」Fausto Papetti YouTube











 (ウイキペディアより)
(ウイキペディアより) (アマゾンHPより)
(アマゾンHPより) (ウイキペディアより)
(ウイキペディアより) (ウイキペディアより)
(ウイキペディアより) (ネット画像より)
(ネット画像より)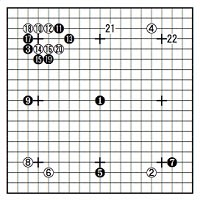 (ウイキペディアより)
(ウイキペディアより)
 (同HPより)
(同HPより)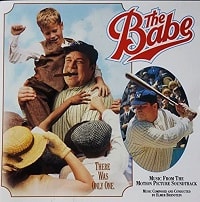 (ネット画像より)
(ネット画像より) 
 (ネット画像より)
(ネット画像より)
 (ネット画像より)
(ネット画像より)




 (yahooニュースより)
(yahooニュースより) (ネット画像より)
(ネット画像より) (大阪観光より)
(大阪観光より)
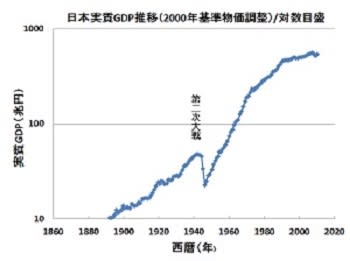
 (ネット画像より)
(ネット画像より)
 (ネット画像より)
(ネット画像より)

 (ネット画像より
(ネット画像より (ネット画像より9
(ネット画像より9


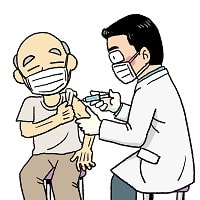 (ネット画像より)
(ネット画像より)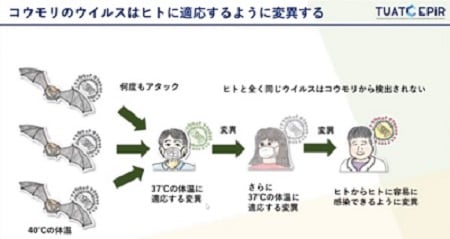


 (ネット画像より)
(ネット画像より)
 (デジタル庁ページより)
(デジタル庁ページより) (ネット画像より)
(ネット画像より)
 (ネット画像より)
(ネット画像より)





