関西弁で、とんちんかん、まぬけ、当てが外れること などを意味しますが、このタイ
トルの小説(文庫本)を、昨年11月末に若冲展を京都・相国寺に観に行った折、帰りがけに
“これ、新幹線で読んだら・・! 面白かったよ”ってKuさんが手渡してくれたのでした。
新幹線で読み始めたものの、眠くなってそのまま鞄に入れたまま、帰宅してからも机に出し
て、それっきり失念してしまって、ようやく暮れも押し詰まって読み始めたという失態を
演じてしまいました。
小説「すかたん」(朝井まかて著、講談社文庫、2014.5)は、江戸時代末期頃の大坂天満
の青物問屋を舞台に、主人公の江戸っ子の知里と青物問屋の若旦那の織りなす物語で、
大阪弁で展開される青物市場、農家のからみから、大店問屋の家風など多くの登場人物の
性格やことの運びがテンポ良く語られていて大変面白く一気に読んでしまいました。
すかたん
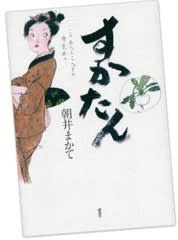 (アマゾンHPから)
(アマゾンHPから)
主人公知里は、江戸詰藩士の夫の赴任先、大阪に住むことになるのですが、急な病で夫が
亡くなり、慣れない土地で自活することになってしまいます。住み込みの奉公先は、天下の
台所、大阪でも有数の青物問屋「河内屋」で、お家さんつきの上女中として住み込みで奉公
することになるのですが、言葉や習慣の違いに戸惑いながら、厳しいお家さんの叱責にも、
浪速の食の豊かさに目覚め、いつしか若旦那との恋も芽生えてくるのです。
この若旦那は、はやとちりで後先の見境いがない“すかたん”なんですが、青物に関して
の情熱は人一倍で、目先の利益ではなく、生産者、消費者そして流通のあり方など広い視野
から、問屋・農家の敵対問題を見事に解決して行くのです。
若旦那の人柄、お家さんの風格、大店主人の貫禄、そして知里の純粋で有能な働き者が
うまく描かれていて、当時を知る由もありませんが、イメージが膨らんでくるのでした。
青物屋の主人であった伊藤若冲の描いた絵が出てきたり、それが、丸大根であったり、
若冲展を見た帰りだけに、心憎い思いがよぎるのでした。
作者の朝井まかては、1059年、大阪府羽曳野市生まれとありますから、根っからの大阪弁
(時代は遡りますが)を、ふんだんに展開されていて、何か懐かしい感じがしました。
「すかたん」は、2012年に単行本で出版されたものですが、それが2014年に文庫本として
世に出されると同時に、2014年、「恋歌」が、第150回直木賞を初候補で受賞しているのです。
すかたんのほかに、文面に懐かしい大阪弁が出てきましたので、いくつかを紹介しておき
ます。
・「おなごの性根は縫物をさせたら、ようわかる。あんたの縫い目はあっちへよろよろ、
こっちへよろよろ、いやいややってるのが丸わかりや。こらえ性の無い、せっかちのおっ
ちょこちょいで、おまけに下手くそのくせに心が籠ってない。 ・・・あれ、あんた、目ぇ
に見えへん心の内にまで踏み込んでまで説教されとぉない、そないな顔してるな」
・「いやいや、それでもな、皆、口を揃えて言うんや。もう二度と来んといて欲して思う
んやけど、ちょっと間ぁが空いたら待ち遠しゅうなるんやてな。若旦那さんと一緒に畑して
たら、自分らみたいな者(もん)でも楽しんでええんやて、そないな気ぃになるてな」
・「あん? 小万、お前、小万やないか」「今頃、何言うてはりますのん。若旦那さん、
ほんまに呑み過ぎやわ」「ええねん、今夜はええねん」「かなんお人やねぇ・・」
・「そやけど本当にこれで良かったんかて、近頃、ふと思うことがある。惣左衛門はんに
してみたら子ぉを楯に取られた格好や。私に要らぬ気ぃ回さはるし、こっちも継子苛めして
るてなことを一寸たりとも思わすもんかて気ぃ張って・・とうとう互いの胸の内がようわか
らんようになってしもうた。」
最後に、いくつかの言葉を・・
・口銭(こうせん) 手数料、儲け
・転合(てんご) ふざける、いたずら
・お為(おため) お駄賃、お返し、ご祝儀、
・最前(さいぜん) さきほど
・前栽(せんざい) 座敷の前庭
・ほな それでは、それなら、ほんなら
ほな、これで失礼します。










 (ウイキペディアより)
(ウイキペディアより) (ウイキペディアより)
(ウイキペディアより)

 (ネットから)
(ネットから)






