今日は二十四節気の「春分」です。お彼岸の中日ですね。全国的にお天気は雨模様の
先週の月曜日から、風邪の症状で、特に喉の痛みがこれまでにない激しさで、内科から
このような状況でしたが、次第に元気が戻り、先ごろ手元に届いていた会報に、喉に
「誤嚥性肺炎から命を守る術」と題した、昨年10月に行われた講演記録(稲川利光氏、 前置きが長くなり申し訳ありません。
加齢に伴って、足腰が弱り、体力が落ちてくることは避けがたいことですが、同時に
食べて、物を飲み込むとはどういうことか? そして、その機能を老化から少しでも
嚥下と呼吸に係わる器官
嚥下と呼吸に係わる器官で、鼻と口は喉で繋がっていることは、よくわかっていますが、
(日本耳鼻咽喉学会HPより)
余談ですが、今回、私が耳鼻科で鼻から入れたカメラで撮った画像はまさしくこの図で
で、嚥下の瞬間は、食塊が咽頭まで移動してくると、自動的に「嚥下反射」が起こり、 このように、食べ物を飲み込むには、多くの器官の神経や筋肉が巧みに協調して動くの
①舌の食塊保持がうまく出来ず、嚥下反射が起きる前に食塊が咽頭に流れ出す ②嚥下した後にも咽頭に食塊が残る ③嚥下時に食塊の一部が喉頭に侵入する(喉頭侵入) ④嚥下時に食塊が鼻腔へ逆流する
私の経験では、たまに③が起きることがあり、咳き込んでなかなか元に戻らない時が
人には、誤嚥防御反応という防御機能が備わっています。 ①嚥下時、喉頭蓋が喉頭侵入を防ぐ ②仮に食塊が喉頭まで侵入しても、嚥下中は声帯が閉じているので誤嚥が防げる ③嚥下直後、②で閉じていた声帯がパッと開いて。呼気が出て、この呼気によって喉頭 ④食塊が気管に入った時は、咳嗽(がいそう、cough)反応が起こって強い咳が出て食塊
通常は、このような防御機能により、誤嚥が防げられていますが、高齢なると、体力が
末尾に、誤嚥予防体操を引用しますが、その前に、誤嚥性肺炎の予防に役立ついくつか
①口の中を清潔に保つ 誤嚥性肺炎の中で一番大切なことは、口の中を清潔に保つこ ②口を閉じ、鼻から呼吸をする 口から食べる能力を維持するには、舌の働きを低下
嚥下予防体操(めぐみ訪問介護ステーションHPより)
昨日は、風もなく良いお天気で、気温も上がり暖かな春日和でしたが、外出を控えて、
VIDEO

















 (
(
 (ウイキペディアより)
(ウイキペディアより)









 (アイスランド公演より)
(アイスランド公演より) (ネット画像より)
(ネット画像より)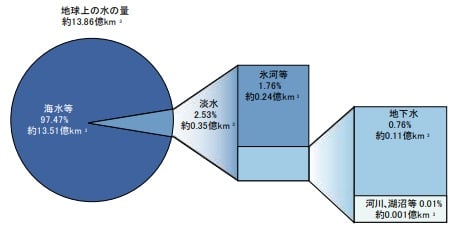


 (日本耳鼻咽喉学会HPより)
(日本耳鼻咽喉学会HPより)









 (日経新聞より)
(日経新聞より)
 (㈱和泉屋HPより)
(㈱和泉屋HPより)










 (警視庁HPより)
(警視庁HPより) (ウイキペディアより)
(ウイキペディアより) (ネット画像より)
(ネット画像より)
 (HPより)
(HPより) (ネット画像より)
(ネット画像より) (ウイキペディアより)
(ウイキペディアより) (同HPより)
(同HPより) (ネット画像より)
(ネット画像より)
 (ネット画像より)
(ネット画像より)






