除夜 (じょや) とは「旧年を除く夜」という意味で、12月31日の 大晦日 (おおみそか) の 夜のことをいうのだそうです。
古い年を除き 去り、新年を迎える日という意味とも。
この夜、各地のお寺でつきならす除夜の鐘は仏教でいう人間の百八の煩悩を一つ一つ消し去るといわれ、
刻一刻と新しい年に移って行くのです。
つまり、この鐘は煩悩解脱・罪業消滅を祈って108回つきならすのです。
なぜ、108かということについては、ネットウイキペディアには、以下のように書かれていました。
1. 煩悩の数を表す
眼(げん)・耳(に)・鼻(び)・舌(ぜつ)・身(しん)・意(い)の六根のそれぞれに好(こう:気持ちが好い)・悪(あく:気持ちが悪い)・平(へい:どうでもよい)があって18類、この18類それぞれに浄(じょう)・染(せん:きたない)の2類があって36類、この36類を前世・今世・来世の三世に配当して108となり、人間の煩悩の数を表す。
2. 一年間を表す
月の数の12、二十四節気の数の24、七十二候の数の72を足した数が108となり、1年間を表す。
3. 四苦八苦を表す
四苦八苦を取り払うということで、4×9+8×9=108をかけたとも言われている。
また、108回のうち107回は旧年(12月31日)のうちに撞き、残りの1回を新年(1月1日)に撞くのだそうです。
NHKの紅白歌合戦が終る11時45分には、いきなりどこかのお寺の映像・・時に雪深いお寺の鐘が“ご~ん”となり、
あぁ、今年も終わったんだ・・となる。
ウイキペディアには、こんなのも書かれていました。
“初夜の鐘(そやのかね)
午後8時、その日最初に撞かれる鐘。
正岡子規が詠んだ「柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺」の「鐘」は、奈良・東大寺の初夜の鐘であった。”
(追加)
また、ついでに“四苦八苦”も見ておきましたのでご参考までに・・・。
四苦八苦(しくはっく)とは、仏教における苦の分類で、 苦とは、「苦しみ」のことではなく
「思うようにならない」ことを意味する。
根本的な苦を生・老・病・死の四苦とし、 この根本的な四つの思うがままにならないことに加え、
愛別離苦(あいべつりく) - 愛する者と別離すること
怨憎会苦(おんぞうえく) - 怨み憎んでいる者に会うこと
求不得苦(ぐふとくく) - 求める物が得られないこと
五蘊盛苦(ごうんじょうく) - 五蘊(人間の肉体と精神)が思うがままにならないこと
の四つの苦(思うようにならないこと)を合わせて八苦と呼ぶ。4苦+8苦で12苦あるわけではありません。















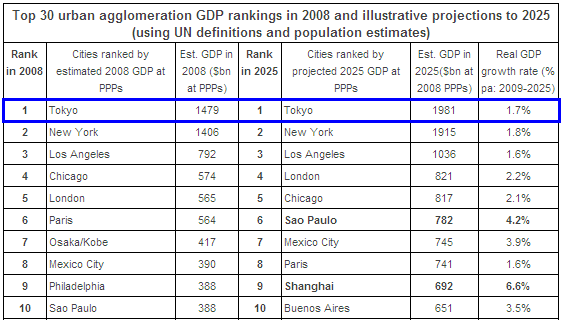
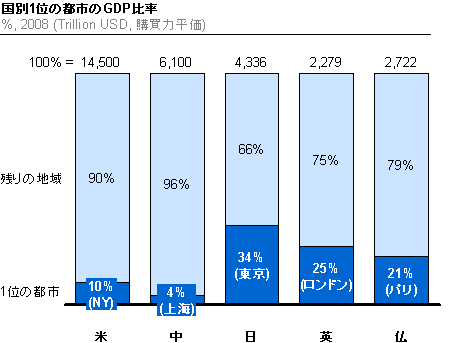




 (ネット時事通信より)
(ネット時事通信より)














