閏日(うるうび、じゅんじつ)とは太陽暦において暦と太陽の運行(季節の移り
変わり)とのずれを補正するために入れられる日のことです。
地球は自転(23.4度傾斜して)しながら、太陽の周りをほぼ一年をかけて回っています(公転)が、
ちょうど1周する(例えば、春分から春分まで)には、春分回帰年といって、
およそ365.2424日であるため、一年を365日と定めた暦(グレゴリオ暦)では、
季節(太陽の回帰年)に対して0.2424日少ないことになり、この差が積み重なって
暦と季節が無関係なものになってしまうことを防ぐため補正を入れる必要があるのです。
この事は、大体の方はご存じのはずですね、やや専門的な分野になりますが、いろいろと
面白い事柄があることをちょっとご紹介しておきたいと思います。
地球の公転
(ネットより)
この、暦の一年と季節が丁度一回りする一年の差を補正するやり方にはいろいろと
考えられてきましたが、現在統一的に扱われているのが、グレゴリオ暦において400年に97度(回)、
閏年とし、2月の日数を1日増加させるとされています。このとき付け加えられた日が
閏日であり、加えられる日は2月29日とする。歴史的な理由から欧州で2月24日を閏
日とする国もあるそうです。
なぜ2月なのか? それは、その昔ローマ暦での年始は3月1日であり、2月は年末の月であった。
そのため、年末の2月が日数の調節に使われた。そのまま現在の暦でもこれが引き継
がれてきた。 なぁ~んだ、割と単純なんだ。
で、400年に97度の閏年を設ける仕方が次のように定められています。すなわち、
現行の太陽暦であるグレゴリオ暦では
① 、年(西暦)が4で割り切れる年は閏年とする
② 、①のうち、年が100で割り切れる年は閏年としない(つまり平年とする)
③ 、②のうち、年が400で割り切れる年はこれを適用しない(つまり閏年とする)
というルールが定められています。
したがって、西暦2000、2400年はうるう年であるが、1900、2100、2200、2300年は
4で割り切れるが、100でも割り切れるのでうるう年ではなく平年となります。
うるうの年は、オリンピックがあり「オリンピックイヤー」などと呼ばれたりし、また、
このうるう年はアメリカ大統領選挙の年でもありますが、ともに4年ごとのために一致しており、
うるう年でない年でもオリンピック、アメリカ大統領選があることになります。
また、2000年はY2K問題があったことを思い出しますが、これは、コンピュータ内での
年を表すのに、下2桁だけで表示していたので、1999年を99、2000年を00と表示して
誤って計算する可能性(問題)があり、これを是正する必要があったためです。
さらに、この2000年は、うるう年だったのですが、誤って上の条件①と②のみを適用し、
うるう年としなかったプログラムが存在したため、この対応も併せて必要とされたのでした。
ちょっと余談になりますが、③番目のルールに当てはまる400年に1度のうるう年の
2月29日の曜日は必ず火曜日になります(2000年の2月29日は火曜日)。理由は、
この400年の総日数(365日×400+97日=146097日)は7で割り切れるため、曜日も400年で
繰り返すことになるからです。
さらに長くなって恐縮ですが、「うるう秒」というのがあります。
しかし、うるう秒とうるう日(うるう年)は全く無関係なんです。
うるう日(年)は上で述べてきた通り、一年を365日としたことと現実にちょうど
同じ季節(春分なら春分)に戻る日数の誤差を調整するための物でありました。
これに対して、うるう秒というのは、地球の自転の不整と原子時計の間の時間の調整なんです。
もし、この「うるう秒」の時間調整がなければ、長い目で見れば、一日は24時間なのに
地球が一周自転するのは25時間となってしまうなどのズレが生じてしまうのです。
ちょっとややこしいですが、我慢してください。
国際協定により人工的に維持されている世界共通の標準時、「協定世界時」
(きょうていせかいじ、UTC - Universal Time, Coordinated)というのがあり、原子による
正確な時間間隔を発生する原子時計と、天文学的(地球の自転により)に決められる世界時(UT1)
との差が0.9秒以内になるように「うるう秒」を挿入して維持しているのです。
地球の自転はちょうど24時間ではなく誤差を生じるため、世界時は日常生活の時間感覚として便利であるが、
精度が保てなくズレを生じてしまう。 そこで、原子時計の正確な時間間隔を基準として
その間を調整しているのです。言い換えれば、
国際原子時の利点を保ちつつ、世界時の利点をなるべく失わないようにする方法が、
うるう秒による調整なのです。協定世界時は、1秒の長さや秒を刻む歩調は国際原子時に
合わせつつ、世界時 との時刻の差をうるう秒による調整で縮めているのです。
1958年1月1日0時に国際原子時が開始された後、1967年に1秒の定義がセシウム133原子
を用いた現行の定義へ変更されました。(原発関連ブログで、問題とされたセシウムは、
セシウム137でした。)
そして、1972年1月1日0時に現行の協定世界時(UTC) = 国際原子時(TAI)- 10秒 に
調整されて開始されました。同年6月30日に、第1回の閏秒調整が行われました。
これによりUTC = TAI - 11秒 となりました。 その後、同年12月以降1979年12月まで
毎年+1秒の調整が行われ、1980年は調整せず、81~83年は6月末、84は調整なし、85年は6月、
87年12月、89~90年12月、92~94年は6月、95年12月、97、98年は各6月12月に、その後ずっと調整なく
2005年12月に、2008年12月、そして今年6月に+1秒の調整が予定されています。
こまごまと書いて来ましたが、この事は、私たちの日常生活にとって大変大事なことがらを含んでいるのです。
すなわち、電波時計、GPS,時報サービス、ネットワーク時間(NTP)に直接関連しているのです。
えっ、GPSまで・・?
以下にネット記事を参照しながら順に述べてみます。
●電波時計 は標準電波を利用して時計の時刻を校正するサービスで、日本では
独立行政法人 情報通信研究機構 (NICT) が提供する標準電波および標準時刻のサービスJJYを利用して、
実際の製品では単に、表示として(日本標準時)9時00分00秒が2回繰り返される。
8時59分59秒がとばされるだけという動作が多い。実際の電波時計は常時受信可能と
は限らないため、1時間に1回、あるいは1日に1回程度しか校正しない場合がある。
いずれの場合も、次の校正時刻でこのような動作になる。
●GPS(Global Positioning System) は、原子時計(これもまた地上からの指令
で校正される)を積んだ複数の人工衛星から受信地点まで電波が届く時間を計測して
各衛星と受信地点の距離を求め、そこから立体三角法で位置を推定するシステムである。
時間が肝要なシステムであるため、受信機は相対性理論すら考慮に入れられた、
極めて高精度の時刻を得ている。
●NTTの時報サービス NTT東日本・NTT西日本の時報サービス(電話番号117)は過去、
正の閏秒の調整には、秒音追加ではなく秒音間隔を伸ばすことで対応している。
すなわち、「午前8時58分20秒」の秒音の後、「午前9時」の秒音まで、秒音間隔を通常より
1/100秒長い101/100秒にし、秒音100回で101秒となるようにしている 。 この間に
つき日本標準時(JST) と比べると、「午前8時58分21秒」の秒音から
「午前8時59分59秒」の秒音までの99回に限って符合せず、「午前9時」の秒音で符合することになる。
なお、両社の「ひかり電話」の時報サービスでは前述と異なり、挿入される「午前8時59分60秒」と
その1秒後の「午前9時00分00秒」に2回続けて「ポーン」音を鳴らして調節している。
●NTP(Network Time Protocol) は、コンピュータ同士の時刻を同期させるプロトコル(規約)である。
正確な時刻の同期が必要なサーバ系OSで広く使われています。 NTPサーバは時刻を比較する
相手となる他のNTPサーバと時刻情報をやり取りして調整している。
こんなに長くなるとは思いませんでしたが・・・最後までお付き合いくださいま
してありがとうございました。
また、機会がありましたら「二十四節気」についてもアップしたいと思っています。ご期待ください。
かなり疲れましたので、音楽などをアップします。
VIDEO













 (ネットより)
(ネットより)


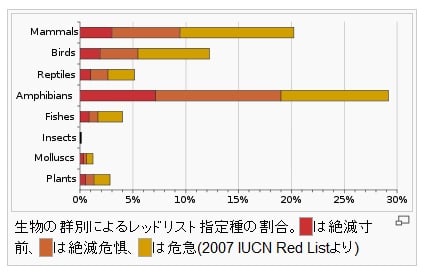










 (BANDAI)
(BANDAI)


 蠟梅のつぼみ
蠟梅のつぼみ






