蓼科農園での“畑開き”で、身体のアチコチの筋肉痛がまだ残るなか、一昨日の夕方、
3か月に一度くらいの割で開催されている、もう10年以上続く集まり(飲み会併用)で、
「自然農法」に魅せられて、自ら神奈川県秦野市に農園を営む O氏の楽しいお話を伺い
ました。
自然農法は、有機農法や循環農法などとも呼ばれている農業のやり方で、すなわち、
耕さず、化学肥料は使わず、草や虫を敵とせず共に生きる、命の営みに素直に従い すべ
てを仲間として尊重しながら農業を行う方法を言っています。
2015年には、「小農学会」(事務局鹿児島県)が設立されているとありました。
ウイキペディアによれば、『自然農法とは、不耕起(耕さない)、不除草(除草しな
い)、不施肥(肥料を与えない)、無農薬(農薬を使用しない)を特徴とする農法。
考案者の一人である福岡正信はこれを4大原則としている。ただし、自然農法の実践者で
あっても手法はさまざまであり、耕起や除草を許すかどうかに違いがある。なお、法律
(JAS法等)では「自然農法」「自然栽培」は定義されていない。』とあります。
自然農法(ネット画像より)


これまで、いろんな方々が 実践を通じた、その方法や意義について書物を著していま
す。岡田茂吉「自然農法解説1951」、福岡正信「自然農法 わら一本の革命」、川口由一
「自然農」、木村秋則「自然栽培」などが挙げられていましたが、この他にも関連する
考え方の書も多く、資料には、「宮中侍従物語」(入江相政編)文中の昭和天皇のくだ
りが延べられていました。『・・どんな植物でも、みな名前があって、それぞれ自分の
好きな場所で生を営んでいる。人間の一方的な考えでこれを雑草として決めつけてしま
うのはいけない。・・』
これらの書物の中で、偶然、私は7~8年前に、福岡正信「自然農法 わら一本の革命」
を読んだことがありました。読後の印象は、漠然と今も覚えていて、“耕さず、農薬は
使わず、自然の虫や雑草などと共生しながら、わらなども、切らずにそのまま長いまま
で、畑にまき散らす。それで、収量も期待通り、味、形なども良いと・・全く不思議な
思いでしたが、その言い回しや、方法論の随所に、時流に意識して反発しているような
思想がちらついている”そんな印象がありました。内容は確かに素晴らしく感心しまし
たが、何かしら同調しにくいという思いが残ったのでした。
こんな思いがありましたから、お話しの後講師に質問してみました。 “自然農につ
いて、一冊の書物を読んだだけですが、このような印象を持ちましたが、自然農を営む
講師はどのような考えですか?”と。 すると、やはり、私の感じたのとほぼ同じよう
な印象をお持ちで、“やはり、世の中に迎合しては やって行けない。反発ではないが、
何かそのような強い気持ちがそこに流れている”・・そんなような回答でした。
飲み会の様子

場のいろんな人たちも、それぞれの感じから質問や提言がありましたが、最終的に
私は、次のように理解したのでした。
「自然農法は、環境を重んじ、食害を無くすやり方として、確かに素晴らしいが、この
農法によって生計を維持するのは、やはり無理である。生計を維持するすべが他にある
場合に限り、その主義は実現できる」と。
自然農法は、小規模・家族農業ともいわれ、いわゆる 産業化された大規模農業とは
違い、今日 日常口にする野菜の殆どは、大規模農業から出荷された野菜なんですね。
ウイキぺディアの有機農業の項には、以下のような記述がありました。
『 有機農業については、農林水産省の「有機農産物の日本農林規格」では、有機農業で
生産された農産物(有機農産物)は次のように定義されている。
- 有機農産物
1) 有機農産物:農薬と化学肥料を3年以上使用しない田畑で、栽培したもの。
2) 転換期中有機農産物:同6ヶ月以上、栽培したもの - 特別栽培農産物
3) 無農薬栽培農産物:農薬を使用せずに栽培したもの
4) 無化学肥料栽培農産物:化学肥料を使用せずに栽培したもの
5) 減農薬栽培農産物:その地域での使用回数の5割以下しか農薬を使わずに栽培
したもの
6) 減化学肥料農産物:同化学肥料を使わずに栽培したもの 』
とあり、蓼科農園で、私たちがやっている農法は、さしずめ、特別栽培農産物の中の3)、
4)あたりのようです。 ほんの少し、化学肥料を使用することもありますが・・。
最後に、理想の食として、「食の健康手帖」(長山久夫、中央公論社)から、
まごはやさしい=豆、ゴマ、ワカメ・海産物、野菜、魚、シイタケ・きのこ類、イモ
がありました。
飲み会の場所は、飯田橋(駅陸橋から、市谷方向を見る)


















 横道にそれましたが、襟を正して本題に入ります。
横道にそれましたが、襟を正して本題に入ります。


 (過門香點 有楽町にて)
(過門香點 有楽町にて)



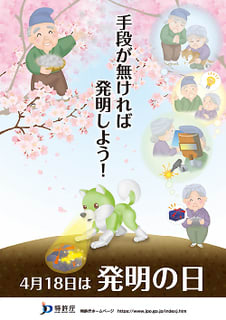 (特許庁HPより)
(特許庁HPより)

 (ネット画像より)
(ネット画像より)

 (ネット画像より)
(ネット画像より) (西大寺HPより)
(西大寺HPより) (ネット画像より)
(ネット画像より)
















 (ウイキペディアより)
(ウイキペディアより) (ウイキペディアより)
(ウイキペディアより) (ウイキペディアより)
(ウイキペディアより)

 (ネット画像より)(ダイヤモンド社)
(ネット画像より)(ダイヤモンド社)
 (ウイキペディアより)
(ウイキペディアより)








