9月も早く過ぎた感じです。次々と台風がやって来て、経験したことのないよう
な強い風を伴った凄い低気圧の台風もありましたが、どちらかといえば、線状降水
帯などによる豪雨被害が各地に残して行きました。 国葬も無事に済みましたが、
臨時国会ではしばらく燻ぶりそうですね。 窓を開けると、ベランダのススキに
穂が出て、キンモクセイの良い香りが運ばれてきます。
もう29回目になりました「不思議な日本語」です。まったく脈絡なく、言葉を
思いつくままに列記しています。 では・・
・すずなり 意味するとこは大体想像はつきますが、語源由来辞典によれば、
鈴なりの「鈴」は、神楽鈴のことだそうです。 神楽鈴は、12個または15個の小さ
い鈴を繋いで柄に付けたもので、神楽殿で巫女が神楽舞を舞う時に手に持っている
アレですね。 果実が群がって成るさまが、神楽鈴の鈴の付き方に似ていること
から「鈴なり」と呼ぶようになったとあります。 果実などが、神楽鈴のように
「鈴なり」になっている。 物や人が群がり集まることも意味するようになった
そうです。
神楽鈴
 (ネット画像より)
(ネット画像より)
鈴は、魔除けや神様を呼ぶ効果があるとされ、神社の参拝時に鳴らす鈴にも同
じ意味があるといいます。この鈴を三段の輪状に付け、普通下から七個、五個、
三個になっていて、別名七五三鈴とも呼ばれているともありました。
ほとんど関係はありませんが、英語にグレープフルーツ(grapefruit)」という
呼称は、この木の果実が小枝に3から10ほどの房状に、まるでグレープ(ぶどう)
のように木になるので、1800年代にそう呼ばれるようになったそうです。
グレープフルーツの木
 (ウイキペディアより)
(ウイキペディアより)
・おもむく こちらも、語源由来辞典を見てみますと、『赴くとは、ある方
向・場所へ向かって行く。物事・状態がある方向に向かう。気が進む。』という
意味で、おもむくは、「おも(面)」+「むく(向く)」で、顔がその方向に向
くという意味に由来しているとあります。(顔向け?)
趣く(おもむく)というのもありますが、どう違うのでしょうか?
ネットには、『「赴く」は、ある場所や方向へ向かって行くことで、「趣く」は
心や考え方がある方向に向かうこと』とありましたが、『「本能の赴くまま」や
「好奇心の赴くまま」などの言い回しで用いられ、欲求を敢えて律することなく
身を委ねる様子を意味する。』などがあるところを見ると、あまり明確な区別が
ないようでもあります。趣味、趣向などをみれば、心が動く方向とも読み取れま
すね。
反対語としては、「背く」(そむく)あたりでしょうか?
・きんつば よくご存じのあのきんつばです。 ウイキペディアに『寒天を
用いて粒あんを四角く固めたものの各面に、小麦粉を水でゆるく溶いた生地を付
けながら、熱した銅板上で一面ずつ焼いてつくる「角きんつば」であるが、本来
のきんつばは、小麦粉を水でこねて薄く伸ばした生地で餡を包み、その名の通り
日本刀のつばのように円く平らに形を整え、油を引いた平鍋で両面と側面を焼い
たものである。』とあります。 なるほど、刀の「鍔」(つば)なんですね。
丸いきんつば
 (ネット画像より)
(ネット画像より)
もともとは大阪で考案された菓子だそうで、上新粉(米粉)で作った生地で餡
を包んで同じよう焼いたもので、当時はその形と色から「ぎんつば(銀鍔)」と
呼ばれていたそうです。それが1600年代後半に大阪から江戸に伝わると「銀より
も金の方が景気が良い」よいうことで、「きんつば」となったそうです。
現在のきんつば
 (ネット画像より)
(ネット画像より)
現在のきんつばの元祖は、神戸元町の紅花堂(現、本高砂屋)で、明治時代に
考案されたものとありますが、私が子供の頃、大阪では、「出入り橋のきんつば」
が、いいなんておふくろが言っていたのを覚えています。 金沢に勤務していた
頃は、「中田屋」のきんつばが有名でした。お土産によく買いましたね。
富山県高岡には、今でも円形で鍔の文様を付けたきんつばがあるそうです。
・もっぱら goo辞書に、『「専ら」は「もはら」の音変化で、①[副]他
はさしおいて、ある一つの事に集中するさま。また、ある一つの事を主とするさ
ま。ひたすら。ただただ。「―練習に励む」「休日は―子供の相手をする」「―
のうわさだ」 ②[形動ナリ]専念するさま。また、主要・肝要なさま。』とあ
ります。
古語の「もはら」を見てみますと、ひたすら。まったく。という意味と、〔下
に打消の語を伴って〕少しも。全然。決して。の二通りの意味があるとありました。
前者の例では、「逢(あ)ふことのもはら絶えぬる時にこそ」(古今集) 後
者では、「かく奉(たいまつ)れれども、もはら風止(や)まで」(土佐日記)
が挙げられていました。
また、似たような言葉に、「ひたすら」、「ひとえに」があります。
もっぱら:主として。主に~だ。
酒といえば、もっぱら日本酒を飲んでいる。
ひたすら:長い時間ずっと、そのことばかりをやる様子
彼女のことをひたすら思い続けて、もう15年・・
ひとえに:他のことはさておき、全く、ただただ
こんにちあるのは、ひとえに先生のおかげです。
もっぱら日本酒といえば、ワインやビールも飲むこともある となりますが、
ひたすら日本酒 となれば、これはもう日本酒ばかり・・
・のべつまくなし 休みや切れ目がなく続くさま。ひっきりなしに続くさ
まをいいますが、何がないのでしょうか? 語源由来辞典には『のべつ幕なしは、
「のべつ」に同義語の「幕なし」を重ねて強調した言葉である。』とあります。
あぁ、「幕」がないのです。芝居で、幕を引かずに演じ続けることを指している
のですね。「のべつ」は「述べ(のべ)」に助動詞の「つ」が付いた語で絶え間
なく続くさまをいい、江戸時代から使われていたそうですが、「のべつ幕なし」
が使われたのは明治からだとあります。
のべつくま(隅)なし や のべつひま(暇)なし などもっともらしい意味
合いをもって使われたりすることがあるそうですがいずれも誤用だとありました。

それにしても「まくなし」など芝居の幕を充てていうのは不思議ですね。大昔
の人達のセンスというか、物事の発想が豊かというか自由そのものであったと感
じられますね。
Doris Day - It's Magic











 (ネット画像より)
(ネット画像より) (ウイキペディアより)
(ウイキペディアより) (ネット画像より)
(ネット画像より) (ネット画像より)
(ネット画像より) (ネット画像より)
(ネット画像より) (ネット画像より)
(ネット画像より)
 (科学技術振興機構より)
(科学技術振興機構より) (ウイキペディアより)
(ウイキペディアより) (ネット画像より)
(ネット画像より)
 (同HPより)
(同HPより)
 (ネット画像より)
(ネット画像より) (ネット画像より)
(ネット画像より) (ネット画像より)
(ネット画像より) (ネット画像より)
(ネット画像より)








 (ネット画像より)
(ネット画像より)



 (舎密局記事より)
(舎密局記事より)


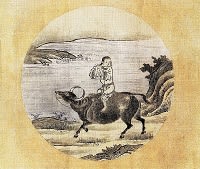 (ネット画像より)
(ネット画像より) (ネット画像より)
(ネット画像より) (ネット画像より)
(ネット画像より) (ネット画像より)
(ネット画像より)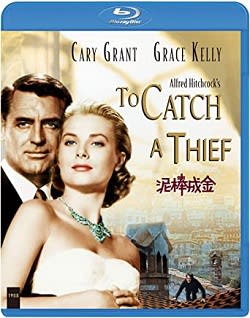 (ネット画像より)
(ネット画像より) (ネット画像より)
(ネット画像より) (ウイキペディアより)
(ウイキペディアより)


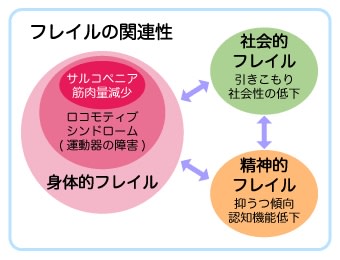 (日本成人病予防協会より)
(日本成人病予防協会より)
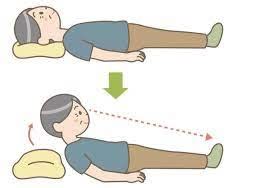
 (ネット画像より)
(ネット画像より)



 (ネット画像より)
(ネット画像より) (ネット画像より)
(ネット画像より) (ネット画像より)
(ネット画像より) (ネット画像より)
(ネット画像より) (ネット画像より)
(ネット画像より) (ネット画像より)
(ネット画像より) (ウイキペディアより)
(ウイキペディアより) (ネット画像より)
(ネット画像より) (ネット画像より)
(ネット画像より) (ネット画像より)
(ネット画像より)






