日本シリーズはなかなか面白い良い試合を展開しています。五分の戦績で、最
終の神宮へ・・今日。
気温は、11月中旬~12月の寒さだという。あの暑い夏はどこに行ったのか?
季節は巡る・・もう来週は11月なんですね。
不思議な日本語も30を迎えました。アトランダムに、思いつくままに選んでいます。
では・・
・包丁 庖丁とも書きますが、今は包丁ですね。台所にある調理に使うアレ
のことをどうして庖丁(ほうちょう)というのでしょうか? ウイキペディアには、
もの凄い量の解説がありましたが、その中からかいつまんで記してみます。
「庖」というのは中国語で台所を意味するとあり、「丁」は、園丁、馬丁という
ように、その職場で働く青年の召使男性を指していたそうです。 なので、そも
そもは「台所で働く成年の召使男性」を指していたのだそうです。 日本語でも
「庖丁」には、料理人、料理役といった意味があるそうで、元々刃物ではなかっ
たようです。 ある時、庖丁(料理人)が、みごとな刀さばきを見せて調理した
その「調理刀」を「庖丁」と呼ぶようになったとあります。
世界各地の包丁
 (ウイキペディアより)
(ウイキペディアより)
左から、中華包丁、中華包丁をドイツのゾーリンゲンが作った、三徳庖丁=文化包丁、
フランス料理などで使う、ペアリングナイフ=フルーツなど
日本では、平安時代頃までは、すべて「刀」と呼ばれて、調理用についても特段
の区別はなかったそうですが、鎌倉時代末期あたりから、庖(台所、厨房)で働く
専門の職人を庖丁者、庖丁人と呼ばれていて、それらの人が使用する「庖丁刀」
を後に略して「庖丁」といったとあります。

包丁を、材質で区分すると、石器時代には、石斧や石の刃物がありましたが、
現代では殆どが金属製で、ステンレス、チタン合金製などもあるようです。また、
近年 窯業製品で、セラミック、ファインセラミック製の包丁もあります。
文化圏別では、和包丁、中華包丁、洋包丁があります。
和包丁は、軟鉄と鋼を接合したものが一般的ですが、その使用する対象によって
たくさんの形状等に分けられています。菜切り包丁から出刃包丁、刺身包丁など
が一般的ですが、穴子切包丁、鱧切り、どじょう切り・・さらに、麺切り、もち
切り、豆腐切り、スイカ切などなどたくさんありました。
中華包丁には、用途別に片刃、切刃、前片後斬刀、斬刀などがあるそうです。
洋包丁は、西洋包丁とも呼ばれ、多くは両刃です。牛刀、筋引、洋出刃、ペティ
ナイフ、三徳包丁、パン切包丁・・などたくさんの種類があるようです。
また、包丁の各部分の呼び方(名前)が細かく分かれていて、ここでは省略し
ますが、刃の研ぎ方もそれぞれに工夫があるようです。
友人に、包丁研ぎをシルバーセンターの仕事としてやっている人がいますが、
包丁の「切れ味」が悪くなっている家庭の多いことに驚かされています。
庖丁だけで、記事が終わりそうです。長くなりました。
・いっさい 「一切」のことなんですが、「すべて」「全部」を意味するとあ
ります。「一切れ(ひときれ)」といえば、いくつかに切った一片を表すのに、
「一切」は、どうして「全部、すべて」の意味になるのか、いろいろと調べまし
たが、明快な答えを得ることはできませんでした。
「一切合切(いっさいがっさい)」の合切は、明治の頃女性が身の回りのもの
をすべて合切袋に入れていたところから合切=すべての意となり、一切合切は、
一切を強調している‥とありました。
仏教にも、「一切我今皆懺悔(いっさいがこんかいさんげ)」などというの
がありますね。
・八つ当たり ネットに、『「八つ当たり」とは、「だれかれ区別なく周り
の人に当たり散らすこと」「不満を覚え、無関係の人に当たったり攻撃すること」
という意味とありました。何かに失敗するなどして腹を立てると、物を壊したり
周りの人に強い言葉を向けて気持ちを静めようとすることがあります。 これを
八つ当たりと呼びます。』とあります。
八つ当たりの語源は、「八方」だそうです。八方とは「あちこち」という意味で、
だれかれ構わず周りの無関係な人という意味に使われているのですね。四方八方。
つまり全方位型ということですね。八方美人、八方ふさがり・・などという言い
方もあります。
で、八つ当たりは、ちょっとした不満や腹を立てることでストレスを感じてし
まい、それを発散する為に周りの無関係の人に強い言葉を向けるなどの行為で、
無関係の人にも向かうので、注意が必要ですね。
もともと「八」には「数多い、全部」みたいな意味があり、仏教では、「八方
地獄」「八方奈落」など非常に多くの地獄などがあることを言いますから、この
意味と同じく数が多いことや全方位型のたとえとして言葉に使われたのだと思わ
れます。
江戸に多数の町があることを「八百八町」大阪では「八百八橋」・・「嘘八百」
もありますね。 古川柳に、八百八町とかけて、『嘘よりも八町多い江戸の町』
というのもありました。
単に数字の八(8)を意味するのもあります。八丁味噌:岡崎城から西へ八丁
離れた八丁村で製造され味噌、大八車:車台が8尺(約2.4m)のものなど。
酒樽を積んだ大八車
 (ウイキペディアより)
(ウイキペディアより)
・別条 goo辞書には、その意味は「他と変わったこと。いつもとは違った事
柄や状態。」とあり、「別条なく旅を終える」や「命に別条はない」などの例が
あります。これらから類推すれば、別条とは「取り立てて問題にすることはない」
「特段の支障はない」という意味と考えられますが、この「別条」がなぜそのよう
な意味になるか、ちょっと不思議に思えてきたのです。
なので、「別」「条」の漢字の意味を調べてみることに・・。
「別」は、1、わける(区別、識別、選別、判別) 2、わかれる(選別、送別)
さらに 3、分けられた異なる物とみなされる(別格、別個、別人、特別)の意味
がありました。
「条」は、1、くだりごとに書き分けた文(条件、条項、条文、条約、別条・・)
2、すじ。道筋。通り道(条理、軌条) 3、都市の区画。東西の大路(条里)
4、伸びる(条達) 5、えだ。分かれた細い幹。小枝(枝条) 6、細いものを
数える語(一条) などがありました。
次第にわからなくなってきましたが、要するに、「キチっと書かれた条目から
離れた(別れた)」との意味を表すのでしょうね。普段と違う・・普通と違う・・
変わった、という風な意味と考えられるのでしょうね。
なお、別条は別状とほぼ同じ意味でどちらも使われているようです。
ついでに、「命に別条はない」というのは、重病なのか、軽傷なのか? 命に
係わるほどの重病ではない(死なない)程度・・ですから、重傷なんでしょうね。
・似たり寄ったり 互いに(優劣などに)大した違いのないこと の意味です
ね。 「生徒たちの作品はどれも似たり寄ったりだ」「どの旅行会社の企画も似
たり寄ったりだ」のように言います。五十歩百歩、大同小異、どんぐりの背比べ‥
というところでしょうね。
ネットを見ていると、その語源は『似たりたるものが寄りたり』が縮まって
『似たり寄りたり』→『似たり寄ったり』となったとか!
しかし、「似たもの同士」のような似た部分を取上げて(強調して)いうので
はなく、大差がない・・違っているように見えるが本質を見極めてみると大した
変わりがないというニュアンスなんですね。
似た者が寄る‥という表現は面白いですね。
お疲れさまでした。
 (ネット画像より)
(ネット画像より)
Destiny Tico-Tico















 (ウイキペディアより)
(ウイキペディアより)
 (ネット画像より)
(ネット画像より) (ウイキペディアより)
(ウイキペディアより) (ウイキペディアより)
(ウイキペディアより) (ウイキペディアより)
(ウイキペディアより)
 (ネット画像より)
(ネット画像より) (スポニチサイトより)
(スポニチサイトより) (ネット画像より)
(ネット画像より)










 (
( (ネット画像より)
(ネット画像より)

 (ウイキペディアより)
(ウイキペディアより)
 (ネット画像より)
(ネット画像より)
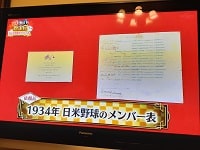





 (ネット画像より)
(ネット画像より) (ネット画像より)
(ネット画像より) (ネット画像より)
(ネット画像より) (ネット画像より)
(ネット画像より)
 (2022.10.4)
(2022.10.4) (2022.10.4 20時頃)
(2022.10.4 20時頃) (ネット画像より)
(ネット画像より) (日本BMI協会より)
(日本BMI協会より)





