
坑道の内部を進みます。狭い通路、涼しい風、うつろに響く音。女の子と一緒
なら、お化け屋敷みたいでウキウキするだろうけどなぁ(^益^)w
ひとりだと、昔の鉱夫は悲惨な生活だったのだろうなあ、と想像したり(゚益゚)w
広い坂道に出ました。結構深いところまでいったりするのです。
出口の手前に、鉱山の仕事の様子が描かれて説明がついていました。これが
なかなか面白かった。
一枚目は「四つ留之図」。「四つ留」とは坑道の入口で、丸太の木を組んで
土石が落ちないように造ったものです。おっちゃんはキセル吸ってるのか?
右上と下では堀子人夫たちが鉱石を掘っています。右は天井が崩れないように
横木を渡しているところ。左は坑内の溜まり水を水箱に段々と竹のポンプで
吸い上げているところです。手作業だから大変だろねー。
これも木製のポンプで段々と水をくみ上げているところです。どんどん湧き出て
くるところは休むことができないでしょう。右のほうに、狭い通路をはいつく
ばって進んでいる人がいます。埋まって死んじゃうよーwww
暗闇、明かりから出る油煙、狭い空間での石塵。そして落盤の危険、ガスや
水が襲ってくる恐怖。たまりませんねェ。。。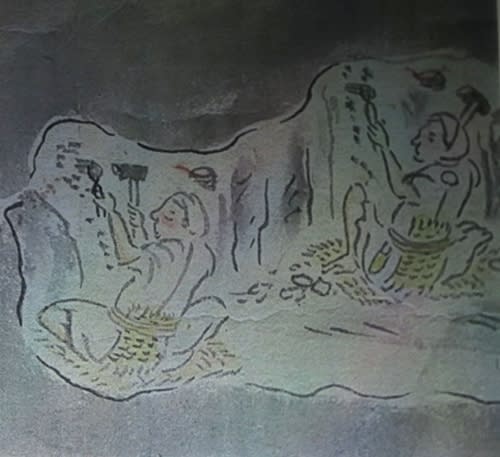
でもこの人たちの生活は、きっと豊かじゃなかったんだよw
手に持っているのは、サザエの殻のランプだったそうです。
何度も何度も往復したのでしょう。一番奥で掘っている連中よりは
ましなのかなあ。
どんどん湧き出てくる水を汲むのも重労働だった。なにせ休むことが
できないのだから。腰にくるだろねー。
いったい一日に何時間くらい働いていたの?きっと24時間営業で、交代制
だったのでしょうね。鉱夫たちは次々に死に、管理している上の連中には
莫大な富をもたらしたと。銀は海外との貿易に使われたそうです。
フヒー、出口だ。
たった30分あまりの見物でしたが、シャバに出て、新鮮な空気を吸える解放感を
感じました。。。









