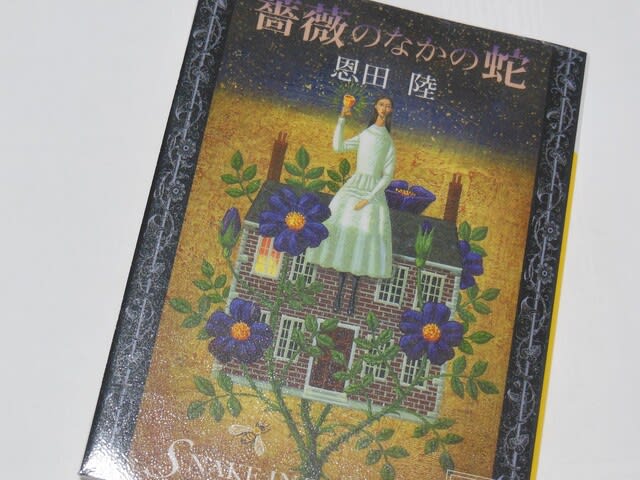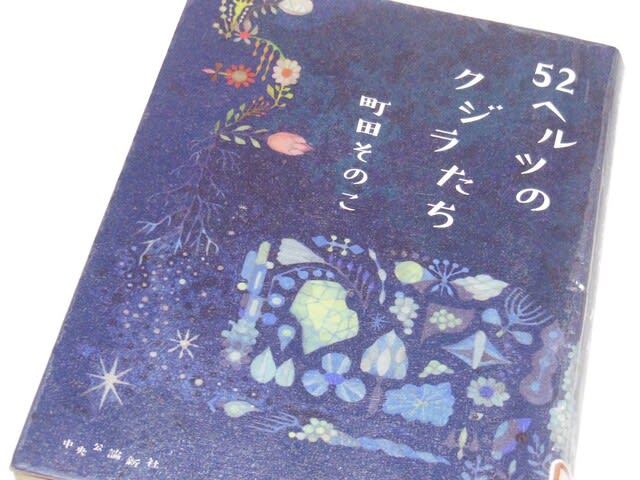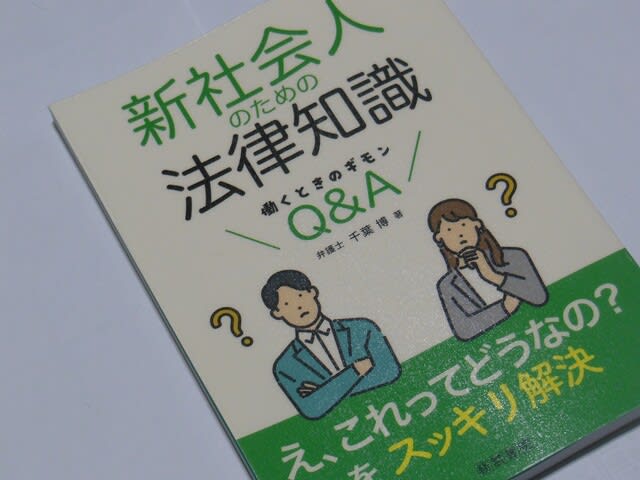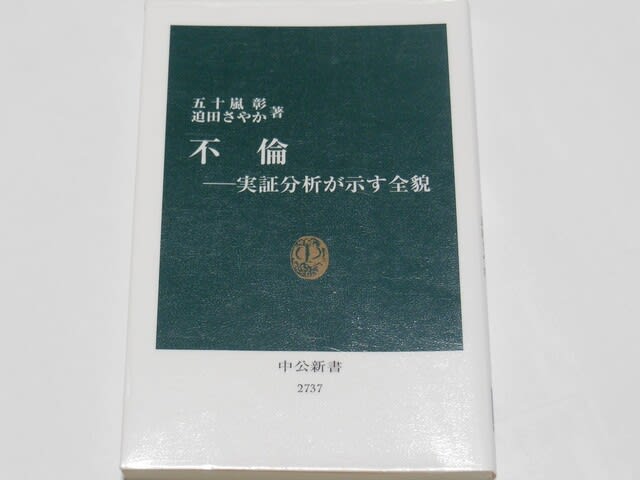文章を読むときになんとなく読むのではなく、筆者の主張の根幹とその根拠・理由を中心とした要約をして思考の軸を獲得する習慣をつけ、それを他の文章を読んだり会話をする際にその視点を活用しようということを提唱する本。
後半では、その実践として杉原泰雄の「憲法読本 第4版」の地方自治に関する文章(94~96ページ)、庵功雄編著の「『やさしい日本語』表現事典」からの外国人等に対する標識等の表示に関する文章(142~146ページ)、「The Asahi Shinbun GLOBE+」からの難民支援NGOの試みに関する文章(168~171ページ)を課題文として、小刻みに要約のプラクティスの過程を示しています。この要約の過程自体は、繰り返しが多くくどい感じがしますが、要約の技法自体よりも、課題文の選択に著者の立ち位置が見えて、そちらに少し共感しました。

小池陽慈 青春出版社 2023年6月5日発行

後半では、その実践として杉原泰雄の「憲法読本 第4版」の地方自治に関する文章(94~96ページ)、庵功雄編著の「『やさしい日本語』表現事典」からの外国人等に対する標識等の表示に関する文章(142~146ページ)、「The Asahi Shinbun GLOBE+」からの難民支援NGOの試みに関する文章(168~171ページ)を課題文として、小刻みに要約のプラクティスの過程を示しています。この要約の過程自体は、繰り返しが多くくどい感じがしますが、要約の技法自体よりも、課題文の選択に著者の立ち位置が見えて、そちらに少し共感しました。

小池陽慈 青春出版社 2023年6月5日発行