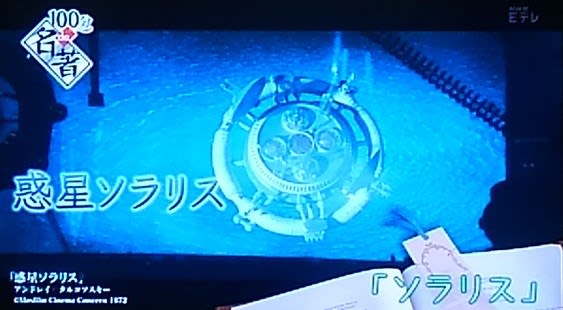■「ソラリス」スタニスワフ・レム著@100分 de 名著
【出演】伊集院光、島津有理子アナウンサー
【指南役】沼野充義(東京大学教授、ロシア・東欧文学研究者)
【朗読】田中哲司(俳優)、中村優子(俳優)
【ゲスト】瀬名秀明(SF作家)
【ナレーション】小口貴子
 心の中のベストフィルム~『惑星ソラリス』(1972)
心の中のベストフィルム~『惑星ソラリス』(1972)
私の大好きな映画と、哲さんがリンクするとはビックリ
番組内でも映画のシーンをたびたび使っているのも嬉しい

【内容抜粋メモ】
 第1回 未知なるものとのコンタクト
第1回 未知なるものとのコンタクト



ポーランド初のSF小説として40以上の言語に翻訳され半世紀以上読み継がれてきた
SF小説でありながら、人間の存在とは何か、哲学的な問いを投げかけてくる
難解なためなかなか読めないという人も多い
沼野さんは、高校時代に本作と出会い、ポーランド文学にのめりこんだ
ロシア語からの翻訳が多いところ、ポーランド語からの翻訳をして話題となり
著者とも長年にわたって交流を深めた

沼野さん:
自分にとっては原点のような小説
日本ではアメリカのSF小説が人気だが、まったく違う
面白いだけでなく、ちょっと怖くなる
形而上学的恐怖を感じる
読む前と後で自分が少し変わったような、世界が違って見えるような作品
<基本情報>

もう2編あるのか/驚
ファーストコンタクトとは?
最初の接触 SFの場合、宇宙にいるかもしれない地球外生命体と初めて接触した時
何が起きるのか、人間と分かりあえるのか、コミュニケーションができるのかを描くので、SFでは定番のテーマ
しかしレムは、人類の文明の未来、宇宙の起源に思考を発展させた
SFを超えたSFを作った人 メタ・サイエンスフィクションとも言われる
レムは「宇宙人と戦う 」などのイメージに批評的な立場をとる SF批判のSF
」などのイメージに批評的な立場をとる SF批判のSF
<内容>
宇宙科学者ケルヴィンは、宇宙を16ヶ月も旅し惑星ソラリスを目指した
赤と青の太陽の周りを複雑な軌道を描いて周回しているソラリスは
人類が100年以上も前に発見した惑星

惑星を覆う海は、高度な知性をもつ生命体のようで、まだ解明されていない謎めいた存在
その観測ステーションに派遣された(このアニメも本格的


到着すると、内部の荒れ果て様に当惑する
スナウト博士はなにかに脅えて正気ではなく、先輩科学者ギバリャンはいない
サルトリウスも実験室にこもって出てこない


<朗読>

<設定>

2つの太陽の周りをまわる「二重星」は実際にあるが、本来、軌道が不安定になったりするはず
この惑星は安定していて科学的に説明がつかない
このゼリー状の海は高度な知性をもつ生き物じゃないかという仮説が出てきて
この海そのものが小説の本当の主人公かもしれない
そもそもコンタクトできるのか 人類は研究してなんとか意思疎通を図ろうとしてきたがまだできていない状況
<構成メンバー>

サイバネティクス=人工頭脳学
伊集院:スナウトの手に血がついてるってサスペンスのにおいがしてくる
クリスはギバリャンがおかしくなったのではと連絡を受けて様子を探りに派遣されてきた
閉ざされた一種の極限状況で起きるミステリー
(1人が死んでるってネタばれしてしまって「あ」て、沼野さんお茶目w
ギバリャンは精神を病み自殺していた
クリスは巨体の黒人女性と出会う(映画になかったような?
サルの部屋からは子どもの笑い声がもれ聞こえる



「お前は一体何者だ?!」
実体のある彼らを「お客さん」と呼んでいる
クリスはある試みをする 人工衛星が送ってくるソラリスの軌道をあらわす数字と
自分が計算した数字がある誤差の範囲ならこれは幻覚ではない
数字を見て、自分が狂っていないことで希望が消える
疲れ果てて眠り、目が覚めると、彼がかつて愛したハリーという女性にそっくりな人物が座っている

ぬ:恐怖と、自分が正気であるかどう証明する科学者的な冷静さがせめぎあっている
伊集院:
「お前は一体何者だ?!」て言われるって、自分も“それ”なのかもしれないと思われてるってことですよね?
お客さんは誰か前半では明かされないが、人の記憶の奥深くに秘められたものを実体化した存在
不可解なことが多く、ヒトの理解、理性を超えたことが起きているのではないか
<本作がどうしてできたのか 20世紀の激動を経験した著者レムの人生>
テディベア抱いて可愛い

オーストリアから独立間もないポーランドでユダヤ人として産まれた
1939年 第二次世界大戦によりルヴフはソ連、次いでナチスドイツに占領され
知人の多くはホロコーストの虐殺で命を落とした



戦後、一家は財産を奪われ、ソ連領となった故郷を追われる
レムは戦争に翻弄されながら青年時代を過ごした

1995 自宅でのインタビュー:

「ところが実際はそうじゃない
たとえば私は戦前のポーランドで20年近く暮らしました
まずソ連の赤軍がやってきて、その後ドイツ軍、そしてまたもやソ連がやってきて
われわれをルヴフから追い出した
こうした恐ろしいほどの変化、体制の脆さを体験してきた
そして、あらゆるものは移ろいやすく、不確かだと思い知らされた
これこそまさに我々の20世紀の本質ですよ」
戦後、医学を学びながら、SF長編『金星応答なし』(1951)を発表し作家デビュー
初期の作品はスターリン支配の下、社会主義の影響を強く受けたユートピア的な作品だった



2年後、スターリン死去(1953)にともない、
ソ連、東欧では、文化・芸術が雪解けの時代を迎える


その中で書かれた『ソラリス』はレムの才能を一気に開花させた
ルヴフは今はウクライナ領 20世紀の間に支配国が5回変わったことになる
オーストリア→ポーランド→ソ連→ドイツ→ウクライナ
ぬ:
東欧の辺境に生きて、ユダヤ人として生き延びた体験は
絶対彼の世界観になんらかの影響を与えていると思う
<レムの思想とは>

ヒトは次第に傲慢になり、自分の理性が絶対と思うと、
世界も宇宙もなんでも分かったという立場になりがちだが
レムは宇宙にはヒトの理性では理解できないものがまだいっぱいある
宇宙を支配するなんてことはまだ出来ないんだという眼差し
ある種の政治、哲学をこれだけが正しいという目でしか見ない
共産主義、ナチスなど絶対的なものを押し付けてくるものに対して
これだけが正しいなんてことはないと疑いの目を持つ
真実は1つではない
言うのは易しいが、こうした彼の時世の中で貫くことはかなり大変なことだったと思う
ソラリスの海は、ヒトの理性を拒絶する、絶対的な他者
それに出会った場合、ヒトはどうするべきか ある意味道徳の問題がある
それを乱暴に殺してしまえという立場もあるが、
レムは他者の「違和感」に身を晒しながらも
そこから顔を背けない姿勢がある
 第2回 心の奥底にうごめくもの
第2回 心の奥底にうごめくもの
惑星ソラリスでは、思い出したくない記憶が実体化してあらわれる
クリスの前にも自殺したはずの恋人ハリーが現れる
ステーションの3人にも謎の存在がとり憑いていることが分かる
ぬ:
本作はヒトの記憶にまつわる物語
嬉しかったことより、恐ろしかったこと、悲しいこと、罪の記憶が傷のように残っていることが多い
大抵のヒトが「トラウマ」(心的外傷)を抱えていると思うが
いつもそれと向き合っていたら生きていけないので普通は封印してしまう
だが、一番封印したい記憶に向き合わされる
宇宙に行って他者に出会ったと思ったら、実は自分の一番心の奥底に出会うことになるところが面白い
<つづき>


ハリーを最後に見たのは10年前のはずが、彼女はまったく変わらぬ姿
だが、ドレスをめくると腕に注射針の跡がある
ハリーは10年前、クスリを注射して自殺した
脚にピックを刺して夢ではないと分かる
ドレスにはボタンがなく、ささいなことにクリスは違和感を覚える


<お客さんとは?>
ぬ:
ポーランド語では「存在F」と言っている 翻訳では私の訳語で「幽体F」という言葉を敢えて使った

ヒトの脳にはいろいろな情報が入っている
なにものかがそれを探り出して実体化する
形のない記憶や思い出を形にあらわす
しかも心の傷になっている一番痛ましい、おぞましいもの、二度と見たくないものをむしろ選び出して形にしてくる
ハリーの自殺はクリスが原因らしい
<ハリーの謎>
アナ:ボタンのことは、クリスは覚えてなかったということ?
ぬ:クリスは男だから、女性の服装については記憶に残ってなかった(なるほど!
伊集院:
CGで緻密に再現された世界でも、データがないと真っ暗な空間になってたり
テキトーな柄で埋め尽くされてるのと一緒ですね
ぬ:
面白いのはハリーはクリスと一瞬も離れたくない
愛してるからというより、物理的に離れられないような存在になっているようす
アナ:
ヒトなら感情で動くけれども、なんでか自分でも分からないのは
なにか別のモノで作られている感が出てる
ぬ:
それはクリスだけでなく、他のメンバーの幽体も記憶の主のヒトからまとわりついて離れられない
なにか非常に悲劇的なことがあって、トラウマになっている可能性がある
<つづき>
ハリーは実物そのもののようでいて違っていた
眠らないし、食事もとらない
彼女が本物ではないと確信したクリスはハリーを騙してロケットに押しこめ
厄介払いでもするように宇宙へと飛ばしてしまう
共通体験をしたクリスは、スナウトにハリーの自殺の経緯を話す
ケンカ別れをし、家を出たが、注射薬を忘れていたことを思い出して
3日目に帰るとハリーはそれを注射して死んでいた
「しかし一番恐ろしいのは、起きたことではなく、起こらなかったことだ
正常な人間とはなんだろう?
酷いこと、下劣なことを一度もしたことがない人間だろうか?
そんな人間がいるだろうか?」
伊集院:最後のほうすごい恐くて震えが止まらないですね
<幽体の排除>
ぬ:
クリスはある種パニックになって、とにかく消し去りたい
これなら絶対大丈夫だという方法が宇宙船に押しこめて飛ばすこと
どうやら他のメンバもいろいろ試して厄介払いをしては失敗している 絞め殺そうとしたりとか
ヒトは自分で理解できない他者を「排除」しようとする
アナ:「一番恐ろしいのは、起きたことではなく、起こらなかったことだ」とは?

2番目のことのほうが恐ろしいという
恐ろしいことを思い描いても実際にはやらないが
思っただけのことが形になって出てきたらどうなるか
伊集院:
僕、高校の時、すごい孤独に暮らしてたんですよ
学校にも行けなくて、世の中がなくなればいいと思っていて
すごい幼稚ですけど、ヤギの怪獣が出てきて、全部食べればいいと思っていた 集合写真を食べるみたいに
それを家でマンガに描いたことがある
オレの場合は、それが出る可能性がある
それは絶対恐い 病んでる時の妄想が出てきたら対処できない
とすると、スナウトはこの2番のほうが出てる可能性もあるってことですよね
<つづき>
スナウト:これが我々が望んでいたもの 異文明とのコンタクトさ
クリスが来る何年も前、ギが海に放射線をはなったことがあった
お客さんの到来はその10日後ほどから始まった
<お客さんは海からのコンタクト>
海がどうしてそうしたのか結局意図は分からないまま
怒って仕返しをしたのか、機械的反応なのか、単に遊んでいるだけなのか
スナウトが言っていることで面白いのは
ヒトは宇宙に出て他者とコンタクトしたいと思っているが
ヒト以外の全然違うものと出会いたいとは思ってなくて
自分の理想化した姿を宇宙に投影したがっている(なるほど
でも実際は、ヒトが隠してきた卑小な心の奥底を
拡大されて突きつけられてしまい、ヒトは受けつられない
逆説的なのは、どんどん大きな外の宇宙に出て行ったのに、還ってきたのは、
ヒトの一番心の奥底の世界にあった卑小なものが拡大されて突きつけられたということ
伊集院:
意図が分からないのが面白い
心の奥底を見せれば、一番の弱点を突いて、兵器より効果があると思っているのか
アナ:「おもてなしではないか」と書いてある本もあるとか?
ぬ:
おもてなしかもしれないし、復讐かもしれないし
この後、ハリーは戻ってきてしまい、2人の間にラブロマンスが展開する
でも、ヒトとヒトではないから、本当の意味でのラブロマンスではないわけですから
(そこが一番悲しいな
 第3回 人間とは何か? 自己とは何か?
第3回 人間とは何か? 自己とは何か?
ハリーは自分の存在に疑問を持ちはじめる
人間とは? そして愛とは?
ぬ:
クリスの場合は、愛した女性にもう一度会えるという
ある意味ではとても甘く切ない存在でもある
懐かしさと恐ろしさと両方に引き裂かれる
ここがこの小説の緊張感を盛り上げる要素
<つづき>
ハリーはクリスの仕打ちを知らずにまた戻ってくる


クリスを通して人間らしさを増していくハリー
ある時、クリスがベッドの下に隠したテープレコーダーを見つけて再生してしまう

そこには自殺したギが残した幽体Fの説明が残されていた
ハリーは自分が本物の人間ではないことを理解し、自身の存在に大きな疑問を持つ
アナ:戻ってきたハリーは、ロケットで飛ばされたハリーではない?
ぬ:
これがよく分からないが、同一体ではない
つまり、新しいハリーが作られて送りこまれてきた
これをどう考えたらいいのか
他の箇所で「ミモイド=擬態形成体」という言葉が出てくる
<海のつくりだすミモイド>

ぬ:
ソラリスの海は非常にフシギな能力を持っていて、変幻自在、いろんな形になるが
ヒトそのものに変身することもできる
ミモイドはレムが作った新造語 なにかにソックリの形のものを作る
ハリーもミモイドではないか
破壊できない 追い払ってもまた同じものが出て来るから不死身の存在
海はヒトの記憶を読み取って、常時、設計図をアップデートしていく
最初はハリーのコピーにすぎなかったものが、クリスと過ごすうちにだんだん変わっていく
個性を持っていく 幽体でありながら、元のハリーとは別の自意識が芽生えはじめるのが面白い
伊集院:
そこが最新のAIによく似ているなと思う
メーカー側のアップデートもあるけど、学習機能による成長もあるみたいな
アナ:クリスは別の人格としてハリーを愛し始めるわけですね
ぬ:
このハリーと過ごすうちに自分で引き受けようという覚悟が出て来る
ついに、ここを出て、他の場所へ行こうとする
本当の妻、パートナーとして生活を始めたいとまで言い出す
<幽体ハリーのけなげさ>
ぬ:
この小説の逆説的なところは、幽体ハリーは現代のヒトには陳腐で言えないようなことを
非常にピュアな真面目な気持ちで言って、2人の愛を確かめ合おうとしている構図になっている
伊集院:
本物のハリーではなくて、彼の心の中を分析して作られているであろうというところが
とてもよく出来てると思う 本物より魅力的、理想的だったりする
<つづき>
幽体Fは何者なのか クリスがハリーの血液を調べると、とてもよく出来ているが、
決定的に違うのは、素粒子「ニュートリノ」でできているのかもしれない
3人のメンバは急遽、電話会議を開く
サ:幽体を「ニュートリノ潰滅装置」で消滅させる と提案するがクリスは反対する
ク:潰滅する際に巨大な余剰エネルギーが生まれ、ステーションも吹き飛んでしまう
と言うが、実はハリーを消したくない思いからだった
ハリーは自分がクリスを苦しめているのではないかと思いつめる
ある夜、ハリーの姿がない
液体酸素を飲んで自殺したハリーが倒れている
気管も肺も焼けただれもだえ苦しむが、やがてよみがえる
ハリーは自分では存在を消せないと知る

伊集院:ハリーに感情移入するととても切ない話ですね
アナ:なぜハリーは自殺を図った?
ぬ:
幽体ハリーは自分の正体を知り、自分がいてはいけないと考えて
「自己犠牲」から自殺を図る 幽体ハリーがクリスを愛しているということでもある
<2人のハリーの自殺>
ぬ:
ここでは類似的な反復が行われているが、前のハリーの自殺は自己犠牲ではない
ケンカした後のある意味、腹いせというか「自己主張」のための自殺
ほんとに死ぬつもりではなく、クリスが気づいて助けてくれると思ってやったと思う
伊集院:
ハリーは狂言自殺をしようと思ったのに本当に死んでしまった
でも、幽体ハリーは純愛から本気で死のうと思ったが死ねないという対になってる
ぬ:同じ自殺でも全然動機が違うし、結果が違う
<自分の存在を問うハリー>



ぬ:
コピーをやめて自分の存在を問いはじめる
幽体ハリーはヒトじゃないはずなのに、自分はどこから来たのか、何者なのか
ある意味、究極の人間的な問い 存在的な問いに直面する
アナ:哲学の真髄みたいなことをコピーが言う
ぬ:ヒトにとって根本的な問いを幽体が言い出している
アナ:クリスを愛する気持ちは、実物より深いくらい 人間より人間らしい
ぬ:何が人間で、何が人間じゃないか、境界すら怪しくなってきている
<つづき>
クリスは自分のために死のうとしたハリーとともに生きる決意をする
クリスはハリーとともにステーションを出て行くとスナウトに告げると
クリスが愛しているのは自分の思い出に過ぎないと冷静に答える
科学者はある実験を試みる
眠っている時に記憶を読み取る海に対して、目覚めている時のクリスの脳波をX線照射するというもの


クリスは自分の心の中にハリーを疎んじる気持ちがないか
もしそれが海に伝われば、ハリーは消えてしまうのでは?と密かに脅える
伊集院:
スナウトの言ってることはよく分かる
かなりデオドラントされたハリーを好きだと言ってもちょっと違うんじゃないかい?ていう
相当痛いところを突かれている
ぬ:
幽体ハリーはこれまでクリスの過去の記憶で成長してきたと言えるけれども
でも、ここで過去の情報を新たに得ることを拒否したのが面白い
つまり、自分は昔の人間ハリーとは違う存在であると自己主張を始めた
伊集院:本来なら少しでも足りないデータが欲しいと言うはずですものね
アナ:女性としてはよく分かる 私を愛して欲しいんだっていう
伊集院:元カレに似てるから付き合ってるんだ、みたいなことを言われるのは嫌ですものね
<「脳電図照射」>
ぬ:
海はヒトが眠っている時に記憶を取っている
ヒトは眠っている時、理性などをコントロールできてないから
逆に目覚めている時の脳の情報を直接海に送り込めば違う結果が出るのではないかという発想
クリスの心の中に疎んじる気持ちがあれば、ハリーが消えてしまう可能性がある
でもクリスはもうハリーを愛しはじめていますから
アナ:結局、自分の心がずっと戦ってるみたいな
伊集院:この先どうなるのか連ドラ観ているみたいな 次早く観たい状況になっています
 第4回 不完全な神々のたわむれ
第4回 不完全な神々のたわむれ
クリスは幽体ハリーを愛しながらも超えられない違和感をぬぐえなかった

SF作家でもあり科学者である瀬名さんはレムから大きな影響を受けてきた
今は人工知能の最前線を取材している


<瀬名さんにとって『ソラリス』とは?>
瀬名さん:
大きなテーマの1つに、人間であるものと、人間でないものの違いは何かが描かれていて
現代のロボットや人工知能のテーマとまさにつながると思う
<瀬名さんの考えるロボットの3つのパターン>

コミュニケーションロボットは、たとえばアイボやペッパーくんのような
ヒトと会話をして、こちらの気持ちを向こうが感じてくれているように感じたりする
3つ目は最近よく出来てきている
タレントさんや落語家さんにソックリなロボット
ほんとにその人らしい部分もあれば、ここは違うぞというところもあり
「違和感の正体」てどこにあるんだろうにもつながる
ハリーと対面してなにかしっくりこない その違いが「その人らしさ」(個性だよね
【ブログ内関連記事】
 人間とは何か? アンドロイド研究最前線@サイエンスZERO
人間とは何か? アンドロイド研究最前線@サイエンスZERO
 こうすれば充実!親の介護@あさイチ
こうすれば充実!親の介護@あさイチ
<つづき>
「脳電図照射実験」
2日照射し、15日目、海に変化があらわれる
海の表層は2つに切り裂け濁りはじめた
翌日、光の斑点が全体に広がった(なんだかいい予感

突然、闇に包まれ、それ以来、新たな幽体はあらわれなくなった
クリスとハリーは地球に戻り穏やかに過ごすプランを立てる
だが、クリスはステーションが私たちが住める唯一の場所だと信じていた

アナ:海にはコンタクトできたと考えていい?
ぬ:どうしていいか分からないから、やってみたら功を奏した
瀬名:
実際コミュニケーションがとれたかは分からない
あいつらは幽体を嫌がったから送りこむのを止めようと思ったのか
コミュニケーション、知能ってそもそも何なんだろう?ってことをFは問いかけている
ぬ:
幽体ハリーが地球に戻ったら、まず戸籍をどうするんだとかねw
互いに自分を騙しながら、束の間の愛の時間を持っていた
<つづき>
ハリーは物思いにふけることが多くなり、クリスは彼女がふいに消えてしまうのではと不安になる
ハリーは喉が渇いたと2人でジュースを飲む(あれ? 幽体に飲食は必要なかったのでは? また変化したの?
いつのまにか眠り、ハリーは消えている
ハリーはスナウトが開発した「ニュートリノ潰滅装置」を使って自分を消滅させてしまった
「私から彼に頼んだことだ」というメモがあり、自ら実験台になったことが分かる
クリスはハリーは不死身だからまた戻ってくると希望的観測を願うが
スナウトは終始冷静で「X線照射の後は誰も戻ってこない」と言う

あいつ=海のこと
ぬ:
憎しみは相手を人間扱い、人間に準じたものと扱っているからできる
スナウトはあの海はそういう対象ではないと言っている
<結末>
クリスは改めて考え「ソラリスの海は、欠陥を持った神なのではないか」という考えに至る
一人ヘリコプターで海に向かうと、ミモイドの島がある

降り立つと半ば廃墟と化した古代都市のようなものが現れる
モロッコあたりが天変地異で崩れ落ちたようだった
(映画と随分違うぞ クリスの脳内の記憶の景色ではなくて?

“私は見惚れ、茫然となって、近寄りがたいと思われていた無為と無感動の領域に降りていき
ますます強まる強烈な自己喪失の感覚の中で、この目の見えない液体の巨人と一体になった
まるで一切努力もなく、言葉もなく、何も考えることなく、この巨人に対して
すべてを許せるような境地だったのだ
それでも、残酷な奇跡の時代が過ぎ去ったわけではないという信念を
私は揺るぎなく持ちつづけていたのだ”
その後、クリスが地球に戻ったかどうかはハッキリしない

<欠陥を持った神>
ぬ:
たしかにこれは唐突な終わりと言ってもいいかもしれない
最後に「欠陥を持った神」というのが出てきて、小説の結論めいたものになってしまう
恐らくこれはレムの一種の宇宙観だったと思う
宇宙では常に神々が生まれ、神々は人間が分からない次元で遊び戯れている
星を作ったり、消したりしてるのではないか
神ではあるが、自分でやったことに責任が取れなくなっちゃうような
強いて言えば「神さまの赤ん坊」のようなもの
それにヒトが翻弄されて、理解しようと頑張ったけれども
実は、子どもの神さまの遊びだったのかもしれない
アナ:
そう言われるとちょっと納得できる
赤ちゃんて同じことをしても笑ったり、怒ったりして、大人は翻弄される
瀬名:
ひょっとしたら、僕たちの深層意識を読んで、そこにあるんだから
大切なものだろうと思って「はい、どうぞ」てあげた
そこには「クリエティヴィティ(創造性)」があるという考え方
僕はクリスがここに一種の「希望」を見出したのではないかとも読んだ
アナ:クリスは地球に帰った?
ぬ:
すべての文学作品同様、ハッキリ言わずに読者に判断を委ねているところがある
最後の描写を見ると、帰りたいと思いつつ、目の前の他者に対して
背を向けて立ち去ろうとしていないように見える
アナ:
本書はタルコフスキー監督によって映画化されている
そこでは原作とラストシーンが違うことが話題になった
映画ではクリスは故郷の家にいて、両親と再会する
しかし、それはソラリスの海の上だった



<懐かしさに回帰する映画版のラスト>
ぬ:
このラストシーンは、限りなく懐かしい故郷
親が住んでいた家だけれども、カメラが引くとソラリスの海だった
タルコフスキーも含みをもたせている
そこはレムの姿勢とはまったく違っていると僕は思う
レムはこう解釈されるのが大嫌いみたいで、「このバカヤロウ」とタルコフスキーに言って
ポーランドへ帰ってしまった(映画ファンとしては残念・・・よくあることだけどw
瀬名:
レムは違和感を持ちつづけさせようとしたが、タルコフスキーは懐かしさ
「ノスタルジー」に転換してしまった
父に抱きついて懐かしさに溺れてしまう
(映画は映画としてタルコフスキー風味で良いのでは? それぞれの解釈なんだから
「違和感」とは、今の自分に対して関係性があるから保てるもの
でも、「懐かしさ」は今の自分とは時間的にもう切り離されている
今の自分とは無関係だから懐かしい
いや、まだまだこいつとは格闘できるところがあるんじゃないのかと一歩踏み出すのか
その辺がたぶん2人の違いだったと思う
(本人たちにしか分からないけどね
<「残酷な奇跡」とは>
「残酷な奇跡の時代が過ぎ去ったわけではないという信念を、私は揺るぎなく持ちつづけていたのだ」
ぬ:
宇宙にはヒトが理解できていない、ひょっとしたら素晴らしいかもしれないけど
ワケの分からないことがあって、それとヒトはこれから出会っていく
それは必ずしも愉しくて、甘いものばかりではない
出会ったことでこちらも影響を受けて変わらなければならない
厳しいものを突きつけられるかもしれないという意味で「残酷」と言っていると思う
でも、そういう新しい時代がこれからあるんだと確信しているのはレムらしい
(変わらなきゃ 人間のほうがよほどちっぽけな赤ん坊なんだから
瀬名:
レムは「違和」をそのまま持ち続けることこそが、ヒトらしい本当の勇気なのではないか
と言いたかったのではないかと思う
克服できない「違和感」としか言いようがないけれども、
それを持ち続けることこそ人間らしさではないか
伊集院:
無理やり屈服させようでも、巻かれてしまおうでもなく
「違和感」はあっても、「自分」も持ったままそこにいること
<『ソラリス』の現代性>
ぬ:
今作が論じていることは、今の世界にもものすごく関係があって
異質な他者と向き合うにはどうしたらいいか
難民であったり、外国人であったり、グローバル化の世の中でどんどん増えていくわけで、避けられない現実
分からないから嫌だと背を向けたり、他者を抹殺したりということが社会で起こらないとも限らない
レムの場合は宇宙を舞台にしたSFですから、現実とは関係ない絵空事のように読んでもいいけれども
レムの提起した問題は今にもつながっている
他者と付き合うのはキレイごとじゃない
自分がまったく変わらないで受け入れてあげましょうとかでは
本当に受け入れることにはならない
自分もそれに応じて変わらなければならない覚悟が必要だから
それは結構大変なこと
【出演】伊集院光、島津有理子アナウンサー
【指南役】沼野充義(東京大学教授、ロシア・東欧文学研究者)
【朗読】田中哲司(俳優)、中村優子(俳優)
【ゲスト】瀬名秀明(SF作家)
【ナレーション】小口貴子
 心の中のベストフィルム~『惑星ソラリス』(1972)
心の中のベストフィルム~『惑星ソラリス』(1972)私の大好きな映画と、哲さんがリンクするとはビックリ

番組内でも映画のシーンをたびたび使っているのも嬉しい

【内容抜粋メモ】
 第1回 未知なるものとのコンタクト
第1回 未知なるものとのコンタクト


ポーランド初のSF小説として40以上の言語に翻訳され半世紀以上読み継がれてきた
SF小説でありながら、人間の存在とは何か、哲学的な問いを投げかけてくる
難解なためなかなか読めないという人も多い
沼野さんは、高校時代に本作と出会い、ポーランド文学にのめりこんだ
ロシア語からの翻訳が多いところ、ポーランド語からの翻訳をして話題となり
著者とも長年にわたって交流を深めた

沼野さん:
自分にとっては原点のような小説
日本ではアメリカのSF小説が人気だが、まったく違う
面白いだけでなく、ちょっと怖くなる
形而上学的恐怖を感じる
読む前と後で自分が少し変わったような、世界が違って見えるような作品
<基本情報>

もう2編あるのか/驚
ファーストコンタクトとは?
最初の接触 SFの場合、宇宙にいるかもしれない地球外生命体と初めて接触した時
何が起きるのか、人間と分かりあえるのか、コミュニケーションができるのかを描くので、SFでは定番のテーマ
しかしレムは、人類の文明の未来、宇宙の起源に思考を発展させた
SFを超えたSFを作った人 メタ・サイエンスフィクションとも言われる
レムは「宇宙人と戦う
 」などのイメージに批評的な立場をとる SF批判のSF
」などのイメージに批評的な立場をとる SF批判のSF<内容>
宇宙科学者ケルヴィンは、宇宙を16ヶ月も旅し惑星ソラリスを目指した
赤と青の太陽の周りを複雑な軌道を描いて周回しているソラリスは
人類が100年以上も前に発見した惑星

惑星を覆う海は、高度な知性をもつ生命体のようで、まだ解明されていない謎めいた存在
その観測ステーションに派遣された(このアニメも本格的


到着すると、内部の荒れ果て様に当惑する
スナウト博士はなにかに脅えて正気ではなく、先輩科学者ギバリャンはいない
サルトリウスも実験室にこもって出てこない


<朗読>

<設定>

2つの太陽の周りをまわる「二重星」は実際にあるが、本来、軌道が不安定になったりするはず
この惑星は安定していて科学的に説明がつかない
このゼリー状の海は高度な知性をもつ生き物じゃないかという仮説が出てきて
この海そのものが小説の本当の主人公かもしれない
そもそもコンタクトできるのか 人類は研究してなんとか意思疎通を図ろうとしてきたがまだできていない状況
<構成メンバー>

サイバネティクス=人工頭脳学
伊集院:スナウトの手に血がついてるってサスペンスのにおいがしてくる
クリスはギバリャンがおかしくなったのではと連絡を受けて様子を探りに派遣されてきた
閉ざされた一種の極限状況で起きるミステリー
(1人が死んでるってネタばれしてしまって「あ」て、沼野さんお茶目w
ギバリャンは精神を病み自殺していた
クリスは巨体の黒人女性と出会う(映画になかったような?
サルの部屋からは子どもの笑い声がもれ聞こえる



「お前は一体何者だ?!」
実体のある彼らを「お客さん」と呼んでいる
クリスはある試みをする 人工衛星が送ってくるソラリスの軌道をあらわす数字と
自分が計算した数字がある誤差の範囲ならこれは幻覚ではない
数字を見て、自分が狂っていないことで希望が消える
疲れ果てて眠り、目が覚めると、彼がかつて愛したハリーという女性にそっくりな人物が座っている

ぬ:恐怖と、自分が正気であるかどう証明する科学者的な冷静さがせめぎあっている
伊集院:
「お前は一体何者だ?!」て言われるって、自分も“それ”なのかもしれないと思われてるってことですよね?
お客さんは誰か前半では明かされないが、人の記憶の奥深くに秘められたものを実体化した存在
不可解なことが多く、ヒトの理解、理性を超えたことが起きているのではないか
<本作がどうしてできたのか 20世紀の激動を経験した著者レムの人生>
テディベア抱いて可愛い

オーストリアから独立間もないポーランドでユダヤ人として産まれた
1939年 第二次世界大戦によりルヴフはソ連、次いでナチスドイツに占領され
知人の多くはホロコーストの虐殺で命を落とした



戦後、一家は財産を奪われ、ソ連領となった故郷を追われる
レムは戦争に翻弄されながら青年時代を過ごした

1995 自宅でのインタビュー:

「ところが実際はそうじゃない
たとえば私は戦前のポーランドで20年近く暮らしました
まずソ連の赤軍がやってきて、その後ドイツ軍、そしてまたもやソ連がやってきて
われわれをルヴフから追い出した
こうした恐ろしいほどの変化、体制の脆さを体験してきた
そして、あらゆるものは移ろいやすく、不確かだと思い知らされた
これこそまさに我々の20世紀の本質ですよ」
戦後、医学を学びながら、SF長編『金星応答なし』(1951)を発表し作家デビュー
初期の作品はスターリン支配の下、社会主義の影響を強く受けたユートピア的な作品だった



2年後、スターリン死去(1953)にともない、
ソ連、東欧では、文化・芸術が雪解けの時代を迎える


その中で書かれた『ソラリス』はレムの才能を一気に開花させた
ルヴフは今はウクライナ領 20世紀の間に支配国が5回変わったことになる
オーストリア→ポーランド→ソ連→ドイツ→ウクライナ
ぬ:
東欧の辺境に生きて、ユダヤ人として生き延びた体験は
絶対彼の世界観になんらかの影響を与えていると思う
<レムの思想とは>

ヒトは次第に傲慢になり、自分の理性が絶対と思うと、
世界も宇宙もなんでも分かったという立場になりがちだが
レムは宇宙にはヒトの理性では理解できないものがまだいっぱいある
宇宙を支配するなんてことはまだ出来ないんだという眼差し
ある種の政治、哲学をこれだけが正しいという目でしか見ない
共産主義、ナチスなど絶対的なものを押し付けてくるものに対して
これだけが正しいなんてことはないと疑いの目を持つ
真実は1つではない
言うのは易しいが、こうした彼の時世の中で貫くことはかなり大変なことだったと思う
ソラリスの海は、ヒトの理性を拒絶する、絶対的な他者
それに出会った場合、ヒトはどうするべきか ある意味道徳の問題がある
それを乱暴に殺してしまえという立場もあるが、
レムは他者の「違和感」に身を晒しながらも
そこから顔を背けない姿勢がある
 第2回 心の奥底にうごめくもの
第2回 心の奥底にうごめくもの惑星ソラリスでは、思い出したくない記憶が実体化してあらわれる
クリスの前にも自殺したはずの恋人ハリーが現れる
ステーションの3人にも謎の存在がとり憑いていることが分かる
ぬ:
本作はヒトの記憶にまつわる物語
嬉しかったことより、恐ろしかったこと、悲しいこと、罪の記憶が傷のように残っていることが多い
大抵のヒトが「トラウマ」(心的外傷)を抱えていると思うが
いつもそれと向き合っていたら生きていけないので普通は封印してしまう
だが、一番封印したい記憶に向き合わされる
宇宙に行って他者に出会ったと思ったら、実は自分の一番心の奥底に出会うことになるところが面白い
<つづき>


ハリーを最後に見たのは10年前のはずが、彼女はまったく変わらぬ姿
だが、ドレスをめくると腕に注射針の跡がある
ハリーは10年前、クスリを注射して自殺した
脚にピックを刺して夢ではないと分かる
ドレスにはボタンがなく、ささいなことにクリスは違和感を覚える


<お客さんとは?>
ぬ:
ポーランド語では「存在F」と言っている 翻訳では私の訳語で「幽体F」という言葉を敢えて使った

ヒトの脳にはいろいろな情報が入っている
なにものかがそれを探り出して実体化する
形のない記憶や思い出を形にあらわす
しかも心の傷になっている一番痛ましい、おぞましいもの、二度と見たくないものをむしろ選び出して形にしてくる
ハリーの自殺はクリスが原因らしい
<ハリーの謎>
アナ:ボタンのことは、クリスは覚えてなかったということ?
ぬ:クリスは男だから、女性の服装については記憶に残ってなかった(なるほど!
伊集院:
CGで緻密に再現された世界でも、データがないと真っ暗な空間になってたり
テキトーな柄で埋め尽くされてるのと一緒ですね
ぬ:
面白いのはハリーはクリスと一瞬も離れたくない
愛してるからというより、物理的に離れられないような存在になっているようす
アナ:
ヒトなら感情で動くけれども、なんでか自分でも分からないのは
なにか別のモノで作られている感が出てる
ぬ:
それはクリスだけでなく、他のメンバーの幽体も記憶の主のヒトからまとわりついて離れられない
なにか非常に悲劇的なことがあって、トラウマになっている可能性がある
<つづき>
ハリーは実物そのもののようでいて違っていた
眠らないし、食事もとらない
彼女が本物ではないと確信したクリスはハリーを騙してロケットに押しこめ
厄介払いでもするように宇宙へと飛ばしてしまう
共通体験をしたクリスは、スナウトにハリーの自殺の経緯を話す
ケンカ別れをし、家を出たが、注射薬を忘れていたことを思い出して
3日目に帰るとハリーはそれを注射して死んでいた
「しかし一番恐ろしいのは、起きたことではなく、起こらなかったことだ
正常な人間とはなんだろう?
酷いこと、下劣なことを一度もしたことがない人間だろうか?
そんな人間がいるだろうか?」
伊集院:最後のほうすごい恐くて震えが止まらないですね
<幽体の排除>
ぬ:
クリスはある種パニックになって、とにかく消し去りたい
これなら絶対大丈夫だという方法が宇宙船に押しこめて飛ばすこと
どうやら他のメンバもいろいろ試して厄介払いをしては失敗している 絞め殺そうとしたりとか
ヒトは自分で理解できない他者を「排除」しようとする
アナ:「一番恐ろしいのは、起きたことではなく、起こらなかったことだ」とは?

2番目のことのほうが恐ろしいという
恐ろしいことを思い描いても実際にはやらないが
思っただけのことが形になって出てきたらどうなるか
伊集院:
僕、高校の時、すごい孤独に暮らしてたんですよ
学校にも行けなくて、世の中がなくなればいいと思っていて
すごい幼稚ですけど、ヤギの怪獣が出てきて、全部食べればいいと思っていた 集合写真を食べるみたいに
それを家でマンガに描いたことがある
オレの場合は、それが出る可能性がある
それは絶対恐い 病んでる時の妄想が出てきたら対処できない
とすると、スナウトはこの2番のほうが出てる可能性もあるってことですよね
<つづき>
スナウト:これが我々が望んでいたもの 異文明とのコンタクトさ
クリスが来る何年も前、ギが海に放射線をはなったことがあった
お客さんの到来はその10日後ほどから始まった
<お客さんは海からのコンタクト>
海がどうしてそうしたのか結局意図は分からないまま
怒って仕返しをしたのか、機械的反応なのか、単に遊んでいるだけなのか
スナウトが言っていることで面白いのは
ヒトは宇宙に出て他者とコンタクトしたいと思っているが
ヒト以外の全然違うものと出会いたいとは思ってなくて
自分の理想化した姿を宇宙に投影したがっている(なるほど
でも実際は、ヒトが隠してきた卑小な心の奥底を
拡大されて突きつけられてしまい、ヒトは受けつられない
逆説的なのは、どんどん大きな外の宇宙に出て行ったのに、還ってきたのは、
ヒトの一番心の奥底の世界にあった卑小なものが拡大されて突きつけられたということ
伊集院:
意図が分からないのが面白い
心の奥底を見せれば、一番の弱点を突いて、兵器より効果があると思っているのか
アナ:「おもてなしではないか」と書いてある本もあるとか?
ぬ:
おもてなしかもしれないし、復讐かもしれないし
この後、ハリーは戻ってきてしまい、2人の間にラブロマンスが展開する
でも、ヒトとヒトではないから、本当の意味でのラブロマンスではないわけですから
(そこが一番悲しいな
 第3回 人間とは何か? 自己とは何か?
第3回 人間とは何か? 自己とは何か?ハリーは自分の存在に疑問を持ちはじめる
人間とは? そして愛とは?
ぬ:
クリスの場合は、愛した女性にもう一度会えるという
ある意味ではとても甘く切ない存在でもある
懐かしさと恐ろしさと両方に引き裂かれる
ここがこの小説の緊張感を盛り上げる要素
<つづき>
ハリーはクリスの仕打ちを知らずにまた戻ってくる


クリスを通して人間らしさを増していくハリー
ある時、クリスがベッドの下に隠したテープレコーダーを見つけて再生してしまう

そこには自殺したギが残した幽体Fの説明が残されていた
ハリーは自分が本物の人間ではないことを理解し、自身の存在に大きな疑問を持つ
アナ:戻ってきたハリーは、ロケットで飛ばされたハリーではない?
ぬ:
これがよく分からないが、同一体ではない
つまり、新しいハリーが作られて送りこまれてきた
これをどう考えたらいいのか
他の箇所で「ミモイド=擬態形成体」という言葉が出てくる
<海のつくりだすミモイド>

ぬ:
ソラリスの海は非常にフシギな能力を持っていて、変幻自在、いろんな形になるが
ヒトそのものに変身することもできる
ミモイドはレムが作った新造語 なにかにソックリの形のものを作る
ハリーもミモイドではないか
破壊できない 追い払ってもまた同じものが出て来るから不死身の存在
海はヒトの記憶を読み取って、常時、設計図をアップデートしていく
最初はハリーのコピーにすぎなかったものが、クリスと過ごすうちにだんだん変わっていく
個性を持っていく 幽体でありながら、元のハリーとは別の自意識が芽生えはじめるのが面白い
伊集院:
そこが最新のAIによく似ているなと思う
メーカー側のアップデートもあるけど、学習機能による成長もあるみたいな
アナ:クリスは別の人格としてハリーを愛し始めるわけですね
ぬ:
このハリーと過ごすうちに自分で引き受けようという覚悟が出て来る
ついに、ここを出て、他の場所へ行こうとする
本当の妻、パートナーとして生活を始めたいとまで言い出す
<幽体ハリーのけなげさ>
ぬ:
この小説の逆説的なところは、幽体ハリーは現代のヒトには陳腐で言えないようなことを
非常にピュアな真面目な気持ちで言って、2人の愛を確かめ合おうとしている構図になっている
伊集院:
本物のハリーではなくて、彼の心の中を分析して作られているであろうというところが
とてもよく出来てると思う 本物より魅力的、理想的だったりする
<つづき>
幽体Fは何者なのか クリスがハリーの血液を調べると、とてもよく出来ているが、
決定的に違うのは、素粒子「ニュートリノ」でできているのかもしれない
3人のメンバは急遽、電話会議を開く
サ:幽体を「ニュートリノ潰滅装置」で消滅させる と提案するがクリスは反対する
ク:潰滅する際に巨大な余剰エネルギーが生まれ、ステーションも吹き飛んでしまう
と言うが、実はハリーを消したくない思いからだった
ハリーは自分がクリスを苦しめているのではないかと思いつめる
ある夜、ハリーの姿がない
液体酸素を飲んで自殺したハリーが倒れている
気管も肺も焼けただれもだえ苦しむが、やがてよみがえる
ハリーは自分では存在を消せないと知る

伊集院:ハリーに感情移入するととても切ない話ですね
アナ:なぜハリーは自殺を図った?
ぬ:
幽体ハリーは自分の正体を知り、自分がいてはいけないと考えて
「自己犠牲」から自殺を図る 幽体ハリーがクリスを愛しているということでもある
<2人のハリーの自殺>
ぬ:
ここでは類似的な反復が行われているが、前のハリーの自殺は自己犠牲ではない
ケンカした後のある意味、腹いせというか「自己主張」のための自殺
ほんとに死ぬつもりではなく、クリスが気づいて助けてくれると思ってやったと思う
伊集院:
ハリーは狂言自殺をしようと思ったのに本当に死んでしまった
でも、幽体ハリーは純愛から本気で死のうと思ったが死ねないという対になってる
ぬ:同じ自殺でも全然動機が違うし、結果が違う
<自分の存在を問うハリー>



ぬ:
コピーをやめて自分の存在を問いはじめる
幽体ハリーはヒトじゃないはずなのに、自分はどこから来たのか、何者なのか
ある意味、究極の人間的な問い 存在的な問いに直面する
アナ:哲学の真髄みたいなことをコピーが言う
ぬ:ヒトにとって根本的な問いを幽体が言い出している
アナ:クリスを愛する気持ちは、実物より深いくらい 人間より人間らしい
ぬ:何が人間で、何が人間じゃないか、境界すら怪しくなってきている
<つづき>
クリスは自分のために死のうとしたハリーとともに生きる決意をする
クリスはハリーとともにステーションを出て行くとスナウトに告げると
クリスが愛しているのは自分の思い出に過ぎないと冷静に答える
科学者はある実験を試みる
眠っている時に記憶を読み取る海に対して、目覚めている時のクリスの脳波をX線照射するというもの


クリスは自分の心の中にハリーを疎んじる気持ちがないか
もしそれが海に伝われば、ハリーは消えてしまうのでは?と密かに脅える
伊集院:
スナウトの言ってることはよく分かる
かなりデオドラントされたハリーを好きだと言ってもちょっと違うんじゃないかい?ていう
相当痛いところを突かれている
ぬ:
幽体ハリーはこれまでクリスの過去の記憶で成長してきたと言えるけれども
でも、ここで過去の情報を新たに得ることを拒否したのが面白い
つまり、自分は昔の人間ハリーとは違う存在であると自己主張を始めた
伊集院:本来なら少しでも足りないデータが欲しいと言うはずですものね
アナ:女性としてはよく分かる 私を愛して欲しいんだっていう
伊集院:元カレに似てるから付き合ってるんだ、みたいなことを言われるのは嫌ですものね
<「脳電図照射」>
ぬ:
海はヒトが眠っている時に記憶を取っている
ヒトは眠っている時、理性などをコントロールできてないから
逆に目覚めている時の脳の情報を直接海に送り込めば違う結果が出るのではないかという発想
クリスの心の中に疎んじる気持ちがあれば、ハリーが消えてしまう可能性がある
でもクリスはもうハリーを愛しはじめていますから
アナ:結局、自分の心がずっと戦ってるみたいな
伊集院:この先どうなるのか連ドラ観ているみたいな 次早く観たい状況になっています
 第4回 不完全な神々のたわむれ
第4回 不完全な神々のたわむれクリスは幽体ハリーを愛しながらも超えられない違和感をぬぐえなかった

SF作家でもあり科学者である瀬名さんはレムから大きな影響を受けてきた
今は人工知能の最前線を取材している


<瀬名さんにとって『ソラリス』とは?>
瀬名さん:
大きなテーマの1つに、人間であるものと、人間でないものの違いは何かが描かれていて
現代のロボットや人工知能のテーマとまさにつながると思う
<瀬名さんの考えるロボットの3つのパターン>

コミュニケーションロボットは、たとえばアイボやペッパーくんのような
ヒトと会話をして、こちらの気持ちを向こうが感じてくれているように感じたりする
3つ目は最近よく出来てきている
タレントさんや落語家さんにソックリなロボット
ほんとにその人らしい部分もあれば、ここは違うぞというところもあり
「違和感の正体」てどこにあるんだろうにもつながる
ハリーと対面してなにかしっくりこない その違いが「その人らしさ」(個性だよね
【ブログ内関連記事】
 人間とは何か? アンドロイド研究最前線@サイエンスZERO
人間とは何か? アンドロイド研究最前線@サイエンスZERO こうすれば充実!親の介護@あさイチ
こうすれば充実!親の介護@あさイチ<つづき>
「脳電図照射実験」
2日照射し、15日目、海に変化があらわれる
海の表層は2つに切り裂け濁りはじめた
翌日、光の斑点が全体に広がった(なんだかいい予感

突然、闇に包まれ、それ以来、新たな幽体はあらわれなくなった
クリスとハリーは地球に戻り穏やかに過ごすプランを立てる
だが、クリスはステーションが私たちが住める唯一の場所だと信じていた

アナ:海にはコンタクトできたと考えていい?
ぬ:どうしていいか分からないから、やってみたら功を奏した
瀬名:
実際コミュニケーションがとれたかは分からない
あいつらは幽体を嫌がったから送りこむのを止めようと思ったのか
コミュニケーション、知能ってそもそも何なんだろう?ってことをFは問いかけている
ぬ:
幽体ハリーが地球に戻ったら、まず戸籍をどうするんだとかねw
互いに自分を騙しながら、束の間の愛の時間を持っていた
<つづき>
ハリーは物思いにふけることが多くなり、クリスは彼女がふいに消えてしまうのではと不安になる
ハリーは喉が渇いたと2人でジュースを飲む(あれ? 幽体に飲食は必要なかったのでは? また変化したの?
いつのまにか眠り、ハリーは消えている
ハリーはスナウトが開発した「ニュートリノ潰滅装置」を使って自分を消滅させてしまった
「私から彼に頼んだことだ」というメモがあり、自ら実験台になったことが分かる
クリスはハリーは不死身だからまた戻ってくると希望的観測を願うが
スナウトは終始冷静で「X線照射の後は誰も戻ってこない」と言う

あいつ=海のこと
ぬ:
憎しみは相手を人間扱い、人間に準じたものと扱っているからできる
スナウトはあの海はそういう対象ではないと言っている
<結末>
クリスは改めて考え「ソラリスの海は、欠陥を持った神なのではないか」という考えに至る
一人ヘリコプターで海に向かうと、ミモイドの島がある

降り立つと半ば廃墟と化した古代都市のようなものが現れる
モロッコあたりが天変地異で崩れ落ちたようだった
(映画と随分違うぞ クリスの脳内の記憶の景色ではなくて?

“私は見惚れ、茫然となって、近寄りがたいと思われていた無為と無感動の領域に降りていき
ますます強まる強烈な自己喪失の感覚の中で、この目の見えない液体の巨人と一体になった
まるで一切努力もなく、言葉もなく、何も考えることなく、この巨人に対して
すべてを許せるような境地だったのだ
それでも、残酷な奇跡の時代が過ぎ去ったわけではないという信念を
私は揺るぎなく持ちつづけていたのだ”
その後、クリスが地球に戻ったかどうかはハッキリしない

<欠陥を持った神>
ぬ:
たしかにこれは唐突な終わりと言ってもいいかもしれない
最後に「欠陥を持った神」というのが出てきて、小説の結論めいたものになってしまう
恐らくこれはレムの一種の宇宙観だったと思う
宇宙では常に神々が生まれ、神々は人間が分からない次元で遊び戯れている
星を作ったり、消したりしてるのではないか
神ではあるが、自分でやったことに責任が取れなくなっちゃうような
強いて言えば「神さまの赤ん坊」のようなもの
それにヒトが翻弄されて、理解しようと頑張ったけれども
実は、子どもの神さまの遊びだったのかもしれない
アナ:
そう言われるとちょっと納得できる
赤ちゃんて同じことをしても笑ったり、怒ったりして、大人は翻弄される
瀬名:
ひょっとしたら、僕たちの深層意識を読んで、そこにあるんだから
大切なものだろうと思って「はい、どうぞ」てあげた
そこには「クリエティヴィティ(創造性)」があるという考え方
僕はクリスがここに一種の「希望」を見出したのではないかとも読んだ
アナ:クリスは地球に帰った?
ぬ:
すべての文学作品同様、ハッキリ言わずに読者に判断を委ねているところがある
最後の描写を見ると、帰りたいと思いつつ、目の前の他者に対して
背を向けて立ち去ろうとしていないように見える
アナ:
本書はタルコフスキー監督によって映画化されている
そこでは原作とラストシーンが違うことが話題になった
映画ではクリスは故郷の家にいて、両親と再会する
しかし、それはソラリスの海の上だった



<懐かしさに回帰する映画版のラスト>
ぬ:
このラストシーンは、限りなく懐かしい故郷
親が住んでいた家だけれども、カメラが引くとソラリスの海だった
タルコフスキーも含みをもたせている
そこはレムの姿勢とはまったく違っていると僕は思う
レムはこう解釈されるのが大嫌いみたいで、「このバカヤロウ」とタルコフスキーに言って
ポーランドへ帰ってしまった(映画ファンとしては残念・・・よくあることだけどw
瀬名:
レムは違和感を持ちつづけさせようとしたが、タルコフスキーは懐かしさ
「ノスタルジー」に転換してしまった
父に抱きついて懐かしさに溺れてしまう
(映画は映画としてタルコフスキー風味で良いのでは? それぞれの解釈なんだから
「違和感」とは、今の自分に対して関係性があるから保てるもの
でも、「懐かしさ」は今の自分とは時間的にもう切り離されている
今の自分とは無関係だから懐かしい
いや、まだまだこいつとは格闘できるところがあるんじゃないのかと一歩踏み出すのか
その辺がたぶん2人の違いだったと思う
(本人たちにしか分からないけどね
<「残酷な奇跡」とは>
「残酷な奇跡の時代が過ぎ去ったわけではないという信念を、私は揺るぎなく持ちつづけていたのだ」
ぬ:
宇宙にはヒトが理解できていない、ひょっとしたら素晴らしいかもしれないけど
ワケの分からないことがあって、それとヒトはこれから出会っていく
それは必ずしも愉しくて、甘いものばかりではない
出会ったことでこちらも影響を受けて変わらなければならない
厳しいものを突きつけられるかもしれないという意味で「残酷」と言っていると思う
でも、そういう新しい時代がこれからあるんだと確信しているのはレムらしい
(変わらなきゃ 人間のほうがよほどちっぽけな赤ん坊なんだから
瀬名:
レムは「違和」をそのまま持ち続けることこそが、ヒトらしい本当の勇気なのではないか
と言いたかったのではないかと思う
克服できない「違和感」としか言いようがないけれども、
それを持ち続けることこそ人間らしさではないか
伊集院:
無理やり屈服させようでも、巻かれてしまおうでもなく
「違和感」はあっても、「自分」も持ったままそこにいること
<『ソラリス』の現代性>
ぬ:
今作が論じていることは、今の世界にもものすごく関係があって
異質な他者と向き合うにはどうしたらいいか
難民であったり、外国人であったり、グローバル化の世の中でどんどん増えていくわけで、避けられない現実
分からないから嫌だと背を向けたり、他者を抹殺したりということが社会で起こらないとも限らない
レムの場合は宇宙を舞台にしたSFですから、現実とは関係ない絵空事のように読んでもいいけれども
レムの提起した問題は今にもつながっている
他者と付き合うのはキレイごとじゃない
自分がまったく変わらないで受け入れてあげましょうとかでは
本当に受け入れることにはならない
自分もそれに応じて変わらなければならない覚悟が必要だから
それは結構大変なこと