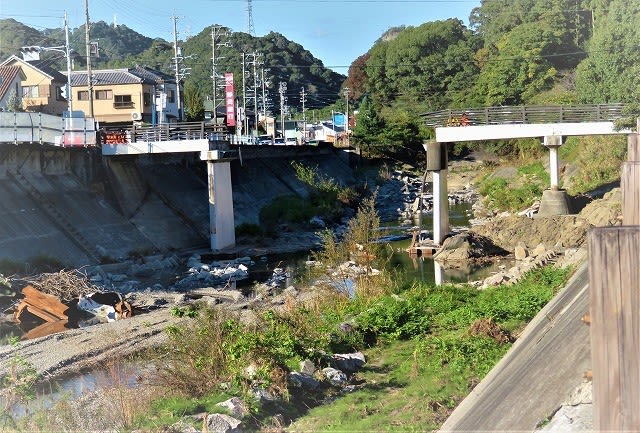今月の上旬に畑の畝立てをしてから黒マルチを施し、中旬には野菜の種も撒いてきた。そろそろ、野菜の芽が出るころかなと様子を見に行く。するとなんと、畝と畝との間にハトムギの芽がニョキニョキでているではないか。昨年バケツ一杯分も収穫したのに、こぼれ種が多数畑に残っていたことが判明した。

心配になって黒マルチをめくってみると、やっぱり同じように芽が出ていた。ハトムギの生命力を考えると多少の予想はしていたものの、いやはや予想を大きく超えていた。10cm以上を越える新芽も少なくない。これは畝を全部やり直さないとダメかと覚悟を決めた。一本一本抜いていくと時間がかかる。しかし、畝全体を見たら、ハトムギの「爆発」は半分くらいだったことが分かった。

初冬に抜根しておいたハトムギの根っこを見てみると一部はまだ生きていた。この生命力は尋常ではないと痛感する。バーチャルな文明と戦争に明け暮れる人類に対する怒髪天の怒りだろうか。
ハトムギを利用した製品はけっこう様々なジャンルで販売されていることがわかる。わが家ではフライパンで焙煎してハト麦茶を飲んでいる。硬い殻をうまく除去できればいいが、それには数十万円もする機器が必要だ。

したがって、体に良いのがわかりながらもシコシコ対応するしかないのが現状だ。今年のハトムギ栽培はこぼれ種でも十分対応できる。わが家はこのところこういうこぼれ種で栽培するぐーたら栽培や放任栽培が多くなってしまった。放任の山菜や果樹はその最たるものだ。それでも、食べきれなくて近隣にお裾分けすると、返礼品がやってきてそれがまた食卓を豊富に補充してくれるという循環だ。貧乏だが「わらしべ長者」のような満足感がそこにはある。さて、ハトムギをいかに活用しようか、宿題が出されている。