本日、 後
後 。
。
前日のスクールの疲れを癒すため、月曜日の午前中はのらりくらり野良仕事をしました。
菜園教室が表の仕事だとすると、裏の仕事は自給自足の野良仕事などになります。
週末働いて、平日自給自足の暮らしをはじめて、早7年目。
いろいろあり、退屈せずに楽しめるようになってきたように思います。
今日のブログは、週末の菜園教室の後編(午後)の実習をご紹介します。

Azumino自給農スクールの自然菜園実践コースの午前が栽培についてであれば、
午後は、自給できる農園創りについて実習を行っております。
今回は、堆肥造りの応用技術「改良型橋本式踏み込み温床」つくりの体験です。
前回、自然育苗コースで造った堆肥の山は、見事に3日で40℃を超す温度があがりました。
そこで、今回発酵をはじめた堆肥の山を

ハウス内の枠の中に投入します。
保温できるように、ハウス内には穴が掘られ、ワラなどが敷きつめられています。

堆肥を山をフォークや手で、一輪車に積まれ、

どんどんハウス内に一輪車リレーで運び込まれます。

堆肥は発酵の際に、湯気を出し水が蒸発してしまうので、
ジョウロで加水しながら堆肥の山を重ねていきます。


踏み込み温床の由来でもある、堆肥の踏み込みは、コツがありみんなでほかほかの温床を踏み込みました。


最終的には、土とクン炭で整地するのですが、今回はそれまでに数日あるので、
ネズミ対策で焼きたての火の匂いが残るクン炭を撒きました。

クン炭の上から

ムシロなど保温できるものを敷いてから、

保険に、激辛トウガラシ「ブードジョロキアーノ」を漬けた木酢液をかけて、ネズミの温床にならないように念を入れました。

最後に、ハウスの外でクン炭を焼いて、1日の自然菜園実践コース終了でした。
踏み込み温床は、古の業(わざ)です。
農業を農の商売という方もいらっしゃいますが、師匠曰く「農業は、農の業(わざ)。」、
生きていくための業(わざ)だとおもいます。
踏み込み温床は、夏野菜の苗を、寒い時期から育てるために欠かせないもので、
今は、堆肥造りが大変ということもあり、電熱線に代わってしまいましたが、
踏み込み温床は、堆肥から出る二酸化炭素が、光合成率を高め、良い苗を育てると再評価されてきています。
便利さとは何か、福岡正信師の言葉が思い出されます。
「便利とは、不便をつくり、不便の状態を解消すること」とおっしゃっていました。
含蓄のある深い言葉だと思います。
Azumino自給農スクールでは、師匠たちが教えてくれた自然の営み、自然の智慧をお伝えできたらと思います。
次回の自然菜園実践コースは4月27日(土)です。土曜日なのでお間違えなく、、、。
4月のカルチャーセンター教室
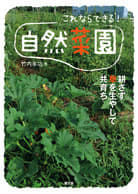
◆『これならできる!無農薬 自然菜園入門』
松本教室(NHKカルチャー)
長野教室(メルパルクカルチャー、城山公民館教室)

◆『はじめよう日本みつばち自然養蜂 重箱式の巣箱を作る』
在来の日本みつばちの自然養蜂の基礎から、取り込み方まで学びます。組み立てるだけの簡単な伝統的な重箱式の巣箱を作ります。今年の春から養蜂に挑戦できます。
■日本みつばち自然養蜂とは?
■重箱式の巣箱を作る
■質疑応答
3/29(金) 13:00~16:00
**********************************
2013年度の自然菜園講座の一つ「あずみの自然農塾2013(第7期)」の募集が始まりました!
まだ若干名余裕がございます。

2012年12月の講座での集合写真
「あずみの自然農塾2013(第7期)」の募集が始まりました!(12/25~2月末)
先着24名。耕さず、草と虫を敵としない川口由一さんのはじめた自然農に特化したシャロムヒュッテに1泊2日しながら、全10回の体験型ワークショップです。
耕さない田んぼに、畑で実際に、自然の理を学び、実践できます。
しかも、自分の小さな菜園区画が付いているので、3~12月の間自然農で野菜を育てることができます。
半農半Xの暮らし、自然農にご興味がある方にお奨めの講座です。
自然農法で自給自足の農園が学べる「Azumino自給農スクール2013」
穂高養生園で、日帰りも食事、宿泊もできる自然菜園入門講座も間もなく募集がはじまります。
お好みでお選びください。
【お迷いの方へ】
・耕さない自然農を学びたいなら→「あずみの自然農塾2013(第7期)」
・無農薬栽培の基本から応用を学び、我が家の自給率をアップしたいなら→「Azumino自給農スクール2013」
【拙著のご紹介】
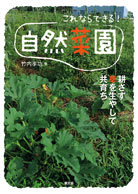
『これならできる!自然菜園』

『コンパニオンプランツで失敗しらずのコンテナ菜園』
好評発売中~
 後
後 。
。前日のスクールの疲れを癒すため、月曜日の午前中はのらりくらり野良仕事をしました。
菜園教室が表の仕事だとすると、裏の仕事は自給自足の野良仕事などになります。
週末働いて、平日自給自足の暮らしをはじめて、早7年目。
いろいろあり、退屈せずに楽しめるようになってきたように思います。
今日のブログは、週末の菜園教室の後編(午後)の実習をご紹介します。

Azumino自給農スクールの自然菜園実践コースの午前が栽培についてであれば、
午後は、自給できる農園創りについて実習を行っております。
今回は、堆肥造りの応用技術「改良型橋本式踏み込み温床」つくりの体験です。
前回、自然育苗コースで造った堆肥の山は、見事に3日で40℃を超す温度があがりました。
そこで、今回発酵をはじめた堆肥の山を

ハウス内の枠の中に投入します。
保温できるように、ハウス内には穴が掘られ、ワラなどが敷きつめられています。

堆肥を山をフォークや手で、一輪車に積まれ、

どんどんハウス内に一輪車リレーで運び込まれます。

堆肥は発酵の際に、湯気を出し水が蒸発してしまうので、
ジョウロで加水しながら堆肥の山を重ねていきます。


踏み込み温床の由来でもある、堆肥の踏み込みは、コツがありみんなでほかほかの温床を踏み込みました。


最終的には、土とクン炭で整地するのですが、今回はそれまでに数日あるので、
ネズミ対策で焼きたての火の匂いが残るクン炭を撒きました。

クン炭の上から

ムシロなど保温できるものを敷いてから、

保険に、激辛トウガラシ「ブードジョロキアーノ」を漬けた木酢液をかけて、ネズミの温床にならないように念を入れました。

最後に、ハウスの外でクン炭を焼いて、1日の自然菜園実践コース終了でした。
踏み込み温床は、古の業(わざ)です。
農業を農の商売という方もいらっしゃいますが、師匠曰く「農業は、農の業(わざ)。」、
生きていくための業(わざ)だとおもいます。
踏み込み温床は、夏野菜の苗を、寒い時期から育てるために欠かせないもので、
今は、堆肥造りが大変ということもあり、電熱線に代わってしまいましたが、
踏み込み温床は、堆肥から出る二酸化炭素が、光合成率を高め、良い苗を育てると再評価されてきています。
便利さとは何か、福岡正信師の言葉が思い出されます。
「便利とは、不便をつくり、不便の状態を解消すること」とおっしゃっていました。
含蓄のある深い言葉だと思います。
Azumino自給農スクールでは、師匠たちが教えてくれた自然の営み、自然の智慧をお伝えできたらと思います。
次回の自然菜園実践コースは4月27日(土)です。土曜日なのでお間違えなく、、、。
4月のカルチャーセンター教室
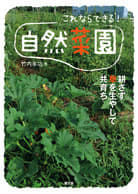
◆『これならできる!無農薬 自然菜園入門』
松本教室(NHKカルチャー)
長野教室(メルパルクカルチャー、城山公民館教室)

◆『はじめよう日本みつばち自然養蜂 重箱式の巣箱を作る』
在来の日本みつばちの自然養蜂の基礎から、取り込み方まで学びます。組み立てるだけの簡単な伝統的な重箱式の巣箱を作ります。今年の春から養蜂に挑戦できます。
■日本みつばち自然養蜂とは?
■重箱式の巣箱を作る
■質疑応答
3/29(金) 13:00~16:00
**********************************
2013年度の自然菜園講座の一つ「あずみの自然農塾2013(第7期)」の募集が始まりました!
まだ若干名余裕がございます。

2012年12月の講座での集合写真
「あずみの自然農塾2013(第7期)」の募集が始まりました!(12/25~2月末)
先着24名。耕さず、草と虫を敵としない川口由一さんのはじめた自然農に特化したシャロムヒュッテに1泊2日しながら、全10回の体験型ワークショップです。
耕さない田んぼに、畑で実際に、自然の理を学び、実践できます。
しかも、自分の小さな菜園区画が付いているので、3~12月の間自然農で野菜を育てることができます。
半農半Xの暮らし、自然農にご興味がある方にお奨めの講座です。
自然農法で自給自足の農園が学べる「Azumino自給農スクール2013」
穂高養生園で、日帰りも食事、宿泊もできる自然菜園入門講座も間もなく募集がはじまります。
お好みでお選びください。
【お迷いの方へ】
・耕さない自然農を学びたいなら→「あずみの自然農塾2013(第7期)」
・無農薬栽培の基本から応用を学び、我が家の自給率をアップしたいなら→「Azumino自給農スクール2013」
【拙著のご紹介】
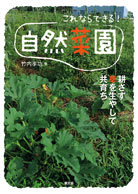
『これならできる!自然菜園』

『コンパニオンプランツで失敗しらずのコンテナ菜園』
好評発売中~




























