

女性向け雑誌の編集29才でバージンのりんこ
その友人との会話を聞いた男が同じ雑誌へ異動してきて
あっさり さっぱり思い切りと度胸は良いヒロインと軟派なようで頼れる男の その恋は どっちも不器用 意地っ張りゆえ 前途多難かも
ハッピーエンドを祈って
若林美樹先生は 大好きな漫画家さんの一人です


女性向け雑誌の編集29才でバージンのりんこ
その友人との会話を聞いた男が同じ雑誌へ異動してきて
あっさり さっぱり思い切りと度胸は良いヒロインと軟派なようで頼れる男の その恋は どっちも不器用 意地っ張りゆえ 前途多難かも
ハッピーエンドを祈って
若林美樹先生は 大好きな漫画家さんの一人です

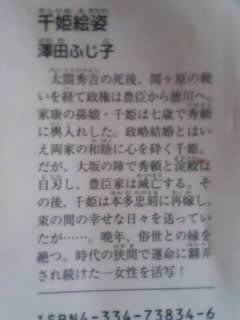
幼くして豊臣秀頼に輿入れし その死後は新しい夫と姫路城で暮らすも 死なれて 江戸に戻った美貌の女性
千姫と言えば誰もが知っているのは そんな話だろうか
私が初めて 千姫を知ったのは 小学生の頃 大映映画で 山本富士子さんが演じた姿によってだった
相手役は本郷功次郎さん
美しくも哀しい女性として描かれていた
最後は千姫様は尼に なる
また東映映画では美空ひばりさんも千姫を演じていた
以来「千姫春秋」をドラマ化した作品では多岐川裕美さん
当代最高 一流の美女が(たまに そうでない時もあるけど)千姫様を演じてきたように 記憶している
奇しくも私が住んでいるのは姫路市であり 他に観光場所もないことから 初めてのよそからの客を案内するのは 姫路城になる
子供の頃 ガイドさんの説明をわくわくしながら 聞いたものだ
だったら今さら 千姫もないだろうと 思われるかもしれない
何を物好きにと
実は夢を見たのだ
明け方の夢の中で盛んに千姫と思しき女性に話しかけられ けれど 何か書くほどの知識は無い自分に気付き 書店に行き 千姫について書かれた本を幾つか手にとった
そのうちの一冊です
地味ではありますが 澤田先生の小説は堅実な筆運びが とても勉強になります
媚びず淡々と
もっと注目されてよい作家の一人ではないかと 思うのです
時代に翻弄された千姫を 誠実に偏ることなく綴った物語です
平介は避けてきたものと 向き合わざるを得ない
お千加 お照は 平介を実の兄と信じている
だが平介はみなしごで姉妹の まだ子がいなかった両親が引き取り自分の子として育ててくれたのだ
今あるのも姉妹の両親のお陰
親代わりとして二人の幸せを見届けなければ
お千加は 前の亭主 新太と 元の鞘におさまりそうだった
そして お照は―これがわからない
自分は恵まれていると思う
店の主人夫婦には可愛がられ
幸吉という気性の良い友人もいる
寂しいなどと 思ってはいけないのだ
ちりちりする想いには 心の奥底で蓋をする
痩せ我慢は江戸っ子の意地
着替えるように気持ちを切り替える
濃い眉の下の切れ長の瞳 響きの良いその声
きらきら屋の客は平介目当ての若い娘も多かった
あれこれ見立てて欲しいと平介に群がる
怒りもせず すきの無い笑顔で平介は応じる
織り(木綿)でなく染め(友禅)の着物を着せてやりたい娘がいる
さぞや似合うだろうに
と また平介は その娘の事を考えてしまうのだ
お磯は 時々溜息つく平介の様子から 好きな娘でもできたのでは―と 心配していた
源十とも相談し おりをみて平介を養子にしたいと思っているから 気早くも子供のように見ている
気立ての良い娘を見つけて夫婦養子になどと先走って考えているのだ
「妹さん達は元気かえ お照ちゃんでしたっけ
いい娘さんですねぇ」
声をかけると いつになく平介が焦った表情になり「おかげさまで」と ようよう答えるので お磯は ちょっと怪訝に思った
鉄太が きらきら屋へ駆け込んで来たのは そんな時だった
「旦那様が お照さんが―」
おりんの養生している家に 男が暴れ込み 丁度 お照も居合わせていたので お供の鉄太に助けを呼ぶよう逃がしたと言う
「早くお行き!」
子供のことで番屋に走り喚いておいて ここまで走ってきたらしい
「すいません ちょっと出てきます」言い終わらぬうちに平介は走り出した
へたりこんだ鉄太を お磯が介抱した
幸吉おりんの暮らす家へ押しかけた男は 勝次と言い むれ竹の半六が おおっぴらにできない仕事を時々頼んでいたごろつきだった
まずは一太刀 幸吉に浴びせておいて 庇うおりんに毒づく
「ええ?人並みな生活送らせてくれた大事な旦那が殺されたのに さすが売女だな
もう他の男咥えこむたぁ」
言い掛かりであるが白も真っ黒にするのが この手合い
ましてや お艶と呼ばれていた おりんを狙っていたものだから 下司の逆恨みで どうにか金にしてやろう
弱みをでっちあげ 好きなようにしてやるのだと決めこんでいる
「この人は わたしの 許婚者(いいなづけ)ガタガタ言われる筋合いはありません」斬られながらも幸吉は強気に おりんを庇い言い返す
「なにおぅ?!」 勝次はどっからくすねてきたのか刀を振り回す 「斬りなさいよ この唐変木」
さっと幸吉の体の上に おりんが覆い被さる
「あたしは 死んだって いいんだ この人に逢えたんだもの
女房になる相手だと言ってもらえたんだもの いっとう幸せな 今のこの気持ちのまま殺してもらえるなら いっそ本望さね」
「言いやがったな」すっかり逆上して勝次が刀を振りかぶる
おろそうとして 横から飛び出してきたお照に飛びつかれ ひっくり返る
勝次の手から離れた刀を持ってお照は逃げた
その刀を持って 庇い合う幸吉とおりんの前に立つ
「て てめぇ」ゆらりと勝次が立ち上がる
細腕に重い刀をぶるぶる震える両手でしっかり お照は持って 相手から目を離さない
「ほれ姉ちゃん物騒なもんはおろしな
別嬪が んなもの持つンじゃねぇよ」
馬鹿にしきって近付いていく「ほれ よこしなってば」
言いながら じろじろお照の胸 腰の線を値踏みする
―こりゃさらって売り飛ばせば 金になる女だぜ 間夫(まぶ)になって稼がせるのも悪くねぇ―勝手なことを考えている
「なんだ勝次じゃねぇか」呆れたようなのんびりした声がかかった
いつの間にきたのか部屋の入口に長身の武士が立っている
勝次は げっと言う表情になった
「大人しく逃げたままでいりゃ良かったもんを わざわざ極門になりに戻ってくるたぁ あんぽんたん いや殊勝じゃねぇか」上品な顔に似ない伝法な台詞である
高い鼻 整った惚れ惚れするような男らしい容貌の持ち主で 勝次とは正反対だった
そこに立っているだけで爽やかな風が吹き抜けていくようだ
「京太郎様―」菊次の家で おりんは顔を見知っていた
「見舞いにくるって吉次が言うので お供で来たのさ 安心しな じき役人も来る」
すっかり逆上して勝次が 京太郎に飛びかかる
無謀であった
けたくって倒しておいて踏み付けた
「ぐぎえっ」と勝次
動こうとする首筋に刀が当てられる
「動くと切れるぞ 切れたら痛いだろうなぁ」と踏んだまま まるでいじめっこの京太郎
そこへ役人 岡っ引きと一緒に平介も飛び込んできた
「お照」
平介の声に刀を落とし わっと泣き出すお照
胸に飛び込んできたのを抱えたまま 平介は幸吉とおりんを気遣う「大丈夫か?」
「幸吉さんが斬られて」おりんは涙声だ
「医者を」と これは京太郎
勝次は役人たちに引っ立てられていった
幸い 幸吉の怪我はたいしたことはなく 今まで半病人だったおりんがやたら張り切って世話をしている
「そんなに動いてまた倒れたら どうするんだい」と心配する幸吉に 「あなたが死んだらお世話もできませんもの」と おりんが答える
あてられたように 早々に京太郎 吉次 平介 お照は 家を出てきた
「あとで精のつく鰻でも届けさせよう」京太郎は首の後ろをかく
「有難うございました」お照が頭を下げる
「お怪我がなくて よろしゅうございましたね こわかったでしょう」吉次が お照を気遣う
「お武家様のおかげでございます 何とお礼すればいいか」
頭を下げる平介に 手を振って京太郎は遮る
「通りかかっただけさ」
半歩遅れて歩く吉次 だが二人の影は気持ちを表すように寄り添っている
橋の所で二人ずつ別れ 平介はまずお照を きらきら屋まで連れていった
主人夫婦が心配してると思ったからだ
お照を休ませておいて 事の次第を説明し鉄太に お千加へ無事を知らせに行かせる
「そんな怖い思いを まあ可哀想に」 さっさか甘い白玉団子こさえてきて お照に勧める
もともと女の子が欲しかったお磯は 世話するのが嬉しくて仕方ない
小座敷で休んでいた主人の源十も呆れるほどだ
「長屋が流されたこと うちに言ってくれたら こちらへ引き取りましたのに平介も水くさいのですから―」などと お磯は言うのだった
「お騒がせしまして すいません」平介は源十に頭を下げる 源十は笑って言う「みんな無事で何よりだ 今夜は泊まって貰って 明日送っていくといい お磯があんなに嬉しそうだ」
ただ黙って深々と平介は頭を下げる
一度お千加は ばたばたと見舞いに菓子を買って駆け付けてきたが 店があるからと お照が元気なのを確認すると戻っていった
いつもより五品も多いおかず 賑やかな食事だった
女の話し相手があることが お磯をおしゃべりにしている
片付けが終わったあと お照がお磯の肩を揉む
やがて お照が部屋に引き取り 灯りが消える
―よく眠れているだろうか―こちらはなかなか寝付けないまま 平介は案じる
思いがけず飛び込んできたしなやかな体 受け止めたその感触が 腕に胸に残っている
妹として育ってきた娘だ
あっちはこっちを兄と信じている
幾度も自分に言い聞かす
―全く世の半分は女だって言うに―
うとうとする平介の瞼の裏に浮かんでいたのは お照の顔だった