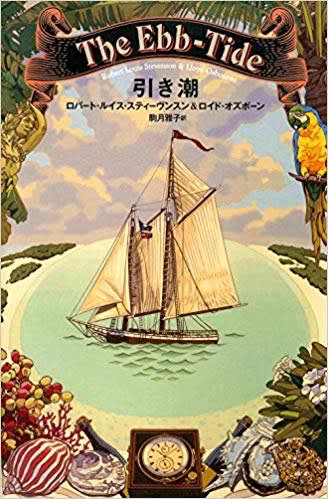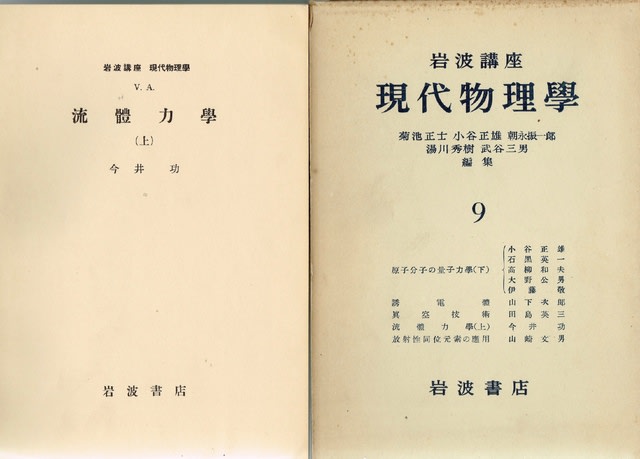新札に わざわざ反転した右向かせ画像を使うことが話題になっている.
ところで右端は,だいぶ前にCD ケースに内側からアクリル絵の具で描いた,Modern Jazz Quartet の John Lewis と Milt Jackson.写真を見ながら描いて裏返したら,当然のことだが左右反対だった.グランドピアノの蓋をあけた角度が逆.すなわち,鍵盤に向かって左が高音部のピアノということになっている.ぼく的にはよくある失敗.
最近のこの絵でも,最初に同じ失敗を繰り返した.これは Second Edition.

Eric Satie で画像検索して出た二つの絵のうち,右側のを左側のに基づいて脚色した.前景のピアノは我が家の YAMAHA.ちなみにFirst Edition では裏ぶたの虚像も帽子をかぶっていた.裏蓋に映る像がどうなるか,昔 図学で習ったラパットというやつだと,ちょっと考えてみたがお手上げ.結局 適当にやっつけた.

ところで右端は,だいぶ前にCD ケースに内側からアクリル絵の具で描いた,Modern Jazz Quartet の John Lewis と Milt Jackson.写真を見ながら描いて裏返したら,当然のことだが左右反対だった.グランドピアノの蓋をあけた角度が逆.すなわち,鍵盤に向かって左が高音部のピアノということになっている.ぼく的にはよくある失敗.
最近のこの絵でも,最初に同じ失敗を繰り返した.これは Second Edition.

Eric Satie で画像検索して出た二つの絵のうち,右側のを左側のに基づいて脚色した.前景のピアノは我が家の YAMAHA.ちなみにFirst Edition では裏ぶたの虚像も帽子をかぶっていた.裏蓋に映る像がどうなるか,昔 図学で習ったラパットというやつだと,ちょっと考えてみたがお手上げ.結局 適当にやっつけた.