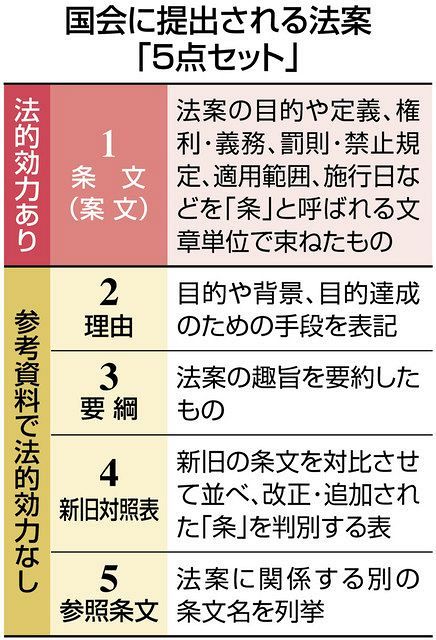【社説①】:週のはじめに考える 情報の真偽を見極める
『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【社説①】:週のはじめに考える 情報の真偽を見極める
桜散る中、新年度が始まりました。
新型コロナウイルス対策も新たな局面に入っています。感染はしつこく再燃し、さまざまな変異株の問題があります。それでも各国でワクチン接種が進み、トンネルの出口が、かすかに見えてきたようです。
一方で、どうにも解決が難しい問題を抱えています。それは、情報の真偽をどう見分けるか、ということです。
◆信頼できるはずなのに
コロナウイルスを巡っては、トイレットペーパーが品薄、コロナは生物兵器、お湯を飲めば感染予防できる、といったデマや誤情報が多く生まれました。
明治時代にハレー彗星(すいせい)が接近した時、「地球の空気が五分間なくなる」という話が伝わり、人々が息を止める訓練をしたり、ゴムチューブが品切れになったりしたそうです。
人間のやること、考えることは大して変わっていないようです。
デマ対策として「会員制交流サイト(SNS)の情報をうのみにしないで」「公的機関など信頼できる情報源にあたって」と言われたものですが、それで十分でしょうか。
中国でウイルスが拡散していたころ、感染対策の本家本元である世界保健機関(WHO)トップが「パンデミック(世界的大流行)ではない」と言い張りました。
欧米では当初、「マスクは有効ではない」と主張する専門家が多く、当時のトランプ米大統領も、マスク着用を拒否し、結局感染してしまいました。国内外の感染症研究者や著名な学者からも、結果的に正しいとはいえない見解が発信されました。
コロナがどんなものかはっきりしないころの情報は、どこから出ようが、信頼度は高くなかったのです。発達した技術によって、誤った情報が高速、大量に伝わりました。
◆データがそろってきた
それから一年。多くの知見が蓄積されて、状況は変わりました。
医学情報には「エビデンス(証拠)のレベル」があります。最も信用度が高いのは、複数の臨床試験の結果を総合的に考察した研究です。中でも本物か偽薬か患者も医師も知らない試験が最も信頼できます。次いで単独の試験、さらに症例報告、最も信用度が低いのは、患者データに基づかない専門家の意見です。
今はワクチンに関してもウイルスの性質に関しても、レベルの高いデータがそろい始めています。専門家の発信内容には、ばらつきが少なくなり、正確さを増してきているようです。
それに比べ、ネットやSNSの世界では、いまだに怪しげな情報があふれています。誰もが発信者になることができる時代。動画で情報を配信するユーチューバーの影響力は、特に大きくなっています。内容が面白ければ、真偽にかかわらずどんどん拡散されます。
「ワクチン有害」を唱えるユーチューブ動画が次々に投稿され、運営側が気付いて、削除に追われるという出来事もありました。
悪意を持って、偽ニュースを作ることもできます。人工知能(AI)を駆使したニセ画像は、もはや人間には真偽を見破れないくらいになっています。
では、どうすればいいのか。
やはり多くの情報にあたり、一つの情報を丸ごと信じない、ということが大事です。他の人はどう言っているのか、新聞やテレビニュースはどう伝えているのか。そして、その情報はきちんとしたデータに基づいているのか、慎重に取捨選択することが必要です。
絶対だまされない、ということは不可能です。せめて、怪しげな情報を拡散させないようにしましょう。うまいもうけ話に落とし穴があるように、面白い話には、うそが含まれている可能性が高いのです。
コロナを忘れたころには、次の災いがやってくるでしょう。別の感染症かもしれないし、地震や噴火、水害、あるいはもっとまれな現象かもしれません。
◆1年間の学びを生かす
突発的な出来事の発生初期は、専門家も間違います。またリスクを過小に評価してはいけないけれども、過大な評価も対処を誤らせて、別の問題を引き起こします。
たとえば昨年の国内がん検診受診者数は三割減りました。出産数も今年大幅減少が見込まれます。コロナのリスクがあまりに大きく伝わり、他のリスクが見えにくくなったためでしょう。
この一年で学んだことを新年度に生かしたいものです。閉ざされていたキャンパスに学生が戻ってきます。イベントやコンサートも復活しそうです。久方の光に満ちた春を満喫したいものです。
ただし、マスクは忘れずに。
元稿:東京新聞社 朝刊 主要ニュース 社説・解説・コラム 【社説】 2021年04月04日 07:40:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。
















 Photo by gettyimage
Photo by gettyimage