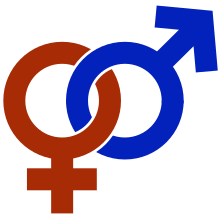【社説①】:週のはじめに考える 「触れない」を超えたい
『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【社説①】:週のはじめに考える 「触れない」を超えたい
テレビ朝日の報道番組「報道ステーション」のCM動画が先月下旬、物議を醸しました。「演出内容が女性蔑視だ」などとネット上で炎上し、同局は公開からわずか三日で動画を削除しました。
問題視された部分はいくつかあるのですが、とりわけ注目されたのは会社帰りの若い女性が「どっかの政治家が『ジェンダー平等』とかっていま、スローガン的に掲げている時点で、何それ、時代遅れって感じ」と語るシーンです。
◆相次いだ女性差別発言
日本社会の現状はジェンダー平等とかけ離れています。そうした中、このせりふは平等の実現を訴える政治家たちの足を引っ張っていると批判されました。「こいつ報ステみてるな」という最後のテロップも「『こいつ』という言い方は女性差別だ」「上から目線」とたたかれました。
CMの前にも、女性差別をめぐる騒動が相次ぎました。東京五輪・パラリンピック大会組織委員会の森喜朗前会長が「わきまえる女」発言で辞任。五輪の開閉会式の演出統括担当が、タレントの容姿を侮辱する演出を提案していたと暴露され、辞めていました。
ただ、今回は擁護論も散見しました。CMの趣旨は「ジェンダー平等」という自明な話に対し、建前でしか対応できていない政治家たち、特に政権与党への皮肉という解釈です。文脈に照らせば、批判は的外れだという指摘です。
本紙文化面の匿名コラム「大波小波」でも応酬がありました。こうした論争は歓迎すべきです。論争によって、相互に気づかぬ点が浮き彫りになるからです。その中で、気になったのはテレビ朝日会長の会見での発言でした。「もうそういうことはやるなと(現場に指示した)」。短時間のCMで繊細なテーマを扱えば、「誤解」を招きかねないという趣旨です。
◆対話による理解が必要
分からないではありません。いまの時代、炎上しそうな発言を鵜(う)の目鷹(たか)の目で探している人がいます。議論よりも断罪が先行しがちです。今回も「番組を打ち切れ」という非難がありました。こうした反応に誰もが萎縮しがちです。
ただ、こうした指示は「そうしたテーマには触れるな」と解釈されがちです。それは困ります。差別をめぐっては「触らぬ神に祟(たた)りなし」という風潮があります。下手に口を開いて騒動を招くくらいなら、話題にしない方がいいという一種の保身です。表向きは平穏になるでしょう。しかし、水面下での差別はなくなりません。
対話による理解や共感が必要だと思うのです。対話を通じて、自らの差別性に向き合う。それを可能にする余裕がほしいのです。
誰にだって無意識に人を差別したり、傷つけてしまうことがあります。その無意識はそれまでの人生や置かれている社会環境の産物なので、その外側の差別の現実に気づかぬことがあります。それに気づき、社会のゆがみを意識していくためには対話が不可欠です。
理由はほかにもあります。問題となっている女性差別は対象となる人びとが多い分、声も大きく、届きやすい。でも、差別の大半は社会の少数派に対してです。少数派の声は多数派にかき消されがちです。それゆえ、対話可能な環境が差別解消の前提になります。
まだ、あります。ジェンダーの平等は既存の男女の「らしさ」からの解放を伴います。「らしくない」人びとの登場に顔をしかめる人もいるでしょう。でも、別の星で暮らすわけにもいかない。理解できなくても、異質な人びとと社会を共有していることを知るために対話は必要です。
ただ、その対話が成立しにくい世相です。どうしたらよいのか。
怒りを抑えよとは言いません。差別に対する怒りの抑制はそれ自体が理不尽な被害です。それでも批判には「作法」が必要だと思うのです。それはお互いに率直な思いを語る機会を守ることです。
差別された側が絶対的な正義をまとって相手を一方的に批判する限り、言われた側は黙るしかなくなります。そこでは新たな関係性が生まれてきません。結果的に差別を温存させてしまいます。
◆批判の「作法」不可欠
そもそも、絶対的な正義を体現できる人などいません。被差別の解放運動に携わってきた女性の知人は「ひと昔前は活動家でも『女は口出しするな』と口走る男性らが少なくなかった。差別に憤りつつも、女性差別には無自覚だった」と語っていました。
理を尽くして指摘する。批判には逃げず、きちんと向き合う。
脳性まひ者の障害者団体「青い芝の会」で活躍した故横田弘さんの言葉を紹介します。
「人間を信じていなければ、(自分らは)黙って殺されるのを待つしかない。どっかで人間を信じているから、こうやって話す」
元稿:東京新聞社 朝刊 主要ニュース 社説・解説・コラム 【社説】 2021年04月19日 06:59:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。