詐欺の世界では、こういうパクリの手口はゴキブリと同じだと言われる。つまり、1件摘発されたらそれは「氷山の一角」に過ぎず、既に世の中では同様の手口の詐欺が無数に行われているというわけだ。まだ発覚していないだけで、給付金詐欺という「おいしい副業」に手を染める役人はまだウジャウジャいる可能性が高い。
また、「氷山の一角」といえば思い浮かぶのが、総務幹部官僚らによる高額接待問題や、鶏卵大手企業の会長による農林水産事務次官や幹部への接待などの「違法行為」も記憶に新しい。
今のところどちらも便宜を図った事実はなかったという調査結果になっているが、「学習能力」の高さでここまでのし上がってきた高級官僚が、目に見えてわかるような「ベタな便宜」を図っているわけがない。
実際、総務省の高額接待では、幹部職員は文春が音声データを出してくるまで、「衛星放送事業について話をした記憶がない」などすっとぼけていたし、東北新社からの接待が発覚した際には「ほかに規程違反の接待などはない」などと説明したが、後にNTTからもちゃっかり接待を受けていたことがバレている。息を吐くように嘘をつく、とはまさにこのことだ。
しかし、マスコミはなぜかこのような官僚の「違法行為」に対して大甘で、真相を追及しようというポーズさえ見せない。なぜかというと、マスコミで働く人々の頭の中には、「官僚=国のために働く善良な人」「政治家=官僚をアゴで使って悪事を働く人」というイメージが半ば常識のように刷り込まれているからだ。
それを象徴するのが先日、某報道番組にコメンテーターとして出演されていた著名ジャーナリストの方のコメントだ。司会から経産省職員の給付金詐欺についてコメントを求められて、こんな感じのことをおっしゃっていた。
「最近の官僚の質が落ちてきていますね。これはやはり政治、特に官邸との距離という問題があってですね」
ご存じのように、日本では長く霞が関官僚が政治を動かしていた。落選や政変でコロコロとキーマンが変わっていく政治家を「軽い神輿」として担ぎながら、政省令を根拠に許認可や予算配分に絶大な影響力を行使し、さながらフィクサーのよう政界を裏から支配してきたのが、高級官僚だった。
そんな官僚たちのユートピアをぶっ壊したのが、ガースーこと菅義偉首相だ。
官房長官時代、霞が関の力の根源である「人事権」を掌握した菅氏は、逆らう者をサクサクと更迭するという恐怖政治で、官僚の影響力を徹底的に排除したのだ。この官邸主導への政治改革は、これまで省益のためにガチガチに守られた岩盤規制に、政治主導で穴が空けられていくという効果があった反面、官僚が官邸の顔色をうかがってヘコヘコするようになったという副作用もあった。
そういう官僚のサラリーマン化は、国をより良くしようと志をもって官僚になった若手などのモチベーションを著しく低下させ「長い物には巻かれろ」「バレなきゃ甘い汁を吸えばいい」などのモラルハザードにつながり、それが官僚の「質」の低下を招いた。
……というのが、この近年、官僚の不正・不祥事が起きるたびにマスコミが繰り返してふれまわってきた「ストーリー」であり、このジャーナリスト氏もそれを踏襲しているというわけだ。
ただ、個人的にはこの「ストーリー」はかなり盛った話だと感じてしまう。「官僚=政治に虐げられた被害者」という方向へ導きたくてしょうがないというプロパガンダの臭いがぷんぷんと漂ってくるのだ。
◆官僚たちの「虚偽答弁」は常習!? 90年代の大蔵省時代もモラルに欠けていた
歴史を振り返れば、戦前から官僚の違法行為など定期的に発生している。贈収賄はもちろん、文書偽造、詐欺、痴漢などあらゆる犯罪をやってきた「前科」がある。厳しい言い方をさせていただくと、「質」が落ちたも何も、「質」が高かった時代などないのだ。
しかも、安倍・菅政権の恐怖政治のせいでモラルが壊れたみたいにやたらと被害者ヅラをするが、官邸主導への政治改革以前のはるか昔からモラルを欠いたことをやってきている。
わかりやすいのが、森友学園問題の国有地売却をめぐる財務省の文書改ざん問題の時に注目を集めた「虚偽答弁」だろう。
マスコミが匂わしていた「ストーリー」はこうだ。佐川宣寿元理財局長(当時)などが国会で虚偽答弁をしたり、文書の改ざんを近畿財務局に命じたりしたのは、安倍首相からそのような命令があったからであって、このような前代未聞の事態が起きたのは、「強すぎる官邸」への恐怖心から、財務省幹部たちのモラルがことごとくぶっ壊れてしまったからだ――というのだ。
ただ、これはかなり無理筋な話である。財務省ではかねて誰に命じられるわけでもなく、ただただ自分たちの保身のためだけに、「虚偽答弁」をしていたからだ。
1991年6月、証券会社が大口顧客に対して総額約2164億円の損失補填を行っていたことが明らかになり、国会では大蔵省がどういう指導を行っていたのだと厳しい質問が浴びせられた。そこで大蔵省の担当者は、準大手の証券会社の補てんについて、このように答弁をした。
「90年3月末までに自主的に報告をしていたのは6社」
顔色一つ変えない典型的な「官僚答弁」だったが、実はこれはデタラメだった。本当のところこの6社のうちの1社が報告したのは4月11日、もう1社も4月に入ってから数回に分けて報告をしていたのだ。なぜこんなしょうもない嘘をついたのかというと、大蔵省が定めた報告の期限が3月末だったからだ。4月にずれ込んでいると公文書に残せば、大蔵省の証券会社行政はぬるいとナメられてしまう。要するに、メンツのためだ(本連載バックナンバー『大蔵省時代にも前科あり、「忖度と改ざん」は財務省伝統の悪癖だ』参照)。
バカバカしいと思うだろうが、もっとバカバカしいのはこの「虚偽答弁」がデタラメだとバレないように、事実の方をねじ曲げて、「虚偽答弁」を「正しい答弁」にしてしまおう、という稚拙な隠蔽工作に走ったことだ。
「大蔵省はことし七月上旬に、この報告日時を同じ昨年の三月三十日付だったこととし、記者会見をする場合も三月中だったと説明するように指導していた」(日本経済新聞1991年10月2日)
この指導に従うということは、証券会社は大蔵省に報告をしたという文書などの日付もすべて書き直さないといけない。つまりは、大蔵省という組織は、自分たちの虚偽答弁を誤魔化すため、監督企業に「改ざん」まで命じていたのだ。
繰り返しになるが、これは別に首相や有力政治家から命じられたり、忖度をしたりしてやったわけではない。あくまで大蔵省という組織のメンツ、ガバナンスを守るために自分たちで進んで手を染めた「違法行為」だ。
◆組織の不正カルチャー、モラルの低さは 上司から部下へ引き継がれる
そこで想像していただきたい。このような虚偽答弁・改ざんを当たり前のようにやっていた組織が、国会で虚偽答弁をしたり、近畿財務局の職員に文書改ざんを命じていたのだ。安倍首相への忖度があったのは間違いないだろうが、なんでもかんでも「政治が悪い」で片付けることに違和感はないか。少なくとも、1年以上もマスコミをあげて大騒ぎをするのなら、政権批判を繰り返すだけではなく、大蔵省時代から続く不正カルチャーにもメスを入れるべきではないか。
「そんな30年も前の不正が関係しているわけないだろ」と怒る人もいらっしゃるかもしれないが、三菱電機の検査不正が35年続いていたことがわかったという先日の報道や、神戸製鋼のデータ不正が40年以上前から続いていたという事実からもわかるように、組織の不正カルチャーは30年くらい平気で継承されるものなのだ。
上司から部下へ、その部下がさらに新入社員へという感じで、組織のカルチャーや独自のノウハウが継承されていくように、「表向きはダメってことになっているけど、実際はこれくらいのことはうちの会社じゃみんなやっているよ」なんて感じで、モラルの低さも後世へと引き継がれていく。中央省庁のようにプロパーが圧倒的に多く、人材の新陳代謝がほとんどない閉鎖的な組織であればなおさらだ。
◆マスコミにとって政治家よりも官僚の方が大事な情報源
さて、このような話を聞くとおそらく皆さんは、「そのような官僚組織の問題があるのなら、マスコミが問題視しているはずだ」と思うだろうが、実はマスコミにはそれができない構造的な問題がある。
霞が関の役人というのは、マスコミにとって継続的に情報をいただく「取引先」だからだ。
「週刊文春」などを見ていただければわかりやすいが、基本的にスクープとは「リーク」である。内部の人間からの情報提供を受けて取材で裏をとってそれを報道するというのが一般的な流れで、これは文春の後追いばかりしているマスコミも変わらない。
では、マスコミにとって「リーク」とは何かというと基本的には官僚からのリークだ。よくマスコミの社長たちが首相などと会食をしているので政治とベタベタだと言われるが、政治家は落選したらただの人。一方、官僚は身分保証されたまま霞が関で30年以上も暗躍できる。マスコミをメーカーとすると、官僚ほど信頼のおけるサプライヤーはいないのだ。
そのような意味では、実はこの国の報道というのは、マスコミと一部の高級官僚が手を携えてつくってきた「官製ジャーナリズム」ともいえるのだ。
これにはもちろん、いいこともあった。政治リーダーが暴走をすると、官僚からマスコミにリークがバンバン流れて、スムーズに政権を潰すなんてこともできた。「官製ジャーナリズム」がうまく機能していた時代も確かにあったのだ。
しかし、今はどちらかというと、その癒着が悪い方向へ流れてしまっている。なぜかというと、マスコミも官僚も「既得権益」でメシを食っているからだ。そんな両者が手を結んでもロクなことにならないのは言うまでもない。口ではイノベーションだ、改革だ、と調子のいいことを叫ぶが、今の日本社会が変わってしまったら、これまでのような「上級国民」の座から引きずり下ろされてしまうツートップが、実はマスコミと官僚だ。
それは彼らの「働き方」を見れば明らかだ。企業には偉そうにああだこうだとご高説を垂れるが、役所ではいまだにファックスやハンコを使っているように、自分たちはほとんどデジタル化は進んでない。
マスコミも同様だ。河野太郎行革大臣に揶揄されたように、この時代に、深夜の記者会見を催して、囲み取材だ、夜討ち朝駆けだと昭和と変わらぬことを続けている。さまざまな企業がオープンイノベーションだと技術や知識を共有する中で、「記者クラブ以外は出ていけ」などとフリー記者を追い出しているのも、いつの時代だよとあきれてしまう。
われわれ庶民はどうしても何か問題が起きると「政治が悪い」と叫んでしまいがちだが、実は政治を盾にして、自分たちへの批判をかわし続けている「知能犯」がいる。その醜悪な現実にそろそろ国民は気づくべきだ。
(ノンフィクションライター 窪田順生)
元稿:ダイヤモンド社 online 主要ニュース 経済・政治 【政治・情報戦の裏側・担当:窪田順生:ノンフィクションライター】 2021年07月01日 04:45:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。
 東京都新型コロナウイルス感染症モニタリング会議へのオンライン参加で公務に復帰した小池百合子知事(撮影・鎌田直秀)
東京都新型コロナウイルス感染症モニタリング会議へのオンライン参加で公務に復帰した小池百合子知事(撮影・鎌田直秀) 東京都新型コロナウイルス感染症モニタリング会議へのオンライン参加で公務に復帰した小池百合子知事(上段中央)(撮影・鎌田直秀)
東京都新型コロナウイルス感染症モニタリング会議へのオンライン参加で公務に復帰した小池百合子知事(上段中央)(撮影・鎌田直秀)











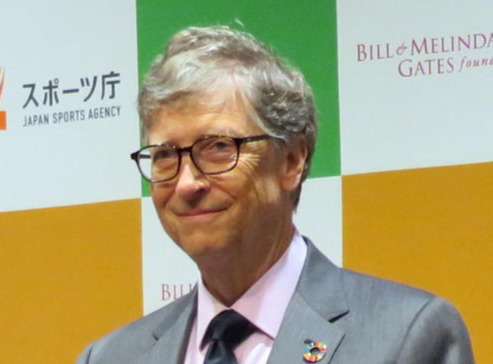 ビル・ゲイツ氏(18年11月撮影)
ビル・ゲイツ氏(18年11月撮影)

 </picture>
</picture> Photo:Yuichi Yamazaki/gettyimages
Photo:Yuichi Yamazaki/gettyimages Photo:PIXTA
Photo:PIXTA




