【社説①】:週のはじめに考える ハナコ 君は悪くない
『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【社説①】:週のはじめに考える ハナコ 君は悪くない
◆差別を理由に「封印」
◆問題の本質は何か
元稿:東京新聞社 朝刊 主要ニュース 社説・解説・コラム 【社説】 2022年02月20日 07:38:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。
【社説①】:週のはじめに考える ハナコ 君は悪くない
『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【社説①】:週のはじめに考える ハナコ 君は悪くない
元稿:東京新聞社 朝刊 主要ニュース 社説・解説・コラム 【社説】 2022年02月20日 07:38:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。
【筆洗】:米国の女性天文学者、ウィリアミーナ・フレミングが天文学に進…
『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【筆洗】:米国の女性天文学者、ウィリアミーナ・フレミングが天文学に進…
米国の女性天文学者、ウィリアミーナ・フレミングが天文学に進む前の職業はメイドさんである
▼一八七八年、夫と英国から米国に渡るも、まもなく離別する。妊娠中だったそうだ。職探しに奔走し、たまたま、ある家にメイドとして雇われた
▼天文学者エドワード・ピッカリングの家。ピッカリングは膨大な恒星の観測データを分類する研究を続けていたが、こうした忍耐と注意力の必要な作業は女性の方が向いていると考えたらしい。大勢の女性を助手として雇い、メイドだったフレミングもやがて助手となる。そこで、才能を発揮し、その時代を代表する天文学者になるのだから、女性の実力を公平に評価したピッカリングの手柄でもあろう
▼女性の実力をめぐる最近の話題にフレミングが浮かんだ。二〇二一年度の医学部医学科の入学試験で女子の合格率がわずかながら男子を上回ったそうだ。データのある一三年度以降で初の逆転である
▼数年前、東京医科大学などで女子を不利に扱う試験結果の不正操作などが発覚し、大きな問題となったことを踏まえ、見直しが進んだ結果である。公平に試験が行われれば合格率は女子が男子とほぼ同じか少し上回る。驚く結果ではなかろう
▼医学部入試での差別が解消に向かっているのならばありがたい。半面かつての曲がった入試で夢を絶たれた女性のことを思えば、悲しくもなる。
元稿:東京新聞社 朝刊 主要ニュース 社説・解説・コラム 【筆洗】 2022年02月20日 07:02:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。
【岸田首相の一日】: 2月19日(土)
『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【岸田首相の一日】: 2月19日(土)
【午前】来客なく、公邸で過ごす。
元稿:東京新聞社 朝刊 主要ニュース 政治 【政局・岸田首相の一日】 2022年02月20日 07:40:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。
【政治まんが】:「出口戦略ままならぬ」 佐藤正明傑作選「一笑両断」発売中
『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【政治まんが】:「出口戦略ままならぬ」 佐藤正明傑作選「一笑両断」発売中
元稿:東京新聞社 朝刊 主要ニュース 政治 【政局・「政治まんが」】 2022年02月20日 06:00:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。
【新型コロナ】:岸田政権が都道府県に「PCR検査を抑えろ」の大号令 交付金差配の内閣府を通じた圧力か
『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【新型コロナ】:岸田政権が都道府県に「PCR検査を抑えろ」の大号令 交付金差配の内閣府を通じた圧力か
〈1日当たりの検査件数を1月第二週における1日当たり平均検査実績の2倍以内として頂くようお願いします〉──。先月27日、内閣府地方創生推進室と内閣官房コロナ対策推進室が、連名で各都道府県に送付した事務連絡の一文である。意図は自治体の無料PCR検査を「抑えろ」だ。
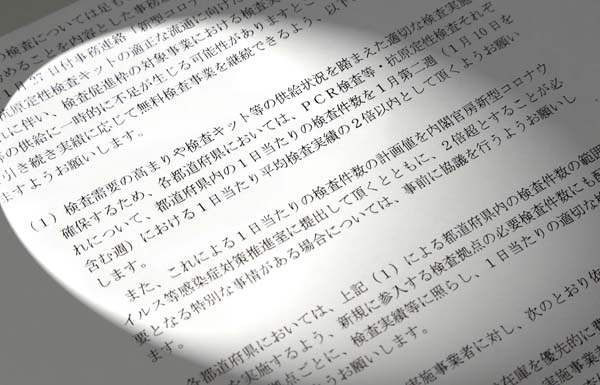
事務連絡を通じた圧力(C)日刊ゲンダイ
当時はオミクロン株が猛烈な勢いで全国に広がり、感染者数はネズミ算式に上昇。寒空の下、各自治体の無料PCR検査会場は長蛇の列で、検査試薬や抗原検査キットの需給逼迫が問題となっていた。そこで同日、厚労省は検査の優先順位を決定。症状がある人を診断する「行政検査」が最優先で、各自治体が行う「無料検査」は下位に位置付けた。それとワンセットで発したのが、前出の事務連絡だ。
地方創生推進室は、新型コロナ対策のために各自治体に配る「地方創生臨時交付金」を所管する。岸田政権は今年度補正予算で、自治体の無料検査を支援する「検査促進枠」を交付金に創設。予算3200億円を計上した。自治体にすれば、財源を牛耳られた政権サイドの圧力に等しい事務連絡は、こう続く。
〈1日当たりの検査件数の計画値を提出して頂くとともに、2倍超とすることが必要となる特別な事情がある場合については、事前に協議を行うようお願いします〉
皆、今後の感染拡大に不安を感じていた頃、交付金差配の権限を背景に無料検査が指定を超えそうなら“事前に協議せよ”と迫るとは随分と高圧的だ。実際に通達を受け取った首都圏自治体の担当者は「無料検査を後押ししてきたのに突然ブレーキを踏めなんて、無理難題を押しつけるな」と感じたという。
◆異常に高い「陽性率」の元凶なのか
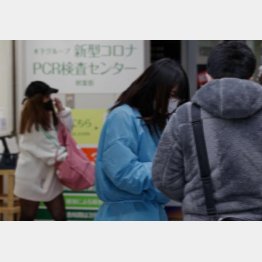 </picture>
</picture>
それでも地方の役人にとって“お上”の命令は絶対だ。貴重な財源を握られていれば、なおさらである。結局、各自治体とも指定の枠内で無料検査を継続しているようだが、解せないのは奇妙な符合があること。事務連絡の送付時期をピークに、全国の行政検査数も一向に増えず、完全に頭打ちに陥っているのだ。
東京都の「検査人数」(7日間平均)は1月29日の2万9698.7人以降はジリジリと減少。大阪の「検査件数」も1月26日の3万9380件を超えていない。おかげで全国の検査件数に占める陽性者の割合を示す「陽性率」は今月6日までの1週間で57.7%に達した。今週は東京と大阪の陽性率も40%台が続く。検査を受ければ、およそ2人に1人が陽性となる異常な高水準だ。
ひょっとして、お上の「検査を抑えろ」の大号令に萎縮し、試薬確保のため、感染の可能性の高い人しか回さず、行政検査まで抑えているのか。事務連絡を作成した内閣官房コロナ対策推進室は「担当者不在」を理由に無回答。通達を受けた側に影響を聞くと──。
東京都は「特に萎縮したことはない。陽性者のデータは即座に国のシステムに入力するが、検査件数の報告は業務逼迫で遅れがち。陽性率の高さはそのせいでは」(感染症対策部・検査体制整備担当)とのこと。大阪府は「そもそも需給逼迫を受けた通達。必要な試薬不足は検査頭打ちの要因のひとつ。また、検査省略の『みなし陽性』の導入で、従来より検査数は減少してしまいます」(感染症・検査グループ)と答えた。
いつになれば「徹底した検査と隔離」という感染対策の基本は実現するのか。
元稿:日刊ゲンダイ 主要ニュース ライフ 【暮らしニュース】 2022年02月20日 06:00:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。
【社説①】:野党の選挙協力 与党と対峙する体制を
『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【社説①】:野党の選挙協力 与党と対峙する体制を
今夏の参院選を控え、野党の選挙協力の体制づくりがまったく進んでいない。
野党第1党の立憲民主党の方針が定まらないことが最大の要因である。
最大の支持団体である連合から共産党との選挙協力に反対を突き付けられ、身動きがとれなくなっている。
連合をつなぎ留めるために内向きになっていないか。これでは多様な民意をくみ取り、政権に批判的な層の受け皿にはなり得ない。
参院選は政権選択選挙と位置づけられないものの、岸田文雄首相の政権運営に対して有権者が初めて審判を下す機会となる。
参院選敗北をきっかけに、政権交代につながったケースもある。
野党がバラバラでは巨大与党に太刀打ちできまい。政権と対峙(たいじ)する体制の再構築を急ぐべきだ。
立憲は議席を減らした昨秋の衆院選の総括で、共産党と合意した限定的な閣外協力について「有権者に誤解を与えた」として「今後はさらに慎重に対応する必要がある」と分析した。
これを受け、泉健太代表は共産党との共闘を「白紙」とする考えを示し、選挙協力の協議に応じていない。
衆院選での野党共闘がそもそも票集めありきで、政権交代後の連立のあり方を含め、どんな政権を目指すのかという理念を欠いていた。立憲の敗北は有権者にそれを見透かされた結果ではないか。
総括は、こうした根源的な疑問に答えていない。
大企業の労働組合が中心の連合の意向に拘泥することなく、党として自らを見つめ直し、野党勢力の再結集に臨む必要がある。
連合は参院選の基本方針に支援政党を明示しなかった。
民主党の流れを組む政党を長く支援してきたが、立憲と国民民主党に分裂し、加盟労組の支持が股裂きになるのを恐れたのだろう。
基本方針は「人物本位」を掲げる一方、共産党を念頭に「基本政策が大きく異なる政党等と連携・協力する候補者は推薦しない」と明記した。
連合の推薦が得られないとなれば、1人区の候補者一本化の足かせになる。国民民主党も東京で都民ファーストとの連携を模索する。野党の共闘が分散すると、与党を利することになりかねない。
政権交代があり得るという状況が政治に緊張を生む。民主主義を健全に保つためにも、与党に代わり得る選択肢が必要だ。
元稿:北海道新聞社 朝刊 主要ニュース 社説・解説・コラム 【社説】 2022年02月20日 05:05:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。
【社説②】:EUの原発回帰 大事故の教訓忘れたか
『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【社説②】:EUの原発回帰 大事故の教訓忘れたか
欧州連合(EU)の行政機関である欧州委員会は、原子力と天然ガスを一定の条件を付けた上で脱炭素に貢献するエネルギー源として認める方針を発表した。
EUは環境に配慮した持続可能な経済活動を分類する制度「タクソノミー」を設けている。グリーンリストとも呼ばれ、これに原発などを加えて投資を促す狙いだ。
反対している国があるものの、EU理事会と欧州議会で承認される見通しという。どのエネルギーを使うかは各国に委ねられる。
再生可能エネルギー中心の社会実現に向けた「過渡的手段としての役割」と位置付けているが、原発回帰と言える動きだ。
地震や火山が多い日本は欧州と地理条件が異なる。福島第1原発事故もあり、国民には原発に否定的な感情が根強い。
日本は欧州の動きとは一線を画し、脱原発と再生エネの拡大による二酸化炭素(CO2)排出削減の道を目指すべきである。
脱炭素を主導してきたEUの制度は、世界で広がるESG(環境・社会・企業統治)投資に影響を与える。原発が「お墨付き」を得ることの意味は小さくない。
世界では新設原発の発電コストが再生エネを上回っている地域が多いとされる。検査やトラブルで長期の運転停止も頻発している。
2007年に着工したフランスの新炉建設は相次ぐトラブルでいまだに完成せず、費用も大幅に膨らんでいる。原発への投資が増えるかは未知数と言えよう。
原発のグリーンリスト入りはフランスやフィンランドのほか、石炭火力脱却を目指す中東欧諸国が求めてきた。ドイツは脱原発を掲げて反対するが、CO2を排出する天然ガス発電には賛成する。
環境団体などは、原発新設方針を打ち出したフランスと、原発の代替に天然ガスを使い続けたいドイツの国内事情を優先させた政治的妥協だと批判している。
福島の事故や、欧州に甚大な被害をもたらした1986年のチェルノブイリ原発(ウクライナ)の教訓を忘れたわけではあるまい。
科学的知見に基づいた判断なのかを欧州委は詳細に明らかにし、欧州議会で議論してもらいたい。
日本の与党や産業界には、EUの動きが原発再稼働や新増設の追い風になるとの期待がある。
日本の再生エネは海外企業の参入もあって低コスト化が進みつつある。政府は洋上風力や送電網を整備する政策をさらに磨き、投資を呼び込んでいくべきだ。
元稿:北海道新聞社 朝刊 主要ニュース 社説・解説・コラム 【社説】 2022年02月20日 05:00:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。
【卓上四季】:地方振興の看板
『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【卓上四季】:地方振興の看板
「産業と文化と自然とが融和した地域社会」と「郷里に誇りをもって生活できる日本社会」―。この実現を誓った
▼1972年に田中角栄氏が自民党総裁選出馬に向けて発表した「日本列島改造論」(日刊工業新聞社)の前書きにある。過疎と過密を同時に解消し、国土の均衡ある発展を図ることが核心だった
▼その理念に古さは感じない。言い換えれば、半世紀を経ても地方が抱える多くの課題は未解決ということか。田中氏は全国9千キロ以上の新幹線と1万キロに及ぶ高速道の整備を打ち出した。計画はまだ途上にある
▼国土の血脈と言える交通網の拡充は地方振興に欠かせない。だがそれは都市に人を吸い寄せるすべともなる。地方の衰退はより進み、超高齢化が追い打ちをかける
▼歴代政権は地方活性化の看板を次々と掛け替えてきた。岸田文雄首相は「デジタル田園都市国家構想」を掲げる。AI(人工知能)の活用などデジタルサービスの強化が柱だが、地方の課題は雇用から医療まで複雑だ。新幹線を整備する一方で在来線の廃止が相次ぐ。結果、車社会が加速し、昨今はガソリン高騰が生活に重くのしかかる
▼思い起こせばガソリン税の上乗せ分は、田中氏が道路整備を目的に導入した。今は一般財源化され、課税根拠がないと指摘される。地方振興の新看板を掲げるのはいいが、改めるべき政策は正さないと看板倒れになりかねない。2022・2・20
元稿:北海道新聞社 朝刊 主要ニュース 社説・解説・コラム 【卓上四季】 2022年02月20日 05:00:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。
【社説①】:日ロ首脳会談 力による変更許されぬ
『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【社説①】:日ロ首脳会談 力による変更許されぬ
岸田文雄首相はロシアのプーチン大統領と電話会談を行った。
両首脳による直接対話は、昨年10月の首相就任直後の電話会談以来2度目だ。
ロシア軍は部隊をウクライナとの国境付近からなお撤収していない。侵攻する可能性が高いと米国が警告する中で実施した。
首相はウクライナ情勢に重大な懸念を伝え「力による現状変更は認められない」と指摘した。「外交交渉によって関係国が受け入れられる解決方法を追求すべきだ」とも伝えた。
国連憲章は他国の領土に対する威嚇や武力行使を禁じている。ロシアは国連安保理の常任理事国でもある。ウクライナの主権と領土を力で侵すことは認められない。
関係国は平和的解決に向けて外交努力を尽くすべきだ。
日本は北方領土をロシアに不法占拠されている。領土に関わる問題には、より毅然(きぜん)とした態度で対応する必要がある。
侵攻すれば先進7カ国(G7)は厳しい制裁を科す方針だ。日本も協調することを検討している。
ただ首相は、電話会談で制裁について言及したかどうか明らかにしなかった。北方領土問題を抱えているため、ロシアとの関係維持に腐心しているように見える。
首相はウクライナのゼレンスキー大統領や英国のジョンソン首相らと電話会談し結束をアピールした。他方、林芳正外相はロシアの閣僚と経済協力を巡り協議した。
日本として発するメッセージは、あいまいさが否めない。
G7はウクライナ情勢を巡って19日にドイツで緊急の外相会合、来週はオンラインで首脳会議を開催する。岸田首相と林外相も参加する予定で、具体的な制裁措置について話し合う可能性がある。
首相は施政方針演説で「新時代リアリズム外交」を打ち出し、自由や民主主義、人権、法の支配といった普遍的価値や原則を重視すると強調した。
法の支配にかかわるウクライナ問題では、より明確な態度を示すべきである。
日ロ電話会談で両首脳は、北方領土問題を含む平和条約締結交渉で対話を続けることを確認した。
安倍晋三元首相が四島返還から日ソ共同宣言を基礎に歯舞、色丹の2島返還を軸にした交渉方針に事実上転換して以降、交渉は停滞している。
だが首相はどのような方針で臨むのか詳細を示していない。四島返還の原則を忘れてはならない。
元稿:北海道新聞社 朝刊 主要ニュース 社説・解説・コラム 【社説】 2022年02月19日 05:01:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。
【社説②】:道の予算案 危機への備えを万全に
『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【社説②】:道の予算案 危機への備えを万全に
鈴木直道知事はきのう、道の2022年度予算案を発表した。一般会計の総額は本年度当初比微減の3兆2262億円となった。
知事は記者会見で「道民の命と暮らしを守る」と述べ、新型コロナウイルス対策に最優先で取り組む考えを示した。
オミクロン株のまん延で高齢者を中心に死者が急増している。新規感染者数の減少傾向も緩やかな中では当然の対応だろう。
医療提供体制確保のほか、《1》暮らしや学びの不安を取り除いて日常生活の回復を支援《2》感染対策と経済活動の両立に向けた支援―などを目指す施策を盛り込んだ。
必要かつ十分な予算と言えるのかどうか、25日開会の定例道議会で議論を深めてもらいたい。
重点政策の一つに「保健所体制の維持・強化」を位置付けた。本年度当初比6億円増の19億円を盛り込み、保健師と事務員約90人の増員などを行う。
保健所の業務は感染拡大の度に逼迫(ひっぱく)し、職員は厳しい環境に置かれている。道立保健所は1997年度までは45あったが、行政改革などで26にまで減らされたことが大きな要因だろう。
コロナ終息後も新たな感染症が流行する恐れは常にある。地域の保健体制立て直しを急ぐべきだ。
ワクチン接種の円滑化やPCR検査体制の整備、時短営業に協力する事業者への支援などは、感染拡大時に機動的に予算執行する準備が欠かせない。
コロナ以外にも、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対策など、道民の安全で安心した暮らしを守るために備えなければならない課題は山積している。危機管理の予算措置は万全にしておきたい。
今回は4月に就任から3年となる鈴木知事にとり、1期目最後の本格予算編成になる。
就任当初は外国人観光客の年間500万人誘致などを目玉公約に掲げていたが、これまでの在任期間の大半はコロナ対策に追われ、独自色を発揮できていない。
コロナ後を見据えた新たな政策を展開するには、財政健全化を急がなければならない。そのために欠かせないのは、類似事業や不要不急事業の見直しだろう。
一例を挙げれば、1次産業のデジタル化で農政部と水産林務部でそれぞれ、異なる情報通信技術の導入支援に向けて予算を計上している。両部が共同して取り組めば節約や効率化も可能ではないか。
財政難で予算編成に制約がある時こそ知事の指導力が不可欠だ。
元稿:北海道新聞社 朝刊 主要ニュース 社説・解説・コラム 【社説】 2022年02月19日 05:00:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。
【卓上四季】:米価安の諸色高
『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【卓上四季】:米価安の諸色高
徳川吉宗といえば時代劇の影響から「暴れん坊将軍」の印象が強いが、歴史上は「コメ将軍」「コメ公方(くぼう)」の呼び名で知られる。先端の治水技術で新田開発を進め、増産に成功した。一方で米余り状態となり、物価全体が上がる中で「米価安の諸色高(しょしきだか)」に陥る
▼ドラマの吉宗なら庶民のため安値安定に奔走しただろうが、実際は逆に高値に導いたという説が根強い。米石高が基本の幕府勘定で、米価下落は財政悪化に直結するからだ
▼備蓄用の米を積み、買米令で商人に強制購入させた。市中に出回る量を減らし値を上げる狙いだ。売買活発化のため、先物取引を担う大阪の堂島米会所も幕府公認とした
▼コロナ禍の今も米余りが深刻だ。外食の需要減が響き、卸売価格は前年比で1割以上安い。店頭でも安くなれば消費者にはむろん大助かりだが、道内は新潟県に次ぐ主産地で農家は困る
▼吉宗と違って、政府は備蓄米を積み増さない。4年前に生産調整(減反)も廃止し「産地の主体的な判断」に任せる建前だ。ただし、昨年産は作付面積5%減を要望した。全国でほぼ達成したが米余りは解消せず、今年産はさらに3%減が必要という。道内は深掘りで5%減を目指すが、いつまで繰り返すのだろう
▼吉宗の時代も一転、大飢饉(ききん)で米価は高騰し、米問屋の打ち壊しが起きた。「平成の米騒動」も記憶に残る。目先だけでなく備えも万全にしたい。2022・2・19
元稿:北海道新聞社 朝刊 主要ニュース 社説・解説・コラム 【卓上四季】 2022年02月19日 05:00:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。
【新型コロナ】:オミクロン死者急増に、ネトウヨ芸人・ほんこんが“高齢者なら死者増えても問題なし”の本音ダダ漏れツイートで、批判殺到!
『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【新型コロナ】:オミクロン死者急増に、ネトウヨ芸人・ほんこんが“高齢者なら死者増えても問題なし”の本音ダダ漏れツイートで、批判殺到!
新型コロナ第6波が猛威を振るっている。10日の全国のコロナ死亡者数は過去最多の164人と、第5波で最多だった昨年9月8日の89人を大幅に上回った。また、重症者数も1270人(10日時点)と増加の一途をたどっている。さらに警察庁は1月の変死事案などのうち、151人が新型コロナに感染していたと発表した。
だが、これは最初からわかりきっていた展開だ。感染者数が増加すれば重症者数や死亡者数も増加することは自明だからだ。ところが、この間、ワイドショーなどでは、オミクロン株は重症化のリスクが低くなっているという報告をもとに「オミクロンはたいしたことない」論が振り撒かれ、橋下徹氏や三浦瑠麗氏といった維新寄りの論客、ホリエモンこと堀江貴文氏や高橋洋一氏ら新自由主義者、木村盛世氏や宮沢孝幸氏といった感染リスク軽視派の専門家、ブラックマヨネーズ小杉&吉田やほんこんといったネトウヨ芸人らが鬼の首をとったように「オミクロンのリスクは風邪と同じ」「感染者数が増えても重症者が少ないから問題ない」「検査は必要ない」「感染症法上の分類を2類から5類に引き下げるべき」などと叫んできたのである。

ほんこんTwitterより
しかし、「オミクロンはたいしたことない」と口角泡を飛ばしてきた論客たちは、過去最悪の事態となりつつあるこの状況下でも、信じられない主張を繰り返している。
その筆頭が、ネトウヨ芸人のほんこんだ。
ほんこんは9日の8時45分ごろに、〈いつまで同じ報道? 再放送か? 意味のない解説 専門家? コメンテーター? 感染者増えたら あなた方の収入が増える〉〈山がもっと上なら 致死率低くない? ヨーロッパと比べるか 日本は、ヨーロッパから 褒められてたけど〉とツイート。同時間帯にコロナ死亡者数が増加していることを取り上げていた『羽鳥慎一モーニングショー』(テレビ朝日)を視聴していたのだと思われるが、このあと、ほんこんはつづけてこう投稿したのだ。
〈死者 何歳? 言って欲しい〉
こんなことはあらためて指摘するまでもないが、乳幼児であろうと高齢者であろうと、年齢に関係なく人の命に軽重はない。しかし、ほんこんは、死亡者の年齢を重視すべきであるかのように投稿したのだ。
しかも、現在コロナで死亡している人の多くが高齢者だ。そのことを踏まえると、「高齢者なら死んでも仕方がない」と主張しているとしか受け止めようがないだろう。
無論、このほんこんのツイートには批判が殺到。〈何歳か聞いて、これだけ生きたから仕方ないとか判断でもするつもり?〉〈何歳ならいいんだよ〉〈ほんこんさんにはご高齢の両親はいませんか?ご高齢の親戚やお世話になってる先輩は?その方に向かって同じセリフを言ってみてください〉〈西川きよしさんも高齢ですが、死んだらいいと思いますか?〉といった声が寄せられているが、批判が起こるのはあまりにも当然だろう。
◆感染者数が急増したら「死者数言え」、死者数が増えたら「年齢言え」…ほんこんはコロナを矮小化したいだけ
そもそも、ほんこんといえば、菅義偉・前首相が内閣官房参与として重用した高橋洋一氏と昵懇の仲で、高橋氏が昨年5月にコロナによる死者が1万人を超えていたにもかかわらず〈日本はこの程度の「さざ波」。これで五輪中止とかいうと笑笑〉とツイートして問題になった際も高橋氏を擁護。さらに、高橋氏と同様に番組共演者であり、「ワクチンも治療薬もできたなかでは感染を無理に止めない(でいい)」「(オミクロン株は)あきらかに風邪のウイルスに近づいている」などとコロナを矮小化する発言を連発している木村盛世氏に絶大な信頼を置き、ほんこんもコロナを軽視する発言を繰り返してきた。
しかも、ほんこんは、第6波で感染者数が急増していた1月13日には〈従来のインフルエンザと見分けがつかない 5類でええやん 騒ぐワイドショー 何を目指しているのか 何年繰り返すねん〉〈もうええでこの専門家 死者数は言わない 重症化にならんから死者は出ないのでは〉などと投稿。つまり、死亡者が出ていないことを根拠にワイドショーは騒ぎすぎだと批判していた。ところが、死亡者が増え始めると、今度は “高齢者だから仕方がない”と言わんばかりの主張をはじめたのである。
だが、これが「オミクロンはたいしたことない」論者の本音なのだろう。実際、大阪府がクラスターが起きた高齢者施設などを往診し、抗体治療薬などの治療を提供した医療機関に協力金を出すという方針を伝えた夕刊フジの記事のなかで、木村氏は「日本の平均寿命が80代ということもあり、80代の重症者や死者を減少させることは不可能に近い。協力金を出しても医療機関の逼迫を招くだけではないか。高齢者施設や家族らの間で、感染したときにどう対応するかをしっかり話し合っておくことの方が重要だろう」などとコメントしているのだ。
言わずもがな、いまコロナに感染して亡くなっている多くの高齢者は、たまたま寿命がきて死亡したのではなく、コロナに感染したことによって持病が悪化したり、発熱や食欲不振などで衰弱するなど、コロナが引き金になっているのだ。にもかかわらず、「80代の重症者や死者を減少させることは不可能に近い」「協力金を出しても医療機関の逼迫を招くだけ」とコロナ治療の実施を否定し、挙げ句、「感染したときにどう対応するかをしっかり話し合っておくことの方が重要」などと暗に死を受け入れる覚悟を迫っているのだ。
これは2020年に大阪府の吉村洋文知事が「命の選別」発言をおこなったこととも通じる。ようするに、ほんこんや木村氏なども含めて、「オミクロンはたいしたことない」論者の思想的バックボーンになっているのは、“生産性の低い高齢者は早く死んだほうがいい”という、新自由主義=維新的な優生思想だということなのだろう。
◆三浦瑠麗は「2月1日〜9日にピークアウトする」と楽観論を先導、死者急増を無視
しかも、グロテスクな言動をさらけ出している「オミクロンはたいしたことない」論者は、ほんこんだけではない。もうひとりが、国際政治学者の三浦瑠麗氏だ。
三浦氏といえば、1月29日深夜放送の『朝まで生テレビ!』(テレビ朝日)で「医者がワイドショーを観てコロナを怖がりすぎてる」「医者は自分ごとだと思ってない」などと嘲笑した挙げ句、医師である上昌広・NPO医療ガバナンス研究所理事長に「(医療現場に)立ってみられたらいい」と反論されると、「私、医者じゃないんで(笑)」と言い放ったことに非難の声があがったことも記憶に新しいが、最近はすっかり「ピークアウト芸人」と化している。
というのも、三浦氏は「チームCATs」なる有志グループでビッグデータ分析などに基づいた感染状況の予測モデルを開発。1月27日には〈東京都は来週ピークアウトする可能性が高く、緊急事態宣言の要請は踏み留まるべきです〉とツイートし、緊急事態宣言の要請に待ったをかけた。
このツイートには〈この人、いつから感染症の専門家になったの?〉〈感染症の専門家でも何でもないのに、無責任にも程がある〉〈えっと感染症の専門家でしたっけ?〉といった声が続出したが、一方、三浦氏は予測モデル研究チームの一員としてメディアにも積極的に露出。「第5波の予測もシークレットにやってて、ほぼ完璧に当たってるんですよ」(TBS『サンデー・ジャポン』2月6日放送)と後出しアピールし、「2月1日〜9日にピークアウトする」という予測を発信してきた。
たしかに、東京都の新規感染者数は前週比で減少しつつあるが、検査がまったく追いついていない状態では何の判断もできない。だが、それ以前に、死亡者数が過去最多を更新し、大阪などが医療崩壊状態に陥っている現状のなかで、いまピークアウトしているのかどうかを論じることは、現状の矮小化にほかならない。むしろ、「コロナ怖がりすぎ」「もうすぐピークアウトする」などと喧伝し、感染拡大を食い止める策を講じることをせせら笑って経済優先を主張してきたことが、現在の検査不足や医療崩壊、死亡者急増という最悪の事態を招いたのではないか。だが、三浦氏はピークアウト予測を声高に叫ぶことによって、本来なら守れたかもしれない人命が失われている現実を無視し、いまだにコロナを軽視しつづけているのだ。
しかも、ほんこんや三浦氏といった「オミクロンはたいしたことない」論者は、すぐに「ワイドショーが煽りすぎだ」と批判するが、実際にはワイドショーをはじめとするテレビの報道は死亡者数が過去最多を更新しても北京冬季五輪の話題ばかりで、むしろ伝えられるべき情報が伝えられていない状態だ。さらに、ほんこんや木村盛世氏、高橋洋一氏らが出演する『教えて!NEWSライブ 正義のミカタ』(朝日放送)では、2月5日放送回でも“コロナは普通の風邪”などという主張がおこなわれているような状況なのだ。
この放送のなかで、ほんこんは「専門家以外がテレビで煽ってる」「専門家以外はいらんこと言わんほうがええわ」と口にしていたが、それこそ、ほんこんや三浦氏といった専門外の人間がメディアでコロナを矮小化することこそが害悪だと言っておきたい。(編集部)
元稿:LITERA・リテラ(本と雑誌の知を再発見) 主要ニュース スキャンダル 【失言・炎上】 2022年02月12日 11:00:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。
【新型コロナ】:「陽性率」東京・大阪40%超えの異様 コロナ第6波は本当にピークアウトしているのか?
『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【新型コロナ】:「陽性率」東京・大阪40%超えの異様 コロナ第6波は本当にピークアウトしているのか?
「新型コロナの感染拡大は2月上旬にピークを越えた」──。政府の専門家からはこんな指摘が上がっている。確かに、17日の東京都の新規感染者は1万7864人と、前週の同じ曜日に比べて約1000人減少。前週の同じ曜日を下回るのは9日連続だ。しかし、「検査陽性率」は40%と異常な高さになっている。検査が追いつかず、実際の感染者はもっと多い可能性が高い。「ピークアウトした」と危機感を緩めるメッセージを出すのは時期尚早だ。

“世界基準”は5%なのに、東京40・2%大阪43・0%の異常な高さ(小池百合子都知事と吉村洋文府知事=右)/(C)日刊ゲンダイ
■“世界基準”は5%未満
17日夜時点で、東京都の陽性率は40.2%、大阪府は43.0%。検査した2人に1人近くが陽性という異常な高水準だ。WHO(世界保健機関)は2020年、国や地域が感染を制御できていると判断する目安として、陽性率「5%未満」を基準と示している。
「アワー・ワールド・イン・データ」によると、英国は7%で、米国は12%と、“世界基準”の5%未満に近い。国全体で見ても陽性率45%の日本は、検査が追いついていないだけで、実際の感染者数はさらに多い恐れがある。
果たして、本当にピークアウトしているのかどうか。
実際、岩手県や福井県では17日、新規感染者数が過去最多を更新。感染者数を示すグラフは右肩上がりで、ピークに向かって駆け上がっているように見える。
さらに北海道では、いったんは下がった新規感染者数が再拡大し、沖縄県も前週の同じ曜日と比べ微増した。
東京都では17日、従来株より感染力が強いとみられているステルスオミクロン株の市中感染が初確認されたから、再拡大することも考えられる。
島根県の丸山達也知事も、高すぎる陽性率に懸念を示している。15日の全国知事会のオンライン会合で、陽性率が30%以上となった地域が多数あるとのデータを示し、「感染者数の正確な把握ができていない。感染者数でピークアウトを判断できる状況ではない」と警鐘を鳴らしていた。
◆東京・大阪も死者が増え続けている
 </picture>
</picture>
しかも、死者数は増加の一途をたどっている。17日は過去最多の271人を記録し、3日連続で200人を突破。2月1~17日の死者は計2446人に上り、前月同時期(44人)の約56倍に跳ね上がった。
大阪府の17日の死者数は、過去2番目に多い54人。丸山知事は、大阪の惨状を念頭に「緊急事態宣言を出すべき」と指摘していた。それでも吉村府知事は、政府への宣言発令要請を見送った。首都東京のトップ小池知事も宣言発令には消極的とされる。岸田首相も17日、17道府県の「まん延防止等重点措置」を延長する方針を示したが、より強いメッセージが必要ではないか。
昭和大医学部客員教授の二木芳人氏(臨床感染症学)がこう言う。
「新規感染者数が落ち着きつつあるのは、感染者数の増加に国民が不安を覚え、自主的に行動抑制した結果でしょう。政府のメッセージはほとんど響いていないように見えます。宣言や重点措置より重要なのは、ターゲットを絞った機動的な対応です。今は、子供から高齢者に感染が広がってきていることが大きな問題。子供たちに対し、短期間で強い行動制限をお願いすることが肝要です。『教育機会を奪うな』という指摘がありますが、命の方が大事なのは言うまでもありません。これは、政府の基本的対処方針の変更で実現可能でしょう。宣言や重点措置よりこうした対応を素早く取ることが重要です」
岸田首相は「機動的に」と常々口にしているが、全然現実が伴っていない。
元稿:日刊ゲンダイ 主要ニュース ライフ 【暮らしニュース】 2022年02月18日 13:50:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。
【大阪府】:吉村“ワースト知事”の呆れた開き直り 大阪府コロナ死者数が全国最多、通常病床すでにパンク状態
『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【大阪府】:吉村“ワースト知事”の呆れた開き直り 大阪府コロナ死者数が全国最多、通常病床すでにパンク状態
大阪で新型コロナウイルスによる死者が急増している。16日の大阪の死者数は全国最多の38人に上った。第6波(今年1月以降)で見ても391人とダントツ。人口が1.5倍の東京の179人をはるかに上回っている。しかも、すでに軽症中等症病床はパンク状態。この先、入院できないコロナ患者が増え、さらに死者が相次ぐ恐れもある。なぜ、大阪が最悪の事態に陥っているのか。
 死者が多い理由を問われ…(大阪の吉村洋文府知事)/(C)日刊ゲンダイ
死者が多い理由を問われ…(大阪の吉村洋文府知事)/(C)日刊ゲンダイ
◇ ◇ ◇
昨春の第4波の時、大阪では重症病床が満床になった。あふれた重症者は軽症中等症病床での治療や自宅療養を余儀なくされ、死者の激増を招いた。
第6波でも事情は異なるが、すでに医療崩壊が起きつつある。オミクロン株は重症化率が低いため、重症病床はすいているものの、軽症中等症病床がすでにパンク状態なのだ。
コロナは軽症でも既往症など、他の病気が重症の患者を含めた実質の重症病床使用率は40.4%(15日時点)。一方、軽症中等症病床の使用率は一時、100%を超え、15日時点でも94.1%とほぼ入院できない事態が続いている。府は14日、すべてのコロナ受け入れ病院に対し、コロナ以外の入院患者がコロナに感染した場合、自院で治療を行うよう通知を出した。府がコロナ病床を用意できないからだ。
◆救える命が救えない恐れ
 </picture>
</picture>
各地で軽症の自宅療養者が急変し、亡くなるケースが起きている。ましてや、中等症患者は入院の上、治療を行う必要があるが、大阪では今後難しくなる可能性が高い。その結果、入院できない患者があふれ返り、救える命が救えない事態が起こりかねないのだ。
なぜ、大阪が第6波の死者数ダントツなのか。東京と何が違うのか。医療ガバナンス研究所理事長の上昌広氏は首をかしげる。
「第6波の死者数が東京179人に対し、大阪391人は、確かに多いと言える差です。ただ、残念ながら要因は思いつきません。大阪と東京でワクチンの接種時期や医療提供体制に差があるとは思えない。なぜ、大阪の死者数が突出して多くなるのかを吉村知事はしっかりと検証し、次のアクションにつなげる必要があります」
42人の死者が確認された15日、記者から「死者数が他の都道府県や東京都と比べて多い理由を分析しているのか」と問われ、吉村知事はこう開き直った。
「陽性者に対する亡くなった割合を全国で見てほしい。大阪が群を抜いて多いとの質問が多いがそうではない。東京はかなり低いが、大阪はちょうど真ん中ぐらいになっています」
絶対数の多さを“死者率”にすり替えて責任逃れでは、何の解決策も見いだせない。大阪は“ワースト知事”でも突出しているようだ。
元稿:日刊ゲンダイ 主要ニュース ライフ 【暮らしニュース】 2022年02月17日 14:30:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。
【新型コロナ】:吉村知事は大誤算…肝いり臨時医療施設はごっつい不人気 ■稼働800床で利用者たった3人
『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【新型コロナ】:吉村知事は大誤算…肝いり臨時医療施設はごっつい不人気 ■稼働800床で利用者たった3人
重症病床使用率が緊急事態宣言の要請基準(40%)に近づき、医療が逼迫する大阪府。その一方で、吉村知事肝いりの臨時医療施設「大阪コロナ大規模医療・療養センター」は想定外の不人気ぶりだ。
 ベッドに横たわるパフォーマンスも披露したが…(大阪の吉村洋文府知事)/(C)共同通信社
ベッドに横たわるパフォーマンスも披露したが…(大阪の吉村洋文府知事)/(C)共同通信社
■事業総予算は84億円!
国内最大全1000床のうち、先月末から40歳未満で軽症患者用の800床が稼働中だが、これまでの累計利用者はたった3人。事業の総予算は約84億円、1カ月あたりの運用コストは最大2億4000万円もかかるのに、これでは無用の長物となりかねない。
昨年の「第4、5波」で入院できずに自宅療養者が死亡した事例が相次いだのを受け、吉村知事が「大阪で野戦病院をつくる」と表明したのは同年8月末のこと。10月に大阪市住之江区の国際展示場「インテックス大阪」に臨時医療施設が整備されると、吉村知事は早速、現地を視察し、ベッドの寝心地を確認。「快適に過ごせる。自宅で不安に過ごすより安心感がある」と例のドヤ顔でアピールしたが、寂しい現状ではだだっ広い空間でポツンと過ごす入所者はさぞかし不安を募らせているのではないか。
交通の便は良くない立地だが、入所希望者には府が搬送専用のタクシーを手配する。パーティションで区切られた個室のほか、幼い子供と一緒に過ごせる家族向けの部屋も用意。全室にテレビと冷蔵庫を完備し、共用部には洗濯機や畳敷きのくつろぎスペースもある。食事は3食分の弁当が提供され、シャワーやトイレは共用だ。
◆なぜ誰も寄り付かない?
 </picture>
</picture>
医療従事者も決して不足していない。現在は計27人の看護師が交代制で日勤10人、夜勤4人が常駐。常勤医師は1人で、24時間のオンライン診療にも応じる。手厚いサポートが期待できそうだが、なぜ誰も寄り付かないのか。府の見解はこうだ。
「まだ府内の宿泊療養施設に空きがあり、若い軽症患者はホテル療養を希望する傾向にある。また、オミクロン株は感染力が非常に強く、家庭内で1人が感染すると、療養施設に移る前に他の家族がほぼ全員、感染してしまう。このケースだと大体、皆さんが自宅療養を選ぶ。デルタ株による感染拡大状況との違いから、想定より利用者は少ないのが現状です」(危機管理室災害対策課)
残る中等症患者用の200床は15日にも稼働、年齢不問で高齢者も受け入れる。肝いり施設の不発に吉村知事は「何らかの受け皿として活用する」と、まだイキっているが、ごっつい不人気は解消されるのか。
元稿:日刊ゲンダイ 主要ニュース ライフ 【暮らしニュース】 2022年02月16日 06:00:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。