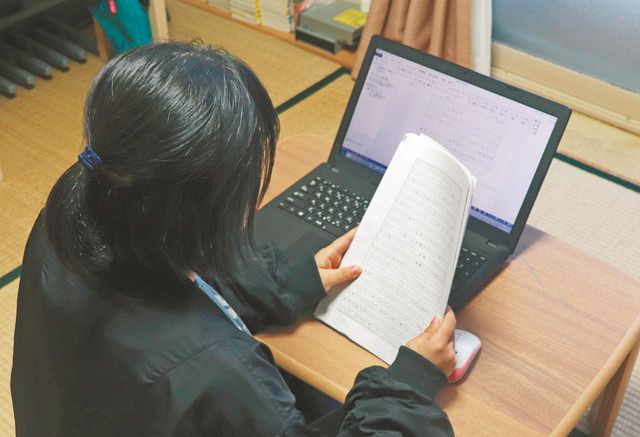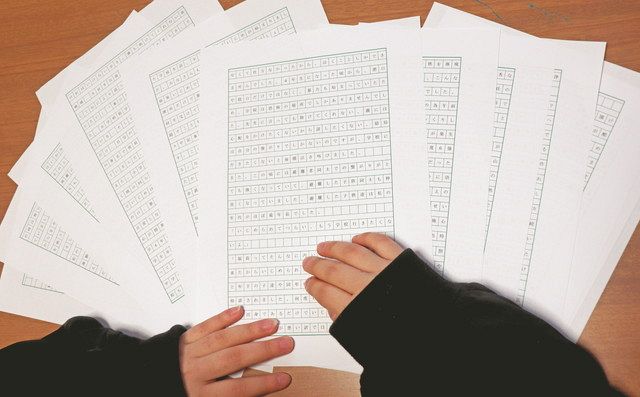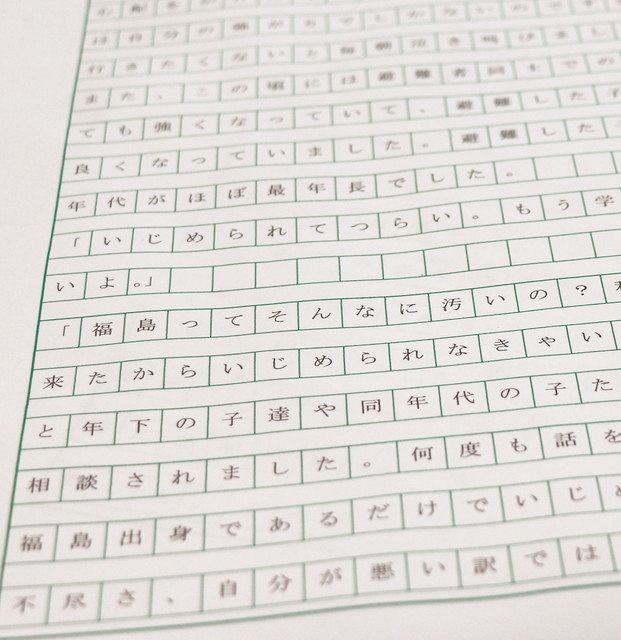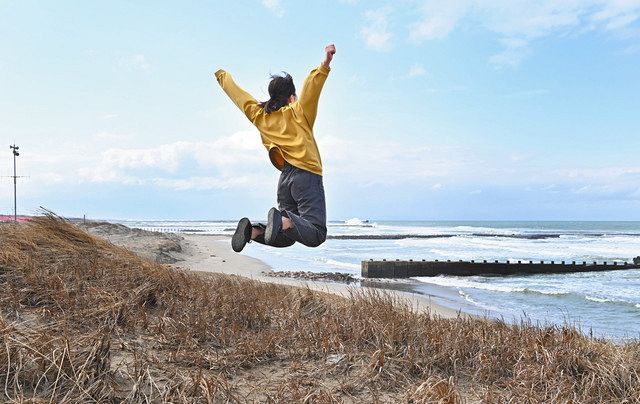【風・論説委員室から】:入管問題の根断つ時だ 相内亮
『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【風・論説委員室から】:入管問題の根断つ時だ 相内亮
出入国在留管理庁の名古屋の施設で、スリランカ人女性ウィシュマ・サンダマリさんが適切な医療を受けられずに亡くなって1年が過ぎた。
入管施設での外国人の病死や自殺は多発している。
その元凶と目されているのが入管の強大な裁量権だ。
入管は入管法上、在留期間を超えるなどした外国人を全員、司法の審査なく、無期限に施設収容することができる。
閉ざされた空間に長く拘束され、精神的にも肉体的にも追い詰められる外国人は多い。
送還を拒む外国人に圧力をかける装置として施設が使われていると言っていい。
この運用は、国際人権ルールに反しているとして国連の機関が是正を求めている。
だが日本政府は応じていない。ウィシュマさんに関して入管庁が昨年公表した最終報告書は、職員の意識や医療体制などを改善点に挙げるにとどまり、事を矮小(わいしょう)化した。
政府は問題の核心に向き合っていないと言わざるを得ない。
外国人を人と思わないかのような入管行政の根っこに何があるのかを知ろうと、昨年末から専門家に話を聞いてきた。
OBの立場から入管改革を訴える元東京入管局長の水上洋一郎さん(80)は「戦後の入管の当初の実体は、朝鮮半島からの密航を取り締まり、在日朝鮮人を管理する機関だった」と解説した上で、「2018年の入管法改正に伴いやっと共生社会に向けた総合調整の役割も担うようにはなったが、入管法の基本は『外国人の出入国管理』のまま変わっていない」と話した。
入管が、朝鮮半島をはじめとする外国の人々に対する差別性を内に宿したまま今に至ったことがうかがえる。
その歩みの中で、外国人を管理の対象としてのみ見る習性が染みついたのではないかと疑わざるを得ない。
日本とアジアの関係史が専門の田中宏・一橋大名誉教授は、「東西冷戦構造の西側に組み込まれ経済発展した日本は、戦争が遠景となる中、かつて支配したアジア諸地域との関係構築やその出身者の処遇に十分向き合わなかった。入管問題はそういう流れの中で考えるべきではないか」との見方を示した。
戦後日本は米国追従を強め、アジアと距離を置いた。入管が変わらずにきた背景にアジア軽視があるとも言えそうだ。
日本には300万人近い外国人が暮らす。すでに移民大国だと見る専門家もいる。
ウィシュマさんらの悲劇は外国人との共生が求められる時代に入管行政が対応できていないことの表れと見るべきだろう。
入管問題は戦後日本の歩みに深く根ざしている。その根を断つ抜本改革が急務だ。
現在の入管法と入管庁に代わって、外国人を日本社会の一員に位置づけ対等な共生社会の実現を図る新法と、それに関する政策を主導する新組織の設置を国会と政府に強く求めたい。
戦後日本のアジアでの立ち位置に関しては、国際政治に詳しい我部政明・琉球大名誉教授にも話を聞いた。
我部氏は「アジアに友好国がない日本には、米軍がいなければ安心できないという『おびえ』がある。それが日米同盟を支える原動力だ。政権には『対米関係さえ良ければ』という考えが強い」とした上で、「そのツケでアジア近隣国と良好な関係を築けていないのが日本外交の弱み。アジアの一員となる姿勢が求められる」と指摘した。
入管の抜本改革を、日本のおびえを過去のものとするための一歩にすべきだとも考える。
元稿:北海道新聞社 朝刊 主要ニュース 社説・解説・コラム 【風・論説委員室から】 2022年03月13日 10:30:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。













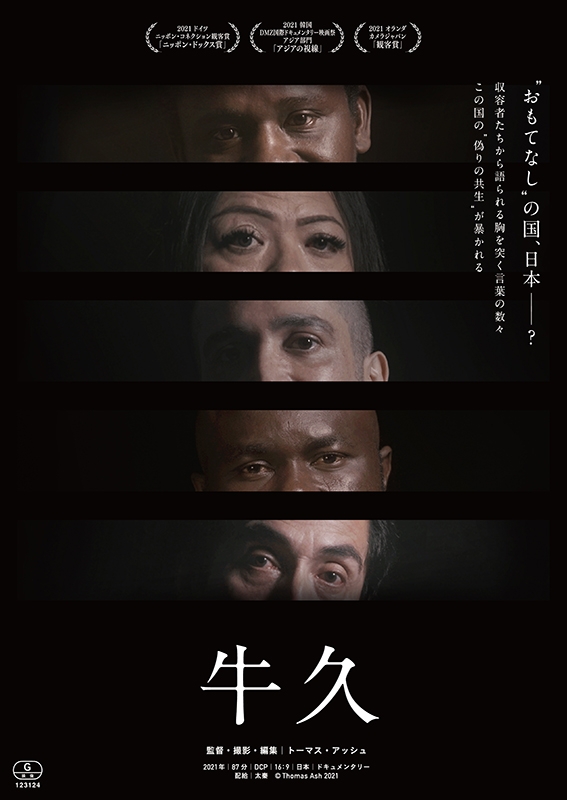
 </picture>
</picture>