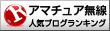地面から垂直に立てたバーチカルアンテナは、エレメントが1/4波長が基本。アースが必要ですがアースがダイポールで言う反対側のエレメントを担います。
でもアースの大きさって地球サイズ、全然1/4波長じゃない。
どうやら鏡面効果と言う理屈で動作しているらしい。
地面を鏡に見立ててそこに写るバーチカルアンテナが対称のエレメントになる、そういう感じです。
イメージ的には鏡面がピカピカなほどいいわけでそれはアースの抵抗値が低いほどいい、と言うことになろうかと思います。
一方バーチカルアンテナとそっくりなグランドプレーンアンテナは、ラジアルと言う疑似地面を空中に設置してバーチカルアンテナの地上高を稼いでいる、かに見えますが、ラジアルと地面の容量結合でそのような動作もしていないこともありませんが、あれは変形ダイポールアンテナのコールド側のエレメント。と考えることが出来ると、むしろその方が妥当だと思っています。
釣竿を使って自作の垂直アンテナを立てていますが、カウンターポイズの調子、地面の湿り具合とか様々な環境変化で良し悪しがかなり変化します。
地面との結合が良ければその長さは適当でよく(鏡面効果に期待する)、結合が良く無ければ1/4波長で数本広げてラジアルを設置するようにすれば上手く動作します。後者は長さが同調周波数に大きく影響します。
地面から浮いた状態で設置するならコールドエレメントを張って対応する、と言うのと同じ意味です。
MPー1と言うアンテナがなるべく高さを稼ごうとするよりも、トライポッドで地面ギリギリに設置した方が調子がいいのは鏡面効果に期待する方がこのアンテナに合っているからなのでしょう。
ただ、地上高0メートルは余程広い丘のてっぺんでも無い限り不利でしょうからそこは一長一短なのです。
これまでたくさん製作したオフセンター給電の垂直アンテナは、コールド側を含めた全長が1/2波長、つまりダイポールアンテナ。短めのコールド側が地面との結合が良くなってしまうと鏡面効果が悪さして、結果ホット側と対の長さとして動作してしまう、同調周波数が下がってしまうので注意が必要です。
移動運用の場合、毎回設置環境が異なりますので必ず上手く動作するとは限りません。せめていつもと同じテーブルと釣竿はキープしたいところです。
こうなってくると一波長で安定動作してるループアンテナはいいなぁ。
アンテナによって鏡面効果を求めるか否か、それが肝心ですね。
でもアースの大きさって地球サイズ、全然1/4波長じゃない。
どうやら鏡面効果と言う理屈で動作しているらしい。
地面を鏡に見立ててそこに写るバーチカルアンテナが対称のエレメントになる、そういう感じです。
イメージ的には鏡面がピカピカなほどいいわけでそれはアースの抵抗値が低いほどいい、と言うことになろうかと思います。
一方バーチカルアンテナとそっくりなグランドプレーンアンテナは、ラジアルと言う疑似地面を空中に設置してバーチカルアンテナの地上高を稼いでいる、かに見えますが、ラジアルと地面の容量結合でそのような動作もしていないこともありませんが、あれは変形ダイポールアンテナのコールド側のエレメント。と考えることが出来ると、むしろその方が妥当だと思っています。
釣竿を使って自作の垂直アンテナを立てていますが、カウンターポイズの調子、地面の湿り具合とか様々な環境変化で良し悪しがかなり変化します。
地面との結合が良ければその長さは適当でよく(鏡面効果に期待する)、結合が良く無ければ1/4波長で数本広げてラジアルを設置するようにすれば上手く動作します。後者は長さが同調周波数に大きく影響します。
地面から浮いた状態で設置するならコールドエレメントを張って対応する、と言うのと同じ意味です。
MPー1と言うアンテナがなるべく高さを稼ごうとするよりも、トライポッドで地面ギリギリに設置した方が調子がいいのは鏡面効果に期待する方がこのアンテナに合っているからなのでしょう。
ただ、地上高0メートルは余程広い丘のてっぺんでも無い限り不利でしょうからそこは一長一短なのです。
これまでたくさん製作したオフセンター給電の垂直アンテナは、コールド側を含めた全長が1/2波長、つまりダイポールアンテナ。短めのコールド側が地面との結合が良くなってしまうと鏡面効果が悪さして、結果ホット側と対の長さとして動作してしまう、同調周波数が下がってしまうので注意が必要です。
移動運用の場合、毎回設置環境が異なりますので必ず上手く動作するとは限りません。せめていつもと同じテーブルと釣竿はキープしたいところです。
こうなってくると一波長で安定動作してるループアンテナはいいなぁ。
アンテナによって鏡面効果を求めるか否か、それが肝心ですね。