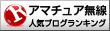レコーディング技術、これはこれで大変奥が深いようで、結構専門誌が出ています。
我々アマチュア無線家は録音自体はしないのですが、無線機にいい音を送り込んで、了解度の高い質の良い変調を作る、という点では共通する部分が多いと思います。
音圧を上げる、というテーマの本を買ってみました。
音楽もCDという限定された世界に音を詰め込む作業なので、ダイナミックレンジも周波数も限られています。とても小さな音からどでかい音まで、そのまま入れるわけにはいきません。よく聞こえるようにもしないといけません。そのために加工のノウハウがいろいろとあるようです。
音量ではなく音圧。聞いた感じの違いでしょう。
目からウロコだったのは、コンプレッサーの二重がけ、三重がけがよく使われていること。
ボーカル、各楽器、それぞれ個別の音をそれぞれ作り、最後にミックスするわけですが、それぞれの音がそれなりの大きさ、存在感でないといけない。そのための下準備として、また全体の総仕上げとして、いろんなところで適度に使われています。
当局のマイクシステムは
スタジオコンデンサーマイク → ボーカルプロセッサー(ファンタム電源、イコライザー、ゲート、リバーブ) → オーディオプロセッサー(イコライザー、コンプレッサー(リミッター)) → マルチバンドコンプレッサー(故障のため現在は省略) → 無線機 でした。
最初のボーカルプロセッサーはコンデンサーマイクを使うためのマイクアンプ代わりで、ファンタム電源が最も重要な機能。他にいろいろと機能があるのですが主にゲートの仕事をしてもらっています。喋っていない時のバックノイズを少し下げています。これも良し悪しで、喋ればバックノイズがオンになるわけで、ノイズっぽい変調に聞こえたりしますから、喋っていない時のバックノイズをゼロに抑え込むと結構不自然になります。程度問題ですね。さらに後々下がってしまいがちな高音をイコライザーで上げておきます。あとかかっているかどうかわからないくらい極弱くリバーブをかけています。
コンプレッサー機能もあるのですが、最後にマルチバンドコンプレッサーが控えていたのでかけないでいました。
次のオーディオプロセッサーでは、細かいイコライザー設定とリミッターをかけています。コンプレッサーはかけているつもりでいましたが、勉強してみたらかかっていませんでした。(笑)
最後に今は故障中ですが、マルチバンドコンプレッサーで全体の音圧を高めて、ギュッと実のある音にしていました。
本を読んで試しているのは、最初のボーカルプロセッサーで軽くコンプレッサーをかけ、次のオーディプロッセッサーでも軽くコンプレッサーをかけるという、ミキシングしているわけじゃないから要らないかも、ですが、コンプの二重がけを試しています。
なんというか、目的が違うんですね。
イコライザーも二重がけで無駄なようですが・・・コンプレッサーを通す度に高音は下がる傾向があるらしく、それなりに効くのだそうです。
まだまだほんの小手先で遊んでいるだけですが、コンプレッサーの実際のかけかたとか、本で読むと勉強になります。
無線ではとにかく平均トークパワーを上げるために派手にコンプレッサーが使われる傾向がありますが、聞きやすいいい音を作るのにも適度に使うといいようです。