『ルポ 貧困大国アメリカ』(堤 未果岩波新書)
アメリカの低所得者向け住宅ローン・サブプライム(subprime lending)の破綻から世界経済は大打撃を受けた。大和総研のコラム「サブプライム問題の本質」は以下のように書く。
「2003年後半から2005年にかけて、米国では好景気と銀行間の競争激化により、与信基準が大きく低下。一大住宅ブームが沸き起こった」
http://www.dir.co.jp/publicity/column/070322.html
同工異曲の「経済記事」はこれまでに何度も読んできた。
本書のプロローグが紹介する、サブプライムローンの融資基準は以下である。
1)過去12か月以内に30日延滞を2回以上、または過去24か月に60日延滞を1回以上している
2)過去24か月以内に抵当権の実行と債務免除をされている
3)過去5年以内に破産宣告を受けている
4)返済負担額が収入の50%以上になる
上記4つのうち一つでも当てはまれば、融資しない、のではない。
上記4つのうち一つでも当てはまれば、融資する、のである!
サブプライムローンの支払いが滞り、家を失って路頭に迷っているメキシコ移民のマリオは、50万ドル(5500万円)の融資を受けて、マリオと妻と息子の家族4人で、毎月3100(34万円)ドルの利息を払っていたという。数年後には、10~15%(550~825万円)に利息が上がるところだった。
ほかにも、『華氏911』のマイケル・ ムーアがアメリカの劣悪な医療制度を暴いたドキュメンタリ映画『シッコ SiCKO』や監督のモーガン・スパーロックが30日間毎食、マクドナルドのファストフードだけを食べ続けた記録を撮影した『スーパーサイズ・ミー』が明らかにした貧困と肥満の直接的な関係などが、本書でも取り上げられている。
世界でもっとも豊かな「世界帝国」の真下に、世界最貧国があるようなものだが、格差社会が進行して結果的にそうなったのではない。政策の失敗や社会の歪み、あるいはアメリカの恥部といった一部のことでもない。「レーガノミックス」以来の「小さな政府」を目指した規制緩和により、貧乏人を食い物にする「貧困ビジネス」に政府が道を開き、擁護してきたからだと本書は論述している。
「9.11以降特にスピードを増した、「小さな政府」と「大きな市場」という新自由主義政策は、「いのち」や「くらし」に加え「教育」のエリアも浸食していった」(100p)。
以上のように、新聞の連載記事のように平明で読みやすいが、「いのち」や「くらし」といった日本の新聞独特の言葉づかいは、アメリカのルポにはなじまない気がする。
また、「小さな政府」という考え方自体は一概に否定できない。少なくとも「大きな政府」を提言する動きは先進国間ではほとんど見られないだろう。では、「大きな市場」に問題があるとすれば、どのような処方箋が可能なのか。具体的な動きがもう少し知りたかった。
著者・堤未果は、血液製剤によるエイズ被害者として告発運動の先頭に立ち、現在は参議院議員の川田龍平と結婚しているそうだ。
(敬称略)
アメリカの低所得者向け住宅ローン・サブプライム(subprime lending)の破綻から世界経済は大打撃を受けた。大和総研のコラム「サブプライム問題の本質」は以下のように書く。
「2003年後半から2005年にかけて、米国では好景気と銀行間の競争激化により、与信基準が大きく低下。一大住宅ブームが沸き起こった」
http://www.dir.co.jp/publicity/column/070322.html
同工異曲の「経済記事」はこれまでに何度も読んできた。
本書のプロローグが紹介する、サブプライムローンの融資基準は以下である。
1)過去12か月以内に30日延滞を2回以上、または過去24か月に60日延滞を1回以上している
2)過去24か月以内に抵当権の実行と債務免除をされている
3)過去5年以内に破産宣告を受けている
4)返済負担額が収入の50%以上になる
上記4つのうち一つでも当てはまれば、融資しない、のではない。
上記4つのうち一つでも当てはまれば、融資する、のである!
サブプライムローンの支払いが滞り、家を失って路頭に迷っているメキシコ移民のマリオは、50万ドル(5500万円)の融資を受けて、マリオと妻と息子の家族4人で、毎月3100(34万円)ドルの利息を払っていたという。数年後には、10~15%(550~825万円)に利息が上がるところだった。
ほかにも、『華氏911』のマイケル・ ムーアがアメリカの劣悪な医療制度を暴いたドキュメンタリ映画『シッコ SiCKO』や監督のモーガン・スパーロックが30日間毎食、マクドナルドのファストフードだけを食べ続けた記録を撮影した『スーパーサイズ・ミー』が明らかにした貧困と肥満の直接的な関係などが、本書でも取り上げられている。
世界でもっとも豊かな「世界帝国」の真下に、世界最貧国があるようなものだが、格差社会が進行して結果的にそうなったのではない。政策の失敗や社会の歪み、あるいはアメリカの恥部といった一部のことでもない。「レーガノミックス」以来の「小さな政府」を目指した規制緩和により、貧乏人を食い物にする「貧困ビジネス」に政府が道を開き、擁護してきたからだと本書は論述している。
「9.11以降特にスピードを増した、「小さな政府」と「大きな市場」という新自由主義政策は、「いのち」や「くらし」に加え「教育」のエリアも浸食していった」(100p)。
以上のように、新聞の連載記事のように平明で読みやすいが、「いのち」や「くらし」といった日本の新聞独特の言葉づかいは、アメリカのルポにはなじまない気がする。
また、「小さな政府」という考え方自体は一概に否定できない。少なくとも「大きな政府」を提言する動きは先進国間ではほとんど見られないだろう。では、「大きな市場」に問題があるとすれば、どのような処方箋が可能なのか。具体的な動きがもう少し知りたかった。
著者・堤未果は、血液製剤によるエイズ被害者として告発運動の先頭に立ち、現在は参議院議員の川田龍平と結婚しているそうだ。
(敬称略)











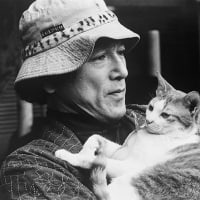

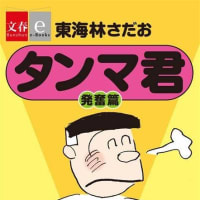












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます