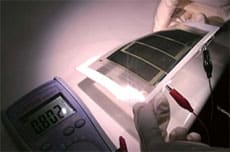■
【太陽電池世界一の技術力】

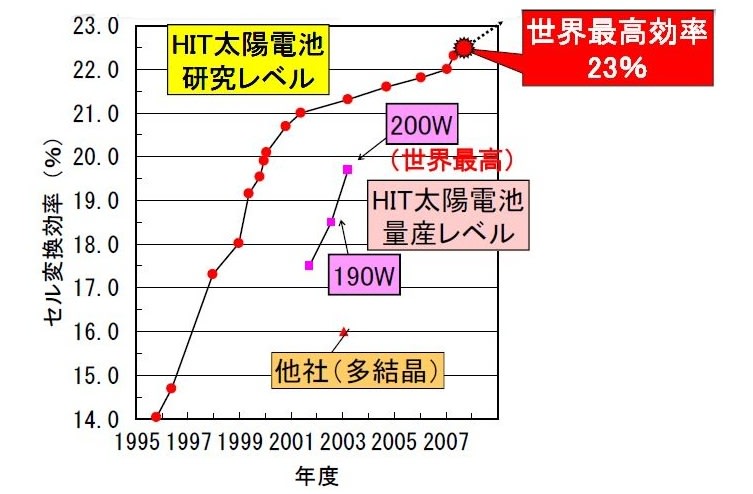
赤 鬼「ドイツの動きはわかったが、日本のレベルはど
うなんだ?」
亜幌論「2009年5月には、HIT太陽電池セルで世界最高の
変換効率23.0%を達成していて技術的にはトッ
プランナーだが、ドイツのように政府意志が希
薄で国内波及が遅い。普及を早めながら効率を
上げるという両面作戦が必要です」
赤 鬼「韓国は買取制度を導入しているから日本は中国
などを含め普及率ではベスト3から陥落するの
も時間の問題や」
舳離雄「現場研究者の名誉ためにいっておきますが、23
%は少し前では考えられないことでした。とは
いえ、モジュール変換効率を23%に持って行く
にはセルレベルで27%の変換効率が必要です」
※HITは‘Heterojunction with Intrinsic Thin layer’の略。HIT
太陽電池は、三洋電機が開発した独自構造の太陽電池セ
ルで、結晶シリコン基板とアモルファスシリコン薄膜を
用いて形成したハイブリッド型。高変換効率・温度特性
等の優位性により、設置面積当たりの発電量世界No.1を
誇る。
秋海棠「これはシリコン系ですよね。つまり無機物系で
すよね。有機物系というのはないのですか」
舳離雄「色素と酸化金属と有機溶媒を使い電気化学の原
理で発電する色素増感型太陽電池は複合系にな
りますが、それだとセルで12%の効率が出てい
ます。東京大学と三菱化学の共同開発で9.2%
の世界一の変換効率がセルレベル出ています。
ここ1、2年で飛躍的に変換効率が上がってき
ています」
亜幌論「これらは、次世代太陽電池と呼ばれ、原料に炭
素や窒素を使い、厚さは数百ナノメートル。イ
ンクジェット方式で自動車などの曲面印刷も可
能で、シリコン系の1/10程度のコストで生産で
きるといわれているがどうなんだろう」
舳離雄「半導体デバイスローコストで製造するだけでな
く変換効率にも気配りしなければなりませんが
p型半導体とn型半導体とを順番に塗布しつく
っていては高効率のもの得られません。つまり、
下図(右)の次世代型のように接触面積を広く
した構造にする必要があるのです」
赤 鬼「へぇ~、作りにくそうな形状やないか」

舳離雄「そこで考えたのが、直接2種類の半導体フィル
ムを貼り合わせるのではなく介在フィルをいれ
て貼り合わせるのです。簡単な例えで言えば両
面テープの離型フィルムでこのフィルムを取り
除き2種類半導体フィルム貼り合わせるのです
が。この時、無色個体のアダマンタンを使いま
す。
具体的には、化合物Aと化合物Cを含む層の成
膜、クロロホルム/モノクロロベンゼンの1:1
混合溶媒に、下図のSIMEF化合物を0.6%、アダ
マンタンを1.4%溶解した液を調製し、ろ過した
ろ液を2層目の正孔取り出し層上に1500rpmでス
ピンコートし、グローブボックス中180℃で20分
間加熱し、加熱によりSIMEF化合物をテトラベ
ンゾポルフィリンへ変換します。テトラベンゾ
ポルフィリンはp型半導体材料の化合物Aで、
アダマンタンは半導体材料ではない化合物Cで
す。
次に、化合物Bによる化合物Cの置換ですが、
トルエンにSIMEF化合物のフラーレン誘導体を
1.2%溶解した液を調整し、3000rpmで化合物A
と化合物Cとを含む層上にスピンコートし、65
℃で10分間加熱処理を施します。SIMEF化合物
フラーレン誘導体はn型半導体材料です。こう
することで、化合物C(アダマンタン)を化合
物B(フラーレン誘導体)で置換して、化合物
Aと化合物Bとを含む層を形成するというもの
です。勿論、電子の移動速度は10-4cm2/V・s以
上という大前提をクリアしていますが」
亜幌論「それじゃ、A+C→A+Bの式からC=Bでな
くて、CがBに化ける過程があり、一種の化学
的バインダー(介在物)という‘錬金術’を使
っているだ」
舳離雄「そうですが、簡単そうですが、有機化学合成に
精通していなければそれは考えられなかったの
ではないかと思います。ナノ領域の世界ですが
難しい技術を使わなくても、柔軟な発想で考え
れば‘効率×コスト逓減’という課題がブレー
クできるという好例ではないでしょうか。これ
で一気に量産化できる見通しがついた判断し、
公開に踏み切ったものと思います」

※「半導体デバイスの製造方法及び太陽電池 」
秋海棠「良いことづくめのようですが、弱点はないので
すか?」
舳離雄「シリコン系の耐用年数は20年以上と言われる段
階ですが、有機化合物系は‘ターンオーバー’
という限界を抱えています。実際、色素増感型
太陽電池は、色素のターンオーバー数は千三百
万回だという数値もみられます」
亜幌論「ターンオーバーとは2つの意味で使われる。1
つは生物学におけるターンオーバー(metabolic
turnover:代謝回転)。生物を構成している細胞
や組織 (生物学)が生体分子を合成し、一方で
分解していくことで、新旧の分子が入れ替わり
つつバランスを保つ動的平衡状態のこと。この
結果、古い細胞や組織自体が新しく入れ替わる
が、生物種や細胞・組織の種類、分子種によっ
て、ターンオーバー速度には大きな差異がある。
2つめは、合成化学の触媒反応において、一分
子の触媒がどれだけ反応生成物を作り出せるか
を表す指標で、(生成物のモル数)/(触媒の
モル数)で表す。それにしても4年前より3倍
の変換効率ですから凄いことだね」
赤 鬼「回転数ってか、水商売の時間当たりの顧客数÷
席数と同じで、家内安全・商売繁盛!」
と言いつつ赤鬼は真っ赤な顔をして上機嫌で『金亀』を
豪快に飲み干した。
※「太陽光を利用したクリーンエネルギー生成(H19年)」
※「有機薄膜太陽電池を高効率化するには」