
武田邦彦が彦根にきて講演したという(上のひこにゃんをクリック)。「『原発を知ろう』子どもたちの未来の
ために」と題し講演。原発大国・フランスと日本の原発を比較し、「フランスには地震や津波がなく、原発がセ
ーヌ川の上流にあり、電源も地下にある」「(津波で浸水した)福島原発の電源も地下にあったが、これはフラ
ンスの設計をそのまま持ってきたためだ」と指摘。「日本の原発は世界で一番危険な場所に建っている。これま
でどれほどの日本人がまじめに原発の事を考えたか」、福島の原発事故で放出された放射性物質(セシウム)の
量が、広島に落とされた原爆時の186倍だとし「被ばく地で放射性物質の量が10分の1になるには百年かかる」
「もし原発が14基ある福井県で1基でも事故があれば、彦根市も百年は住めなくなる」とか。「石油がもうすぐ
無くなるというのはうそ。石油会社が掘らないだけで、いくらでもある。あと1万年はもつ」、温暖化の原因と
される海水温の上昇は「二酸化炭素で海水温は高くならない。今、暑いのは太陽活動が活発だからだ」「地球温
暖化だと騙されているのは日本人だけ」と持論展開し、有色人種の中で日本だけが独立を保っていることにふれ
「国際社会は食うか食われるかの世界。地球温暖化防止、リサイクル推進、節電など、ぜんぜんダメで子どもの
ためにならない」「このままの生活が50年続ければ、日本は中国の属国になる」と警告したという。
学者馬鹿という言葉があるが、極端から極端に走りやすいと心得ているから別に驚きもしないが、原子力発電で
飯を食ってきて今度は宗旨替えで反核というか、転向というか騒々しいことだ。この程度なら反<反核>の吉本隆
明の方が筋が通っていてわかりやすい。また「彦根は百年住めない」は、防災・除汚技術の推進との絡みで語ら
なければ不安を煽るだけだし、石油枯渇説に対するゴールド説は宇宙の炭素の分散律や、推定の誤差などを語ら
なければ意味がない。もっとも、石油などは使い切ったら良いと思うし、石油採掘の限界費用などを明らかにし
ておいた方が良いと考えている。ローレンツ方程式を出すまでもなく、地球温暖化懐疑説という太陽の息遣い(
=太陽活動周期変動)をいうのでは、その影響の推定や推定方法の誤差を語らなければ、いま起きている大規模
気象変動に対する処方法は生まれないし、まして、欧米に隷属するか中国に隷属するの二分法も気に入らないし、
専門分野や非専門分野の知識を語るだけでは付加価値は生み出せないと思う。

【瞬間湯沸かし器と直流化】
必要な温度と水量のお湯が自動的に沸かせる時代が押し寄せてきている。それも、一昔前ならお湯を専用のタン
クに沸かしておきそこから供給してくるというもの。どうしても冷めてしまい、自動的に追い炊き、つまり、加
熱する必要があったわけだから、スペース的にも大きくなりエネルギーのロスも大きかったというわけだ。また、
ガス炊きによる自動温水器もあるが、これもガスを着火しその火炎でもって熱交換器を加熱し給湯するため、そ
れでも、そのためのスペースも大きく、ましてガス漏れによる爆発・火災事故やガス中毒事故が絶えなかった。
また、一旦煮沸加熱し作っておいたお湯を保温ポットに注ぎ保存することや電熱器で加熱機能付きポットなども、
高周波加熱の普及とともに、急速加熱ができるようになり、加熱部とポット部が分離されることで手軽に注ぎ込
むことが可能となりました。
※下の写真のように、台所用の電子式あるいは電気式瞬間給湯器は手のひらサイズまでダウンサイジングしてき
ている。
また、大量のお湯を必要とする浴槽や洗面などにも取り入れられて発展してきている(「未来の自動水栓」)。
例えば、自動水洗トイレ用のシャワーなど温水化システムなどもそれで、自動水洗などにも組み込まれ応用され
ています。特に洗面用の自動水洗は、一昔は温水が出てくるまでに時間がかかり水やお湯の無駄遣いとなってい
たが、いまでは自動的に調温できるようになり解消されている。これを可能にしたのは産業科学技術の、とりわ
け半導体技術や素材加工技術の進歩発展が大きく関係している。


ところで、瞬間冷水器(瞬間冷水製造器)というとそれらしきものはあるが、湯沸かし器のような完成されたも
のがない。ないということはチャンスなのだが ^^;、加熱と違って雑菌の繁殖とか冷媒などというものがいる。
ホシザキでは二酸化チタンを透明ビニール内壁にコーティングし蛍光灯を当て光触媒反応を起こし殺菌している。
スターリング冷凍・冷蔵機を使えばコンパクト化できるがデジタル化=コンパクト化にはなじみにくいが、工夫
次第によれば「マイクロスターリングフリーザ」を開発し手のひらサイズ化に成功すれば家庭用として普及する
可能性があるがこれはまたブログで考えてみたい。
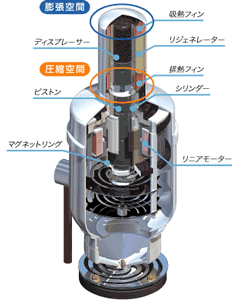

もう1つ考察を加えるとしたら、デジタル化の波は電力の自由化を促すことだ。それも高品質な分散型の電力供
給システムが考えられている。それは、従来の高電圧配電を必要としないということになる。家庭で使う電圧は
250Vもあれば事足りる時代だ。30キロメートルないでの高圧送電システムはすでにデジタル革命で陳腐と化し
ていることは専門家なら周知のこと。分散型の電源は太陽光発電や燃料電池などで、発電時や消費時に二酸化炭
素を出さないクリーンな新エネルギー源として、その展開が21世紀に期待されている。これらのほとんどが直流
で発電をしている。分散型電源の普及は、限られた特定のビルや施設内の使用場所であれば、直流配電の可能性
も十分復活しうると。
ところで、直流送電の歴史は古い。1882年、エジソンは世界に先駆けて電気の供給をニューヨークで開始する。
その方式は直流だった。5年後の1887年、日本でも電力供給が始まり、日本の電力送電もエジソンと同じ直流の
電圧120ボルトで、変圧器が電圧の昇降圧を可能にした(1885年)ので、これを主軸に、交流送電が主流になって
いく。日本でも1889年以後は交流送電が主体となった。しかし近年、巨大化した交流送電システムはさまざまな
問題が指摘され、脚光は直流送電システムヘあたってきた。交流は直流に比べて送電損失が大きい。送電幹線は
交流送電を前提にする限り、これまでも高電圧化されてきたが、その傾向は今後も強められていく。百万ボルト
送電の幹線計画は日本でも進められているが、交流の高電圧化は鉄塔など送電設備の大型化を招き、そのほとん
どが新規の建設になり費用も馬鹿にならない。交直変換は技術的に容易なので、同じ費用をかけるのであれば、
送電幹線の直流化は経済的にも技術的にも非現実的な選択ではないとう。将来的にも、日本の送電幹線は直流の
高電圧化に変えていくことがのぞましいだろう。
直流送電は、交直変換装置のコスト高などの欠点もあるが、それより増して利点の方が多い。まず、送電鉄塔は
交流送電よりはるかに低く小さくできる。経済的送電効率は交流送電に比べ送電距離に比例してよくなり、交流
送電は30キロメートルが最適であるが、直流送電は、一万キロメートルまで送電が可能になる。本格的直流送電
の歴史的幕開けは1954年スウェーデン本土とゴットランド島間の送電に始まる。これは、当時スウェーデンで開
発された高電圧水銀整流器を使用した直流100キロボルト、20メガワットの電力を海底ケーブルで約百キロメー
トル輸送したもので、この成功で直流送電技術の実用性、信頼性が広く認識されることになる。
当面は、市町村単位での社会実験を計画に入れるのも良いだろう。それも西沢潤一教授が教鞭を執った仙台市で
復興がらみでやるのも良いのではと思ったりしている。やりたいことがいっぱいありますねぇ~。




















