● 大河ドラマ 軍師官兵衛
今月24日に長浜の黒田官兵衛博覧会入館者数が五万人を突破したことが報じられた。
NHKの大河ドラマの視聴率は今ひとつ伸びがないが、人気俳優・生田斗真がの『軍師
官兵衛』に出演してから視聴率が上向きだした。生田が演じるのは、キリシタン大名と
して広く知られている高山右近。彼は、主人公・黒田官兵衛とも距離が近く、豊臣秀吉
の配下として活躍したが、後に国外追放となってマニラで没する。右近は、天文21年(
1552年)に大和国宇陀郡の沢城(現在の奈良県宇陀市榛原)を居城とする高山家に生ま
れた。彼の父もイエズス会の人物に影響を受けたことから、彼は12歳の時にキリスト教
の洗礼を受ける。永禄11年(1568年)に織田信長の強力な軍事力の庇護の下、15代将軍・
足利義昭が「摂津三守護」を任命したが、それによって摂津は大きく混乱。高山家もこ
の混乱に巻き込まれ、最終的に荒木村重の支配下として、高槻城に入る。ところが天正
6年(1578年)に、右近の主君である荒木村重が織田信長に反乱するが右近は、高槻城
を落とそうとする織田信長に従い、その離脱により村重側は大きな痛手となる。右近は、
高槻城主として地位を安堵され4万石へ加増され、天正10年(1582年)に本能寺の変が
起きると、右近は羽柴秀吉に従って山崎の戦いで功績を上げる。その後も、秀吉に従っ
て賤ヶ岳の戦いや小牧・長久手の戦い、四国征伐に参戦、天正13年には、新たに播磨明
石郡6万石領地として加増される。ところが、秀吉による「バテレン追放令」が施行さ
れ、領地・財産を棄てて信仰を守る道を選ぶ。暫く、小西行長や前田利家の庇護を得て
いたが、徳川家康のキリシタン国外追放令を受けて、慶長19年(1614年)にマニラへ渡
るものの翌年に没する、享年64歳。

3月16日放送の大河ドラマ軍師官兵衛 11話「命がけの宴」に登場した。高山右近
は、黒田官兵衛に大きな影響を及ぼした人物。真面目で清々しい雰囲気の持ち主だった
といわれ、黒田官兵衛もそんな高山右近に惹かれ右近の奨めで、キリスト教に入信(嫡
子の黒田長政もキリシタン大名)。他にも、名将と言われ、織田信長の娘を娶った、蒲
生氏郷や小西行長、牧村政治、が入信、この他、細川忠興、前田利家らが右近の影響を
受けキリスト教に好意的であった。若くして内紛に巻き込まれ、首の3分の2を切られ
る瀕死(ひんし)の状態から奇跡の生還を遂げ(天正元年、高槻城で高山右近と和田惟
長の斬り合いによるもで、フロイス『日本史』に、まず右近が惟長に致命傷二カ所与え、
右近も片腕を負傷。その後、右近の家臣が暗闇のため、敵と間違って右近の首を半ばほ
ど切断したとある)、ドラマでは首に大きな傷をつけた状態で登場していた。



「キリシタンとして争いのない国をつくりたいという反面、武将として人を殺さなけれ
ばいけない、という葛藤も出していきたい」と話す。念願の大河だ。「役者を続けなが
ら、ずっと思っていたこと。岡田さんとも共演したいと思っていたので、出たいという
意思をあちこちで伝えてきました」とドラマへの意気込みを語る。一方、村重は、右近
が領民から慕われていることを認め、キリシタン宣教を、織田軍は石山本願寺の門徒の
手を焼いていたこともあり奨励する。この村重の妻「だし」までもがキリシタンに入信。
「慈悲の心」で高価な着物を貧しい者に施してしまったという「だし」。「心が晴れ晴
れとなりました」という彼女に、村重は「美しく着飾っている『だし』を見ていたかっ
た」と苦笑いする。
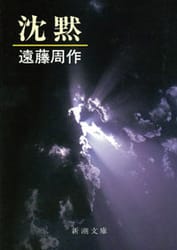
●その後の右近とキリシタンの受難
高山右近は、1552年(天文21年)に高山友照の嫡男として大和国宇陀郡の沢城(現在の
奈良県宇陀市榛原)に産まれ、父の高山友照が奈良で琵琶法師だったイエズス会員ロレ
ンソ了斎の話を聞いて感銘を受け、洗礼を受け家族も入信。バテレン追放後は、親しか
った前田利家の加賀藩内に領地を与えられ、従軍し小田原征伐に赴いたり、加賀藩の相
談役として働らく。秀吉の死後、1614年1月(慶長十八年十二月)、臨済宗の僧、金地
院崇伝の起草による「伴天連追放文」が日本国中が知るべき掟として公布された(慶長
の禁教令)。
日本は神国であり、吉利支丹の教えは正宗なる神仏を惑わす邪宗である。吉利支丹
国の者は日本に商船を来航させ、財貨をもたらすためだけでなく、邪法を広めて正
宗を混乱させ、日本の政治を改変しようとしている、これは大きな禍の兆しである
2月には京都から宣教師が去り、長崎へと護送されていった。4月京都に残り棄教を拒
んだキリシタン達71名が奥州は津軽へ流罪となる。九州へ宣教師追放と教会破却のため
伏見城番山口直友が派遣され、各地で宣教師や日本人信徒を摘発し、11月6日には高山
右近の一族と共にマカオとマニラに追放し、長崎の11の教会を焼却した。その後有馬地
方にも赴き、キリシタンの摘発と棄教を迫り、従わぬ者は処刑した。慶長禁教令による
迫害はこれが最初である。その迫害のすさまじさは、遠藤周作の小説『沈黙』で有名な
フェレイラ神父の棄教として描かれている(※彼は、元天正遣欧使節の中浦ジュリアン
と共に穴吊りの刑に処されている:キリシタン史「江戸初期の大迫害」参考)。
●大一大万大吉は家紋?
関ヶ原合戦図屏風(井伊家本)などを見ると、石田三成は、陣幕に「大一大万大吉」と
いう合わせ文字紋を使用しているが、この文字紋は、実は江戸末期以前の文献史料には
見当たらないという。三成は、石田家の家紋としては、基本的には九曜紋を使用してい
た。九曜紋については、石田家のルーツを辿ると、代々使用している紋でもあり、三成
がこの紋を使用した史料も残っているらしく、とりあえずは三成の家紋は九曜紋という
のが確定的とされるが、「大一大万大吉」が江戸末期までの史料に見えなくなるのは、
徳川家の陰謀といわれる。
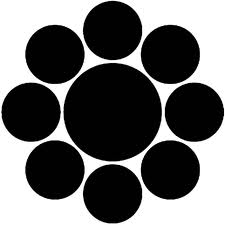
「大一大万大吉」は、源平合戦の時代に木曾義仲を討ち取った石田次郎為久という武将
が用いていたものを三成が気に入って使ったというが、その意味は「一人が万民のため
に、万民は一人のために尽くせば、天下の人々は幸福(吉)になれる」。そう、アンド
レ・デュユの『三銃士』の銃士の合い言葉「国王は銃士のために、銃士は国王のため」
(One for all, All for one)である。石田三成は天正18年(1590) に佐和山に入城。佐和山
城は、安土城を築く以前、織田信長が上洛の途中によく利用した城。入城当初は10万石
程度の石高であったが、後に、犬上、坂田、浅井、伊香の湖北4郡を与えられて19万4
千石の大名となる。佐和山城主としての領内の政治は、現在湖北各地に残る13か条、9
9か条の掟書で詳しく分かる。この掟書は、十三か条が12点、九ヶ条が10点 合計22点
の存在が確認できる。文禄5年(1596)3月1日付で、一斉に、領内津々浦々に配布さ
れた。掟書の目的は、農村で生活し年貢を支払う百姓を、基本的領民として把握しその権利
と義務を明確化にある。例えば、第一条では年貢の決定方法を細かく規定。第九条では、検地
帳に記載された耕作者の権利をしっかり保障している。当時の諸大名で、これほど綿密で長文
の規定を領内に明確に示している領主はいない。農作業の実態を熟知し、領内の状況もにつ
いても、村単位で実情を把握していたことを示している。石田三成の領主として、統治者(知事)
としていかに有能であったかが如何得るという。
その能力が、1583年の賤ケ岳の戦いでまた石田三成の能力が発揮される。秀吉軍本隊が
大垣付近に布陣し、北近江本陣が留守の間に、柴田勝家軍の一部軍勢が攻撃。その情報
を得た秀吉は急遽、大垣から北近江まで52キロの道のりを戻ることになったが、当時の
標準的な移動時間からすると、最低でも12時間はかかる。重い兵糧を腰にまいての移動
では確実に間に合わない。しかし、秀吉軍本隊はこの時なんと、この距離をわずか5時
間で走り抜いている。この「不可能」を「可能」にしたのが石田三成。なんと、大垣か
ら北近江までの往還沿いの村々に命じ、松明と握り飯の用意を命じておいたのです。こ
の三成の戦略によって、軍は重い兵糧を運ぶ必要がなくなり、休憩時間を大幅に短縮さ
せることができました。そればかりか、空が暗くなる夜には、沿道の家々に松明を用意
させ、暗さによって起こる軍の走行スピードの低下を防いだのでした。これは石田三成
の並みはずれた「指導力」と先を読んで確実に予測する「計算力」によるものと評され
ている。
また、秀吉の時代になり、最終的に三成の居城になり、三成は佐和山城に大改修を行っ
て山頂に五層(三層説あり)の天守が高くそびえたつほどの近世城郭を築く。ただしあ
くまで実戦本位に造った城であって、城の壁は粗壁であり、庭には風情のある植木もな
く手水鉢は粗末な石、また何の装飾もない質素な造りで、これは三成が収入のほとんど
を仕事に使い、自分のために残さなかったという清廉潔白さを表すという。関ヶ原後の
東軍の寄せ手が佐和山城を落としたとき、さぞかし豪勢で、私財を貯えているだろうと
思っていたが、金銀もなく、あまりの質素さに驚いたというほどである東軍についた武
将には、三成の高邁な思想など想像だにできなかったと伝承されている。つまり、これ
は九曜と七曜との家紋の星の数や禄高の違いや信仰(布教)政策の違いはあるものの三
成も右近も善政を敷き領民に普く慕われていたことは共通している。
●その才能故、疎まれた黒田官兵衛
黒田氏の家紋は「石餅(石持)」と「藤巴」である。『寛永諸家系図伝』などによれば、
賤ヶ岳山麓の近江国伊香郡黒田村の出身とされるが、定かではない。孝高の祖父・黒田
重隆の代に備前国邑久郡福岡村から播磨国に入り、置塩城の守護赤松晴政、後に晴政重
臣で御着城(現在の姫路市東部)を中心に播州平野に勢力を持っていた戦国大名の小寺
則職・政職父子に仕えた。小寺氏は黒田氏を高く評価し、重隆を重臣として天文14年(
1545年)姫路城代に任じた。重隆の子、黒田職隆には自らの養女を嫁がせ、小寺の名字
を名乗らせている。影の軍師として秀吉に仕えた官兵衛は、1546年、姫路城城主黒
田職隆の長男として生まれたが、当時は城主もいないようなちっぽけな御着城の出城。
毛利攻めの大返しに、黒田官兵衛が天下取りを進言した秀吉が後年、「(秀吉が)どう
してよいかわからぬときに、官兵衛は即座に策を述べた」と何遍も周辺に話しており、
秀吉が本能寺の後すぐ自分が天下人になれるかもって思う気持ちを回りに悟られたくな
かったのではとの指摘があるが、官兵衛のその"勝負師の言動"(野心家)が覚られる何
かがあったということにもなる。ここが石田三成や高山右近と異なるところだろう。と
は言え、石田三成、高山右近、黒田官兵衛に共通する鋭利さ、その実行力(特に、三人
とも築城名人と称されている)、行政力(ただし、人望につい単純に比較できない)は
他の武将とは並み離れていたことは肯くけるだろう。
官兵衛は、秀吉による九州平定の論功行賞として、天生15(1587)年7月に京都
・築城・仲津・上毛・下毛・宇佐の豊前6郡12万石の大名となり、翌年、中津城を築
城。以来、慶長5(1600)年息子長政に与えられた筑前(現福岡市)の領地に移り
住むまでの13年間、一国の領主でありながら秀吉の軍事参謀としての活躍が続いた。
天生15(1587)年、豊前6郡の領主となった官兵衛は、入国すると直に下記の3ヵ条の掟書き
を発し、主従関係の確保、治安維持、年貢米(税)・土地支配の姿勢、という領国経営の基礎方
針を簡潔に領民にわかりやすく打ち出しす。
一、 主人、親、夫に背くものは罪として罰せよ。
一、 殺人、盗み、強盗をしたもの、それを企てたものはその罪を罰せよ。
一、 隠田、畝ちがえ(田畑を隠す、広さを隠す)などをしたものも同前である。
官兵衛が行った検地は、検地奉行の派遣による正確な実測を行うものではなく、指出と
呼ばれる申告による検地。当然申告は実際より少なくなるが、官兵衛は見栄を張らず石
高を低く抑え、農民の税負担を軽減したが、宇都宮一族は、文治元(1185)年に初
代信房が源頼朝から豊前国を拝領して以来、弟や子を豊前の谷々に置き、400年にわ
たって支配し続け勢力を大きくしたが、天生15(1587)年、秀吉による九州平定
の論功行賞として豊前6郡は官兵衛に与えれ、それまで統治していた宇都宮一族の本家
宇都宮鎮房は城井谷から伊予への転封を秀吉に命じられた。これを受け入れられない鎮
房を中心に、検地に反対する豊前の国人が一揆を起こした。これに対し、官兵衛は毛利軍
の手助けを受け徹底して一揆を鎮圧。幾度もの合戦が行われ、いくつもの城が落城した。なか
でも、長岩城(耶馬溪町川原口)の城主野仲鎮兼は一族最大級の兵力をもって激しい攻
防を繰り広げたが、黒田軍の前に敗れた。最後に当主宇都宮鎮房は降伏するも、中津城
内にて討たれ、宇都宮一族は滅ぶ。このように、知略により人を殺さずに話し合いでの
決着を図ってきた官兵衛だが、宇都宮鎮房の謀殺事件では、かなりむごい仕打ちをした
のは、この時期、肥後一揆を封じこめられなかった佐々成政が秀吉に切腹させられてお
り、一揆の徹底鎮圧は秀吉の指示でもあったととも言われている(「豊前の国中津統治
時代」参照)。最後に、ダウンタウンの松本人志の官兵衛評を紹介し、" 戦国時代の三
国の城主" についての今夜の話を切り上げよう。
息子の大活躍により、関ヶ原の戦いは半日で終わる息子の長政が、西軍の小早川秀
秋や吉川広家を寝返らせて、家康軍を勝利に導くという大手柄をあげたんです。お
気に入り詳細を見る 長政は、官兵衛に家康が自分の手を取り、なんどもお礼を述べ
たことを告げる家康から「よくやってくれた」と言われたのを自慢げに話しました。
官兵衛「そのとき、内府(家康)はお前のどちらの手を取った?」
長 政「右手でした。」
官兵衛「その時、お前の左手はどうしていた?」
長 政「・・・」
これは、なぜ左手で家康を殺さなかった?という意味。息子は親の官兵衛の戦略を
理解していなかったようです…残念。






















