 「君に友だちはいらない」の購入はコチラ
「君に友だちはいらない」の購入はコチラ 「君に友だちはいらない」という本は衝撃的な題名ですが、夢を語り合うだけの「友だち」は不要で、ともに試練を乗り越え、ひとつの目的に向かって突き進んでいく「仲間」を持つことが重要という内容です。
特に歴史というのは後世「作られる」ものであることから、えてしてひとりの天才がすべてを達成したかのように語り継がれることが少なくありませんが、重要なのはひとりで事業を立ち上げて成功にいたったわけではなく、すべて「チーム」の力によって大きな業績を成し遂げているということです。
また大きな業績を残すには大きな目標を立てること、そして多種多様な専門分野の出身者からなるチームを作ることが肝要とのことです。
それから自分の人生をよりよくするには、自分の人的ネットワークが自分を規定することから、友人・仲間は十分に選び、また自分のネットワークが弱いつながりによって多様性を確保しているか常にチェックすることが大事とはナルホドと思いましたね。
また成功するには、ギブをしまくることも大切なようです。
「君に友だちはいらない」という本は、大きな夢を達成する秘訣や自分の人生をよりよくするヒントがたくさん散りばめられ、とてもオススメです!
以下はこの本のポイント等です。
・大きな世の中のパラダイム・シフトというのは、「世代交代が引き起こす」ということである。古いパラダイムを信じている前の世代を説得して意見を変えさせるのは、不可能であるし、それに労力を注ぐのは時間の無駄だということだ。自分たちの信じる新しいパラダイム、必要とされるパラダイムの心奉者を、少しずつ増やしていくこと。そうやって「仲間」をつくっていくうちに、いずれ旧世代は死に絶えて、新たなパラダイムの時代となるのである。ビジネスの世界でも、停滞している分野ほどベンチャー企業が有利であるのはそれが理由だ。業界に長い間君臨してきた企業はかつての成功体験、固定観念にとらわれているために冒険ができない。その固定観念自体が時代の変化にともない、間違ったものになってしまっていることに、気づかないのである。
・過去の歴史を振り返っても明らかなように、時代を変革するのは常に若い世代の人間である。明治維新を例にとれば、薩長同盟が成立したとき、薩摩の代表・大久保利通は35歳、長州の木戸孝充は32歳だった。伊藤博文は大久保利通の亡き後、36歳で内務卿となり、事実上の国政のトップに就任した。明治政府で逓信大臣や文部大臣などの重要ポストを任された榎本武揚は、幕府の海軍を率いて函館で明治新政府軍と戦ったとき、32歳である。美辞値氏の世界も東西を問わず、革命的な企業を作り上げたのは20代から30代の若者だ。長年にわたって日本を代表する企業であり続けてきたパナソニック、ソニーは、それぞれ松下幸之助が24歳、井深大が37歳のときに起業している。現在の日本経済を牽引する企業であるソフトバンク、日本電産、ユニクロは、孫正義が22歳、永守重信が28歳、柳井正が35歳のときに社長になった。アメリカの企業はさらに若い。アップルのスティーブ・ジョブズは21歳、グーグルのラリー・ペイジは25歳、マイクロソフトのビル・ゲイツとフェイスブックのマーク・ザッカーバーグにいたってはわずか19歳のときに会社を設立しているのである。ビジネスだけでなく政治の世界も同様だ。イギリス首相のデヴィッド・キャメロンが保守党の党首になったのは39歳のとき。韓国の李明博前大統領は、ヒュンダイグループの中心企業である現代建設の社長に35歳で就任している。重要なのは、彼らもひとりで事業を立ち上げて成功にいたったわけではなく、「チーム」の力によって大きな業績を成し遂げたということだ。
・本書のテーマである「仲間づくり」(チームアプローチ)を、私がよく使う別な言葉で表現するならば、それは「今いる場で、秘密結社をつくれ」ということになる。秘密結社というとおどろおどろしいイメージがあるが、要するに「さまざまな出身のメンバーが、ひとつの目的の達成を目指して、自発的に集まった集団」のことを意味する。企業のなかでも新しいチャレンジを試みるのは、しばしば「社内で部署横断的に集まった秘密結社的チーム」だ。
・コモディティ化がすすむふつうの個人が個人の力だけで立ち向かうのは無謀すぎる。弱者こそチームの力を利用せよ。
・パラダイム・シフト、社会の変革は、世代交代によっておこる。したがって、今こそ若者のゲリラチームが重要。
・あらゆる投資の本質は、人への投資であり、チームメンバーだけが究極の差別化。弱いもの、非エスタブリッシュメント、コミュ障こそチームをつくれ。
・圧倒的な成果がひとりの天才によってなされたと考えるのは後世の人が作った幻想。実際にはチームの力であり、「七人の侍」という映画はその内容も、成り立ちもチームの重要性を象徴している。
・カッツェンバックらは、さまざまなプロジェクトのケーススタディを通じて、「まあまあ」よい成果ではなく、「抜きんでた」成果をあげたチームには、共通の特徴があることを発見した。「よいチーム」はたいていの場合、
1少人数である
2メンバーが互いに補完的なスキルを有する
3共通の目的とその達成に責任を持つ
4問題解決のためのアプローチの方法を共有している
5メンバーの相互責任がある
という大きな共通点を持つことを見出した。この5つの共通する特徴を、チームづくりに活かすというのがチームアプローチの基本的な考え方である。
・「フェイスブックの友だちは選んだほうがいい」とツィッターで以前私が書いたところ、少なくない数の人の賛同を得た。なぜフェイスブックでは友だちを選んだほうがいいのか。それはフェイスブックの友だちにどんな人がいるかで、その人の評価が決まってしまうことがあるからだ。今ではビジネスで知り合った人が、どんなバックボーンを持った人なのかを知るために、フェイスブックでその人のプロフィールを見るのは当たり前の行動になっている。で、怖いのは、プロフィールに出てきた「友だち」に「痛い人物」が含まれていた場合、その人も「痛い」と判断される可能性が高いことだ。つまりその人のまわりにどんな人がいるかによって、その人物のパーソナリティがくっきりと明確に浮かび上がるのである。古くから言う「類は友を呼ぶ」ということわざは本当なのである。フェイスブックで無闇に友だちを増やすのが考えものなのは、それが大きな理由だ。同じくネットサービスのツイッターも、「誰をフォローしているか」見ることで、その人物の思想や知的レベルをかなりの部分類推することができる。ツイッターで誰をフォローするかは、個人の完全な自由であるがゆえに、タイムラインがその人の価値観を反映する。ツイッターではよく事実無根の情報が拡散して問題となるが、そのような「デマ」に踊らされる人は、ダメな情報しか集まってこないような環境を自らが作っているだけなのだ。これは現実の世界でも同じことが言える。ダメな奴とずっと同じ時間・同じ場所で過ごし、ダメな情報ばかりに囲まれていると、自分もその水準になってしまうことは避けられない。
・モノも知識も、たくさん持ちすぎると、それを自分がコントロールしていると思っていながら、逆にそれらに縛られてしまうということがある。いわゆる「専門バカ」というのがそれだ。ある分野については膨大な知識を持っているがゆえに、それ以外の視点からは物事が見えなくなってしまうのだ。だからそれを防ぐためにも、ときどきは自分の持つ「モノ」や「知識」を手放したほうがいい。これは勇気がいることだが、「持っているものが多いこと」が貴いのではなく「必要なものが少ない」のが貴いのである。仲間についても同じだ。仲間の数を増やすのではなく、少数の仲間の質を追求することが、肝要となるのだ。
・人間もまた、まわりに成功している人が多ければ、成功することが当たり前だと思って努力する。しかしまわりに成功者がいない人は、「成功するというイメージ」が持てないために努力ができず、ひどい場合には「成功することで人間関係が悪くなる」ことを恐れたり、「自分が成功するはずがない」と深層心理レベルで思っているので、成功の直前で突然自滅的な行動をとったりするのだ。
・大学では、専門分野に特化せずに、歴史、経済、社会理論、芸術、文化、語学などの幅広い教養を身につけることが意味を持つ。一度社会に出てしまったら、自分の仕事とは直接関係することのない、幅広い教養を身につけられる時間を作りだすことは、たいへん困難となるからだ。教養の持つ大切な機能の一つが、「自分と違う世界に生きている人と会話できるようになること」だ。外国語の習得もそのためにある。
・若い従業員の労働力を搾取するだけの会社は問題外だが、非常に仕事が厳しくても、その業務を通じて大きく成長することができる会社は、ブラックではないのだ。
・チームのメンバーが似たような専門分野の出身者である場合、イノベーションの平均的な経済的価値は高いが、画期的な発明が生まれる可能性はきわめて低い。それと対照的に、多種多様な専門分野の出身者からなるチームが生み出すイノベーションは、失敗の可能性も高く、平均すると金銭的価値も低くなるが、ひとたび画期的な発明が生まれると、その時点でもっとも優れた発明をはるかに凌ぐ高い価値を生み出す。
・転職においては自分と似通ったバックグラウンドの人に相談するよりも、まったく自分の業界とは関係のない人に相談したほうが、その後の転職活動がうまくいく。それが統計的に証明されたのである。なぜそうなるのか、考えてみると答えは明らかだ。自分と同じタイプの人、自分が持っているリソースと似通っている領域で生きている人に相談や協力を求めても、それはせいぜい1が2になるぐらいの足し算的な変化しかおこらない。自分と「強い絆」を持っている人は、自分と似たような情報、似たような思考様式、似たような人脈しか持っていないので、すでに自分が所有しているリソースに対して新たな付加価値をもたらす可能性が低い。それゆえ「強いつながり」の人物とばかり交流しても、1が10にもなるような、掛け算の変化はおこらないのだ。
・チームを作るうえでも、弱いつながりに着目することが大切だ。「自分と違うネットワークを持っている人」とつながることが、後々に大きな意味を持ってくるのである。
・「なるほど、成功というのは、その人のまわりの人の成功によって決まるのだな」と感じた。そもそもひとつのギブに対して、すぐにテイク=見返りを求めるのは愚かなことだ。人は何かの恩を受けたとしても、そのときすぐにお礼ができるタイミングではないこともある。でも困ったときに助けてもらったという記憶は鮮明に残るし、まわりの人にそれを話すこともあるだろう。ギブ&テイクの関係を一回ごとに築こうとすることは意味がない。とにかくギブをしまくっていることで「ギブのネットワーク」がまわりに構築され、そのネットワークが大きくなり、情報や交流の流通量が高まれば高まるほど、もたらされるメリットも大きくなるに違いない。
・ネットワークを構築する前には、まず今の自分が持っているネットワークの「棚卸し」をする必要があるだろう。
・自分が頻繁に会っているのはどういう人か。
・たまにしか会わないけれど、自分にとって重要な人は誰か。
・どれほど多様なコミュニティに属しているか。
・自分の近くにいる人で、別のコミュニティのハブとなってくれそうな人はいるか
この4点を確認することで、今の自分のネットワークがどういう状態にあるか、理解することができる。その結果が望ましいものであれば、さらによい方向に伸ばしていけばいいし、「変えなければならない」と思うのであれば、一刻も早く適正化する努力をすべきだ。ネットワークは「自分がどういう人間か」で決まる。頻繁に会っている人が客観的に見てロクでもない人間であるとするならば、自分自身がロクでもない人間になっている可能性が高いのである。どのような人を引き寄せるか、どんな人が自分に対して関心を抱くかは、その人自身の人生の反映であり、「まわりにロクなやつがいない」というのは、鏡に向かって悪口を言うのに等しい。自分の行動、態度を変えれば、まわりに集まってくる人も変わってくる。自分の置かれている環境は、少なからず自分が過去にしてきた意思決定の反映なのだ。
・SNSで、友だちの数を競ったり、ライン(メッセンジャーサービス)の既読に一喜一憂したり、居酒屋やシェアハウスで、愚痴を言い合ったり、そんな、「友だち」ごっこは、やめにしないか、人生の無駄遣いである。
・自分の人的ネットワークが自分を規定する。友人、仲間は選べ。学校と会社そして仕事と無関係な趣味のサークルこそネットワークのハブである。
・会社を選ぶときは、「ブートキャンプ」「見晴らしのよい場所」を意識しろ。
・自分のネットワークが弱いつながりによって多様性を確保しているか常にチェックせよ。
・主人公が最初に掲げるチームのミッションやビジョンは、現状の自分たちからすると、いったいどうすればいいのか、どこに行けばいいのか検討がつかないぐらい「大き過ぎる」ものでちょうどよい。ふつうに考えれば実現不可能だが、もしかするとやれるかもしれない・・・ぎりぎりメンバー全員がそう思えるほど大きな目標が望ましいのだ。なぜならば「容易に達成が可能と思われる小さな目標」は、容易なだけに誰でも思いつくし、すでに他のチームが掲げている可能性が高いからだ。安易な目標はチームメンバーの心を捉えない。また中途半端な人格者のところには、人は集まらない。外部の人間からの注目も集まらないだろう。むしろ人は「でかすぎるビジョン」を掲げる、「穴だらけの人物」に注目する。
・これまでの日本の教育は、工業化する社会のなかで、決められたモノを決められた手順で作るのに最適なスキルをもった人を生み出すためのものでした。しかしもはやそれでは、日本が立ちいかなくなることは目に見えています。これからの教育は、21世紀の世界を生き残る力を与えてあげることを目的として、それができるクリエイティビティとリーダーシップを持つ人を教師にしなければいけない。
・仲間を集めてチームをつくっていく過程では、何度も何度も同じことを繰り返し語っていかねばならない。それに上達するためにも、ぜひ次に掲げる訓練を実際にやってみてほしい。
・まずストーリーの「コア」を作る。
・いくつかの聴衆(ターゲット)ごとに話の内容をカスタマイズする。
・実際に3分程度で話してみる(ストップウォッチで測るとよい)。
・まわりの友人や知人に語ってみて、分かりにくい点、共感を覚えにくい点などのフィードバックを得て、修正する。
・この基準にメンバーが該当したら、絶対にチームから手を引かせないといけない。それは、「倫理性」だ。世の中には本当にいろいろな人がいる。平気でウソをつく人、法律を平気で破る人・・・。こうした人に出会ったときに思い出してほしいのが、「ゴキブリ」理論である。部屋でゴキブリを一匹見つけたとき、「たまたま一匹だけ部屋にまぎれこんだ」ということは、まずありえない。実際には家のどこかに巣があって、見つかっていないゴキブリがたくさんいて、たまたまそのうちの一匹が見つかったに過ぎないのだ。不正も同じである。一つの不正行為を見つけたら、その背後にはまだ見つかっていないたくさんの不正行為が潜んでいると考えたほうがよいのだ。また、そういう人々は、善悪の判断基準が緩いので、本人が「これはグレーゾーンなんですよ」と強弁しているケースでも、客観的には黒も黒、即アウトであることが少なくない。実際、私も過去に、「この人は危険だから、近づかないでおこう」と判断した人が、何年も経ってから事件を起こして、新聞紙上を騒がせるということが何度かあった。悪事はたいてい、止める人がいなければ、行き着くところまで行き着いてしまうものだ。「倫理」にかかわる問題は、自分が直接の当事者でなくても、参加者全員の評判に傷をつける。
・今の日本企業には「志が大きなチャレンジを数多く繰り返す」という姿勢が欠けている。だからかつてのウォークマンのような革新的な製品が生み出せずに、どうでもいいような付加機能を”てんこ盛り”したモデルチェンジ商品ばかりが発売され続けるのである。
・大切なのは、「冗長性の少ないネットワーク」をなるべく多く持つことだ。冗長性とは情報科学でよく使われる言葉で、「無駄や重複がある状態」のことを言う。つまり「冗長性の少ないネットワーク」とは、自分がこれまで所属してきたネットワークと、重なる部分が少ないネットワークのことだ。より簡単にいえば「自分のことを知らない人たち」ばかりいるネットワークのほうが、自分にとって価値が高いということである。自社だけの狭い組織で働き続けていると、「自社の常識は他社の非常識」の状態に知らず知らずに陥っている。「他業界の常識」については、その存在すら知ることができない。だが自分とまったく関わりがない集団に入れば、自然と「外部」の価値観を知ることができる。
・多様な人が多様なチームに属することが社会のダイナミズムを生む。
・日本は、自然発生的に集まった「なあなあ」の関係のゲマインシャフト的な集団を、目的がきちんとあるゲゼルシャフト的な集団へと転換していくプロセスにある。
・歴史的には、日本こそ、東アジアのフロンティアであり、リスクをとってチャレンジする人たちが集まった国である。
・他人の作った作り物の物語を消費するのではなく、自分自身の人生という物語の脚本を書き、演じろ。
面白かった本まとめ(2014年上半期)
<今日の独り言>
Twitterをご覧ください!フォローをよろしくお願いします。






















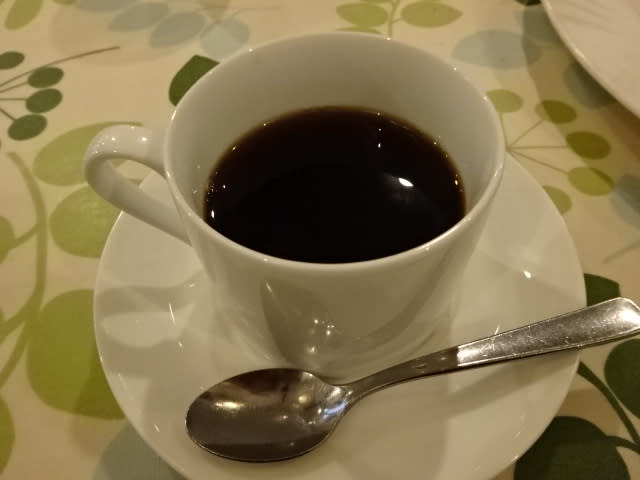

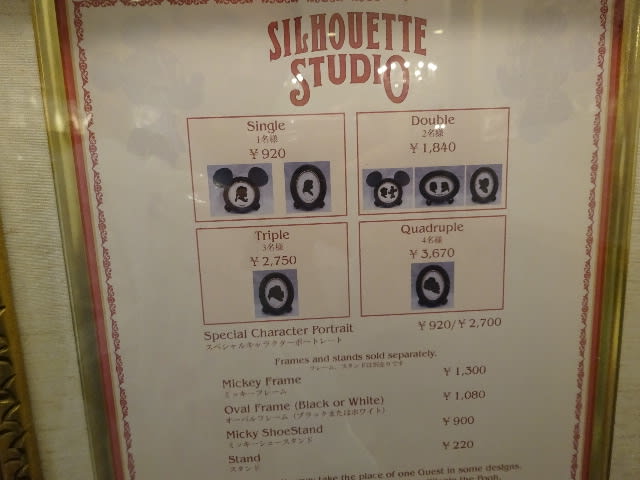


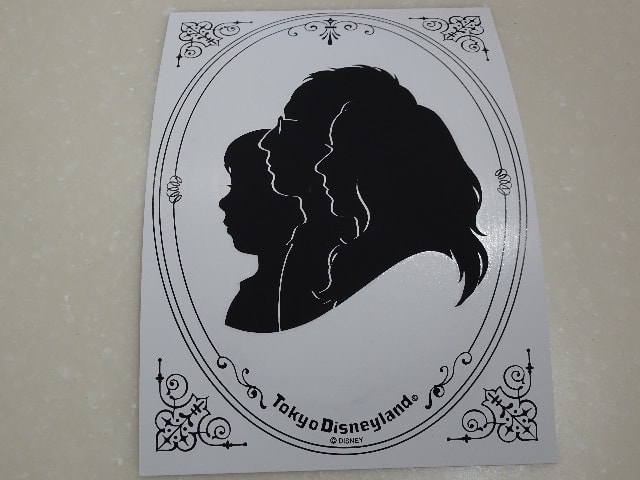
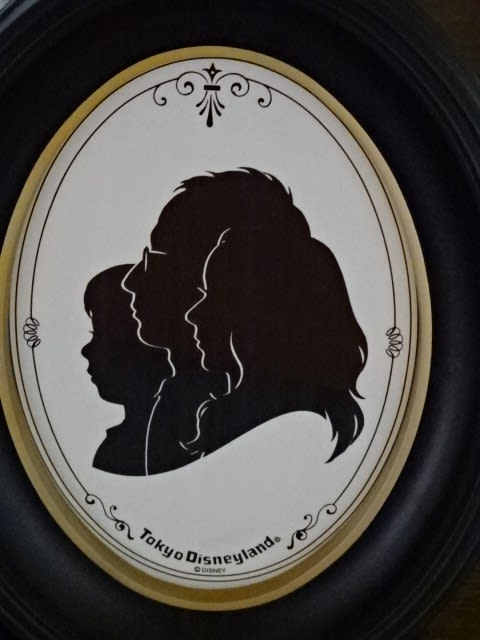
 「一流の人だけが実践している成功術」の購入はコチラ
「一流の人だけが実践している成功術」の購入はコチラ 














 「7日間で突然頭がよくなる本」の購入はコチラ
「7日間で突然頭がよくなる本」の購入はコチラ 



















