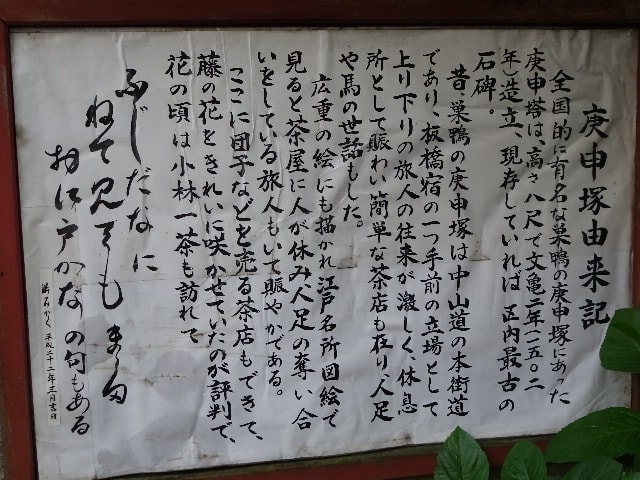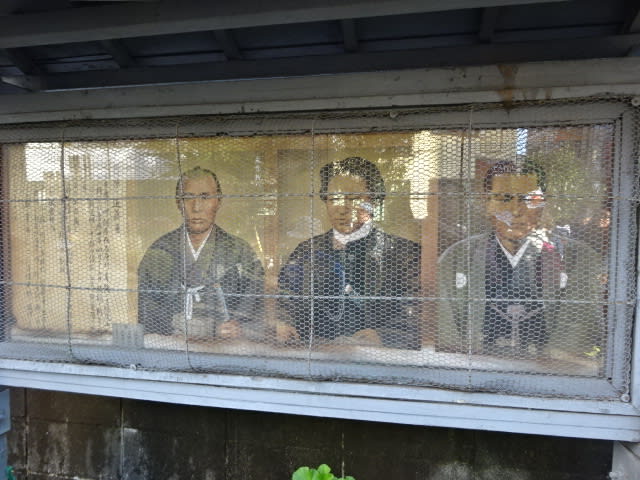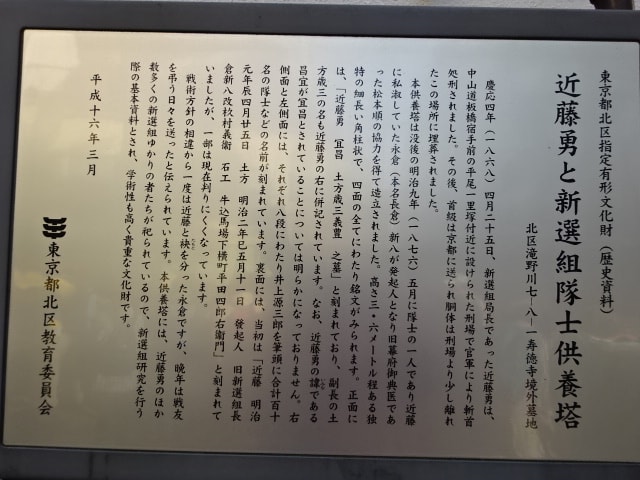「小説家という職業」の購入はコチラ
「小説家という職業」の購入はコチラ
「小説家という職業」という本は、著者が小説家となった経緯や、小説家になるにはどうすれば良いのか、小説家として続けるための心構えや姿勢、小説執筆のポイント、出版界の問題等について自らの体験を踏まえて分かりやすく正直に書かれたものです♪
「小説家になりたいのだったら、小説など読むな」というのには驚きましたが、人の作品を研究したところで生まれる作品など、たかが知れるようです。
オリジナリティのあるものを生み出すことが最重要のようです。
これは、他のいろんな世界でも共通ですね♪
そのため小説を楽しく書こうと思うのではなく、金儲けのために小説を書くという決意が重要なようです。
そして、どうすれば良いかと考える暇があったら、とにかく小説を書くこと、これに尽きるようです。
著者は、初めにトータル20時間ほどで原稿用紙300枚程度の小説を書き上げ、出版社に応募し、そしてその結果を待つまでにも次々と小説を書き、半年後には4作目から小説家としてデビューし、最初の1年で3冊の本が出版され、その年の印税は当時の本業(国立大学勤務)の給料の倍にもなり、それで驚いていたら翌年には4倍になり、3年後には8倍、4年後には16倍となったようです♪
売れる作家というのはすごいですね♪
そのためにも作家を続けることが大切で、ビジョンを持って長い目を持つことが重要なようです。
「小説家という職業」という本は、そのほか小説家や出版社の世界もよく分かり、とてもオススメです!
なお、以前このブログで紹介した同じ著者の続編?の「作家の収支」という本も小説家の具体的な収支が分かりとてもオススメです!
以下は本書のポイント等です。
・最低限守らなければならないことがある。それは、「意味が通じる」ということ。あなたが書いたものを読んでくれる人に、あなたが書きたかったものが理解されること。これこそが、文章の最も重要な機能である。もちろん、100%伝わるということはありえない。個人の能力的なこともあるし、また知識や価値観の差もある。それでも、書かれている文章の示すところがまったく伝わらないのでは話にならない。また、読むに耐えないといった悪文も問題がある(これは実は微妙だ。というのも、意図した悪文には、それなりの効果が認められる)。言葉が通じるということは、人間関係においても重要なファクタであって、信頼は、すなわちこのコミュニケーションの確かさから築かれる。作家と読者の間のコミュニケーションも、まずは「通じる」レベルから始まり、しだいにもっと深いもの、もっと多様なもの、というレベルへ至る。読み手は、自分がなにかを感じることができると、それをもたらした作り手に信頼感を抱く。通じない、あるいは通じにくい作品でも、何度か繰り返し読んでもらえれば、いずれは通じるようになるかもしれない。しかし、世の中にはいくらでも作品が存在するわけで、わざわざ通じにくいものを続けて読んでくれる人は少ないだろう。当たり前のことを書いているようだが、このポイントは実にクリティカルである。なにしろ、「小説家になりたくてもなれない」という人の大半は、この部分をクリアしていない。もっと具体的にいえば、自分だけが読める作品を書いている。それでは暗号文を作っているようなものだ。
・デビューをして、そのあと作家専業で一生食べていける、という人が割合として非常に少ないのは事実なのだ。それどころか、編集者たちが話すところでは、10年以上続けられる人が、既にほんの一握りだという。これを聞いたとき、僕は「一握りって、具体的にどれくらい?」と尋ねた。すると「10人に1人くらい」という答えが返ってきた。もちろん、統計データが示されたわけではなく、編集者たちの「感覚」なのだとは思う。だから、「作家であり続けることは難しい」という表現にもなるわけである。
・作家が続かない理由を考えてみよう。一般的なものとしては、ほぼ3つではないかと想像する。まず、デビュー作に全力を注いだために、後続の作品がそれを超えられなかった、という理由である。最初の作品というのは、それ以前の人生の長い時間において蓄積されたものすべてがネタにできるため、情報量が豊富であるし、また作家になりたい時間が長かった場合には、それだけ熟成期間も長くなる。練りに練った作品になった下地がある。よく聞かれるものに、「誰でも1作は小説が書ける」という格言(?)がある。創造をしなくても、自分自身の経験を記録すれば、それが物語になる、という意味もあるだろう。だが、2作目となると、処女作で出し切ったあと、まったくゼロの状態から書かなくてはならない。
・2つ目の理由とは、「読者の慣れ」によるものである。読者も、1作目は初体験の作家なので、そこには必ず何かしらの新しさが発見できる。また、どんなものを書く人なのかわからない、予備知識のない白紙の状況は、まさに「無心」の境地と同じ。この理想的な読書体験をするわけだから、作品が気に入ったときの感動の度合いは増幅される。2作目になると、もう好きなことはわかっている作家になるので、もっと面白いものを、という期待が自然に生まれる。そこそこ同じ程度のものならば、インパクトに欠けるものの、「やはり思った通りの面白さ」と好意的に見てくれるかもしれないが、それでも、「1作目よりは落ちる」という評価を受けるだろう。まして、1作目よりも冴えない作品であれば、がっかりされることは間違いない。その2作目を最初に読んでいれば「面白い!」と叫んだかもしれない読者であっても、である。人間は飽きる動物だ。
・3つ目の理由は、僕自身は感じたことがないもので、これは何人かの人を観察して見出したことだ。特にそれは、「作家になりたい」という強い動機によって突き動かされた結果、運良くデビューした人に見られる傾向である。簡単にいえば、「作家になりたい」一心で努力をしてきた、まさにどの動機が、作家になったことで失われる。つまり、作家になること、自分が書いた作品が出版されることがゴールだったわけで、処女作が本になった時点でゴールインしてしまうため、その後の動機が見つけられなくなる、という症状らしい。これに似たことは、「結婚」でもあるようだ。結婚にあまり憧れていると、結婚したことでゴールインしてしまい、そのあと生き甲斐を失ってしまう。そのゴールだけを思い描いていたため、その先のことがビジョンとして頭になかった、あるいはその思い(もっと正確にいえば計画、予定、方針)に欠けていたということである。作家になるというイメージは、「自著が書店に並ぶ」「他人が自分の作品を読んでくれる」「印税がもらえる」「ファンレターが届く」など、いろいろあるだろう。これらは、最初の一冊が出るとすぐに実現することばかりである。案外、作家志望の人というのは、「書きたいものがたくさんあって仕方がない」というよりは、前記のようなあこがれの未来像を抱いている場合が多い。「とにかく書きたい衝動が抑えられない」というような人間ならば、本が出ようが、ファンレターが来ようが、無関係なはずだ。どんどん次の作品を書き続けるだろう。書いていれば、しばらくは必ず本になる。書いていれば、スランプに襲われることもない。一方、「作品を書きたい」よりも「作家になりたい」という思いが強い人は、作家になったあと、創作の原動力が弱まることは確実である。このタイプの作家志望の人は、「生涯に100作は発表したい」とか、「ベストセラー作家となって1億部は出版したい」とか、そこまでいかなくても、「最低でも20年間は作家活動を続けたい」というようなデビュー後の未来像を持っていない。デビューしたすぐあとのイメージは頭にあっても、作家生活数十年後の未来までは考えていない(これも結婚志望の人が、結婚して数十年後の生活を夢見ないのと同じだ)。無理もない。作家も結婚生活も、未然の立場からは、最初の関門が目前に立ちはだかり、どう見てもそこが最も難しそうだからである。その難関さえ切り抜ければ、あとはどうにだってなるだろう、という楽観が生じるのも人情といえる。しかし、ここで僕が述べたいのは、「人間というのは、自分が望んでいる以上のものには絶対にならない」ということである。「デビューができればそれで充分だ」と考えている人は、デビューして消えていくだろう。「○○賞作家になってやる」と思わない人は、そのとおり○○賞作家にはならない。芸術であれ、ビジネスであれ、この法則は適用できる。なぜなら、人間の行為というのは、自分の価値観と周囲の要求のせめぎ合いに常にさらされ、こうしたときの一つ一つの細かい判断によって道筋が少しずつ決まっていくからだ。本人が望まない方向へは、けっして進まない。「当たるかもしれない」と期待している人にだけ、くじは当たる。「当たる」ことが頭になければ、くじを引く機会さえ見過ごすからである。以上のような3つの理由に気をつけていれば、作家を持続することができるだろう。つまりは、早い段階からそれらを意識しておくことが重要だと思われる。
・まずはその作家がどんな本を出しているのか、という情報を整理したホームページが必要だろう。本の巻末や見返しなどにリストが載っていることはあるけれど、それは同一出版社内のラインナップでしかない。読者は「その作家の本」について知りたいのに、出版社側はそういった情報を提供していなかった。さらに、過去の情報だけではなく、僕は先々の予定についても公表すべきだと考えた。いつどんな本が出るのか、1年くらい先までは予告をした方が読者の期待も高まるだろう。その予定に従って遅れることなく本が発行されることが、ビジネスとして最低限必要な姿勢ではないか、とも思えた。それが、信頼というものだ。こんな当たり前のことが、出版界では実現されていなかったのである(現在もあまり変わっていない)。
・僕は「近況報告」なるものを自分のホームページで公開することにした。デビューして半年後(1996年夏頃)だった。そして、最初からその「日記」を本にして出版するつもりで書いた。当時、ネットで無料で見られるコンテンツをわざわざ印刷するという発想はなかった(あるいは無謀だと認識されていた)けれど、その後、僕はこの形式で、日記を18冊、日記以外でも10冊以上出版した。今では日記h(入力方式の簡素化によって)「ブログ」と呼ばれるようになり、ブログ本もごく一般的な存在となった。そのほか、僕はファンからのメールにはすべてリプライすることにしていた。郵便で届いたファンレターには一切返事を書かないことに決めて、そのかわりにネットで応答をする、と公表したのだ。全リプライは、読者にはかなりの驚異だったと思うし、出版界でも「よくやりますね」と呆れられた。けれど、小説家というビジネスを考えたとき、これは宣伝効果があったと自己評価をしている。この全リプライ作戦は約12年間続けた。2008年末で終了したので、現在は行っていない(理由は、宣伝の必要がなくなったためだ)。1日に届くメールは200通以上になったし、新刊が出れば、その1冊について何千通もの感想メールが届くようになった。
・出版社は自分たちが作った書籍という商品に対して、そのユーザの意見を集める努力を熱心にはしていない。出版社(特に営業)が「お客」だと認識しているのは、「書店」であって、「読者」ではない。そこの意識がまるで間違っている。なにしろ、出版社はその商品をコピーしているだけで、自分たちで創作しているのではない。メーカーではなく商社なのだ。だから、こうなるのも仕方がないかもしれない。
・小説は、家庭用品などの実用品ではない。人間の感性を売り物にした芸術的な商品であり、歴史的に見ても特殊な存在である(この種の商品は数百年の歴史しかない)。便利さや使いやすさ、あるいはそれらの性能向上が売れるベクトルではない。では、何を目指して作るのか?それは大変難しい問題だけれど、あえて一言でいうならば、「新しさ」である。今までにないもの、珍しいもの、そういうものを消費者は無意識に求めている。また、整ったもの、安心して消費できるものは、既に「名作」として膨大な数のストックが揃っていることも念頭に置かねばならない。「さらに生産する理由」がどこにあるのか、を生産者は常に考える必要があるだろう。
・僕が採用した方針はマイナーな路線であり、「隙を突く」作戦だった。大当たりはしないけれど、「今までにないものならば、ある程度のニーズがある」という観測に基づいている。これまでの世の中では、このようなマイナーなものは、大宣伝でもしない限り存在さえ気づいてもらえない。しかし、今はネットがある。発行部数が少なくて、目にする機会がほとんどなくても、ネットの口コミでその「新しさ」なり「珍しさ」なりが必ず伝わる環境になった。ここが昔と全然違う点である。マイナーは、競争相手がいないという状況で、それを求めている消費者を確実に引きつける。むしろ、メジャーな商品よりも安定して売れるだろう。このことは、インターネットが普及する以前からは兆候はあった。ガンダムがそうだし、コミケット(同人誌即売会)がそうである。「そんなマイナーなもの」とマスコミが取り上げようとしないものが、いつの間にか、とんでもない人数を集める一大勢力になった。数でいえば、メジャーなものをとっくに凌駕していたのだ。ネットの普及によって、それらがより明確になり、より確実になり、さらに世界へと輪を広げるようになった。これからも、このような状況が当分は続くだろう。
・ネットの活用に関して、僕が小説の執筆に取り入れたものは多数ある。一例を挙げるなら、ミステリーにおいて「結論をしっかりと書かない」結末や、作品の中にちりばめられた答のない謎である。このようなものは、それまでのミステリーにはほとんど例がなかっただろう。ミステリーとは、読後にすべての謎がすっきり明かされるものだった。そうでないと、解答編のない問題集のように、爽快感は味わえない、気持ちが悪い状態のままになる。だが、ネットがある世の中ではそうではない。気持ちが悪いままの読者たちは、きっとネットにアクセスするはずだ。そこで、作中には書かれていなかった解答を、他の読者が導いていたり、あるいは大勢が議論していたりするのを見ることになる。「ああ、そうなのか」とようやく納得すると同時に、「他の読者」の存在を体感し、大勢の仲間に入れたという安堵を感じる。そもそもこの感覚は、読後に「ほかの人たちは、これを読んでどう感じるのだろう?」という好奇心として昔から存在したものだ。ネットは、そういった欲求m同時に解決する機関(新しい社会)なのである。
・僕は、図書館や古書店の問題には、「何度も読みたくなるような作品」で対抗するしかない、と考えた。作品の随所に、簡単には読み解けないものを織り混ぜておく。その作品ではなく、別の作品でそのヒントを見せる。ネットで、こういった部分が話題になれば、「もう一度読みたい」と思う人が増えるだろう。再読するためには、本を手許に置いておかなければならない。「いつかもう一度読んでみよう」と思わせるような作品とは、初読時にはすっかり消化ができないようなものだ。そういう理屈になる。また、ネタばれについても、簡単にそれができないような機構を盛り込むことで対処ができる。一言で説明できないネタにすれば良い。あるいは、人によって解釈が異なるようなネタにする。他人の意見が自分と違っていれば、もう一度確かめたくなるだろう。さらには、わざと問題点を忍ばせておく、という手法もある。誤解を誘うようなものでも良い。「なんか、おかしい」「これ、間違っているんじゃないか?」と思わせるような部分を故意に入れておくのである。読み手は、これで苛立つことになる。そしてネットでそのことを指摘したり、あるいは「間違っている」と糾弾するような書き方もするだろう。しかし、それが作品を広める。つまり、宣伝効果があるという計算である。
・「小説家は芸術家なおであって、良い作品を書いていればそれで充分。商売をするのは、出版社の役目である」という主張も当然ながらあるだろう。僕だって、そういうものだと最初は少なからず信じていた。しかし、それは間違いである。なぜならば、作家を将来にわたってプロモートするようなビジネス戦略を出版社ではまったく誰一人考えていないのだ(せいぜい、目の前の一冊だけについて、オビやポップのキャッチ文など、効果の極めて小さなものに優秀な頭脳を使っている程度である)。小説家には、マネージャがいない。出版社はしてくれない。だから、自分で自分の作品のマネージメントをしなければならない。それをしないでも売れる人も、もちろん一部にはいる。運が良ければ何かのブームに乗って、自然にマネージメントが機能することもある。しかし、ほとんどの場合は、まったくの放置といって良い。今から小説家になろうという人は、このことを肝に銘じてほしい。あなたの作品は、値段をつけて売られる商品になるのだ。読んでくれた人のうち、有志だけがあなたに寄付をするのではない。これはどう見たって、立派なビジネスなのだ。きれいごとでは済まされないはずなのに出版界には芸術的なきれいごとがまかり通っている。
・ネットでもう一つ重要な要素は、読者の個々の意見が直接作者に伝わるということである。読者との関係というのは、作家という仕事を継続する上で非常に重要だからである。結局のところ、この信頼関係が上手く成り立っていれば、作家として長く活動ができるのではないかと想像する(僕にはまだ十数年の経験しかないので想像する以外にない)
・もし読者の多くがある作品に対して「ここが良かった」と指摘してきたら、同じことはやりにくくなる。「もっとこうしてほしい」と書いてきたら、そちらへ進んではいけない。逆に、読者が「ここがつまらなかった」と批評してきたら、もう一度それに挑戦してみる。そういうあまのじゃくの方針が、より「創作」にふさわしいと僕は考えている。極端にいえば、「たえず読者の期待を裏切ること」が作家の使命なのだと信じる。
・けなされている書評の方が、僕にとっては価値がある。そういうのを読んでいると、頭がにやけてしまうほどだ。明らかに誹謗中傷とと取れる類もあるけれど、それも含めて面白い。「どうして、この人はここまで人の悪口を言いたいのか」と考えると、人間の心理がさまざまと垣間見えてくる。まるで小説のように面白い。意外なものの一例を挙げると、たとえば「こんな主人公は好きになれない」という理由で作品をけなす人がいる。これには、目からうろこが落ちた。何だろう、小説の中に恋人でも見つけようというのだろうか。嫌いな人間が出てくるものは読めない、というのであれば、小説の大半は読めなくなる。主人公だけには感情移入したい、という気持ちはわからないでもない。そういう読者がわりと多いこともわかった。ついでに、ミステリーにおいては、ネタばれを望んでいる人の方が多数だということもわかった。犯人が最後まで誰かわからないような話は読めないという意見も多い。人間というのは本当にバラエティに富んでいる。しかし、そういう批判には耐えられないという純真無垢な作者も、きっといるだろう。僕が天の邪鬼なのであって、そういう素直なタイプが普通かもしれない。ただ、そういう人は小説家には向かないような気がする。たぶん、小説家にはなれないだろう。これをもう少し突き詰めると、自分の作品を人から批判されて腹が立つ人は、もう書くのをやめた方が良い、ということだ。腹が立つこと自体が自信がない証拠だし、笑って聞き流せない思考力、想像力では、創作という行為においては明らかに能力不足だろう。
・人間を観察することが、小説を書くための基本的な下準備である。常日頃から、できるだけ多くの人を観察することを心がける。ドラマや小説の中の登場人物ではない。現実社会で生きている人たちを見て、「リアル」や「ナチュラル」を取り入れること。これらが、創作に不可欠な素材となる。
・人間というのは、自分が弱い部位を、相手に向かったときも攻める傾向がある。自分が言われたら腹が立つ言葉を、相手を攻撃するときに使う。その言葉にダメージを与える効果があると感じているからだ。したがって、悪口を言ったり、いじめたりする人間は、自分が悪口を言われたり、いじめられたりすることを極度におそれている。いじめる方も、いじめられて傷つく方もこの点で共通している。いじめられても気にしない人は、人をいじめない。悪口を言わない人間は、悪口を言われても腹が立たないのである。こういう人間の「傾向」というのも、「リアル」な世界を創り上げる基本になるものであり、すべてが現実の観察から導かれる。
・仕事には〆切がある。いつまでになにを書くのか、そのあとのシリーズの展開はどんなふうにするのか。近いものは3年くらい先まで、すべて予定を決め、遠いものは10年くらいさきまで、だいたいの方針考えておいた方がよい。予定を立ててもその通りに行かない、という人は多いけれど、だからといって、予定を立てなければ、そのまま予定どおり、なにもできないだけである。予定を現実に歩み寄らせて、「予定どおりだ」と満足することに価値があるのではない。たとえ予定どおりにいかなくても、現実を多少でも予定(つまり理想)に近づける努力をすることが、有意義な人生というものだと思う。もし、予定のとおりに現実を築くことができれば、それが「自由」というものではないか。予定を守るということは、第一には自分に対してであり、また、ビジネスであるからには、仕事関係(つまり出版社や読者)に対しても、約束を守ることが結局は自分の利益につながる。驚いたことに、この業界では、作家が〆切を守らないのが日常だ、といった風潮がある。それを許す体質も間違っているし、それに甘える精神も腐敗している。おそらく、「芸術というのは仕事ではない」という主張なのだろうけれど、そういうことを言うのは二流の芸術家に決まっている。もし、あなたが小説家を目指して頑張っているのならば、〆切を守る誠実な作家になってほしい。それには、まず自分で立てた予定を守ること。その習慣をつけることが大事だ。1度でも破れば、10回守り続けてきたことが無になる。信頼というのは、築くに難く、崩れるに易いもの。1回くらいは、と考えているとしたら、それは信頼の意味がわかっていない不誠実な人間である。どんな仕事をしても中途半端になるだろう。根本的に考えを改めなければ、今以上の状況は望めない。
・僕は常々、フィクションを読む人よりも、ノンフィクションを読む人の方が多いと感じていた。僕の周囲にいる人間はほとんど小説を読まないからだ。現に、書店に行っても、雑誌やビジネス書の前に立っている客が圧倒的に多い。小説のコーナーは閑散としている。ところが、僕の本は小説の方が圧倒的に売れる。エッセイを出しても10分の1くらいしか部数が出ない。小説家が書くエッセイは面白くないものばかりだという風潮があるのかもしれないけれど、出版社もとにかく小説を出したがる。このギャップが不思議だなと感じていた。その理由は、一人が読む冊数の違いにあったのだ。ノンフィクションを読む人は1ヶ月に2冊くらい読むかもしれない。それに比べてフィクションを読む人は1日1冊は読む。前者の人口が10倍多くても、本は後者の方が売れる道理だ(この数字は説明のための仮のもので実際のデータではない)。
・これだけ年心なマニアに支えられている小説であるけれど問題もある。この頃では人気作家の新刊が図書館で読める。ベストセラー作家の本になると、図書館は何冊も同時に仕入れる。また古書の流通が当たり前になったからよく本を読む人ほど、節約のために古書を買うことになり、出版社や作家の利益が損なわれている。その構図は、自分たちの望む環境を自分たちで崩すものだ。傍から見ていても、良い状況とはけっしていえない。こういった流通の問題が将来どうなっていくのかといえば簡単である。小説は音楽のようにネット配信になる。近い将来のことだろう。そうなると極端な話、出版社も印刷会社も取次も書店も必要ではなくなる。古書店も図書館も成り立たない時代がすぐに来る。安泰なのは作家と読者だけだ。作家から読者へコンテンツが直接配信されるといったことも可能であり、事実増えるだろうけれど、もちろんなんらかのマネージメントをする機構が現れるはずである。利潤を生むところには、人が集まるからだ。
・作家としてはどうすれば良いだろうか?簡単だ。たくさん売れること、ベストセラーになることをねらわず、地道に作品を発表する。これだけである。10万部売れる本を作ることは非常に難しい。しかし1万部売れる本を10冊出すことなら、それよりは容易だ。5000部売れる作品を20作書くことなら、さらにずっとやりやすい。結局、大きなものを狙わず、まじめに自分の仕事をすれば良い。そうしていれば、なにかのチャンスが巡ってくることもあるだろう。そして、作品の数が多いほど、そのチャンスは増えるのである。
・僕の場合、たとえば「スカイ・クロラ」の映画化がそうだった。売れないシリーズだったのに、押井守監督のアニメ作品になったおかげで、シリーズで100万部を突破した。本の印税のほかにも、さまざまな商品の原材料として収入につながる。映画化のおかげで1億円以上いただいた計算になるだろう。新たに書いたわけではない。なにも仕事をしていないのに収入になる、というのは著作権の素晴らしいところだ。「創作」の価値は社会でこれほど認められているのである。もちろん、狙ってできることではないが、宝くじよりははるかに確率は高い。確実なのは、こういったチャンスも、作品を書かなければ訪れない、ということだ。
・たくさん書こうにも、一つの出版社ではそんなに続けざまに本を出してくれないかもしれない。そんなときは、数ある出版社を広く利用し、他社とも仕事をしよう。お世話になっている出版社を裏切らないように一社だけとしか仕事をしないというのは危険である。他社で本を出すメリットは印税が同じなのだからほとんどない、というようなことを書いたけれど、もし一社としか仕事関係を結んでいなければ、作家の立場は非常に弱い。なにかトラブルがあったとき(たとえば編集者とケンカになったりした場合)に、別の出版社と仕事関係がある場合とない場合では、かなり違ってくる。作家にとっては、「どうしてもダメなら他社で書きます」という選択肢だけが唯一の交渉の切り札なのだ。
・娯楽のコンテンツを生産する仕事の中で、小説家は最も個人的な職種の一つといえる。音楽のように仲間を必要としないし、マンガのようにアシスタントもいらない。同じ文章でも、ノンフィクションのように文献調査や取材をする必要も少ない。元手はまったく関わらないし、いつでも書ける。特に日本語というのは日本人にとっては書くことが容易な言語だ。英語が母国語の人が英文を書くことに比べて格段に簡単なのである(英文を書くプロになるためには、並はずれた知識と才能が必要だ)。話し言葉と書き言葉が、現代の日本語はほとんど一致していることもあるし、国民のほとんどが読み書きできる、という文化も条件としてプラスである。絵を描くこと、曲を作ること、あるいは詩を書くこと、などに比べても、小説は敷居が低い。道具の使い方を覚える必要もないし、なによりも、非常に自由でルールがない。何をどう書いても良い。そういうものを小説というのである。
・僕がここでいいたいことは、作家を目指すとしたら、なんらかの「売りもの」が不可欠であるというこおだ。作家志望の人は、自分の「ウリ」が何かをしっかりと自覚していなければならない。それが即答できないようではデビューはおぼつかないだろう。もし、「ウリ」がないのなら、今からすぐにそれを作るべきである。
・プロの小説家になれば自分の作品が評価されることになる。実は最重要の評価指標とは、「どれだけ売れたか」であるけれど、個人による批評が文章で示されるケースも無数に存在している。たとえば、最近はネット書店に素人の書評や採点が表示されている。作家も読者も、人によっては気になる数値かもしれないが、売れる本と評価値はむしろ反比例していることをご存じだろうか。僕は自著に対してデータを集計したことがある。すると、売れている本ほど、読者の採点が低くなる傾向があることに気づいた。理屈は簡単である。採点が低いからよく売れるのではなく、よく売れるほど、その作品に合わない人へも本が行き渡るから、低い評価を受ける結果になる。逆に、ものすごくマイナーで部数の少ない本は、コアなファンだけが買うので評価が高い。そもそも、ファンというのは、「自分にだけわかる価値」を無意識に欲しがるものであり、「珍味」のように特別性を高く評価する傾向にある。だが、珍味に美味いものなし、というではないか。誰にとっても美味いものならば、もっと広く普及するから珍味にはならないのだ。ネット書店で、100万部突破のベストセラーに対する書評を読んでみると良い。「どうしてこんなものがベストセラーになるのか」と大勢が怒っているのが眺められ。アイドルだって、人気が出るほど悪口をいう人が増えるだろう。売れるほど酷評を受ける道理がここにある。このような「読者の声」が直接聞こえることは、メーカーである作家にとっては、とても有用な環境である。どんな消費者がいるのか、という調査が簡単にできるからだ。相手が見えることは何事につけても有利である。しかし、相手の意見をそのまま作品に取り入れる必要はない。ここは注意が必要だ。なぜなら、読者というのは素人であり、創作者ではない。意見というのは千差万別さまざまであって、すべてに対応していたらキリがないし、多数の意見に応じれば、どっちつかずの製品を作らされてしまうだろう。
・小説から教訓を見出そうとしたり、小説の中で新たな知識を得ようとする人もたまにいるが、これは本来の小説の機能ではない。そういったものは、小説以外から得た方が効率が高く、なによりも「正しい」ものが手に入りやすい。小説に書かれているのは、たとえば、登場人物が話したことであり、考えたことであり、認識しているだけのことなのである。登場人物が誤解をしている、間違っている、勘違いしている場合もあるから、真偽はまったくわからない。作者にも責任はない。小説はなにを書いても、わざと「嘘」を書いても責められないのだ。だから、そんな小説から、教訓や知識を学ぼうとするのは、(副次的なお特感はあるけれど)できればやめた方が良い、と僕は思う。学んだ気がする、得をした気がする、という錯覚に一瞬微笑む程度が適切だろう。本を閉じれば、酔いは急速にさめる。
・僕は分厚い小説のブームのときに、読者の多くの反応から「もっと本を薄くしなければ」と感じたので、自分の新シリーズでは、シンプル、ショート、スパイシィという3Sを目指して書き始めた。編集者からは「時代に逆行しているのでは」と言われたけれど、それは編集者が「遅れていた」だけのことである。ネットのおかげで、今では編集者よりも作家の方が読者に近い。その分、プログレッシブだ。否、それどころか、読者だって作家に比べれば遅れている。作家は常に時代をリードしなければならない。ニーズに応えるのではなく、ニーズを新たに作る、それが創作である。
・人は、結局は「人に感動する」ものである。それは、自然の中にあって、最も自分自身に近い存在だkらだ。人間の行為、その行為の結果がもたらしたものを通して、その人間の存在を感じる。はるか昔の人よりも、同時代に生きている人の方が、存在を感じやすい、というのも「近さ」のためだ。作品を通してその人の存在を感じ、それを感じた自分を対面に置き、反響させて感動を増幅する。芸術の起源はここにあるといっても良いし、僕が「小説には将来展望がある」と考える理由もここにある。そう断言できるのは、一人で創れるものだから、人件費がかからない、比較的時間も労力も少なく、効率が高い、というビジネス上の有利さ以前に、このジャンルの基礎部分に、非常に固い、崩れることのない構造が成立しているからである。
・僕がデビューした頃、講談社の担当者だったK氏は小説についていろいろなことを教えてくれた。その中で一番印象的だったのは、「決まりはありません」というものだった。「全部、作者が自由に決めて下さい」と言われた。文章に関するあらゆる約束ごとは、あくまでも平均的なものであって、厳守する必要はない、という意味だ。ときには、文法だって無視して良い。漢字を普通とは違う読み方にしても良い。なにをどうしようが、自分のルールさえしっかりとしていれば問題はない、ということだった。「そうか、それが小説というものか」と僕は納得した。簡単にいえば、やりたい放題なのだ。
・文章が上手くなるためには、とにかく文章を書くこと。そして、自分の書いた文章を何度も読み直してシェイプアップすることである。書いたすぐあとに直すのではなく、せめて1日、できれば数日置く。これは料理だったら「寝かせる」というところだが、文章はただ寝かせてコクが生まれるわけではない。ようするに、書いた本人が忘れるだけのこと。忘れることが非常に重要なのだ。すなわち、書いた人間ではない別人になって読み、より客観的に文章を捉えることになる。ときには、自分の書いた文章がわかりにくかったり、もっと酷いときは意味不明だったりするだろう。誤解を招くような表現だったりすることも、矛盾していることも、くどかったりすることも、発見しやすくなる。
・小説全般にいることかどうかわからないが、ミステリーなどでは、「ネタ」になる発想がいくつか必要で、それをあらかじめ準備しておく書き方が一般的なようである。僕はそうではないが、聞いた話ではだいたいそうらしい。ネタ帳のようなものを作り、ときどき思いついたアイデアを書き留めておく。それを執筆のときに使っていく、という手法である。これはパーツをあらかじめ用意し、それを利用してものを作る、というやり方だ。僕の場合も、それに近いことを試した経験はある。しかし、上手くいかなかった。ネタがあらかじめ存在すると、書いているときに、それらに拘束される。「これを使わなければならない」という観念に囚われてしまうのだ。使いたいネタがあったとしても、もっと緩やかに考え、それを必ず全部使おうと思わない方が良い。ネタに関しては、「もったいない」なんて気にしないことだ。無駄を出し、「贅沢」であるべきだと思う。書いているときには、その作品世界の空間が広がり、時間が流れている。その中における「自然さ」を尊重すべきである。その自然さが、読者に与える「リアルさ」になるだろう。ネタというのは、トリックばかりではない。たとえば、こんなキャラクタ、こんな言い回し、こんな比喩、こんな会話、などなど、ほんのちょっとしたことまで、小さなパーツとして小説の中にちりばめられている。執筆以外の時間にそれを思いついたら、すぐメモをしておかないと、いざ書くときに思い出せない、という不安を持つ人が多い。おそらく、忘れてしまうということが、ある種の恐怖なのだろう。しかし、僕はそうは考えていない。忘れるものは、忘れるだけの理由がある。自分では素晴らしいと感じても、忘れてしまうことがあって、すばらしさだけが印象として残るから、思い出せないことが腹立たしい。「もったいない」とまたも感じてしまう。だがここでも「創作は贅沢であるべき」だ。もったいないものをどれだけ捨てられるか、良いネタを大盤振る舞いで浪費できるか、がむしろ作品のレベルを高める。使いたいネタがしっくりこないと少しでも感じれば、潔く捨てよう。同様に、忘れてしまうようなものは、そもそも印象が薄い証拠である。忘れたままにする方が得策だ。こんな理由から、僕はメモを一切取らない。ネタ帳はない。事前に作品の構想を考えることはもちろんある。細かい表現についても、シーンについても、あれこれ思い浮かべることは頻繁にある。だが、それをその場でメモとしてアウトプットしてしまうと、発想はそこで終わってしまう。頭の中に入れたままにしておく方が育つ。もっと形を変えて、もっと的確なタイミングで思い浮かぶかもしれない。無理に「これを使おう」と自分に課さないことである。たとえば、会話に表れるしびれるようなフレーズとは、これをしゃべろうと待ちかまえていたものではない。流れの中でふと思いついて自然に出るから輝くのだ。執筆においても、あらかじめ考えておいたものをいつ使おうか、などと考えていては、自然な会話にはならないだろう。
・会話を活き活きと書くためには、そこに登場している人物たちそれぞれになりきること、これに尽きる。どんな履歴を持った人物なのか、今はどんな状況なのか、相手をどう思っているのか、何を考えて話しているのか、といったことを思い描くことは基本であるが、さらに大切なのは「流れ」だろう。現実の会話も、「流れ」に大いに従っている。くどくどと説明をするようなことはない。親しい間柄になればなるほど、どんどん省略される。それでも通じるからだ。小説では、読者に通じなければならないので、多少の「丁寧さ」が必要な例外があるものの、それでもとにかく「切れるだけ切って」ちょうど良いくらいだと僕は思う。それぞれの人物になりきると、当然ながら、会話が途切れたり、別の話題に急に飛んだり、口にしたもののすぐに後悔したり、あるときは嘘をついたり、いい間違えたりする。人物になりきらず、客観的な(たとえば監督や脚本家の)立場で書くと、そういったリアルさが出にくい。
・下手な会話シーンというのは、作者が一人で問答をしている結果でとても別の個人どうしが言葉を交わしているとは感じられない。まるで片方が悩み相談のカウンセラーか、インタビュアーか、太鼓持ちのようだ。実際の会話というのは、一つの話題のときも、それぞれは別々のことを考えている。人間は常に勝手に考えるという特性を持っているのだ。それを素直に表現するだけで、自然にキャラクターの個性がにじみ出る。読み手に「生きている」と感じさせることができるだろう。もちろん、会話だけではない。考えているからこそ、それが行動や仕草に出る。関係のないことを突然したり、勘違いをしたり、忘れたり、失敗したりする。普通の人が当然するこれらの無関係で無駄な行為が、生きている証拠でもある。ストーリーを説明するために動いている役者ではあるけれど、そう見せないことが小説家の技量といえるだろう。
・書き始めを印象的にしようと思い悩むとちっとも始められないので、それはまたあとで修正するとして、とにかく書き進めよう。ここがやや問題だなとか、ここが上手く書けないと感じたら、そこを飛ばして先へ進む。ワープロなのだから、いくらでもあとから補填ができる。気楽に文字数を増やそう。難しいのは終わり方である。小説のラストは、かなり難しいと思う。一番難しいのは最初にタイトルを決めることで、その次に難しいのが、この最後の一文だろう。こだわらなければ、別に気にしなくても良い。終わり方に決まりがあるわけではない。句点で終わらせなくても良い。なんだって「あり」だ。
・書いている途中では、自分が退屈しないことが大事で、退屈しそうになったら、面白いことを考えて、それを書く。こうしておけば、きっと読者も眠くならずに読んでくれるにちがいない。たとえば、どうしようもなく退屈だなと感じたら、「そのとき、背後から迫りくるものがあった」などと書いてみる。書いてから、「はて、なにが迫りくるのだろう?」と考えれば良い。まさに成り行きである。面白いストーリーというのは、このような流れの中で生み出されるもの。だからこそ臨場感がある。書いている本人が臨場感を抱く必要があるだろう。ただ、同時に、小説家は常に「読者どう読むのか」という視点を持たなければならない。舞台を作る人間は、客席の視点を常に意識している。文章に落とす行為が、その視点への伝達なのだ。
・一年中執筆をしているわけではない。たとえば僕の場合、1作を書いている期間は、長くても2、3週間だ(1日にせいぜい2時間程度しか書けない)。この執筆している期間には、僕は小説を読まないし、映画も観ない。なにもしない時間が必要だ、と感じるためだが、別にあれこれ考えているわけではない。ただ、ふと思いつくことはある。一番良いのは、散歩をしたり、ドライブをしたり、手を動かしてなにかを作ったり、といった比較的抑揚のない平坦な時間だと思われる。本を読む人は、本当に暇を惜しんで読書をする。どこでも読めるように、いつも本を持っている。文字通り「暇を潰す」行為であるけれど、創作期間中はそうではなく、できる限り「暇を潰さない」方が良いだろう。頭は、外から刺激があれば、それについてしか考えない。リラックスしていれば、ちゃんと自分から発想するものである。
・僕は執筆期間中でもパソコンから離れると、今どんな小説を書いているかを忘れてしまう。思い出すのに20秒くらいかかる。だから、作品について考えるということは見かけ上はない。むしろそれ以外のことを考える。ところが、執筆作業に戻ると、全然関係のなかった発想が、次々と結びつく。これに近いのが夢を見る行為だろう。夢は、寝る前に「これについて考えよう」とテーマを決めているわけではない。しかし、起きたときに夢を覚えていて、「ああ、これは使えるな」ということが多々ある。僕は、夢をとても丁寧に見るようにしている。起きるときも、忘れないように慎重にゆっくりと目を開ける。夢から見た発想は実に多い。起きているときにも、夢見心地になれれば素敵だ。ただし、酔っていてはダメである。頭はできるだけ冴えていないと。
・一作の執筆を終えると、他の芸術に触れたくなる。アウトプットしたため、飢えるのだろう。他者の目を通すなと書いたけれど、優れた才能に出会うことは、美味しいものを食べるのと同じで、人間の基本的な欲望といえる。ただ、お腹がいっぱいになると、自分で料理を作る気がしなくなる。ものを作るときには、少しハングリーな方がコンディションとしては良いという意味だ。こういった自分のコンディションをコントロールできるようになれば、プロとして非常に有利である。
・これは一般的ではないかもしれないが、僕が一番時間をかけて考えるのは、タイトルだ。作品のタイトルを考え始めてから決定するまでには、3ヶ月から半年くらいかかる。タイトルさえ決まれば、もう半分以上は書いたも同然と思えるほどだ。よく「どんなふうにしてタイトルを決めるのか」と問われる。しかし、「これです」というルールはない。とにかくひたすら「考える」。そして、納得がいくまで決めないことにしている。僕は、タイトルが決まらない状態で小説を書き始めることはない。あとで決めれば良い、というふうには考えない。本文ができてしまったあとに適切なタイトルをつけるなんて、それは無理な話だ。タイトルを決めれば、それに相応しい小説がかける。その反対はきわめて困難だ、と少なくとも僕は思う。
良かった本まとめ(2016年上半期)
<今日の独り言>
Twitterをご覧ください!フォローをよろしくお願いします。

















 「世界で活躍する人が大切にしている小さな心がけ」の購入はコチラ
「世界で活躍する人が大切にしている小さな心がけ」の購入はコチラ 


















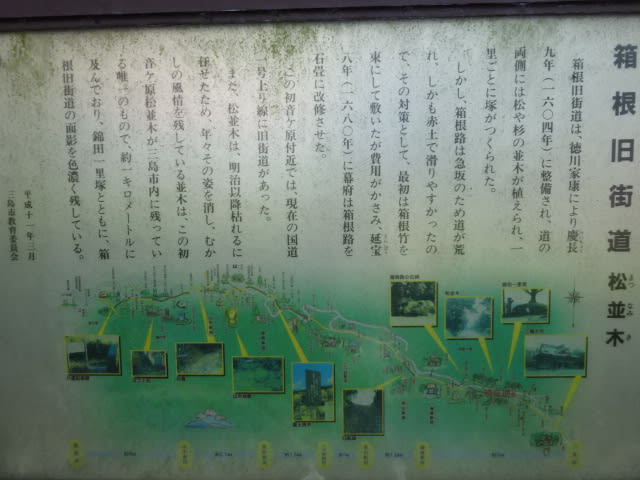





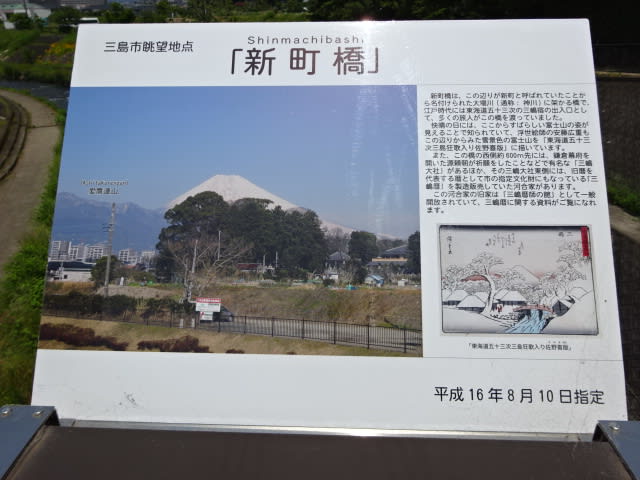


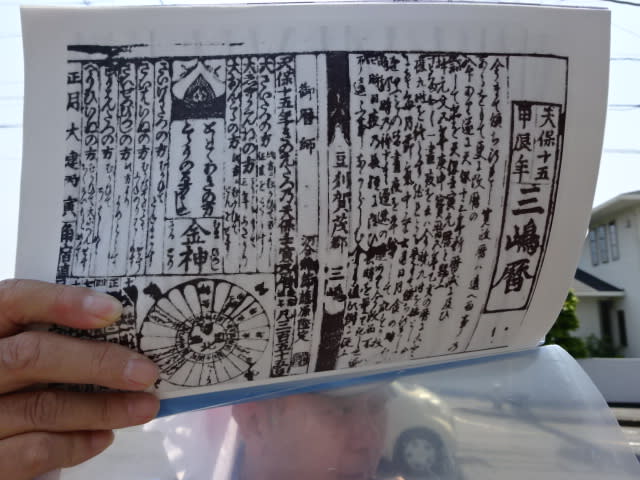


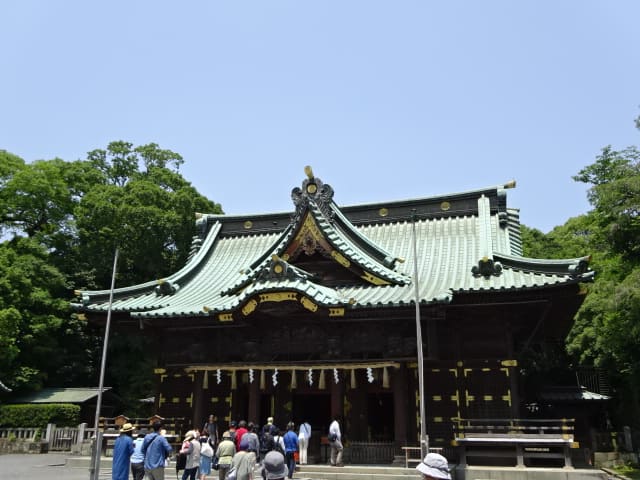









 「小説家という職業」の購入はコチラ
「小説家という職業」の購入はコチラ