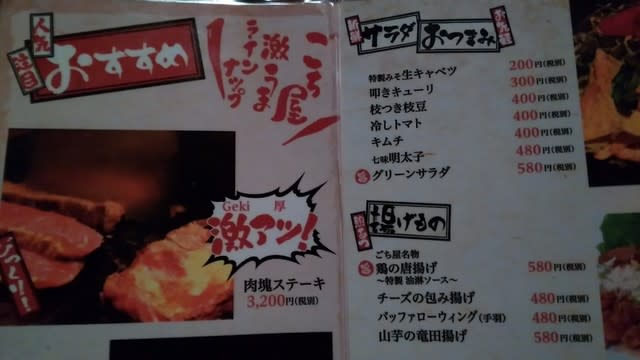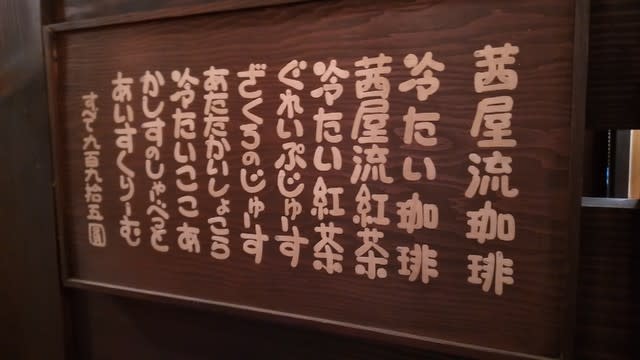「トランプ自伝-不動産王にビジネスを学ぶ」の購入はコチラ
「トランプ自伝-不動産王にビジネスを学ぶ」の購入はコチラ
「トランプ自伝-不動産王にビジネスを学ぶ」という本は、現在のアメリカ大統領であるドナルド・トランプ氏が41歳の時に書いた自伝で、当時既に資産30億ドルあり、マンハッタンに68階建ての超豪華ビル「トランプ・タワー」を建て、4つのカジノを所有して、しかも本書はベストセラーとなったようです♪
本書では、昼食も食べずに一所懸命不動産業で働くその具体的な一週間の電話や取引等の内容、取引を成功させるための11のコツ、生い立ちや家族、父から学んだこと、トランプ・タワー建設、カジノ建設、USFLのアメフトチームオーナーとしての仕事、市に代わってのスケートリンク建設などについて書かれていて、その活躍ぶりがよく分かり、またその戦略や苦心さがとても勉強になると思います♪
また、訳者あとがきでは、妻イヴァナのコメントとして「大統領選挙へ出馬することも絶対にないとは言い切れません」と書かれているのは秀逸ですね♪
本書にも書かれていますが、大きく物事を考えることは大切ですね。
ただ、逆にソ連での取引についても書かれていて、大丈夫かな?とも思いました^_^;)
それから当時のニューヨークは行政がうまくいっておらず、大変な街だったということもよく分かり、逆にそれを活かして活躍しているのは素晴らしいと思います♪
「トランプ自伝-不動産王にビジネスを学ぶ」という本は、真面目に事業を成功させるコツや粘り強さ、考え方など勉強になり、またトランプ大統領のこれからの政策を考える上でも参考になり、とてもオススメです!
以下はこの本のポイント等です
・私は金のために取引をするわけではない。金ならもう十分持っている。一生かかっても使いきれないほどある。私は取引そのものに魅力を感じる。キャンバスの上に美しい絵をかいたり、素晴らしい詩を作ったりする人がいるが、私にとっては取引が芸術だ。私は取引をするのが好きだ。それも大きければ大きいほどいい。私はそれにスリルと喜びを感じる。大方の人は私のビジネスのやり方を見て驚く。私は気楽に仕事をする。アタッシュケースは持ち歩かないし、会合の予定もあまりぎっしり入れないようにしている。可能性を多く残しておくのが私のやり方だ。組織化しすぎると、想像力や起業家精神を発揮する余地がなくなる。私は毎日オフィスに来て、今日はどんなことがあるだろうと期待するのが好きだ。私の生活には一週間の決まったパターンはない。朝は早く、6時頃に起きることが多い。それから1時間ほどかけて朝刊を読む。オフィスには9時頃行き、電話をかけたり受けたりし始める。その回数が50回以下という日は珍しく、大抵は百回を超える。電話の合間には、少なくとも12~3人の人に会う。前からの約束ではなくその場で決めることが多く、ほとんどは15分以内に終わる。昼食のために休憩することはまずない。6時半にはオフィスを出るが、夜中の12時まで自宅から電話をかけることが多い。週末の間はずっと家から電話する。仕事はこんな具合に切れ目なく続く。私はこのやり方が気に入っている。過去の経験から学ぶように心がけはするが、将来の計画をたてる際はもっぱら現在に焦点を合わせる。そこに仕事の楽しみがある。楽しくなければ、仕事などする価値はない。
・私の秘書役で、生活上の細々としたことをとりしきってくれるノーマ・フォーダラーに、昼食を持って来てくれるよう頼む。昼食といっても、トマトジュース一缶だけだ。食事をしに外に行くことはめったにない。時間がもったいないというのが主な理由だ。
・正直言って、私はパーティはあまり好きではない。世間話というやつが苦手だからだ。しかし残念ながらこれも仕事のうちなので、心ならずもあちこちのパーティに顔を出すことになる。だがその場合も、なるべく早く引き上げることにしている。幸いなことに、なかには心から楽しめるパーティもある。何ヶ月も先のパーティの招待にはつい応じてしまうことが多い。あまり先なので、その日は永久に来ないような気がするのだ。だがいよいよその日が近づいてくると、一体なぜ承諾したのだろうと、自分自身に腹が立つ。でも時すでに遅しなのだ。
・昨年私はヒルトン社から二つ目のカジノを買い取ってトランプ・キャッスルと改名したが、その時妻のイヴァナにここの経営を任せることにした。彼女は生まれつき管理能力に長けており、どんなことでも完璧にこなしてしまう。イヴァナは一人っ子としてチェコスロヴァキアで育った。電気技師の父親は優秀なスポーツマンで、イヴァナがごく幼い頃からスキーを教えた。6歳になる頃には、彼女はあちこちの試合でメダルをとるようになっており、1972年の札幌冬季オリンピックには、チェコ代表スキー・チームの補欠として参加した。一年後、プラハのカレル大学を卒業してからモントリオールへ行き、ほどなくカナダのトップ・モデルになった。私たちは1976年8月のモントリオール・オリンピック大会で知り合った。私はそれまで数多くの女性とデートしていたが、そのだれとも本気でつきあったことはなかった。だがイヴァナはいい加減な気持ちでつきあえる女性ではなかった。それから8ヶ月後の1974年4月に私たちは結婚した。結婚後すぐに私は当時手がけていたプロジェクトのインテリア・デザインをイヴァナに任せた。彼女は見事にそれをやってのけた。イヴァナほど能率的に物事をこなす人はあまりいないだろう。彼女は三人の子供を育てるかたわら、私たちの三軒の家をとりしきっている。トランプ・タワーの中のアパートとマール=ア=ラーゴ、そしてコネチカット州グリニッジにある家だ。その他に現在は約4千人の従業員がいるトランプ・キャッスルの経営も手がけている。キャッスルは順調に業績をあげているが、まだナンバー・ワンではない。私はそのことを厳しく彼女に指摘する。君が運営しているのは町で最大のカジノなのだか、当然最高の収益を上げていいはずだ、と言ってやるのだ。イヴァナは私に劣らず負けず嫌いなので、今の状態でそれを達成するのは無理だと主張する。もっとスイートをたくさんつくる必要があるというのだ。スイートの建設には4千万ドルかあるのだが、彼女はそんなことにはとんちゃくしない。とにかくスイートが足りないことが商売に響いており、そのためにナンバー・ワンになることが難しいといい張る。彼女に任せておけば何事も間違いないことは確かだ。
・ソ連を相手にビジネスをしているある著名な実業家から電話がある。モスクワで私が手がけようと考えている建設プロジェクトについての情報を教えてくれるためだ。私がこのプロジェクトに興味を持ったのは、エステー・ローダーの息子である有能な実業家レナード・ローダー主催の昼食会で、ソ連大使ユーリ・ドゥビーニンの隣に座ったことがきっかけだった。話しているうちに、ドゥビーニンの娘がトランプ・タワーについて読んだことがあり、それについてよく知っていることがわかった。そんなことから話が発展し、私がソ連政府と共同で、クレムリンから道路を隔てたところに大きな豪華ホテルを建てるという案が生まれた。私はソ連政府の招きで7月にモスクワに行くことになっている。
・2年前友人が別の取引のことで電話してきたことがある。金のある連中を何人か説得して、ある小さな石油会社を買収しようとしていたのだ。「ドニー、5千万ドルほど出してほしいんだ。絶対に損はさせない。投資した金は数ヶ月で2倍、あるいは3倍になる」と彼は言った。詳細を聞くとなかなかいい話のように思える。私はすっかり乗り気になり、書類の作成なども始めた。ところがある朝起きてみると、何か妙な気がする。そこで友人に電話して言った。「この話はどうもしっくりこないんだ。石油は地下に埋もれてて目に見えないからな。あるいはこの件には創造的なものが何もないからかもしれない。どっちにしてもやっぱりやめとこうと思う」友人は言った。「いいよ、ドニー、好きにしてくれ。だがせっかくのチャンスをふいにすることになるんだぞ」もちろん、その後どうなったかはすでに過去の話だ。数ヶ月後に石油価格は暴落し、友人のグループが買収した会社は破産した。そして投資者たちは出した金をすべて失ったのだ。この経験から、私はいくつかのことを学んだ。第一に書類の上でどんなに良さそうに見える話でも、自分自身のカンに頼って判断すること。第二に総じて自分のよく知っている分野でビジネスをする方がうまくいくこと。そして第三は時には投資を思いとどまることも利益につながるということだ。その取引に加わらなかったおかげで私は5千万ドルと友情を失わずにすんだ。
・画家として成功し、名が売れている友人が電話をかけてきて、美術展のオープニングに招待してくれる。私はこの友人が大好きだ。というのも、彼は私の知っている何人かの芸術家と違って、全く見栄を張らないからだ。2、3ヶ月前、彼がアトリエに呼んでくれたことがある。そこで話していると、彼が唐突に言った。「昼飯前に、僕が2万5千ドル稼ぐのを見たいかい?」「見たいとも」何のことか訳がわからないまま、私は答えた。彼は絵の具の入った大きなバケツを持ち上げ、床の上に広げたキャンバスの上に、絵の具を少しかけた。それから別の色の絵の具が入ったバケツをとって、それもキャンバスにはねかけた。これを4回繰り返したが、その間2分とかからなかっただろう。終わると私の方を向いて言った。「これでいい。たった今2万5千ドル稼いだんだ。さあ、昼飯に行こう」彼はにやにやしていたが、本気でもあった。彼が言いたかったのはつまり、美術品収集家の多くは、彼が2分間で仕上げた絵と、本当に大事に思っている絵との違いが分からないだろうということだ。収集家たちは、彼の名前を買うことにしか興味がないのだ。私は前から現代美術の大半はいんちきだと思っている。名をなしている画家の多くは、芸術家としての才能よりむしろセールスと宣伝の才に長けているのだ。あの日の午後の友人の作品について、私が知っていることを収集家たちが知ったらどういうことになるのだろう、と時々考える。画壇というのはまことに奇妙な世界だから、そのことがわかると彼の絵はますます価値が上がるかもしれない。もっとも友人ははたしてそうなるかどうかあえて確かめてみようとは思わないだろうが。
・私の取引のやり方は単純明快だ。ねらいを高く定め、求めるものを手に入れるまで、押して押して押しまくる。時には最初に狙ったものより小さな獲物で我慢することもあるが、大抵はそれでもやはりほしいものは手に入れる。取引をうまく行う能力は、生まれつきのものだと思う。いわゆる天賦の才だ。別に自慢して言っているわけではない。これは知能の高さとは関係ない。多少の知力は要するが、一番大事なのはカンだ。知能指数170、成績はオールAというウォートン・スクール一の秀才でも、これがなければ起業家として成功することはできない。なかにはカンをもっていることに気づかない人もいる。自分の潜在能力を知ろうとする男気がなかったり、チャンスに恵まれなかったりするためだ。ジャック・ニクラウスよりもゴルフの才が、あるいはクリス・エバートやマルチア・ナブラチロワよりもテニスの才がある人も世間にはいるはずだ。しかし一度もクラブやラケットを振ることがないので一生自分の才能に気づかない。スター選手の活躍ぶりをテレビで見るだけで終わってしまう。
・私は物事を大きく考えるのが好きだ。子供の頃からそうしてきた。どうせ何か考えるなら、大きく考えたほうがいい。私にとってはごく単純な理屈だ。大抵の人は控えめに考える。成功すること、決定を下すこと、勝つことを忘れるからだ。これは私のような人間には、まことに都合がいい。
・大きく考えるためのカギは、あることに没頭することだ。抑制のきく神経症と言ってもよい。これは起業家として成功した人によく見られる特質だ。彼らは何かにつかれたように、何かにかりたてられるようにある目的に向かって進み、時には異常とも思えるほどの執念を燃やす。そしてそのエネルギーをすべて仕事に注ぎ込む。普通の人は神経症で動きがとれなくなるが、彼らはそこから活力を得るのだ。このような特質がより幸せな、あるいはより質の高い人生をもたらすとは限らない。だが自分がめざすものを手に入れるうえでは、これは大いに役に立つ。ニューヨークの不動産業界という百戦錬磨のつわものを相手にする世界では特にそれがいえる。こうした手強い連中を向こうにまわし、彼らを打ち負かすことに私はたまらない魅力を感じる。
・私はギャンブルが好きだと思われている。だが私はばくちを打ったことは一度もない。私にとってばくち打ちとは、スロット・マシンをする人間にすぎない。私はスロット・マシンを所有するほうを好む。賭博場の経営は儲かる商売なのだ。私は積極果敢な考え方をすると人は言う。だが実際には私は消極的な考え方を良しとする。商売ではきわめて慎重なほうなのだ。常に最悪を予想して取引にのぞむ。最悪の事態に対処する方法を考えておけば、つまり最悪を切り抜けることができれば、何があっても大丈夫だ。うまくいく場合は、放っておいてもうまくういく。肝心なのはあまり欲の皮をつっぱらせないことだ。毎回ホームランを狙うと、三振する確率も高くなる。私はあまり高いリスクを犯さないよう心がけている。たとえそのために三塁打か二塁打、あるいはごくまに短打に終わってしまうことがあってもだ。
・私は融通性をもつことで、リスクを少なくする。一つの取引やアプローチにあまり固執せず、いくつかの取引を可能性として検討する。最初は有望に見えても、大抵の取引には何か不都合な点が出てくるからだ。さらに一つの取引にのぞむ場合、これを成功させるための計画を少なくとも5つ6つは用意する。どんなによく練った計画でも、途中で何が起こるかわからないからだ。
・市場に対するカンの働く人と働かない人がいる。たとえばスティーブン・スピルバーグはこのカンをもっている。クライスラーのリー・アイアコッカもそうだ。ジュディス・クアンツも彼女なりのカンをもっている。ウディ・アレンも自分が選んだ観客に対するカンをもつ。彼とは対極に位置するシルベスター・スタローンも同じだ。スタローンを批判する人もいるが、彼の実績は認めるべきだ。41歳という若さで、ロッキーとランボーという映画史上に残る偉大な人物像を二つも作り上げたのだから。彼はいわば磨いていないダイヤモンド、つまりカンがすべてという天才でもある。彼は観客が何を望んでいるかを心得ており、それを提供する。私にもそのようなカンがあると自分では思っている。だから複雑な計算をするアナリストはあまり雇わない。最新技術によるマーケット・リサーチも信用しない。私は自分で調査し、自分で結論を出す。何かを決める前には、必ずいろいろな人の意見を聞くことにしている。私にとってこれはいわば反射的な反応のようなものだ。土地を買おうと思う時には、その近くに住んでいる人々に学校、治安、商店のことなどを聞く。知らない町へ行ってタクシーに乗ると、必ず運転手に町のことを尋ねる。根ほり葉ほり聞いているうちに、何かがつかめてくる。そのときに決断を下すのだ。
・私は有名なコンサルティング会社より自己流の調査によって、はるかに多くのことを学んできた。コンサルティング会社に依頼するとボストンからコンサルタントの一団がやってきてニューヨークのホテルの一室い陣取る。そして長々と調査を行って莫大な料金を請求する。しかし結局何の結論も出さない上、調査にひどく時間がかかるので、有利な取引を逃してしまうことになる。その他に、私が本気でとりあわない相手は評論家だ。私の計画の邪魔になる時以外は連中のことは気にしない。
・取引で禁物なのは、何が何でもこれを成功させたいという素振りを見せることだ。こちらが必死になると相手はそれを察知する。そうなるとこちらは負けだ。一番望ましいのは優位に立って取引することだ。この優位性を私はレバレッジ(てこの力)と呼ぶ。レバレッジとは相手が望むものをもつことだ。もっといいのは、相手が必要とするものをもつこと、そして一番いいのは、相手がこれなしでは困るというものをもつことだ。しかし常にこちらがそうしたものをもっているとは限らない。したがってレバレッジを利用するためには、想像力とセールスマンシップを働かさなくてはならない。つまりこの取引は得になると相手に思わせるのだ。
・不動産に関するもっとも大きな誤解は、成功のカギは一にも二にも立地条件にあるという考えだ。これを口にするのは不動産をよく知らない人間である。成功するためには必ずしも特等地は必要ない。必要なのは第一級の取引だ。レバレッジを作り出すことができるのと同様、宣伝と人間心理の応用により、場所のイメージも高めることができる。
・立地は流行とも関係がある。二等地でも一流の人たちを集めれば、それだけで価値が上がる。トランプ・タワーの後で、私は3番街と61番通りにある土地を安く買って、トランプ・プラザを建てた。はっきり言って、場所としては3番街は5番街にはとても及ばない。しかしトランプ・タワーのおかげでトランプの名前にネームバリューが生じており、私はここに人目を引く豪華なビルを建てた。トランプ・タワーの最も条件の良いアパートが売り切れてしまって手に入らなかった金持ちやVIPがここを求めたので、思いがけず高い値で売ることができた。今日3番街は格の高い土地になっており、トランプ・プラザは大人気を博している。要するに不動産業では、金を山と積んで最高級の土地を買う必要はないということだ。たとえ安くてもろくでもない土地を買えば失敗するのと同様、良い土地を高く買って失敗することもある。土地に金を出しすぎてはいけない。たとえそのために優良な土地を見送ることがあってもだ。立地というものを単純に考えることは禁物なのだ。
・どんなに素晴らしい商品を作っても、世間に知られなければ価値はないに等しい。必要なのは人々の興味を引き、関心を集めることだ。広報専門家を雇い、多額の金を払って商品を売るのも一つの方法だ。しかし私にとってはこれは市場を調査するのに外部のコンサルタントを雇うのと同じだ。自分でやったほうがずっと効率がよい。マスコミについて私が学んだのは、彼らはいつも記事に飢えており、センセーショナルな話ほど受けるということだ。これはマスコミの性格上しかたのないことで、そのことについてとやかく言うつもりはない。要するに人と違ったり、少々出しゃばったり、大胆なことや物議をかもすようなことをすれば、マスコミが取り上げてくれるということだ。私はいつも人と違ったことをしてきたし、論争の的になることを気にせず、野心的な取引をしている。また若くして成功をおさめ、ぜいたくな生活をしてきた。その結果マスコミは好んで私の記事を書くようになった。私はマスコミの寵児というわけではない。いいことも書かれるし、悪いことも書かれる。だがビジネスという見地からすると、マスコミに書かれるということにはマイナス面よりプラス面のほうがずっと多い。理由は簡単だ。ニューヨーク・タイムズ紙の一面を借り切ってプロジェクトの宣伝をすれば、4万ドルはかかる。そのうえ、世間は宣伝というものを割引いて考える傾向がある。だがニューヨーク・タイムズが私の取引について多少とも好意的な記事を一段でも書いてくれれば、一銭も払わずに4万ドル分よりはるかに大きな宣伝効果をあげることができる。おかしなことに個人的には不愉快に感じるような批判的な記事でも、ビジネスには大いに役立つこともある。
・私が心がけているのは、記者たちとは正直に話すということだ。相手をだましたり、自己弁護しないように気をつける。こういう態度をとると、マスコミを敵にまわすことになるからだ。記者に意地の悪い質問をされた時は、見方を逆にして何とか肯定的な答えをするよう努める。たとえば世界一高いビルがウェスト・サイドにどのような好ましくない影響を与えるかと聞かれたとしよう。私はこれを逆手に取り、ニューヨーク市は世界一高い建物を持つにふさわしい町であり、再びこの栄誉を手にすることは市のステータスを高めることになると答える。なぜ金持ちだけを相手に建てるのかと訊かれれば、私の建設工事の恩恵を受けるのは金持ちだけではないと説明する。失業手当を受けている何千人という人々に仕事を与えることになるし、新たなプロジェクトを建てるたびに納税者の数も増えるからだ。またトランプ・タワーのような建物はニューヨーク再興に一役かっていることも指摘する。
・肯定的な面を強調するのが好ましいのは確かだが、時には対決するしかない場合もある。私は決して気むずかしい人間ではない。良くしてくれた人にはこちらも良くする。けれども不公平な扱いや不法な処遇を受けたり、不当に利用されそうになった時には徹底的に戦うというのが私の信条だ。そのためにますます事態が悪化することもあるので、このやり方をみんなに勧めるわけにはいかない。だが私の経験では、自分の信念のために戦えば、たとえそのために人と仲違いすることになっても、結果的には良かったと思うことが多い。
・世間をだますことはできない。少なくともそう長くは無理だ。期待感をあおり、大々的に宣伝してマスコミに取り上げられ、ひと騒ぎすることはできる。しかし実際にそれだけのものを実行しなければ、やがてそっぽを向かれてしまう。
・ジミー・カーターのことを思い出す。大統領選でレーガンに敗れた後、カーターは私に会いにやってきた。ジミー・カーター図書館への寄付を募っているのだという。どれくらい入り用かと訊くと、彼はこう言った。「ドナルド、5百万ドルほど出してもらえるとありがたいんだが」私は仰天して返事もできなかった。しかしこの経験はあることを教えてくれた。それまで私はなぜジミー・カーターが大統領になることができたのかわからなかった。その答えは、彼は大統領としての資質には欠けているが、普通の人には考えられないようなことを要求する度胸と図々しさ、そして根性をもっているという点だ。大統領に選ばれたのは何よりもこの能力のためなのだ。だがカーターが大統領には不適任であることに国民はすぐ気づき、再度立候補したときには完敗した。
・私は必要なことには金を出すが、必要以上には出さない主義だ。低所得者用住宅を建設していた時、最も重要だったのは安く、迅速に適切な家を建てることだった。それを賃貸しいくばくかの金を儲けることができるようにだ。私がコストに敏感になったおは、この時からだ。いい加減に金を使うことは決してしなかった。ちりも積もれば山となるから、1セントでも粗末にしてはいけないことを父から学んだ。今でも下請業者の請求額が高すぎると思うとたとえ1万ドルでも5千ドルでも電話でクレームをつける。「わずかな金のことでなぜ騒ぎ立てるのだ?」という人もいる。だが私は25セントの電話代をかけて1万ドルの金を倹約することができなくなったら、そのときは引退すると答える。
・私は自分を偽らない。人生はもろいもので成功したからといってそれが変わるわけではないことを承知している。変わらないどころか、成功すると人生はいっそうもろくなる。予想外のことがいつなんどき起こるかわからない。だから私は自分が成し遂げたことにあまり執着しないようにしている。私にとって金はそれほど大きな動機ではなく、単に実績を記録するための手段に過ぎない。本当の魅力はゲームをすること自体にあるのだ。ああすればよかったと後悔したり、これから何が起こるだろうと心配したりはしない。今までの数々の取引は、結局のところどんな意味をもつのかと問われると返事に窮する。ただそれをやっている間、楽しかったと答えるしかない。
・成長する過程で私に最も重要な影響を与えたのは、父フレッド・トランプだ。父からは非常に多くのことを学んだ。この厳しい業界でいかにたくましく生きるか、どうすれば人を動かせるかといったことだ。また効率のよい仕事のやり方も教わった。つまりいかにして取りかかり、やり遂げ、しかもそれをうまくこなし、そして手を引くかについてだ。しかし同時に、私は父の仕事には関わりたくないという思いも、早くから植え付けられた。父はクイーンズとブルックリンで、家賃の統制管理された住宅の建設を手がけていた。仕事は順調だったが、利益を上げるのはかなり大変だった。私はもっとスケールが大きく、華やかでエキサイティングな仕事をしてみたかった。それにフレッド・トランプの息子としてではなく、自分自身として世に知られたければ、結局は外に出て成功しなければならないことにも気がついていた。父が自分のよく知っているそして得意な仕事を続けることに満足していたのは私にとって幸いだった。そのおかげで、私はマンハッタンで自由に身を立てることができたのだ。とはいえ、私は父のもおで学んだ教訓を決して忘れることはない。
・父はホレーショ・アルジャーの物語に登場するような腕一本でたたきあげた人物である。フレッド・トランプは1905年、ニュージャージーに生まれた。その父親は子供の頃スエーデンからアメリカへ渡ってきた移民で、そこそこに繁盛しているレストランを経営していた。しかし大酒飲みで荒れた生活をしており、父が11歳の時に世を去った。父の母エリザベスは3人の子供を養うためお針子として働きだした。当時、母親と同じ名の長女エリザベスが16歳、末っ子のジョンが9歳だった。父フレッドは真ん中の兄弟だったが、長男として一家の大黒柱となった。そしてすぐに地元の果物屋の配達から靴磨き、建設現場での木材の運搬などありとあらゆる半端仕事を引き受けるようになった。父は建築に興味をもち続け、高校生の時、夜学に通って大工仕事と図面の見方、見積もりを学んだ。建築のことを学んでおけば、いつでも生計を立てられると思ったのだ。16歳の時には最初の建築を行った。隣人のために造った車2台を収容できる枠組構造の木造ガレージだ。当時、中産階級の人々が車を持ち始めていたが、ガレージのある家はほとんどなかった。まもなく父は1軒50ドルでプレハブのガレージを建設する新商売を始め、順調にこれを軌道に乗せることができた。父は1922年に高校を卒業したが、家族を養わなければならなかったので、大学へ行くことあ考えもしなかった。父はクイーンズの住宅建設業者のもとで、大工の助手として働きだした。父は他の職人より腕が立ったし、その他にも有利な資質をもっていた。まず第一にめっぽう頭がきれた。今でも5桁の足し算を間違わずに暗算することができる。父は夜学で学んだ知識と基本的な良識とを組み合わせて、ほとんど教育を受けていない仲間の大工たちに、仕事の手っとり早いやり方を教えた。たとえばスチール製の直角定規を使ってたるきを組む方法などだ。こうした資質に加え、父は常に向上心を持ち仕事に没頭した。仲間の職人たちはおおむね仕事があるというだけで満足していた。だが父は働きたいと思うだけでなく、良い仕事をしたい、腕を上げたいと思っていた。そして最後に父は仕事が大好きだった。物心ついた頃から、私は父によく聞かされたものだ。「人生で一番大切なのは、自分の仕事に愛着をもつことだ。何かに熟達するにはそれしかないんだから」
・父は高校を卒業してから一年後に、クイーンズのウッドヘイヴンに初めて一戸建ての家を建てた。建築費は5千ドル弱だったが、それを7500ドルで売却した。父は自分の会社をエリザベス・トランプ&サンと名付けた。当時はまだ未成年だったため、法律上の書類や小切手にはすべて母親のサインが必要だったからだ。父は最初の家を売るとすぐに、その利益をもとにまた家を建てた。そして同じようにしてウッドヘイヴン、ホリス、クイーンズ・ヴィレッジといったクイーンズの労働者階級の住む地域に次々に家を建てていった。それまで狭い窮屈なアパートにしか住んだことのなかった労働者たちに父はまったく新しい生活様式をもたらした。つまり郊外風のレンガ造りの住宅を低価格で提供したのだ。それらの家は建設が追いつかないほどの早さで飛ぶように売れた。直感的に父は事業を拡大することを考え始めた。1929年にはより富裕な人々にねらいを定めてこれまでよりはるかに大きな住宅の建設にとりかかった。小さなレンガ造りの家の代わりに3階建てのコロニアル様式、チューダー様式、ヴィクトリア様式などの邸宅をクイーンズの一地区に建設した。やがてこの地区はジャマイカ・エステーツとして知られるようになり、父はここに自分の家族の家も建てた。やがて大恐慌が始まり住宅市場も打撃を受けると、父は他の事業に目を転じた。倒産した住宅金融会社を買い取り、一年後にそれを売って利益をあげた。次にウッドヘイヴンにセルフサービスのスーパーマーケットを建てた。この手のスーパーとしては最初のものだ。肉屋、洋服屋、靴屋といった地元の小売店がみなここの売場にテナントとして入った。1カ所であゆるものが手に入る便利さが受けて、この事業はたちまち成功をおさめた。しかし父は建築業へ戻りたいという思いが強く、1年足らずで店をキング・カレンに売り払い、大きな利益をあげた。1934年頃には大恐慌もようやくおさまり始めていたが、金融は依然として厳しかった。そこで父は再び低価格の家をつくることにした。今度はブルックリンの貧困地区フラットブッシュを建設場所に選んだ。土地が安く将来性があるとみたのだ。この時も父の直感は当たった。3週間で78戸の家が売れ、続く12年間に父はクイーンズとブルックリンの全域にさらに2500戸を建設した。父は大成功を収め始めたのだ。
・1936年に父は私のすばらしい母メアリ・マクラウドと結婚し、家庭を築いた。父は成功したおかげで、自分が受けられなかった大学教育を弟に与えてやることができた。父の援助のもとに叔父ジョン・トランプは大学へ通い、マサチューセッツ工科大で博士号を得た。そしてその後、物理学教授となり、わが国有数の科学者の一人に数えられるようになった。
・私は昔風の家庭で育った。父が一家の稼ぎ手として権力をもち、母は主婦に徹していた。といっても母はブリッジに興じたり、電話でおしゃべりをして日を過ごしていたわけではない。5人の子供の世話をするほか料理や掃除をし、靴下を繕い、地元の病院でボランティアとして働いた。私たちは大きな家に住んでいたが、自分たちを金持ちだと考えたことはない。みな1ドルの価値を勤労の大切さを知るように育てられた。一家の結束は固く、今でも私のもっとも親しい友は家族である。両親は全く見栄を張らない。父はいまだにブルックリンのシープスヘッド・ベイ地区のZ街にある奥まった質素な狭いオフィスで働いている。オフィスのあるビルは父が1948年に建てたものだ。父はどこかよそに移るなどとは考えたこともないのだ。
・第一子である姉のメアリアンは、マウント・ホーリオーク大学を卒業後、しばらくは母と同じ道を歩んだ。つまり結婚し、息子が成長するまで家庭にいたのだ。しかし姉も父の積極性と向上心とを大いに受け継いでいた。そこえ息子のデイヴィッドが十代になると学校へ戻り、法律の勉強を始めた。そして優等で卒業すると、まず民間会社に勤め、その後5年間米連邦地検で連邦検察官として働き、4年前に連邦判事となった。わが姉ながら、なかなか大した女性である。妹のエリザベスはやさしく聡明だが、姉ほどの野心はなく、マンハッタンのチュース・マンハッタン銀行で働いている。
・私は小学生の頃からすでに自己主張の強い攻撃的な子供だった。二年生の時、音楽の先生の目に黒あざをこしらえたこともある。音楽のことなど何も知らないくせにと思って、パンチをお見舞いしたのだ。このためにもう少しで放校処分になるところだった。このことを決して自慢には思っていない。だが私が小さい頃から物事に敢然と立ち向かい、非常に強引なやり方で自分の考えをわからせようとする傾向があったことを、この一件ははっきり示している。ただし今はこぶしの代わりに頭を使うところが違っている。
・私は幼い頃から、近所のガキ大将だった。人から非常に好かれるか、非常に嫌われるかのどちらかで、これは今も変わっていん。けれども仲間うちでは大いに人気があり、みなのリーダー格になることが多かった。思春期には、もっぱらいたずらに精を出した。なぜか騒ぎを起こしたり、人を試したりするのが好きだったからだ。校庭や誕生パーティの席で水の入った風船や紙つぶてを投げて大騒ぎを演じたものだ。攻撃的だが、悪質ないたずらではなかった。弟のロバートはあるエピソードについて話すのが好きだ。弟はこの時に私が将来どの道に進むかがはっきり分かったという。
・13歳になると、父は私を軍隊式の私立学校へ入れることにした。軍隊式訓練が私のためになると思ったのだ。私はあまり気が進まなかったが、やがて父の考えが正しかったことが分かった。私はニューヨーク北部にあるニューヨーク・ミリタリー・アカデミーの8年生に編入した。そして最上級学年までここで過ごし、その間に規律を身につけ、自分の攻撃性を建設的に使うことを学んだ。最上級学年の時には、士官候補生の隊長に任命された。
・私は士官学校ではかなりいい成績をとっていたが、あまり一所懸命に勉強したとは言えない。授業にさほど興味をもっていなかったことを思うと、比較的楽にいい成績をとれたことは幸運だった。私は早い時期に学校で学ぶことはすべて本番のための下準備にすぎないことを悟っていた。本番とは大学を卒業してから私が手がける何かである。
・私はよちよち歩きができるようになった頃から、父と建築現場へ出かけていた。ロバートと私は一緒についていって、ソーダ水の空き瓶を探して時を過ごす。その瓶を店に持って行って金をもらい、預金するのだ。十代の頃は休暇で学校から帰省すると父のあとをついてまわり、商売のことをつぶさに学んだ。業者との交渉、現場めぐり、新たな建設用地を手に入れるための交渉などだ。家賃が統制管理された住宅を建設するという父の商売では、たくましく冷徹でなければ成功することはできない。利益をあげるためにはコストを低く抑えなければならないので、父は常に価格に気を配っていた。モップや床用ワックスを買う場合でも、プロジェクトのより大きな製品を扱う業者に対するのと同様に、手抜きのない交渉をした。父の強みはすべてのもののコストを熟知していたことだ。どの業者も父をだますことはできなかった。たとえば配管工事が40万ドルかかると分かっていればどの程度まで値切れるかがわかる。つまり30万ドルにするよう交渉しようとは思わない。この値段では向こうは商売にならないからだ。しかし業者の言いなりに60万ドルで手を打つようなこともないわけだ。
・安い値段で仕事を請け負わせるための父のもう一つの手は、業者に自分を信頼させることだった。父は相手に低い価格を提示したあとこう言う。「いいか私は必ず支払う。それも期日通りにだ。だが他のやつらでは金が入るかどうかわからないぞ」さらに父は自分との取引では迅速に仕事が終わり、すぐに次の仕事に移れることも力説した。そして最後に、自分は休みなく建設を行っているから将来の仕事も保証できると話した。相手は父の言い分に説得されることが多かった。父はまた、信じがたいほど厳しい現場監督だった。毎朝6時には現場に姿を見せ、作業員たちにはっぱをかける。その仕事ぶりはまるで一人芝居のようだった。父の期待どおの仕事をしていない者がいると、自分が代わってそれをする。父はどんな仕事でもこなすことができた。
・私はまずブロンクスにあるフォータム大学に入学した。家の近くにいたいというのが主な理由だ。大学を運営しているイエズス会修道士たちとはとてもうまくいった。だが2年後、どうせ大学教育を受けるなら、最高のとことで自分を試すほうがいいと思うようになった。そこでペンシルバニア大学の大学院ウォートン・スクールに願書を出し、入学した。当時は実業界で身を立てようと思う者は、ウォートンへ行くべきだと考えられていた。ハーバード・ビジネス・スクールは多くのCEO、つまり大企業の経営者を輩出してはいる。だが本物の起業家にはウォートン出身者が圧倒的に多い。
・ウォートンで学んだ一番重要なことといえば、学業成績にあまり感動してはいけないということだろう。クラスメートたちは特にすぐれたあるいはおそるべき人たちではなく、私が十分張り合うことができる相手であることがすぐにわかった。ウォートンで得たもう一つの重要なものはウォートンの学位だった。私に言わせればそんな学位は何の証明にもならない。だが仕事をする相手の多くはこれをいたく尊重する。この学位は非常に権威あるものと思われているのだ。というわけであらゆることを考えあわせるとやはりウォートンへ行ってよかったと思っている。
・父が建設途中のトランプ・タワーの現場を見に来た時のことはいまだに覚えている。タワーの正面は一面のガラス壁だったが、これはレンガよりはるかに高価だ。その上、手に入る一番高いガラス、ブロンズ・ソーラーを使っていた。父は一目見るなり私に言った。「こんなガラスを使うことはないじゃないか。4、5階までこれを使って、あとは普通のレンガを使ったらどうだ。どうせ上を見上げる者なんかいないよ」これはまさにフレッド・トランプ的発想だった。父は55番通りと5番街の角に立って、数ドルを節約しようと考えているのだ。私は心を打たれたし、もちろん父の気持ちもよく分かった。だが同時になぜ自分が父のもとを離れたかという理由もはっきり認識した。父の商売を継ぎたくなかった本当の理由は、私にはもっと遠大な夢とビジョンがあったからだ。これは父の仕事が肉体的にも経済的にも厳しかったという事実より、はるかに重要だった。ブルックリンやクイーンズに家を建てていては、この夢を実現することは不可能だったのだ。考えてみると、私のショーマン的な性格は母から受け継いだもののように思う。母はドラマチックで壮大なことが好きだった。ごく平凡な主婦だったが、自分を越えた大きな世界観を持っていた。エリザベス女王の戴冠式の時、スコットランド人である母はそれを見るためにテレビの前に釘付けになり、一日中動かなかったことを覚えている。母は式の壮麗さと王室の華やかな雰囲気にただ心を奪われていたのだ。その日の父のこともやはり記憶に残っている。父はいらいらと歩きまわり、母に言った。「メアリ、いい加減にしてくれ。もうたくさんだ。消しなさい。あんなものニセ芸術家の集まりじゃないか」母は顔も上げなかった。この点では二人はまったく対照的だった。母は華やかさと壮大さを好む。だが父はきわめて現実的で能力や効率のよさにしか心を動かされないのだ。
・学生時代、同級生たちが新聞の漫画やスポーツ欄を読んでいる時、私は連邦住宅局の抵当流れ物件のリストに読みふけっていた。抵当流れになっている政府融資による公営住宅のリストを研究するとは少し変わっていると思われるかもしれない。だがこうして私はスウィフトン・ヴィレッジのことを知ったのだ。これは私がまだ在学中に父と共同で手がけた仕事で私にとってははじめての大きな取引だった。
・私は団地全体が清潔で、管理が行き届いているよう気をつけた。私はとてもきれい好きだ。また清潔にしておくことは投資の際にも有利だと思っている。たとえば車を売りたいとする。5ドルをかけて洗車し、ワックスをかけ、少し念入りに磨きあげると、それだけで400ドルは高く売れる。うす汚れた不潔な車を売ろうとしている人を見ると、これはうまくいかないとすぐ分かる。ほんの少しの手間でぐんと見栄をよくすることができるのだ。不動産でも同じことが言える。手入れの行き届いた物件は、そうでない物件よりはるかに高値で売れる。
・私は尊敬する人には素直に耳を傾ける。これもマーケティング研究のためではなく直感でそうするのだ。
・1971年に転機が訪れた。マンハッタンにアパートを借りることにしたのだ。3番街と75番通りにあるビルの中のワンルームのアパートで、窓から見下ろすと隣のビルの中庭の水タンクが見えた。私はふざけてこのアパートをペントハウスと呼んだ。たまたまビルの最上階に近かったからだアパートが広く見えるよう部屋を仕切ってみた。だが何をしても、そこは暗い薄汚れた小さなアパートであることに変わりなかった。それでも私はそこが大いに気に入っていた。このアパートへ引っ越した時は15年後にセントラル・パークを見晴らす5番街と56番通りにあるトランプ・タワーの最上部のトリプレックスへ引っ越した時より興奮したものだ。それもそのはずだ。クイーンズに住み、ブルックリンで働いている若者が突然アッパー・イースト・サイドにアパートを持ったのだ。もっとも重要なのは引っ越しのおかげでマンハッタンをよりよく知るようになったことだ。私はただ訪問したり、商用でやってきた時とはどことなく違う態度で通りを歩き始めた。やがてよい不動産物件もすべて知るようになった。クイーンズ出の若造ではなく、街の人間になったのだ。自分はあらゆるものに恵まれているような気がした。つまり若くてエネルギーにあふれ、マンハッタンに住んでいるのだ。仕事場はブルックリンにあり毎日通勤していたがそんなことは問題ではなかった。
・私がマンハッタンに住み最初にしたのは、ル・クラブへ加入することだった。これは当時ニューヨークでもっとも注目を集めていたクラブで、隆盛時のスタジオ54と同様、選考が厳しいことでも知られていた。東54番通りにあるこのクラブの会員には、世界で最も成功した男や最も美しい女がいた。75歳の富豪がブロンドのスェーデン美人を3人引き連れてやって来るという類のクラブだ。クラブへ入会したいきさつは忘れることができない。ある日私はル・クラブへ電話した。「ドナルド・トランプという者ですが、クラブの会員になりたいのです」相手の男は笑って言った。「冗談だろう」もちろんだれも私の名前など聞いたこともなかったのだ。次の日、また別の手を思いついてもう一度電話した。「会員名簿をいただけますか?知っている人がいるかもしれないので」「残念だがそれはできないんだ」男は答えると電話を切った。次の日また電話をかけた。「クラブの会長さんとお話ししたいのです。さしあげたいものがあるので」どういうわけか、男は会長の名前とオフィスの電話番号を教えてくれた。そこで電話をかけ、丁重に自己紹介した。「ドナルド・トランプという者ですが、ル・クラブに入会したいのです」「会員に友人とか家族がいるのかね?」と会長が聞いたので、「いいえ、だれもいません」と答えた。「ではなぜ入会できると思うんだね」会長が尋ねた。私はひたすらしゃべり続けた。しまいに相手が言った。「それじゃこうしよう。きみはなかなか好青年のようだし、若手の会員が入るのもいいのかもしれない。21クラブで一緒に一杯やらないかね」翌日の晩、私たちは飲むために会った。ただしちょっとした問題が一つあった。私は酒はやらず、何もせずにただ座っているのは苦手なのだ。ところが誘ってくれた相手は酒好きで、しかもやはり酒好きの友人を伴って来ていた。それから2時間、二人が酒を飲んでいる間、私は手持ち無沙汰で座っていた。しまいに私は言った。「そろそろお送りしましょうか?」「いや、もう一杯だけやろう」二人が答えた。私はこうした状況には慣れていなかった。父はまじめいっぽうの堅物だ。毎晩7時に帰宅し、夕食をとり、新聞を読み、テレビのニュースを見る、という判で押したような生活をしてきた。私も父に劣らず堅物だ。したがってこういう世界は全くなじみがなかった。マンハッタンで成功している人物はみな大酒飲みなのだろうか。もしそうなら、私は大いに有利だ、と思ったのは覚えている。10時頃になって二人はやっと飲むのをやめ、私は抱えるようにして二人を家まで送って行った。それから2週間経っても会長からは何の連絡もなかった。ついにこちらから電話すると、向こうは私のことを覚えてもいなかった。そこでまた振り出しに戻り、21からやり直した。ただし今度は会長もあまり飲まず、私を会員に推薦してくれることに同意した。ただ一つだけ気がかりなことがある、と会長は言った。君は若くてハンサムだが、年輩の会員には美しい若い夫人がいる者もいる。君がその夫人たちに手を出しはしないかと心配だ、というのだ。そんなことはしないと約束してくれ、と彼は言った。私は耳を疑った。母も父同様おかたい人物で、父を心から愛している-最近二人は結婚50周年を祝ったところだ。こういう環境で育った私に、この男は他人の妻を盗むの盗まないのという話をしているのだ。ともかく私は約束し、クラブへの入会を許された。これは社交生活の上でも仕事の上でも、大いにプラスになった。私は大勢の若く美しい独身女性と知り合いになり、毎晩のようにデートした。けれども真剣なつきあいにまで発展することはなかった。みな美人だが、まともな会話のできる者はあまりいないのだ。みなうぬぼれが強かったり、一風変わっていたり、わがままだったりした。そして大抵は見かけ倒しだった。たとえば、私はデートの相手をアパートには連れて来られないことにすぐ気づいた。彼女たちの基準からすると、私の家は人が住めるような代物ではないのだ。彼女たちの世界では外見がすべてだった。私が最後に結婚した相手は大変美しい女性だったが、彼女は父や母と同じく堅物でもあった。この同じ時期に、仕事に成功した裕福な人々ともル・クラブを通じて大勢知り合いになった。私は夜出かけるのを楽しんでいたが、仕事のことも忘れなかった。ニューヨークという町がどんなふうに機能しているかを知り、いずれ取引相手になるような人々と親しくなった。また懐の豊かな人々、特にヨーロッパや南米の金持ち連中とも知り合いになった。彼らは後にトランプ・タワーやトランプ・プラザの最も値の高いアパートを買ってくれた。
・条件のいい土地を安く買って損をすることはまずない、というのが私の信念だ。当時ウェスト・サイド一帯は住むには危険な場所と考えられていた。横丁という横丁には生活保護者対象の簡易宿泊所が建ち並び、どこの公園にも麻薬の売人がいた。セントラル・パーク・ウェストからコロンブス街にかけての84番通りの1ブロックがいかに物騒な地域かという記事をニューヨーク・タイムズ紙が何回にもわたって掲載していたことを覚えている。しかしあたりに目をやえば、この環境がたやすく改善できることがすぐわかった。西84番通りのような荒れた横丁でさえ、セントラル・パークの近くには褐色砂岩造りの古い堂々とした建物が建っていた。またセントラル・パーク・ウェストやリヴァサイド・ドライブといった通りには、すばらしい眺望が楽しめる広々としたアパートの入った美しい古い建物があった。人々がこの地域の価値に気づくのは時間の問題だった。
・私に言わせれば、これは全くの近視眼的発想だ。たとえば大抵の会社は売上げが落ちると広告費を削る。だが本当は売れない時こそ広告が必要なのだ。
・大事な取引をする場合は、トップを相手にしなければラチがあかないのだ。その理由は、企業でトップでない者はみな、ただの従業員にすぎないからだ。従業員は取引を成立させるために奮闘したりしない。賃上げやボーナスのためには頑張るが、上司の機嫌を損ねるようなことはしないよう気をつける。したがって取引を上司に取り次ぐ際に、自分の立場ははっきりさせない。取引相手には乗り気の様子を見せても、上司にはこう言うだけだ。「ニューヨークのトランプという人物が、こんな話を持ってきました。いい点と悪い点はかくかくしかじかです。どうしますか」上司がその話を気に入れば、自分もそれを支持するだろう。だがそうでなければ「私も同意見です。ただご報告したまでです」と言うだけだ。
・おかしなことに、私自身の母は生涯平凡な主婦だったにも関わらず、私は多くの重要な仕事に女性を起用してきた。それらの女性は、私のスタッフの中でも特に有能な人たちだ。実際、その働きぶりはまわりの男性をはるかにしのぐことも多い。私の会社の業務執行副社長を10年つとめたルイーズ・サンシャインは、闘志にあふれている点では誰にもひけをとらなかった。営業全般を担当し、私が手がける建物の内装をとりしきる業務執行副社長のブランシュ・スプレイグは、私の知るうちで最も優秀なセールスマンであり、管理者である。私の補佐役のノーマ・フォーダラーはチャーミングで優しい、すてきな女性だが、芯はめっぽう強い。彼女が人の言いなりになるなどと思ったら大間違いだ。妻のイヴァナもすぐれた経営手腕を持ち従業員にはとても親切だが、非常に要求が厳しく、負けず嫌いな面もある。従業員からはとても尊敬されているが、これは彼女がまわりの者を叱咤激励するだけでなく、自らも一所懸命に仕事をしていることをみな知っているからだ。
・まず第一に値段さえ適正ならなるべく立地条件のよい土地を手に入れたほうがよいというのが私の信条だ。第二につむじ曲がりのようだが、私は込み入った取引にひかれる。そのほうが面白いというのも理由の一つだが、難しい取引のほうが狙ったものが安く手に入るからでもある。
・他の業者たちはカジノの運営には慣れていたが、カジノの建設については経験がなかった。したがってこのような周到な準備は行わなかった。早く建物を完成させてオープンしようと急ぐあまり、多くの業者は最終的に許可がおりるのを待たずに、工事を始めてしまった。すると委員たちがやって来て、「だめ、この部屋は小さすぎる」だの、「このスロット・マシンはここでなく、あそこに据えないとだめだ」などと文句をつける。工事の途中で手直しをすると、非常に高くつくことは長年の経験からわかっていた。大規模なプロジェクトの多くが大幅に予算を超過するのはこれが一番の原因ではないかと思う。許可を申請する相手や従うべき規定が多いことについて、私たちが他の業者より有利な点が一つあった。それは私たちが官僚的組織ではないことだ。大規模な株式会社では一つの問題に返答をもらうまでには何人もの重役の手を経なければならない。そしてそもそもその重役は何もわかっていない場合が多いのだ。しかし私たちの会社では、誰でも質問があれば直接私のところに来て、すぐに答えをもらうことができる。多くの取引で私が競争相手よりはるかに敏速に行動することができるのは、まさにこのためだ。
・私はこと経営に関しては、きわめて簡単なルールに従うことにしている。競争会社から有能な人材を引き抜き、より高い給料を支払い、その手腕に応じてボーナスやさまざまな特権を与えるというものだ。こうすれば最高の経営体制を築くことができると信じている。
・いったん負けることによって、勝つための新たな戦術が見えてくることがある。そのとき必要なのは、十分な時間とちょっぴりの”ツキ”である。
・私は自分に対する非難が不当なものだと感じた時にはなおのこと、黙って引き下がりはしない。告訴を受けて立てば訴訟費用がかさむだろうし、こちらの戦術を考え直さねばならなくなるかもしれない。しかし脅しに負けて、ばかげた調停案をのむことだけはなんとしてもできなかった。
・大きな窓はそれだけで大変な価値がある。素晴らしい眺めはちょっとした財産にも匹敵するからだ。
・長年にわたる政治家との付き合いで私が学んだのは、彼らに確実に行動を起こさせるものはマスコミ-厳密にいうとマスコミに対する恐怖だけということだ。圧力をかけたり、哀願したり脅迫したり、彼らが行う各種の運動のために多額の寄付をしても、おおむね効果ははない。しかしマスコミにたたかれる可能性がでてくると、たとえそれが無名の雑誌であっても、たいていの政治家は震え上がる。マスコミに悪く書かれると票を失うおそれがあるからだ。大量の票を失うと再選されなくなる。再選されなければ、会社勤めを余儀なくされるかもしれない。政治家はそうなることを最も嫌うのだ。
・彼の主な批判は、ともかく高い建物は好きではないということのほかに、このプロジェクトが近隣地域と十分にとけあうよう計画されていないというものだった。しかし、これはまさにこのプロジェクトで私が最も気に入っている点だった。まわりの建物と一体となるようなものを建てるのは失敗のもとだと確信していた。十年前、コモドア/ハイアット・ホテル再建の際にも、同じ態度をとった。当時グランド・セントラル駅周辺は荒廃しつつあった。そこで、反射ガラスで覆った壮麗な新ホテルを建て、まわりのくすんだ古い建物と対照させるのが成功する唯一の方法だと考えたのだ。ホテルは大成功をおさめ、評論家たちもやがて態度を変えるようになった。
・1987年1月、ユーリ・ドゥビーニン駐米ソ連大使から、次の言葉で始まる書簡をもらった。「モスクワからのよい知らせをお伝えできることをうれしく思います」次いで、国際観光を司るソ連の有力な国家機関であるゴスコムインツーリストが、私と共同でモスクワにホテルを建設し、その運営を行うことを希望していると書かれていた。7月4日、イヴァナと彼女のアシスタントであるリーザ・カランドラ、そしてノーマと共にモスクワに赴いた。これは実に得難い経験だった。私たちは国営ホテルのレーニン・スイートに泊まり、ホテルの候補地を数カ所見学した。そのうちのいくつかは赤の広場の近くにあった。この商談に対するソ連政府の意欲には感銘を受けた。
・昨年の9月、トランプは10万ドル近い金を投じてアメリカの主要新聞に広告を出し、レーガン政権の対外政策を批判した。こうした動きから、彼が政界への進出を狙っているのではないかと推測する向きもある。トランプ自身は大統領選に出馬する意志は今のところないことを明らかにしている。けれども、元モデルでチェコのスキー選手だった美しい妻イヴァナは言う。「あと10年たってもドナルドはまだ51歳です。そう際限なくカジノを所有したりビルを建てたりするわけにはいきませんから、いずれドナルドは他の分野に目を向けるでしょう。それは政治かもしれないし、何か別のものかもしれません。大統領選挙へ出馬することも絶対にないとは言い切れません」いずれにしても、今年まだ42歳というこのエネルギーに満ちあふれた男が、現状のままにとどまっているとは思えない。トランプがこの先ニューヨークをそしてアメリカをどのように変えていくか、まさに興味津々といったところだ。
良かった本まとめ(2016年下半期)
<今日の独り言>
Twitterをご覧ください!フォローをよろしくお願いします。
 「チャンスをつかむ男の服の習慣」の購入はコチラ
「チャンスをつかむ男の服の習慣」の購入はコチラ 













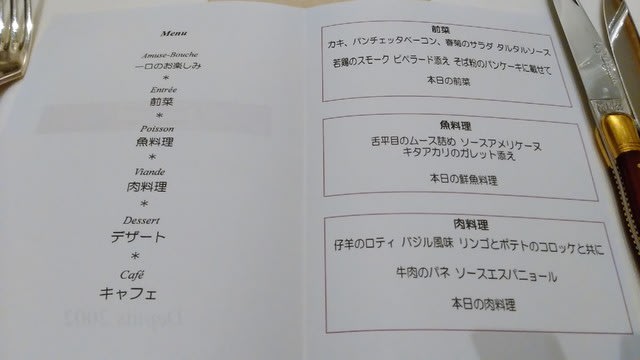








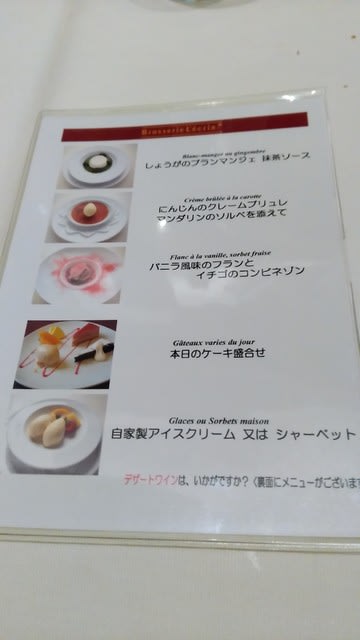




















 「毛玉取りブラシ」の購入はコチラ
「毛玉取りブラシ」の購入はコチラ 






 「下流老人と幸福老人」の購入はコチラ
「下流老人と幸福老人」の購入はコチラ 















 「馬毛歯ブラシ」の購入はコチラ
「馬毛歯ブラシ」の購入はコチラ 


 「トランプ自伝-不動産王にビジネスを学ぶ」の購入はコチラ
「トランプ自伝-不動産王にビジネスを学ぶ」の購入はコチラ 







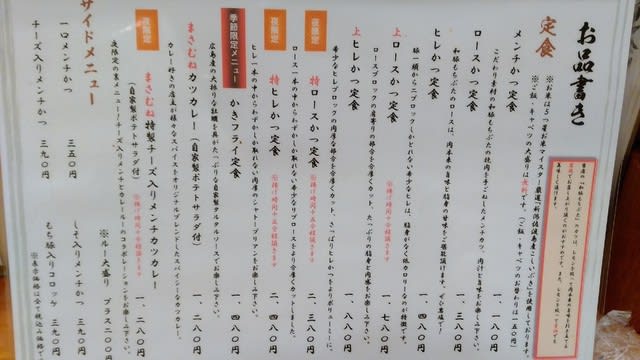
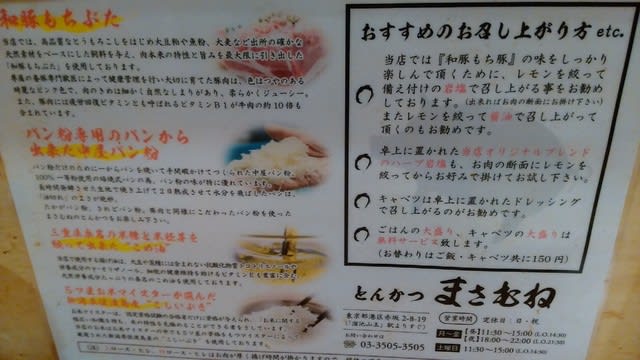

















 「グローバル投資のための地政学入門」の購入はコチラ
「グローバル投資のための地政学入門」の購入はコチラ