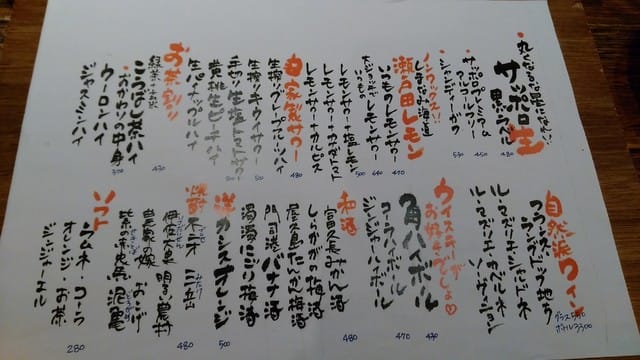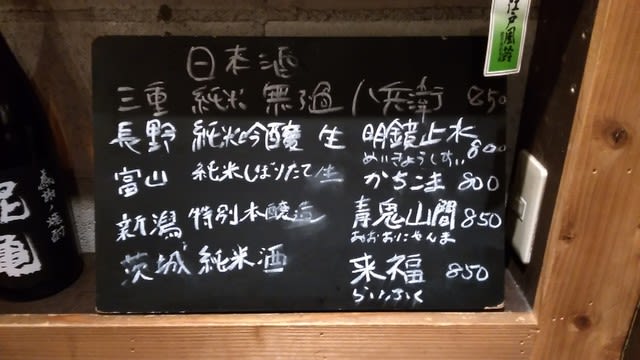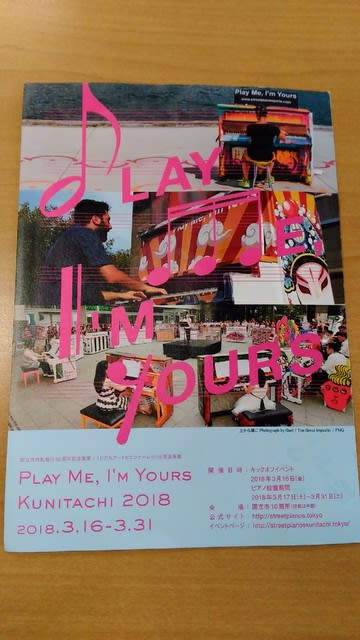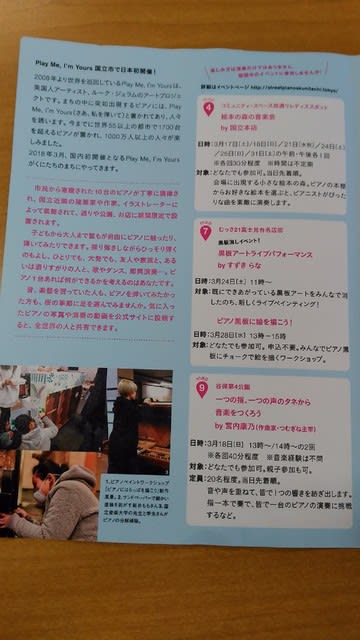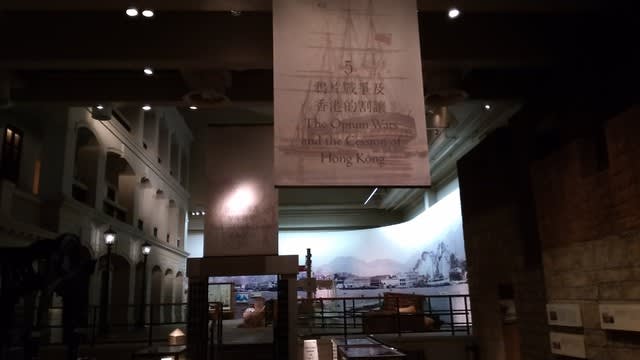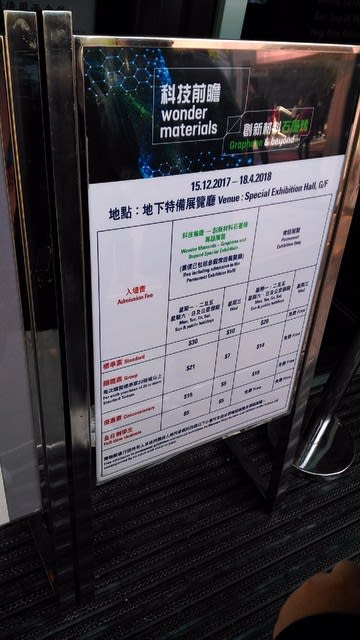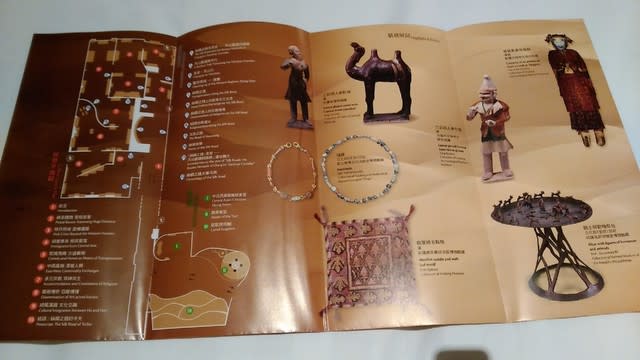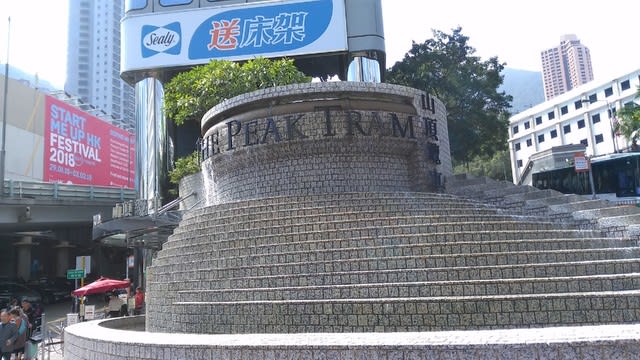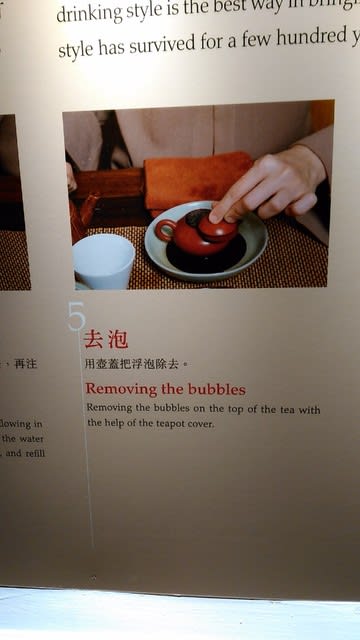「母乳育児」の購入はコチラ
「母乳育児」の購入はコチラ
「日本史の謎は地政学で解ける」という本は、地政学という観点から日本の古代から鎌倉時代や戦国時代、江戸時代、明治時代、第二次世界大戦等の歴史について分かりやすく説明したもので、それら歴史の理由がよく分かり、ナルホドと思うことがたくさんあり素晴らしいと思いましたね♪
目から鱗です♪
特に以下については地政学以外でもナルホドと思いましたね♪
・中世までは瀬戸内海は交通大動脈であり物流ハイウェイとしての役目を担った
・気候変動によって日本の東西の力関係は左右された
・源氏は鎌倉で幕府を開き、足利氏は京都で幕府を開いた理由
・明治天皇の関東行幸は新政権のアピールだった
・ジャガイモやサツマイモが世界的に飢饉を防いだ
・源義経が西へ逃げずに東北へ逃げた理由
・薩摩や長州が幕末に雄藩となった理由
・元が博多湾を攻めたのは補給面等から
・東京湾への黒船来航は江戸への流通を止め危機的だった
・屯田兵はロシアからの防衛のための住民増加と鹿児島士族活用
・征韓論はロシアからの二方面攻撃を防ぐため
・明治の参謀本部は大陸向けの海送ルートは安全のため関門海峡~釜山
・日露戦争後に米国資本を受け入れていればその後の世界は変わった
・ロシアとは地政学的には国後島の帰属はあり得るが択捉島は難しい
・在韓米軍こそが日本の地政学的リスクを減らしている
・今後の日本は宇都宮市から青森市に至るJR東北本線に沿って細長く紐状に首都機能を分散するのが適切
「日本史の謎は地政学で解ける」という本は、日本の歴史について理解を深めるだけでなく、今後の日本の方向性もかなり考えさせられ、とてもオススメです!
以下はこの本のポイント等です♪
・概ね日本という国は西から東へ勢力が伸張して成り立った。このとき山がちの陸路より、海路が活用された。たとえば九州方面から近畿に入るには「太平洋沿岸ルート」「瀬戸内ルート」「日本海沿岸ルート」の3通りが考えられるが、中世までは、このうち瀬戸内ルートが発展し、「物流ハイウェイ」としての役目を担った。
・実は九州南部の日向灘から今の静岡県が面する遠州灘にかけての日本列島の南岸は、一度難破したら生還が期しがたい、舟艇にとってすこぶる恐ろしい海域なのだ。恒常風である西風に、たまたま北風が加わり、船がひとたび陸岸から吹き離されてしまえば、沖合いには強い海流(黒潮)があって、どんどん伊豆諸島方面は運ばれてしまう。その速さたるや、古代人の櫨櫂漕ぎで逆らうことなどとうてい無理だった。運良く伊豆諸島のどこかに乗り上げることができなければ、そのまま北太平洋を果てしなく漂流するのみ・・・。
・神功皇后が近畿から九州北部を再平定する時にも、また「三韓征伐:するための準備段階でも、太平洋沿岸の航路は使われていない。一年を通じて遭難の危険が比較的に小さかった瀬戸内海こそ、日本の歴史的な「交通大動脈」であり、「物流ハイウェイ」だった。
・ヤマト政権もかなり早くから朝鮮半島の諸勢力をさまざまに後援し、工作した。たとえば5世紀以降の日本が、朝鮮半島北部に位置する高句麗をあれこれ援助し、強化してやっていれば、半島南部の新羅は、とても南向きの対日戦争や対九州工作、あるいは任那攻撃の余裕はなくなっただろう。さらにそこには大陸(晋巍六朝)のプレイヤーも干渉した。彼らからみれば、朝鮮半島を併呑するためには、まず新羅を応援して百済や高句麗を「挟撃」するのが省力的である。しかしヤマト政権としては、それを傍観することはできない。なぜなら、もし半島が新羅によって統一されれば、次は大陸勢力と一体化した半島勢力が九州へ直接軍事的に侵攻しち、みちのくの蝦夷の対中央反乱をそそのかしたりしかねないからだ。だから日本の統一政権の首都は、近隣外国に対するこちらからの工作に不便がないことと、外国から幇助された九州の反乱に対処しやすいことと、みちのくの蝦夷が大陸勢力と気脈を通じ合わないようにできるだけ近くから見張っていられることと、万一の外部からの直接侵略の可能性までもを考えて、そのすべてにうまく備えられるように位置を定める必要があった。瀬戸内海が交通路や高速通信手段に使えるおかげで、ヤマト政権による九州反乱の鎮定は、常に低コストで可能であった。大陸が随によって統一されたときは、新羅が高句麗を滅ぼさぬよう日本側から牽制し続け、随に高句麗遠征をもよおさせて、その軍費の過重から随を自滅させた。
・しかし次の唐朝は、海軍力によって半島干渉を有利に進め、高句麗を弱め、新羅と合同して百済を滅亡させてしまう。ヤマト政権は首都を琵琶湖南西岸の大津まで後退させて、唐の海軍が瀬戸内に入ってくる事態に備えた。このときは、半島から秩序立って撤収した日本兵が唐軍に「強敵」の印象を与えていたおかげで、日本本土侵攻は企画されずに終わったのである。
・鎌倉幕府は、当時の温暖気候に助けられて農業生産が急伸中だった「東国」に位置することが経済的に有利であり、かつまた、京都朝廷や寺社の心理工作の引力圏から離れることも好都合であった。足利幕府は逆に、吉野の南朝と気候寒冷化で農業が復調してい「西国」が「反政府」で結託することを封ずるため、京都に居座って見張り続ける必要があった。しかし京都から九州に至る瀬戸内海経済圏は明朝からの政治工作に乗ぜられやすかった。豊臣政権はこちらから攻めることで明朝の弱体化を誘導した。徳川幕府は、西洋海軍が気軽に近づけず、清朝の膨張にも目配りしやすい江戸を動かさなかった。
・北東ユーラシア大陸の陸地が海よりも早く冷えやすい(従って空気が重くなりやすい)のと、偏西風があるせいで、日本の周囲海域には厄介な北西風が吹きがちである。対馬海峡(朝鮮との海峡)には、南シナ海から常に暖流が日本海に向けて流れ込んでいる。その上を北西風が吹くとどうなるだろうか。海流と海上風の向きの不一致から、海面は恐ろしく波立ち、船は安全に航海ができない。日本と朝鮮半島の関係が、決して「英国とフランス」のような関係にならなかった理由がここにある。ドーバー海峡は小舟でも漕ぎ渡ることが可能であったけれども、日本から半島経由で大陸に赴こうとするならば、必ず命がけの覚悟が求められた。このため国家規模の貿易事業こそ行われたが、民間商人たちの自発的な交易活動の蓄積として九州北部の港湾が経済的に栄えることには決してならなかった。同様に朝鮮沿岸にも、南イタリアのナポリ港や北イタリアのジェノバ港のような屈強の商都が成立することがなかった。
・もし太宰府を日本の首都とすれば、大陸や半島の敵勢力は、今の兵庫県あたりで「間接侵略工作」をすすめ、「太宰府政府」を半島と北陸から挟撃しようと企むだろう。あるいは大規模な遠征軍をいきなり山陰海岸へ送り込んで来るかもしれない。そのような企みを未然に粉砕するためには、九州北部はあくまで「アンテナ基地」としておくのが軍事的にも合理的なのであった。
・たとえばソウル市街域を貫流する漢河はかなりの中流まで19世紀の吃水の深い西洋式航洋型帆船であっても、さかのぼって行くことが可能だった。この河川交通の利便性がなかったならば、ソウルにはそもそも何の価値もなく、李氏朝鮮が王都を置こうとこだわる必要も減じたろう。ニューヨークが大西洋の一大商都となったのは、ハドソン川を大型帆船がウェストポイント要塞近くまで楽々と一直線に遡行できたことと、そこより上流も、小型帆船を駆使すればカナダ国境近くまで行き来ができたという恵まれた地理条件があったればこそだ。また米国独立前の最大都市だったフィラデルフィアの人口も、デラウェア川の運輸が支えていた。そしてジョージ・ワシントンの広大な荘園は、チェサピーク湾からポトマック川を遡上して大型航洋帆船がたどり着ける限界の岸辺に開かれていた。ヨーロッパ大陸のライン川(大西洋に注ぐ)、ドナウ川(黒海に注ぐ)などの水量ゆたかでとうとうとした流れについては、ここで筆者が贅言を開陳する必要はないだろう。これら大陸性の大河と比べたなら、いかにも淀川は短く浅い川に過ぎない。が、瀬戸内海全部を「一本の運河」だとみなしたとき、淀川の下流部分の全体は、その大運河の端末の「ターミナル船着場」となっているのである。仁徳天皇の代の前後に、ヤマト政権と大陸諸勢力との間での外交文書使の往来が増加する。これら文書使は大陸から難波津まで必ずしも直航していたのではないにしろ、大小の船舶を乗り継ぎ、早く楽に旅行ができたなら、それに越したことはなかったであろう。
・ヤマト政権の東国征服は、濃尾平野と伊勢湾に沿ってまず順調に進展した。大和から鈴鹿山脈を越え伊勢湾に到達する峠道ルートは、古代のヤマト政権にとって最重要の軍道だった。そこには「鈴鹿関」ができる。琵琶湖の南東岸から伊吹山地を越え美濃に出る峠道ルートが、重要度ではそれに次いだ。今日の関ヶ原にその交通を監視する「不破関」が置かれる。
・関東以上に当時の気候温暖化の恩恵を被っていたのは、陸奥(今の東北地方の一部)と出羽(今の山形県)の農地だった。奥羽地方には素晴らしい開発余地があると全東国人には強く予感されていた。源頼朝の気がかりも、頼朝を頼みに思う気などさらさらない奥州藤原氏の向背にあった。砂金を産出した上に気候の温暖化で農業経済が絶好調だったので、平泉の人口は京都に次いだほどだった。京都の政治司令所(後白河法皇)は、西国武士団と奥州藤原氏とに工作すれば、頼朝の関東武士団も挟撃もできる。頼朝としては、この平泉を征服しないうちは、落ち着いて上洛し、後白河法皇に要求を呑ませることもできかねた。つまりは奥羽からの適切な距離が必要だった。奥羽からの防御がしやすく、また奥羽への出撃もしやすい位置に鎌倉はあった。
・三種の神器が吉野(南朝)から京都(北朝)へ移譲され、「南北朝」動乱の収拾が見えた1392年は1200年までの温暖期が嘘のように、中緯度諸国の気候が寒冷化して久しかった。(その寒冷期は14000年頃まで続く)。東国農業の行く末には、誰もが悲観的になっていた。奥羽方面に「強敵」が出現する可能性は当分ゼロだと信じられた。しかし同じ頃、西国では干ばつが減り、毎年の確実な生産が期待できそうだった。幕府を立ち上げたばかりの足利氏も、その敵にまわろうとする勢力も、西国の経済力をがっちりと自陣に結合させうるかどうかに未来がかかった。それならば「瀬戸内物流ハイウェイ」の東端である近畿に都を置くのが合理的だった。
・織田信長の安土城選定において間違いなく最も考慮された長所は、諸街道の結節点が琵琶湖東岸に形成されていたことだっただろう。北国街道(畿内と越後を結ぶ)、東山道(畿内と陸奥を結ぶ)、東海道、さらに伊勢湾へ抜ける近道も安土城下から分岐していた。もし安土城下が京都に匹敵する人口過密都市に成長したとしても、これだけの物資搬入路があるなら、都市機能はなんの不都合もなく維持されただろう。戦略的にも、織田家の支配領である伊勢、美濃、尾張を「後背補給基地」として、その東にある三河、遠江、駿河は同盟者の徳川家康に保たせておき、主敵となるであろう西国の有力大名たちをこれから逐次屈服させてやろうという長期戦の司令部所在地として安土は京都よりも合理的であった。もし京都に司令部を置いたら、誰か(たとえば北陸から南下した上杉軍)が安土のボトルネックをまんまと占領してしまい、最高司令部(京都)と最大補給基地(東国)の間の連絡が切断されてしまうかもしれないのだ。
・豊臣秀吉の大阪城が狙った機能は誰かの目を驚かせることではなかった。新城郭は天正8年(1580年)に焼かれた石山本願寺の跡地に普請されている。織田信長や徳川家康を悩ませた一向一揆の総本山こそ石山本願寺だった。その最高幹部の顕如は武田信玄とは妻同士が姉妹で、同盟関係だった。信玄は鉄砲時代に自分の領国内では鉛と硝石がほとんど得られないという絶対的な不利を、本願寺によってカバーしようとした。すなわち本願寺をパトロンに仕立て、東アジア各地の海商たちから鉛や硝石を輸入させ、泉州堺港周辺の鍛冶屋に鉄砲を製造させ、紀州の雑賀衆を射手として雇わせ、どの大名にとっても貴重だった弾薬を戦場で惜しみなく射耗させた。これには織田軍といえでもひどく手を焼かされた。当時の本願寺は海軍を自在にあやつる「海の支配者」でもあったのだ。だからまず信長が本願寺跡地に築城して、戦略物資の海外からの輸入を確実に統制しなければならないと決意した。秀吉はその先君の判断を継承した。そのうえで、堺港での対外貿易の実態を承知すればするほど、大阪湾が自分の政権の一大財源になるとも信じられたのだ。かくして、瀬戸内ハイウェイを船でやってくる西国人や明国人に誰が港湾の支配者かを示すようなランドマークが造営された。それが大阪城である。秀吉は敵を滅ぼすよりも活かして利用するタイプの帝国建設者だ。政治的な司令部は伏見からは動かさず、京都朝廷の権威と一体化することの価値もよくわきまえていた。大阪城普請の壮大な事業の人的・物的な動員の模様は、瀬戸内ルートを通じて西国一円に刻々と口コミで伝えられた。いまだ秀吉に恭順する気がなかった四国や九州の有力大名(長曾我部、島津など)も、領民の方が先に「とても上方勢と争っても勝ち目はなさそうだぞ」と印象されてしまえば、決戦に臨もうとする前に足もとの士気と団結は崩されているわけである。そして大阪城が完成した直後、工事と西国遠征にフル動員されていた秀吉方の戦争資源は一転して東国の「小田原攻囲」へ集中された。大阪城は兵糧や弾薬の日本最大の補給倉庫となって、そこから兵たんを支える無数の小舟艇が沿岸航法で相模湾まで物資を届けた。
・1603年当時の武蔵野には雑木林が無限に広がっているように見えただろう。もしそこをすっかり畑にしてしまったとしても、なお秩父山地から河舟で竹木薪炭を集荷することができた。その中間荷捌き点として発達したのが川越市である。(明治8年に鉄道駅を謝絶したことにより衰微する。川越に駅ができたのは大正時代に入ってから)
・幕末には百万都市を維持するために河舟輸送だけではどうにもならなくなっていた。諸国から炭や食料を積んだ船が江戸湾に間断なく入港した。ペリー艦隊は偶然にもこの江戸湾の入口を塞いでしまったことで、江戸幕府に「内陸での持久戦に訴えてでも撃退しよう」という考えを捨てさせた。時間が経てば経つほど、江戸市中では必需物資が絶対的に不足し、それは荷駄や荷車による陸送で補うことはとうてい不可能だったから、人心が幕府を離れて、挙国一致の戦時体制が足元から瓦解してしまうことが分かりきっていたのだ。
・明治元年9月20日には明治帝は「東幸」のため京都を発ち、10月13日には東京城(江戸城)入り。11月19日からは「東京府」が正式にスタートした。天皇は12月にはいったん京都へ帰るものの翌明治2年3月7日に再度東幸。同月28日(旧暦)以降はずっと東京が安定的な御在所となっている。この西から東への大がかりな皇室動座は地政学的にはどんな意味があったのだろうか?明治新政府としては、特に江戸から横浜にかけて各国の外交官や有力な商人たちに、日本国の軍事主権と経済主権がいまや新政府によって確実に掌握されているというところを是非にも見せつける必要があったのだ。「新政府は天皇や朝廷と一体であり、徳川幕府にも実行不能であった関東行幸をさせることすら、このとおり粛々とできてしまう」「わが新政府は旧江戸幕府の全対外債務を東京で継承しますよ」そういったデモンストレーションぐらい、江戸市民を納得させ、外国人を満足させるものはなかった。そのおかげで人々は、これから徳川脱籍軍がいかほど粘り強く抵抗しようとも、日本国の権力が徳川脱籍軍の手に渡るような可能性はゼロなのだと早々と理解した。新政府には確実な「信用」が生まれる。それは列強が露骨な内乱介入を考えることを控えさせるというはかりしれないメリットももたらす。逆に徳川脱籍軍は未来の信用を失うから、誰も彼らに石炭や武器、弾薬、その他の軍需品をツケで売ってやろうとはしなくなる。近代戦争の大前提である「補給」の戦いで、徳川脱籍軍は「敗け」が確定するのだ。
・わが国は新時代に合理的に適応させる目的で、さらに国家中心を東方(北方)の冷涼地へ移すべきなのか?著者思うに、日本の行政首府と最先端大学はぜひとも「熱地圏」からは脱出するべきである。が、別に「ひとかたまりの新都」を定置するというイメージは新時代と整合しない。宇都宮市から青森市までに至る在来鉄道線(ほとんどはJR東北本線)に沿って、細長く「紐状」に、首都機能を分散させるのが適切であろう。今日の核兵器の爆発エネルギーは必ず「三次元的」に放散される。敵の核ミサイルが、同心「円状」に発達したわが大都市の中心部を外すことはまずないだろう。これだと、消防署も、自衛隊基地も、病院も一網打尽にされ、麻痺してしまうから、誰も住民を救えなくなるのだ。しかし、「紐状」に延々と再開発された新都市を一発(もしくは数十発)の水爆で破壊し、殺傷し尽くすことは誰にもできない。「紐状」に点在する消防署や病院などは、爆心点から一定の距離以遠では必ず生き残り、ただちに被災街区に対する救助活動を始動できる。数学的に敵の核兵器の毀害効率をいちばん悪くしてやれるのが、「紐状首都」である。21世紀の重要政策課題として意識すべきだろう。
・672年(寒冷ピーク)の壬申の乱で近畿方面が混乱したときも、西国、特に九州で事変に呼応した動きがあったという記録はない。ちょうど新羅が百済を滅亡させようとする前夜だった。半島側にもそんな余裕がなかったのだ。聖武天皇時代の740年(やはり寒冷期)には、新興漢学エリート官僚たちとの政争に敗れて太宰府へ左遷されていた藤原広嗣ぐが叛乱を起こした。広嗣は新羅や唐と連携するかもしれないと警戒された。しかし、規律厳正な東国軍団が呼び集められて「瀬戸内物流ハイウェイ」経由で派遣されると、烏合の衆に近かった隼人軍は短期間で制圧された。難波津から筑紫への派兵は、半島から九州への派兵よりもずっと早くできたのである。
・ドイツは近世以降に普及した冷涼地向きのイモ「馬鈴薯」(ジャガイモ)のおかげで、近代強国化が実現したともいわれる。日本列島では、その馬鈴薯だけでなく、英国等では栽培が難しい暖地向きの「甘藷」(サツマイモ)も東北以南で栽培が可能であった。どちらも中南米が原産の外来植物であった甘藷と馬鈴薯は、日本国内の西と東の権力バランスにどんな影響を与えただろうか?中央アメリカ高地が原産のサツマイモは、スペイン領時代のフィリピンから明国へ持ち込まれ、そこから沖縄を経由して薩摩に知られたようだ。英国商人が1615年に平戸港にサツマイモを持ち込んだこともわかっている。元禄時代には種子島で大いに栽培されていた。やがて蘭学者の青木昆陽が伊豆諸島に向いた「救荒れ作物」としてサツマイモに着目。関東一円に普及させた。本州では「薩摩芋」と呼び、当の九州では「琉球芋」とか「唐芋(からいも)」と呼んでいたわけはこうした来歴によるものだ。関東諸藩が天保の飢饉(1832年~)を乗り越えられたのはこのサツマイモのおかげであったという。サツマイモは温帯では種芋が大きくなるまでの期間が長いため「裏作」にはならない。しかし連作障害がなく、水田と同じ耕地面積があれば、カロリー・ベースで水稲に匹敵する収量を容易に得られた。他のイモ類より水分が少ないため、掘り出した後も一定期間はそのまま保存できる。まさに南国のシラス台地や火山性離島の住民のために天が与えてくれたような外来新作物であった。
・馬鈴薯の世界的普及の跡をたどるならば、早くは1590年代に南アメリカ原産のナス科の珍植物として欧州へもたらされている。16世紀の「囲いこみ」運動(農地が次々と綿羊牧場に転換される)の帰結として、麦畑を次年に完全休耕させる余地を失った英国人は、蕪や馬鈴薯やクローバーを飼料作物として輪作する方法を編み出した。おかげで英国は小麦を大量に輸出できるようになったうえに人口も2倍に増えたという。農業気候がイングランドより不良なアイルランドでは1780年には家畜ではなく人間が馬鈴薯を主食とするようになった。馬鈴薯ならば、同じ作付け面積で、ライ麦やカラス麦以上の人口を養うことができた。
・概して農民たちはまったく未知の作物にはなかなか手を出したがらぬものだ。そこでドイツ諸邦では君主が率先して国内での馬鈴薯の植え付けを勧奨した。東北諸藩の領主や家老にドイツ諸侯並の研究心と政治的責任感があったのならば、とっくに馬鈴薯は有力な救荒作物とされて、天明の大飢饉(1783~88年)以降の領民の餓死はすべて避けることができたと考えられる。江戸時代の東北の大飢饉は、当事者たちの蒙昧と無気力が招いた「人災」なのである。今、北海道が馬鈴薯の一大産地となっているのを見るにつけ、その感をいっそう強くしている。
・東海道を京都から江戸まで下る間、最大の戦略的ボトルネック(隘路)となるのは箱根峠である。だが箱根峠に至る前にも駿河に2カ所ボトルネックがあった。一つは浜名湖で山側道へ迂回しないで最短コースを急ぐ(舟で湖を渡る)旅客を監視するため、湖の南西に「新居関」が置かれている。もうひとつは由比海岸(由比ヶ浜)だった。ここには関所こそ設けられなかったものの山が海まで迫っていて、通行できる地積がごく狭く迂回路は考えがたい。はるか後年の新幹線時代になっても、東海道本線と新幹線と東名高速道路を、この付近ではほとんど重ねあわせるようにして敷設するほかなかった。ずっと内陸にトンネルを長くうがって「新東名」高速道が開通するまでは、由比は「交通テロ」に脆弱なスポットだともいえた。逆から見れば、近代以前には、東西の往来を監視したり居ながらにして旅行者から全国の情報を聴き集めるためには、由比は屈強の宿場であった。
・全国に300近くもの藩があるなか、なぜ幕末の雄藩として、薩摩・長州だけが浮上したのだろうか?それにはいくつかの理由がある。まず毛利氏の長州も、島津氏の薩摩も、ともに軍事強国でありながら、徳川新体制下で根こそぎまるごとの「転封」や「改易」を免れたことだ。これで領内の一体感を破壊されずに済んだ。それは何世代も後になって有為の人材が登用されやすい環境を準備した。
・毛利氏は、一族である吉川氏が家康と事前に取引をしていて、関ヶ原では戦場のはるか後方に位置し続け、戦闘に加入しなかった(名目は豊臣秀頼の本陣を護衛するため)。おかげで石見銀山の採掘権は幕府に取り上げられたものの、周防国と長門国一円の良港の利用税利権と海峡支配権が従来どおり毛利氏に安堵された。これは「瀬戸内物流ハイウェイ」の通行料金収入を公式にプレゼントされたようなもので、田畑の「石高」などどうでもいいくらいの特権財だった。諸藩や商人が瀬戸内物流ハイウェイを利用する限り、必ずやそれら毛利氏の港湾を利用してカネを落とすのだから。日本国の商品経済が発展するのに比例して、藩の収益も無限に増えるという鉄板の財政基盤であった。
・南西諸島経由で大陸とコネクションを築いていた島津氏は、津島の宗氏と同様に、徳川政権の一方の「外交窓口」としての働きも期待される。島津氏はそれに応え、見返りとして幕府は「密貿易」を黙認した。これによる島津氏の蓄財が巨大であったのだと考えなければ、江戸時代の薩摩藩の人口増加を説明することはできない。しかも、被扶養層である武士階級の人口比率も極めて高い。
・徳川政権が大陸中部以南の商品をオランダ船で輸入してもらうために最初から公認した開港たる「長崎」が薩摩・長州から近く、江戸からはあまりにも遠くに位置したことも、日本の運命に影響した。
・元冦であるが。モンゴル帝国が版図を広げた方式は、独特である。彼らは「降伏しない者は皆殺しにする」と脅迫し、降伏した手近な部族は、そのひとつ外側の部族に対する「奴隷的尖兵」に仕立てて、背中から無慈悲に「督戦」する(後方から監督して戦わせる)。この方式がうまくいくのは、敵勢力が一致団結しておらず「脅し」をかければじきに誰かが裏切ってモンゴル側に寝返ってくれるそのような伝統がある陸続きの地域であった。大陸と半島は昔からそうした風土だったが、日本列島は違った。モンゴルからすると文永も役は「脅し」だった。あれで日本の指導部は降伏すると見込んでいたのだ。ところが日本国内の団結がちっとも崩れないので、次の弘安の役では、大々的に南宋人と高麗人を奴隷的尖兵として動員した。奴隷的尖兵は、相手が強敵の場合は最初から戦意など示さない。すぐ背後からモンゴル兵が監視をしていなければ勝手に脱走したり、敵軍に投降しようとする。だから山陰や北陸に対する放胆な「長駆海上機動」も考えられなかったし、日本列島の広い海岸線にバラバラと上陸させてやるわけにもいかなかった。博多湾上での密集船中泊を選んだのも南風に乗じての逃亡をまとめて監視する必要があると思えたのだろう。しかしモンゴル人には繰船不能となるほどに海が荒れると察知した「奴隷水兵」たちはこれ幸いと夜のうちに船ごと半島方面へ逃げ帰ってしまった。「モンゴル式督戦術」は海上には応用はできかねたのだ。
・敵の元から見た場合、上陸するだけなら日本のどこでもできる。問題はそのあと「大都市の倉庫(食料や軍事備品)」をすぐ確保できるか」や「上陸点に集中してくる守備軍に対抗できうのか」にあったのだ。日本の大都市の倉庫をすぐにも占領できなければ大陸や半島から船で運んできた糧食などはすぐに尽きてしまう。元軍は第1回が3万人、第2回は14万人で押し渡ってきた。コメ「1石」(およそ64kg)が「1人×1年」分の必要量だ。すなわち365人の部隊がいたら64kgの糧食を1日で食いつぶす。3万人だったら1日5t以上も必要なわけだ。それがせめて2週間分ぐらい上陸した海岸の拠点に荷揚げされぬならば、若狭湾に上陸して京阪神まで打通する最短コース作戦にもおぼつかないだろう。つまり73トンとなるが上陸の瞬間からそれをどうやって運搬するのかの大問題に直面してしまうのだ。モンゴル軍は荷担ぎ用の高麗人軍夫を動員できたであろうが、その軍夫も食わねばならないので侵攻部隊の所要補給量は倍増する。そして軍夫は夜間の森林内では簡単に逃亡できた。山陽側では日本軍が舟艇を使って部隊を集中させたい補給することが可能だ。街道が整備されているので馬も使える。日本海岸から南下を図るモンゴル軍は「大都市の倉庫」に到達する前に山道を塞がれ、戦線が膠着する。日本側が2週間支えるだけで、敵軍は飢餓に陥るだろう。あとは時間が勝敗を決定的にしてくれる。若狭湾に橋頭保をつくって略奪持久に励んだとしても逐次に全国から日本軍が集まってきてひしひしと包囲されてしまう。東行する海流と卓越した北西風のため若狭湾から船で出発基地まで撤収することはまずできない。
・結局、九州北部の博多湾に上陸するというプランだけが成算が立ったのである。そこなら多少天候が悪くても揚陸作業は確実にできたし、すぐ近くの太宰府に「大都市の倉庫」があったし、当座は九州在地の日本軍「後備隊」だけが集中してくるだろうから数的にイニシアティブを取りやすく、道路が発達しているから略奪した馬や牛を駆使することも考えられた。不利に陥ったら海路を用いての撤収も確実なオプションにできる。
・1555年にはたった53人の和冦が揚子江河口か南京を襲撃して、明軍5,000人を翻弄しながら悠々と引き揚げている(明国側の記録に残されている)。秀吉の大失策は、直接に明国の海岸を襲ったこれら和冦の成功例をつぶさに研究しないで朝鮮半島の陸路から「唐入り」するのが近道だと錯覚をしたことであった。それは日本人の直感とはうらはらに、いちばん遠回りの道だった。冬季は想像を絶して寒く、補給が続かなくなることが約束されていた不毛のルートだったのだ。道路が劣悪で、沿道には「両班」階級が搾取しまくった残りかすのような貧村しかない。そんな朝鮮半島の実態を承知していたはずの小西行長と宗義智は、この秀吉の致命的な間違いを正してやることができなかった。あるいは秀吉には、遠征の成否はさほど重要でなかったのかもしれない。足利時代末期以降、西国の大名や豪商たちは、めいめいに船舶を建造し、運用して、大陸や南蛮と私に交易し、財力を蓄積していた。これこそが秀吉の脳裏に赤く明滅する「警報ランプ」だったのだ。明朝が基本的に「海禁」(漁業や航海などの規則)政策をとっていたのも沿岸の住民たちが自由に対外交易をするのを許していればその沿岸にやがて有力な「反政府勢力」の地盤がいくつも誕生し、「治安コスト」が国家を破滅させると分かっていたからである。清国が大陸の近海でも獲れるはずの海産物をわざわざ日本から輸入させたのも同じ理由だ。こうした憂慮をまさに秀吉も共有した。ではどうやったら日本全国の私貿易活動を大から小まで完全に停止させるような「いっせい取り締まり」-日本版の海禁政策-が可能になるだろうか?対外渡海遠征を号令すればいいのだ。各地の大名たち、なかんずく西国の諸侯は、この半島攻略作戦のために、すべての船舶と水夫、あるいは財を差しださなくてはならない。秀吉の目を逃れて密貿易など続ける余裕は、津々浦々ありえなくなるはずであった。秀吉は朝鮮出兵によって徳川政権のための「鎖国」-中央政権による統制貿易以外は禁ずる政策-を準備してやったともいえる。はたして明国は、和冦対策と朝鮮出兵とで財政が傾き、ついに北方の騎馬民族を押し戻す体力を喪失した。こう見れば、明にとって代わった清朝もまた、「秀吉がつくってやった」とも評しうるだろう。
・利用できる勢力なら何でも利用する主義であった豊臣秀吉は「バテレン追放令」を発した一方で、ゴア(インド)にあったポルトガル政庁やマニラ(フィリピン)にあったスペイン政庁には入貢を求めた。そして秀吉の死後、徳川家康~秀忠~家光の三代の治世のあいだに、日本国内のキリスト教ブームは逼塞した。プロテスタントのオランダ商館は、仇敵のスペインのカトリック陰謀を悪しざまに日本の要人に告げ口し、自分たちはけっして日本での布教活動をしないことを徳川政権に対して誓い、その約束は最後まで遵守している。なぜ近代以前のわが国は、フィリピンなどとは違い、有益と判断した海外の物資だけを選別的に細々と輸入して、海軍力を有する西洋勢力が押しつけたがった宗教については、いっさいこれを排除するという芸当が可能だったのだろうか?それは我が国が奈良時代以来、大陸からおびただしい量の哲学系および仏教系の「テキスト」を輸入し、咀嚼し、批判し、検討し、取捨選択的に価値を見定めてきた来歴と関係がある。インドの仏典中には先秦時代の大陸の古代の聖人の話など出てこない。同じく「春秋」など漢文の古代史や「詩経」のような古代歌謡集にはインドの神や仏の話は出てこない。どうちらも膨大なテキスト体系を有しており、それぞれ独立に完結した世界観を織り出していた。ここから日本人が推定できたことは、西洋人の宗教もまた、西洋という一地域で完結した信仰であろう。それについて漢訳されたテキストがあれば、面白く研究できるかもしれないが、宣教師はそれを持ち合わせていないという。しかし宣教師たちは、ユニバーサルに応用できる科学や技術も知っているようだ。そちらは幸いにも受領したようではないか・・・。これは本居宣長が「こざかしさ」だとして難じた精神活動かもしれない。しかしその「こざかしさ」のおかげで、日本人は西洋の宗教に対して免疫を持てたのだ。カトリックの宣教師が、「実はこの宇宙はひとりの神が創った」と説いても「ではそのデウス/ヤーウェとやらについて諸仏典はもちろん、古い歴史を伝える「五経」や「史記」などの漢籍、本朝の「日本書紀」「古事記」「風土記」などの中にひとことの言及もないことはどう説明されるのだ?」と日本人なら誰でも疑問に思った。ルイス・フロイスによれば、日本人は西洋の天文学や暦学には深い関心を示したが、「教学」には無関心であった。フロイスが特記しているのは「もしキミたちの神が世界を創ったのなら、悪人までもこしらえているのは不審じゃないか」という日本人の仏教僧たちからのツッコミである。実はこの「よくある質問」には中世キリスト教会が「教父」たちと呼ぶギリシャ語で物事を精緻に考えることのできた偉大なスコラ学者たちが、念入りな答案を用意してくれていた。しかしそれを口頭で日本人に説明するのは至難であった。日本列島からベトナムにかけて、東アジアでは「漢文」が読むテキストとしてとても広く通用するのだから、まず「新約聖書」と「旧約聖書」を漢文に全訳するステップが先行するべきではないのか。そう西洋人が気づいたのはやっと19世紀であった。だがその時点ではもはや、当の西洋人の間でも「聖書」は鵜呑みにはされなくなっていた。
・対馬や壱岐のような離島は、わずかな平時の在地武士だけで外国軍の大敵の上陸を食い止めようとしても絶対に不可能である。領主であることを改易されても困るから、一応の反撃はするのだが、家臣団が文字通り全滅するまで抵抗することもしない。むしろ二度の元寇でも現地のみの外交折衝によって早々と生存を図ったと考えられる。これは当然「正史」には記録されることではない。裏外交史である。だが日本の支配者層は対馬の上層住民が「対半島工作」のエージェントとして役立つことを理解していた。中世から対馬の領主となった宗氏は、織豊政権時代には肥後のキリシタン大名の小西行長と姻戚であった。秀吉は誰にも相談せずに最初に半島遠征を決心したが、その腹案に基づいて、もともと堺の漢方薬輸入商人の出である行長を肥後半国(天草や島原)の領主にしていた。残り半国は加藤清正に与えた。行長・清正の2名が朝鮮出兵で中心的役割を負ったのも偶然ではない。行長と宗義智は、いやでも朝鮮出兵の先鋒と案内役を買ってでなくてはならなかった。小西は一部部隊を壱岐の風本港から直接釜山港へ渡らせて一番乗りの面目を保った。
・沖縄関係の歴史を旧石器時代までさかのぼると、1970年に沖縄本島で出土した1万7千年前の人骨(港川人)を復元したところ、インドネシアのワジャク人に似ていたことが判明している。南西諸島の近海には南から北上する優勢な海流がある。偶然に漂流者や遭難者がそれに乗ってしまえば「稲作を伝えよう」だとか「日本列島に移民しよう」などといった意図は全然なくとも皆、沖縄や九州や山陰・北陸まで自然に運ばれてしまった。もし不運にも南西諸島と九州をすり抜けてしまい、さらに対馬海峡へも入り損ねた場合には、ただ太平洋へ吹き流されて死を待つだけだった。
・薩摩の島津氏は南西諸島すべてが日本国の境域内に含まれ、住民も同じ日本人に他ならぬことを承知していながら、あえて「琉球」は「二流の外国」であるということにし、その「二流の外国」を薩摩藩がうまく服属させているという構図をこしらえた。このようにすると島津氏には別格なステイタスが生じ、秀吉も徳川氏も島津家に対して薩摩からの「転封」を命ずることは難しくなる。そのうえ大陸との間接貿易からの巨利も安全に保証された。島津氏や明朝や清朝に対しての「朝貢貿易」するわけにはいかぬけれども、「琉球王」にそれをさせて薩摩が横から搾取する分には、国際序列上の政治的不利益は生じないのである。
・徳川氏が対外自由貿易を禁じた後も、南西諸島方面海域では大陸の民間船との間で洋上の取引が続いている。なぜ、薩摩だけは続けることができたのだろうか?幕府向けの公式ストーリーとしては「琉球人が密貿易しているらしい。薩摩としてはそれを取り締まって商品を没収するようにしている」とでも口頭説明しておけば、誰にも確かめようはなかった。島津氏は朝廷にも幕閣にも手厚い「付け届け」を欠かさなかった(その財力を背景に通婚政策も進められた)。それらの原資が大陸との直接の密貿易であったとしても「二流外国である琉球人が密貿易しているだけ」という表向きのストーリーが通用する限りにおいては、誰もそれで迷惑する話ではなかっただろう。薩摩が沖縄に力を及ぼしていなければ、英国かフランスが沖縄を軍事占領しようとしたであろうことは間違いない。アヘン戦争(1840~1842)で清国の5港が開放されると、近海の往来船は倍増し、英仏は中間避泊港を欲した。しかし薩摩が南西諸島の「力の真空」を埋めていたおかげで、沖縄は英仏どちらからも占領されることを免れた。
・明治新政府は、薩摩による沖縄住民支配も黙認しなかった。明治5年(1872)には「琉球の王制」を公式に否定。沖縄人民を「二流外人」扱いすることを止めさせ、反動的な西郷隆盛グループ(薩摩武士が全国の庶民を沖縄のように厳格統制する未来を夢見ていた)が西南戦争で一掃された後の明治12年、ついに正式に「日本国沖縄県」とした。それに先立つ明治4年、那覇の漁民が台風のため台湾南部東岸に漂着し、44人が虐殺された事件は、清国に迫って沖縄の日本帰属を公認させるまたとないチャンスだと大久保利通には映った。3年後、外人記者あしらいのうまい西郷従道が、英国の妨害を排除して台湾への膺懲遠征を強行。ドイツ製最新小銃を装備していた現地の1万人以上の清国兵は、3千人足らずの日本軍に蹴散らされた。大久保は北京に乗り込んで清国政府に償金を支払わせ、それによって沖縄が日本国に帰属していることを天下に示したのである。列強もこれで近代日本軍の実力を承認し、幕末からずっと横浜に警備目的で駐留を続けていた英仏両国の軍隊がこの直後に撤兵の運びになった。
・ペリー艦隊(黒船)は、沖縄に貯炭場(蒸気船燃料の補給施設)を設けるという使命も帯びていた。さかのぼると1824年、米国とロシアが条約を結んで、互いの領海で漁労してもよくなった。その結果、日本近海にやってくる米国の「捕鯨船」や「あざらし狩り船」が1840年代には1200艘にも増えていた。やがて米国も対清国貿易に参入。米海員の生命財産の保護のために永久的な「日米和親条約」を結べとペリーは大統領および国務省から命じられた。ペリー提督から米連邦議会への公式報告書である「日本遠征記」によれば、1853年と54年において、沖縄貿易のほとんどが日本船によって行われている。その相手方もすべて日本であった。那覇に入港を許された清国船は一艘もなく、在島中の清国人は密偵につきまとわれ、ののしられ、侮辱されていた。「もしも沖縄が清国の属領ならば、このようなことはないはずだ」とペリーは綴った。
・1790年代後半から1815年(ウォータールーの戦い)までの間、ロシア帝国はナポレオンのフランス軍から少しも注意を逸らすことができなかったという点でナポレオンは我が国の恩人なのだ。1804年に長崎に入港したレザノフが低姿勢だったのも、ロシア政府がヨーロッパ動乱への対応に巻き込まれており、とうてい極東へは軍事力の増援が期待できないことを承知するがゆえだった。1812年にはロシアの古都モスクワまでもが占領されてしまい、「冬将軍」の力を借りてやっとのことフランス軍を撃退した。英国は欧州でロシアやプロイセンに軍資金を与えて反ナポレオン戦争を続行していた一方で、1812年から14年にかけては米国とも再び交戦し、このたびはホワイトハウスを陸戦隊が焼き払うなどやりたい放題だったが、さすがに日本にまで大艦隊を派遣する余裕は残してはいなかった。しかしナポレオン戦争がなければ、英国によるシンガポール確保(1815年)はもっと早まり、その結果アヘン戦争ももっと早く起きたであろう。
・独立戦争後に「連邦の海軍」というものを捨てて省みなかった合衆国議会は1814年の対英敗戦で目が醒め、そこから米海軍が徐々に拡充されはじめた。それがちょうど、スティーヴンソンが蒸気機関車を発明した「動力革命」の黎明期と重なっていた。英国は1842年に南京条約を清国に強いて5港を開かせたうえに、香港を領有した。これで英国は徳川幕府にとっての大きな脅威となった。1852年11月、ペリー提督座乗の蒸気軍艦「ミシシッピ号」が日本を目指してまず米国大西洋岸のノーフォーク軍港を出たとき、すでに英国はボルネオ島東岸も押さえ、シンガポールから香港に至る海域を意のままにすることができた。しかしフランス(ナポレオン三世)やトルコとともに、ロシアの膨張を抑制するためのクリミア戦争が1853年に始まり、極東でも英仏合同艦隊がオホーツク海でロシア艦を追いかけまわしたり、カムチャッカ半島東岸のペトロパヴロフスク軍港を強襲したりという騒動になった。そのさなかになんとか日本を味方につけたいと訪日したプチャーチンが、日本人に対してこわもての態度には出られなかったのも当然だろう。ペリーはこうした国際情勢のタイミングにも恵まれているけれども「日本遠征記」を一読すれば察せられるように、その用意はきわめて周到であり、日本人の感情をいたずらに害しないよう、さりとて徳川幕府から舐められることがないように、全艦隊に終始厳正に規律を守らせた。彼は1904~05年のあのバルチック艦隊よりも長い距離を航海して一艘の事故喪失艦も出していない。この遠征任務のために生まれてきたような男が、自分でプランニングしたミッションを完全にやり遂げた。蒸気式米国艦隊の育ての親であるペリーの個人的才気が、その遠征航路上に米国所有の貯炭場が皆無であるという一大ハンデをも克服し、日本の海岸での戦争に訴えることなく、米国に外交史上の大手柄を挙げさせたのである。
・オランダはフランス軍のため本土を一時占領されて昔の威勢をなくし、長崎出島の商館長は経済的にも軍事的にも鎖国の政策を曲げさせるだけの迫力を持ち得なかった。そのオランダも1856年には日本と「和親条約」を結んでいる。また英国は、米国から少し遅れて同じ年の1854年に、ロシアは1855年に、それぞれ立て続けに日本と「和親条約」を結んでいる。清国はアヘン戦争後も相変わらず「反近代」の儒教国家であり、国と国とは法的に対等であると仮定する西洋近代条約(和親条約)の発想には徹頭徹尾、背を向けていた。
・明治維新の当初において「蝦夷地」(北海道・樺太・千島)を防衛するためには、日本の陸軍が朝鮮半島からポシェット湾(ウラジオストックの100km南西に位置)、さらにニコラエフスク(尼港。アムール川の河口から入った地点にある港湾都市)までも遠征して帝政ロシア陸軍と雌雄を決する必要があると構想することができていたのは西郷隆盛だけであった。これが西郷の「征韓論」のベースだった。「失業士族を元気づけるために韓国と戦争すればよい」などといった短視眼的な思いつきではないのだ。
・日本列島は、朝鮮半島から直接侵略を受けた場合には「一正面作戦」の態勢で防戦することが可能である。これは有史以来、何度も実証された。その場合、北九州が「最前線」となり、本州の西国地方は予備部隊が展開する「第二線」および「後方基地」となり、関東と東北は最も後方の「兵站基地」となって補給品と補充兵員を前線へ送り出す。そのような全国シフトがとられるであろう。ところが、もし帝政ロシア軍が朝鮮半島を征服した後、西方で九州北部に対して渡海侵略を発起すると同時に、北方でも北海道に対して樺太から南侵したらどうなるか?日本は「二正面作戦」の全国シフトを敷かなくてはならなくなってしまう。すなわち関東と近畿がおおもとの「兵站基地」となり、四国中国と東北は「後方基地」となり、九州と北海道の「最前線」を支えなければならない。とはいっても明治前半のわが国の総合国力では、この「二正面」同時の本土防衛戦争はとうてい成算がなかったのだ。それなら、いったいどうすればロシア帝国に対する「二正面防禦」の絶対的な不利に陥らずに済むか?答えが「征韓」であった。
・極東地域に多数の商船隊を維持していないロシアは、沿海州から北海道へ直接上陸作戦をしかけることは不可能であった(この事情は第二次大戦後の冷戦期も同じだった)。沿海州から兵隊だけ船で北海道へ送り届けても、現代戦には勝利できない。上陸後の弾薬消費量は厖大である。その補給が継続できなければ遠征軍は敵中に孤立して降伏するしかなくなる。ロシア軍にとって北海道に対する上陸作戦は、必ず樺太の南端から発起するしかない。樺太は1855年の「日露和親条約」により、日露両国民の雑居地だと定義されたけれども、実態として明治2年(1869)までにロシア人が南端までを制圧した。だから樺太南端での有利な陣地防禦(それが可能であるかぎりはロシア軍は複雑な北海道渡海侵攻は計画しようがないはずだった)は構想しえない。日本は明治8年(1875)の「千島・樺太交換条約」によりその残念な現実を受け入れた。ではロシア帝国は自領である樺太へはどのように物資や増援軍を継続して推進しえたか?これも樺太と沿海州の間が一番狭くなる北樺太の間宮海峡(アムール川の泥の堆積によって水深は非常に浅く、濃霧の名所で、しかも冬は真っ先に流氷で閉ざされる)を、小型の平底船で夏期にシャトリングするしかなかった。その沿海州の渡し場までの物資輸送手段は、夏期の川舟か冬期の馬そりのみである。もし日本軍が夏の間、朝鮮半島からウラジオストックに対して軍事的な圧力を示威することができれば、ロシア軍としては、北樺太への補給推進どころではなくなるであろう。沿海州南部の守備に全シベリアの軍事資源を集中させなくてはならない。それによって日本側とちえは「一正面防禦」の作戦に整理できるわけで、対露国防は現実的かつ合理的に可能になるのである。その反対に、もしも露軍が進駐してしまえば万事は休する。だから西郷隆盛の軍事政策上の「直弟子」だといえた黒田清隆が明治9年に朝鮮に渡り、日本のプレゼンスを画策しようと予備的偵察をしたのだろう。
・近代明治政府の「屯田兵」は、東北6県と等しい面積があるのにまるで住民が希薄な北海道をロシアからどう防衛するかという喫緊の課題と、西郷隆盛の鹿児島士族活用(救済)ポリシーがたまたま一致して実現したものである。
・明治6年に山縣有朋主導で全国に「徴兵令」が発布されたとき、北海道はあまりにも人口が少ないので、徴兵制度の唯一例外地域とするしかなかった。そこで西郷は「開拓使」に子分の黒田清隆を送り込んで実質の「第二陸軍省」にさせ、その開拓使を「薩摩士族の植民地」に変えてしまうという奇策をひねり出した。黒田が屯田兵の創設を建議すると大久保は賛成し、明治8年に札幌の琴似村に最初の屯田兵中隊が置かれた。開拓使と屯田兵の幹部は薩摩士族が独占した。しかし屯田兵の下級兵には、東北の士族が多く志願した。もしもロシア軍が北海道に攻め込んできたときは、屯田兵たちはあくまで持久ゲリラ戦を展開、本州からの逆襲部隊来援を待つ手はずであった。西南戦争では、これら屯田兵部隊も小樽港から汽船で運ばれて熊本戦線に投じられた。ただし将校は交戦を嫌がり、わらじ履きの下士官と兵だけが力闘した。日清戦争では屯田兵を基幹とする臨時第7師団が後詰めとして遼東半島へ送られ、下関会談の間、北京をいつでも占領できるぞという態勢を示威し続けた。明治29年、屯田兵は役割を終え、正式に旭川市に「第七師団司令部」が置かれる。一方の開拓使は明治15年に解消され、明治19年、札幌に「北海道庁」が置かれた。
・帝国陸軍は、「東国の部隊は青森港や新潟港や敦賀港から日本海を渡して輸送コストを下げればよい」という発想を一度も持ったことはなかった。その先の海上輸送中に鈍足の輸送船が拿捕・撃沈されるなどしてしまえば、そこで破綻するしかないのである。だから明治の参謀本部は、大陸向けの海送ルートとしては、最短航路である「関門海峡(下関)~釜山)しか考えなかった。それが対大陸動員計画に一番齟齬を来さないであろう「最適解」だったからだ。日清戦争に動員された広島の「第五師団」は宇品から仁川(インチョン)まで船で40時間あれば到達できたのに、海軍が低速船団の護衛のために軍艦を何日も張り付けておくことを嫌がり、やむなく上陸地を釜山(当時は鉄道未開通地)にするしかなくなっている。ならばいっそ、下関まで鉄道で集めて、そこから乗船させるという手順ではいけなかったのだろうか?それには明らかな不都合があった。敵海軍が優勢で勇敢ならば、関門海峡を直接攻略してくるだろうからだ。
・日清戦争の前夜、日本国内で一個師団を運ぶのに鉄道客車は30両で足りた。輸送スピードは商船とは比べものにならず速い。そこで資本形態が民有・民営であっても、国家火急の要請として、東西方向への鉄道の延伸が促される。「東北本線」は明治24年9月に青森駅まで開通した。これはむしろ北海道での対露有事を考えた補給路だ。陸軍専用埠頭としての宇品築港が竣成したのは明治22年。私鉄の「山陽鉄道」が広島駅(宇品港まで徒歩で6km)まで開通したのは対清開戦が秒読みとなった明治27年6月である。
・明治日本が最も警戒する外国はロシアである。これは地政学上の関係に由来するものだから、基本的に日露が心から友好関係を結ぶことはない。そんな2国が戦争を終結させようとしたとき、割って入ってきたのが米国だ。米国はアジア進出に興味を持っていた。日本にとってロシアを牽制する目的で米国に接近するのは、外交上の得策と思われたがあえてそうしなかった。米露ともに警戒したのである。もしも日本が米国資本を受け入れていたなら、米国は投資が無駄になるような事態を避けただろう。かくして米国は日本の態度を「野心的」とみなし、敵対し始めた。
・明治38年3月、日本陸軍は奉天会戦でロシア陸軍を撃砕できたものの、もはや中隊~小隊を指揮する下級将校を新たに補充することが不可能になっていた。かたや欧州の露軍の兵営には、下級将校はまだいくらでもいたから、ロシア帝国政府は依然として強気であった。同年5月の日本海海戦でロシア海軍(バルティック艦隊)が文字通り消滅すると、アメリカ合衆国大統領セオドア・ローズヴェルトが休戦斡旋に乗り出す。日露両政府がそれに応じ、米国東部のポーツマスにおいて和平交渉が8月から始まった。このおり、米国内の鉄道の半ばを所有し寡占していた業界の風雲児E・H・ハリマン(1848~1909)は8月11日に横浜に上陸し、大連港から奉天駅まで南満州をすでに実力で占領している日本がロシアから正式に利権を譲渡されることが確定的だと思われた「南満州鉄道」の複線化に出資する見返りとして、沿線市場の開発に乗り出したいと桂太郎内閣にもちかけた。これは、「満州市場を米国資本に開放してくれるのならば、日本を後援するぞ」という米国指導者層の大方針に沿ったオファーであった。公式記録こそないけれども、戦費負担に苦しみ抜いていた桂内閣は、その大方針の受け入れを水面下でワシントンへ伝えていた。9月にポーツマスで小村寿太郎によって日露講和条約が調印された。東京の桂はハリマンに「南満州鉄道に関する日米シンジケート組織に対する予備協定覚書」を与えた。ハリマンは満足して10月に帰国の途についた。が、日本に戻った小村がこの話に激しく反対する。桂はハリマンに与えた覚書の破棄を電報しなければならなくなった。戦後、職業外交官にして論筆家の岡崎久彦(1930~2014年)は、このとき日本がハリマン提案を履行していたならば、対露でも対支でも日米はパートナーとなったはずで、日本が対米英戦争など起こす現代史の流れはありえず、第一次大戦以降の世界はまるで違ったものになっていただろう、と総括した。それは本当だろうか?
・南満洲鉄道への米資本参加は諸事情によって謝絶するとしても、満洲や朝鮮、日本の東北地方など他の民間交通インフラなどに関連した開発投資案件で米国資本を導入(利用)する道は、いくらでもあったはずである。もしも内地の東北地方や北海道の経済が日露戦争後に米国資本の力を借りて大発展したならば、誰も米国への移民などを考える必要はなかった。そうした「ウィン・ウィン」の逆提案を、即座にハリマンを通じて提案し返せるようなマクロ経済政策通のキレ者が、明治の日本の指導層に絶望的なまでに欠けていたことをこそ、われわれは真に嘆くべきだろう。
・1945年に北海道の陸軍部隊は、米国が大圏コースの千島列島づたいに侵攻してくるのに備えるため、多数のコンクリート陣地を構築している。しかし米軍は陸海空ともに結局は北からはやって来なかった。この方面の大気が海水温度より極端に低いために濃霧の名所であることと、東から西へと飛ぶ航空機が強い偏西風に正対しなければならないという大きな不利が嫌われたのである。
・戦後のロシア人は、もし択捉島に部宇軍が一大航空基地を整備すると、「オホーツク海はいかなる意味でも、ロシア海軍にとり聖域ではなくなってしまう」と正しく計算している。択捉島から広がる排他的経済水域(EEZ)も巨大だ。だから択捉島を日本に返還する気はモスクワ政府は終始一貫まったくない。かたや国後島の位置条件は、北海道からは多数の軍用ヘリコプターで随時に奇襲侵攻されるのに、逆に樺太からのロシア軍のヘリ増援は、巨利があるために微弱とならざるをえない。ロシア政府は有事には国後島を保持することはできないと理解している。EEZも狭い。よって平時の日露交渉の余地も国後島の帰属に関しては十分にある。もっとも日本政府がこの地政学に無頓着で、道東駐屯の陸上自衛隊第5師団をヘリコプター師団化するでもなく、たんにスリム化して旅団化(2004年)してしまったことにより、ロシア政府は「日本は国後島奪還には関心がない」というメッセージを受け取り現在に至っている。
・現在の我が国は、中華人民共和国とロシア連邦を筆頭に「近代自由主義」の価値観を共有しない厄介な諸国とばかり隣り合わせている。その過半が核武装国だ。しかし幸運にも、近代自由主義の価値観を持ち、希有な軍事超大国であるアメリカ合衆国と正規の軍事同盟条約を結んでいるおかげで、私たちの日本国内には、他の近隣諸国民が享受しえない自由が存在する。こんな本を一私人である著者が書いたり、出版したりできるのもその自由の好例と思う。ロシアは米国に次ぐ核兵器大国だが、「原油か天然ガスか武器しか輸出するものがない」という貿易収支上の悩みが深い。商人の私益が民主的な法律と行政と近代的司法によって守られないという病的な社会構造が、これからもロシアを貧乏で不自由で、不機嫌で、暴力的な人々が暮らす国にとどめておくであろう。
・私たち日本人は米軍が韓国に駐留し、実質「占領」しているがゆえに、韓国政府が日本に戦争をしかけることができないのだという「大構造」があることを片時も忘れてはならない。じつは、戦後の在韓米軍こそが、戦前の日本の地政学的な悩みを忘れさせてくれているのだ。
・中華人民共和国はロシアと違って石油エネルギーを国内で自給できないという大弱点を抱えている。そのためにボルネオ島沖やサハリン沖をうかがっているが、その広義の侵略政策の行き着く先は「大東亜共栄圏」を叫んだ戦前の日本とほぼ同じであろう。
良かった本まとめ(2017年下半期)
<今日の独り言>
Twitterをご覧ください!フォローをよろしくお願いします。
 「デジタルメモ「ポメラ」DM200」の購入はコチラ
「デジタルメモ「ポメラ」DM200」の購入はコチラ 














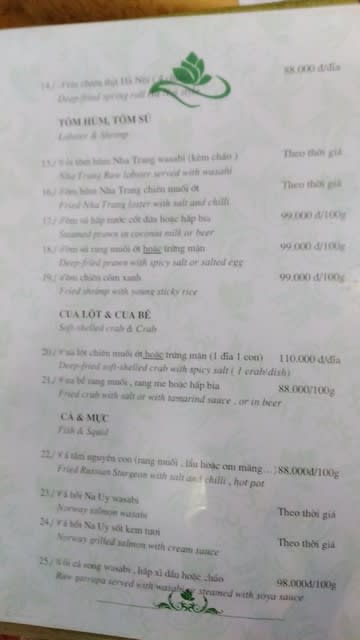































 「母乳育児」の購入はコチラ
「母乳育児」の購入はコチラ