 「中国古典百言百話 老子・荘子」の購入はコチラ
「中国古典百言百話 老子・荘子」の購入はコチラ
「中国古典百言百話 老子・荘子」という本は、中国古典の「老子・荘子」の中から200について分かりやすく説明したものです。
世界史(特に中国)の歴史を学んだ方は記憶にあるかと思いますが、あの老荘思想(ろうそうしそう)の「老子・荘子」となります^_^)
「老子」とは、全文5400字、81章に分かれているもので、中国の古典のなかでは、もっとも短い方に属するようです。
一人の手に成ったものではなく、思想傾向を同じくする不特定多数の人々によってまとめられたもののようです。
本書では全200のうち、70(百言の前半35、百話の前半35)が「老子」から選んだとのことです。
「荘子」とは、全文65000余字、内篇7篇、外篇15篇、雑篇11篇から成り、荘周自身の手に成るのは内篇だけで、外篇、雑篇は後人の仮託と見る説が有力とのことです。
本書では全200のうち130(百言の後半65、百話の後半65)が「荘子」から選んだとのことです。
「老子」によれば、万物の根源に、万物を万物として成り立たせているものが「道」であり、「道」は無としか言いようのない存在だが、それがあることによって初めて万物が生み出されるようです。
しかし「道」はそれほど大きな働きをしながらいささかも自己主張しないもので、まさしく無心、無欲、無為、柔弱、謙虚、質朴、控え目など「無為自然」の徳を体現しているもののようです。
人間は、こういった「道」のありようを自分のものにすることができるなら、厳しい現実をしなやかに生き抜くことができるとのことです。
この「道」を自分のものにしたいですね。
これに対し、「荘子」もまた「道」の存在を認めていますが、目指す方向は、老子とは少し異なっているようです。
「道」という大きな観点に立てば、善だ悪だ、是だ非だと言っても、本質的な違いはないのですが、世間の人間は世俗の価値観に災いされてつまらないことにこだわり、あくせくと生きているもののようです。
せっかくの人生だから、世俗の価値観を超越して、もっと伸びやかに、自由に生きようではないかというのが荘子の考えのようです。
ある意味で「荘子」は、超越の思想であり、また自由人の思想だと言えるようです。
それから、これら「老子」「荘子」が原点の有名なことわざ等も結構あるようです。
たとえば、「和光同塵」「上善如水」「大器晩成」「朝三暮四」「無用の用」「明鏡止水」「莫逆の友」などです。
勉強になりますね。
「中国古典百言百話 老子・荘子」という本は、老荘思想や人生の勉強になるだけでなく、いくつかのことわざの原点がこの老子・荘子にあるということも分かり、とてもオススメです!
以下はこの本のポイント等です。
・聖人は無為の事に居り、不言の教えを行う。
老子によれば、「聖人」とは「道」を体得した人物である。おおむね、理想的な為政者といった意味合いで使われていることが多い。老子のいう「道」は、万物の根源にあって万物を支配している。それほど大きな働きをしておりながら、何ひとつ積極的な働きかけをしない。いわゆる「無為」であり、「不言」なのだ。したがって、「道」を体得した聖人も、おのずか「無為」であり、「不言」にならざるをえない。それを語っているのが、「聖人は無為の事に居り、不言の教えを行う」ということばである。老子によれば、それだからこそかえって大きな働きが約束されるのだという。では、「無為」や「不言」を、もう少し具体的に言えばどういうことになるのか。老子はさらにことばを続けて、こう語っている。「万物を自然の成長にまかせて、みずか手を加えない。手を貸しても見返りを期待しない。功績を立てても鼻にかけない。だから、いつまでもその地位を失わないのである」これが聖人のありようなのだという。私どもも、こんな生き方を心がければ、老子のいう聖人の水準に近づくことができるのかもしれない。
・生じて有せず、長じて宰せず、これを玄徳と謂う
「玄徳」とは、「道」がそなえている大いなる徳である。それは、「生むけれども所有せず、育てるけれども支配しない」、そういう広大無辺なものなのだという。では、「玄徳」とは具体的にどういうことなのか。老子は、こう呼びかけている。「しっかりと自分を見つめ、”無為”の道を守っているだろうか。赤子のように、たくましく柔軟に生きているだろうか。いささかの汚点もなく、心を洗い清めているだろうか。人民を愛し国を治めるに当たって、才知を振り回していないだろうか。自然の移り変わりに対して、女性のように控え目な対応をしているだろうか。すばらしい知謀に恵まれながら、その知謀をひけらかしてはいないだろうか」この呼びかけに対して、「イエス」と答えることができるようなら、それがすなわち「玄徳」ということになるらしい。つまりは、柔軟、無心、謙虚、控え目といったことである。これらの徳を身につけるなら、どんな状況の下でも、しなやかに生きていくことができるのだという。
・唯と呵と、その相去ること幾何ぞ。美と悪と、その相去ること何若。
広大無辺な「道」に目覚めた人物から見ると、この世の中のあらゆる事物、あらゆる価値観はすべて相対的なものにすぎず、固執するに値しないのだという。だから、老子は、「”ハイ”と”ウン”とに、どれほどの違いがあるというのか。善と悪とに、どれほどの違いがあるというのか」と、問いかけているのだ。「唯」とは、丁寧な返事、「呵」とは、ぞんざいな返事である。たしかに老子の語るとおりであろう。少なくともそこに一面の真実があることを認めざるをえない。だが、私どもの現実はどうか。残念ながら、つまらないことに目くじらを立てて、ああでもない、こうでもない、と騒ぎまわっている。白だ、黒だ、勝った、負けた、と血まなこになっている。過ぎ去ってみると、なにか空しい。できれば、白だ、黒だと走り回っている自分のなかに、それを客観的に見つめているもう一人の自分を持ちたいところだ。そうすれば、老子のいうレベルに一歩近づくことができるであろう。また、それだけゆとりのある生き方ができるし、人間の器を一回り大きくすることができるかもしれない。
・希言は自然なり
「希言」とは、おしゃべりでないこと、つまり、寡黙という意味である。弁解も宣伝もしない、そういう寡黙さこそ自然のありようであって、無為自然の「道」にも合致しているのだという。これもまた饒舌の害を戒めたことばであるが、老子は自然を引き合いに出して、こうダメを押している。「疾風といえども半日も吹き荒れることはないし、豪雨といえども一日中降り続くことはない。誰がそれを司っているのかといえば、天地である。その天地でさえ、不自然を長続きさせることはできないのだ。まして、人間の賢しらなど長続きするわけがないではないか」たしかに、わざとらしさは長続きしない。必ずどこかでボロを出す。おしゃべりも、そういった例の一つなのかもしれない。人を競っとくする場合でも、ことばを尽くして説明し、なんとか相手に納得してもらえる。むろん、これも立派な説得には違いない。だが、それよりもはるかに勝っているのが、無言の説得だ。あえて言葉など使わなくても、自ずから相手に納得してもらえる、そんな説得ができたら最高ではないか。そのためには、こちらにそれなりの「徳」が備わっていなければならないことは、言うまでもない。
・軽ければ則ち本を失い、さわがしければ則ち君を失う。
これは、トップやリーダーのあり方について語ったことばである。「軽々しく振る舞えば、国政を破綻させ、やたらに動けば、王位まで失ってしまう」のだという。「論語」にも、「君子重からざれば、威あらず」とあるが、ここで老子が語っているのも、まったく同じ趣旨である。トップやリーダーというのは、組織の末端まで細かく気を配りながら、そんな素振りはいささかも表に出さず、黙ってにらみをきかせえいるのが理想なあり方だ。そうあってこそ、初めて威令が行われるのである。しょっちゅう本拠を留守にして、じたばた動き回っていたのでは、組織に対する抑えがきかなくなる。そうなると、自分の地位を維持することすら難しくなるかもしれない。むろん、トップやリーダーは、時には、自ら洗浄に出向いて陣頭指揮し、率先垂範で事に対処しなければならないこともある。だが、そんなときでも、「ゆったりと構えて心を動かすな」と、老子は警告している。常に冷静な態度で、全局の動きをにらんでいなければならないのだ。軽はずみな行動をしたのでは、たちまち部下の信頼を失ってしまう。
・人を知る者は智なり。自ら知る者は明なり。
訳せば、「人を知る者はせいぜい智者の水準にすぎない。自分を知る者こそ明知の人である」となる。「智」も「明」も同じような意味で、深い読みのできる能力を指している。洞察力と言ってもよい。しかし、二つを比べた場合、「智」よりも「明」のほうが、一段と深い能力であることは言うまでもない。なぜなら、人を知るよりも自分を知るほうが、はるかに難しいからで。私どもはよく、自分のことは棚に上げて、人のことをああでもない、こうでもないとあげつらう。人の欠点はよく見えるが、その割に自分の欠点は見えないのである。それだけに自分を知ることは難しい。「孫子」の兵法に、「彼を知り己を知れば、百戦して殆うからず」とある。戦いに勝つためには、敵を知るだけではまだ不十分で、さらに自分を知らなければならない。これは、戦いだけではなく、人生の厳しい局面を切り抜けていくためにも、まったく同じことが言えるであろう。そのためには、「智」はもとよりのこと、できれば「明」を身につけておく必要がある。
・大方は隅なし。大器は晩成す。大音は希声なり。大象は無形なり。
「大器晩成」ということばの出典が、これである。この一節を訳してみると、次のようになる。「この上なく大きい四角は、角ばって見えない。この上なく大きい器は、完成するのもまた遅い。この上なく大きい音は、耳で聞きとることができない。この上なく大きい形は目で見ることができない」たとえば地球である。丸い形をしているのだが、なにしろ大きいので、平面や直線にしか見えない。小高い丘にでも登って水平線に目をこらすと、かすかに丸みが感得される。大きい円とは、そういうものであろう。また、「天啓のように響く」ということばがある。天啓とは本来大きな音のはずだが、実際は声なき声のようなもので、こちらがその気になって耳をすまさなければ聞こえてこない。老子によれば、「道」もまたそういう大きな存在なのだという。だから、こちらがその気になって耳を澄まし、目を見開かなければ、捉えることができないのである。人間もまた、一見凡庸そうな人物のほうが可能性を秘めている。ただし、「大器晩成」と言っても、努力を惜しんだのではいつまでも未完の大器として終わってしまうかもしれない。
・至人は己なし。神人は功なし。聖人は名なし。
なにものにもとらわれず悠々と大空を舞う大鵬。それを見て笑う地上のセミやコバトたち。セミやコバトたちは、明らかに世俗の価値観を代表しているのに対し、大鵬はそういう一切の価値観から超越した姿を示している。大鵬のありようを体現しているのが、ここでいう至人とか神人とか聖人である。いずれも、荘子が目指している理想の人間像にほkならない。では、彼らのありようはどうなのかといえば、「至人は自分にこだわらない。神人は功績にとらわれない。聖人は名誉に関心を示さない」のだという。世俗の世界に生きる自分、そして功績や名誉。そういうものは、荘子のいう、より大きな立場に立つことができれば、それこそ「小せぇ、小せぇ」ということになり、固執するに値しないものかもしれない。だが、そう言われても、私ども凡人は、なかなかそういう水準には至りえない。いつも厳しい現実に振り回されて、ああでもない、こうでもないと一喜一憂しているのが、私どもの現実の姿である。だが、ときどき荘子の世界に思いをはせるだけでも、ずいぶんと生き方の幅が広がっていくのではないだろうか。
・時に安んじて順に処れば、哀楽入る能わず。
「時のめぐり合わせに身をまかせ、自然の流れに従って生きるなら、悲しみにも喜びにも心をかき乱されることはない」。そういう生き方こそ理想なのだ、というのである。この世に生まれてくるのも自然の摂理なら、この世から去って行くのも自然の摂理である。そのように達観できるなら、喜ぶこともないし悲しむこともない。こういう淡々とした生き方こそが、生を全うする道なのだという。
・鑑明らかなれば即ち塵垢止まらず、止まれば即ち明らかならざるなり。
「きらきら光っている鏡は、ほこりを寄せつけない。ほこりがつけば光が失われる」といった意味になるかもしれない。「荘子」にはさらに、「人は流水に鑑みるなくして、止水に鑑みる」ということばがある。流水は人の姿を映し出さない。映し出してくれるのは、「止水」、つまり静止している水である。だから、自分の姿を見ようとするときは、流水ではなく止水を利用する、というのである。この二つの言葉から、有名な「明鏡止水」という四字句が生まれた。要するに、虚心とか無心の境地といった意味である。人生には、何度か重要な決断を下さざるを得ない場合がある。そんなとき、徹底的に事情を調査することはもちろんであるが、最後の段階では、そえらを突き抜けて「明鏡止水」の心境になることが望まれる。なんとしても成功させたいとか、あるいは、これを成功させたらどうなるかとか、そんな雑念が湧いてくると、成功しそうなものまで成功しなくなる。あくまでも、「明鏡止水」で対処したい。
・含徳の厚きは、赤子に比す。
老子は、「道」と一体になった理想の境地を、しばしば赤ん坊にたとえている。このことばもその一つで、「深い徳を秘めた人物は、赤ん坊のようなものだ」というのである。「赤ん坊は、害虫にも刺されず、猛禽や猛獣にも襲われない。骨は脆く体は柔らかいのに、こぶしは固く握りしめているし、男女の交わりも知らないのに、性器は力強く勃起している。性器が充満している証拠である。一日中泣き叫んでも声がかれないのは、調和がとれている証拠である。調和がとれているのは、”道”と合致しているからだ」老子の主張を要約してみると、要するに次のようなことであるらしい。
1、無心である。
1、柔軟である。
1、活力がある。
1、調和がとれている。
1、ことばを発しない。
これらの点を総合して、赤ん坊のあり方こそ理想に近いと語っているのだ。
・禍は福のよる所、福は禍の伏す所なり。
「禍福は糾える縄の如し」という諺がある。老子のこの言葉も、表現こそ違っているが、同じようなことを語っているのである。禍のなかに福が含まれ、福のなかに禍の芽が宿されていて、先行きどう転ぶかわからないのだという。まさしく「人間万事塞翁が馬」である。確かに人生とはそういうものであるらしい。だとすれば、当然、次のような生き方が導かれてくるだろう。まず、なにか失敗をしでかしたとか調子がどん底だとか、そういったときがだれの人生にも必ずある。しかし、禍は福のよる所だとすれば、落胆することもないし、あきらめる必要もない。「禍を転じて福となす」ことは可能であるし、また、そういう努力が望まれるということだ。逆に、今は絶好調、世の中のすべてのことがバラ色に見えてくる、といったときも、必ず一度や二度は訪れてくる。しかし、福は禍の伏す所だとすれば、一瞬の油断も許されない。そんなときこそ、むしろいっそう気持ちを引き締めて、福を持続させることが望まれるであろう。そんな生き方を心がければ、人生という長いレースを完走できるに違いない。
・怨みに報いるに徳を以ってす。
誰でも一度や二度は、周りの人々から手ひどい仕打ちを受けて、はらわたの煮えくりかえるような思いをしているはずである。そんなとき、あなたなら、どう対処するだろうか。受けた怨みをそのまま相手にぶつけ返す。こんな人もいないではないが、人間学の上から言うと、いささか単純だという気がしないでもない。多くの人は、多分、怒りをむりやり押し殺して、その場を収めるのではないか。なかなか立派だとは言えるが、しかし、怨みの気持ちは、後まで尾を引いて残るに違いない。老子に言わせれば、そんな場合、受けた怨みに対して「徳」(善行)でもってお返しするのがいちばん理想的なのだという。たとえば、Aさんに怨みがあるとする。そんなとき、第三者から「Aさんとはどんな人ですか」とたずねられると、つい相手の欠点をあげつらいたくなるのが人情である。しかし、それはまだ人間が至らない証拠であって、人間のできた人は、そんな場合でも、怨みにこだわらず、「ああ、Aさんは立派な人ですよ」と、相手を褒めてやる。こういう対応の仕方が「徳」をもって報いるということであるらしい。これは人間関係を円滑にするコツであるが、老子に言わせれば、「道」を体得した人物にして、初めてそれが可能なのだという。
・天下の難きは易きより作り、天下の大は細より作る。
「いかなる困難も容易なことから生じ、いかなる大事も些細なことから始まる」のだという。つまり、大きな仕事を成し遂げるためには、些細なことだからといって手を抜いてはならない、些細なことの積み重ねがやがて大きな仕事に結びついていく、というのだ。逆に言えば、最初から一発勝負に出たり、一山当ててやろうと思っても、うまくいくはずがない。一見、平凡そうな毎日の仕事を一歩一歩やり遂げていくことによって、初めて大きな展望も開けてくるのだという。確かに、その通りであるにちがいない。私どもの場合は、ついこういう原理原則を忘れがちである。目の前の仕事をなおざりにして一攫千金を夢みたり、基礎を忘れて一足とびに応用問題を解こうとしたりする。老子に言わせれば、そんなことはもともと無理なのだという。なるほど、毎日の仕事というのは、多くの場合、単調で平板である。誰だって、うんざりしてくる違いない。だが、そえをきちんと処理していかなかったら、将来の展望も開けてこないのである。老子は、「”道”を体得した聖人は、初めから大事を成し遂げようとしない。だから成し遂げることができるのだ」とダメを押している。
・禍は敵を無みするより大なるはなく、敵を無みするは吾が宝を失うに近し。
「敵を軽視してしゃにむに攻撃を加えるほど愚かなことはない。そんなことをすれば国を破滅させてしまうのがオチだ」というのである。「孫子」の兵法の基本原則にも、「勝算なきは戦うなかれ」とある。勝つ見込みのない戦はするな、戦をしようとするからには、これなら勝てるというメドをつけてからやれ、というのだ。勝算もないのに、それ行け、やれ行けとやったのでは、命がいくらあっても足りない。自分の命を落とすばかりか、国まで滅ぼしてしまう。では、勝算がなかったらどうするのか。いったん後ろに退いて戦力を温存し、情勢の変化を待つのである。情勢は必ず変化する。次の機会を待て、と「孫子」は言うのである。老子の言わんとしていることも、基本的にはこれに近い。敵を軽視するのは、①杜撰な戦力分析、②一面的、主観的な判断、この2つからくる自信過剰に基づいている。戦いに際して、自信を持つのはよい。ただし、根拠のない自信では困るのだ。我に利あらずと見たら、あえて後ろに退く勇気をもちたい。
・知りて知らずとするは、尚なり。知らずして知れりとするは、病なり。
「知っているのに知らないふりをする。これが最高のあり方だ。知りもしないのに知ったかぶりをする。これは重大な欠点だ」というのである。孔子は、同じ「知る」ということについて、「これを知るをこれを知るとなし、知らざるを知らずとなせ。これ知るなり」と「論語」の中で語っている。こういう態度によって人間の認識が進み、自分を高めることができるというのが孔子の立場であった。これは、あくまでも理性的な態度だと言ってよい。これに対し、「知りて知らず」とする老子の主張はずいぶんと老獪であって、厳しい現実を生きていく処世の知恵としても活用することができる。たとえば、上司として部下に臨む場合である。部下の能力や生活ぶりを一応把握しておかなければ、上司としての責任が果たせない。だが、それを表に出したのでは帳消しである。「知りて知らず」とするところに、無言の圧力が生じてくることを忘れてはならない。人生の様々な局面で、「知りて知らず」を効果的に使えるようになれば、もはや人生の達人といってよいだろう。
・天網恢恢、疎にして失わず。
「天網」とは、天が悪人を捕らえるために張りめぐらした網。「恢恢」とは、広く大きいこと。「疎にして失わず」とは、網の目は粗いが取り逃すことはないという意味である。中国人は、神をもたない民族だといわれる。その彼らが神に代わって心の拠り所としてきたのが、「天」であり「天道」であった。この「天」の働きたるや、まことに測りがたいものがあって、常に高い所から人間世界を見下ろし、善を助け悪を懲らしているのだという。老子は、こうも語っている。「天の道は、戦わないで勝利を収め、命令しないでも服従され、呼び寄せなくても向こうからやって来、のんびり構えていながら深い謀を秘めている」現実の世界は、一見、悪が栄え、善がしいたげられているように思われないでもない。「悪い奴ほどよく眠る」などともいわれる。だが、それは一時的なことで、長い目で見ると、天は必ず善に味方して悪を懲らし、帳尻を合わせてくれのだという。老子もまたそれを確信していた。この言葉は、特に厳しい現実を生きてきた社会的弱者にとって、大きな心の支えであったに違いない。
・合すれば則ち離れ、成れば則ち破れ、鋭ければ則ち挫け、尊ければ則ちかたむき、為すあれば則ちそこなわれ、賢なれば則ち謀られ、不肖なれば則ち欺かる。
合したかとみると離れ去り、成功したかとみると失敗に見舞われる。鋭いものはたちまち折られ、地位の高いものはたちまち転落する。やる気を起こせば妨害され、賢ければ足を引っ張られ、愚かであればだまされる。これが私どもの生きている人間社会の現実なのだという。この世の中のすべてのものは、常に変化して止まない。一定不変のものなど、なに一つないのだ。一年、二年では、まだ変化は目立たないかもしれない。しかし、10年経てば随分と変わっており、30年もたてば、うたた今昔の感にたえない、といったことにもなりかねない。だとすれば、昇進したからといって有頂天になることもないし、左遷されたからといって悲しむこともない。変化に一喜一憂するのは、あまり賢明な生き方ではない、ということになる。とはいえ、現実の変化に振り回されながら、あっぷあっぷ生きていかざるをえないのが私どもの人生であろう。だが、そうでありながらも、そんな自分を醒めた目で冷静に見つめているもう一人の自分がいれば、もう少しゆとりのある生き方ができるかもしれない。
・人、天地の間に生くるは、白駒のげきを過ぐるが若く、忽然たるのみ。
「白駒」は、白い馬。「げき」は、隙と同じ、戸の隙間という意味である。ちなみに、「人生は白駒の隙を過ぐるが如し」という有名な言葉は、「荘子」のこの文章が出典となっている。20代のころは、人生はこれから、まだまだ先があると、誰でも思っている。ところが50を過ぎて自分の人生を振り返ってみると、過ぎ去った日々の方が遙かに長くなっていることに気づいて、思わず愕然とさせられる。それがまた60代、70代ともなれば、あっという間だったなあという思いは、ますます強くなるに違いない。「荘子」によれば、人間がこの世にあるのはあくまでも仮の姿、変化のなかの一つの過程に過ぎない。だから、生まれてきたからといって喜ぶこともないし、死んでいくからといって悲しむこともないのだという。なかなかそこまで達観しきれない私どもとしては、せっかく与えられたこの短い人生、せめて自分なりに納得のできる生き方をしたいところだ。そうでないと、死んでも死にきれない思いが残るのではないか。
・行きて之く所を知らず、居りて為す所を知らず、物と委蛇してその波を同じくす。これ衛生の経のみ。
「衛生」とは、養生と同じ。与えられた生を全うすること。「経」とは、不変の真理。それはなにかというと、次のようなことだという。「歩いていても、どこに向かうかという目的意識を持たないし、座っていても何をしようかという思慮分別を持たない。ただ、外界の動きに身をゆだねて、少しも逆らわない」ある大いなるものの意志を受け入れ、自然のリズムに合わせて生きていく、そんな生き方を指しているらしい。これをもっと具体的に言うと、どうなるか。「荘子」は、次のようなことを指摘している。
1、自分のペースをしっかりと守って、それを見失わないようにすること。
1、占いなどに頼らなくても、何が吉で何が凶であるか、根本の原理を把握していること。
1、自分の能力の限界をよく心得て、危険なことに手を出さないこと。
1、人を責めたり人に頼ったりしないで、あくまでも自分に頼ること。
1、こだわりを捨てて、愚者のように無欲になり、赤ん坊のように無心になること。
・人に八しあり。
人間には、次の8つの欠点があるのだという。
1、自分がやるべき仕事でもないのに、余計な手出しをする。つまりは出しゃばりである。
2、聞かれもしないのに、こちらからしゃしゃり出て意見を述べる。つまりはおべんちゃらである。
3、相手の意を迎えて調子を合わせる。つまりはおべっかである。
4、是非のケジメなどおかまいなしにしゃべりまくる。つまりはへつらいである。
5、なにかといえば他人の悪口をいいたがる。つまりはねたみである。
6、他人を仲違いさせ、親しい者同士を離間させる。
7、悪を誉め善をけなして相手をだめにする。
8、善悪にはおかまいなしに愛想をふりまいて相手におもねる。
・事に四患あり。
事に当たって、陥りやすい欠点が4つあるのだという。
1、しばしば重大問題に手をつけたがり、やたらに変更を加えて、自分の功名手柄にしたがること。
2、悪知恵を働かせてやりたい放題なことをし、他人を侵害して自分の利益をはかること
3、過ちだとわかっても改めようとせず、忠告されるといっそうむきになって過ちを重ねること
4、相手も自分と同じことをしていれば素晴らしいと誉め、違ったことをしていれば詰まらないと言ってけなすこと。
・人の心は山川よりも険しく、天を知るよりも難し。
なぜ人の心を知るのは天を知るよりも難しいのか。天には春夏秋冬、朝と晩といった具合に一定の周期があるのに対して、人間は容貌を飾って心の中を外に見せないからだという。だが、そんな人間でも、相手を見分ける方法があるのだとして、「荘子」は次の9項目をあげている。
1、遠方で仕事をやらせてみて、相手の忠誠心をためしてみる。
2、近くで仕事をやらせてみて、相手の人柄を観察する。
3、面倒な仕事を担当させてみて、相手の能力を試してみる。
4、思いがけない質問をしてみて、相手の見識を試してみる
5、慌ただしく約束を取り交わして、それを守るかどうかを試してみる
6、お金を与えてみて、どの程度思いやりがあるかを観察する。
7、危険に陥ったことを知らせて、相手の節操を試してみる。
8、酒に酔わせてみて、社会人としてのケジメのつけ方を観察する。
9、女と一緒にしてみて、どの程度色を好むかを観察する。
・窮に八極あり。達に三必あり。
人間が窮地に立たされる原因となるものが8つ、逆に栄達の条件となるものが3つあるのだという。まず、窮地に立たされる原因であるが、それは次の8項目である。
①姿が美しいこと
②立派なひげをたくわえていること
③上背があること
④恰幅がよいこと
⑤威勢がよいこと
⑥華々しいこと
⑦勇気があること
⑧決断力に富んでいること
この8項目は、普通は美点や長所とみなされているが、そのためにかえって窮地に立たされることが多いのだという。
また、栄達を保証する3つの条件とは次のようなものである。
1、自分に固執しないで相手の意向に従っていくこと。
2、対象世界に調子を合わせて無理をしないこと。
3、臆病者の精神に徹し慎重を旨とすること。
この3つの条件は、いずれも荘子的世界の処世法であることは言うまでもない。
面白かった本まとめ(2014年上半期)
<今日の独り言>
Twitterをご覧ください!フォローをよろしくお願いします。












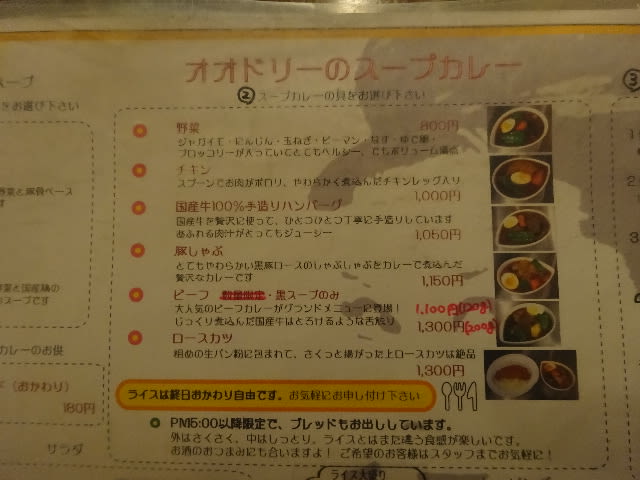












 「中国古典百言百話 老子・荘子」の購入はコチラ
「中国古典百言百話 老子・荘子」の購入はコチラ 








 「ビジュアル世界大地図」の購入はコチラ
「ビジュアル世界大地図」の購入はコチラ 


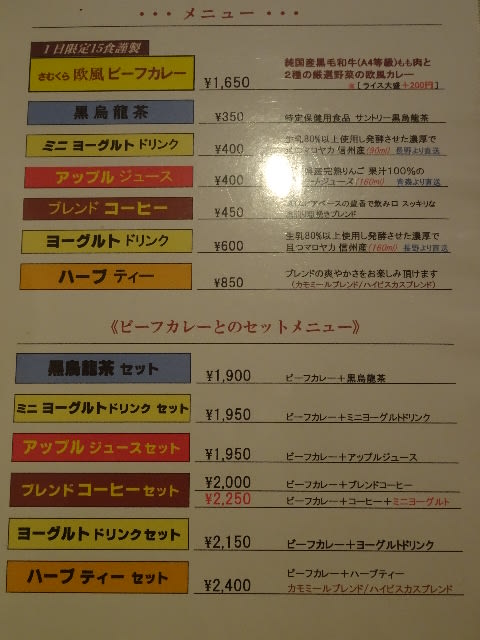


 「脳科学を活用して平凡から非凡へ」の購入はコチラ
「脳科学を活用して平凡から非凡へ」の購入はコチラ 





















