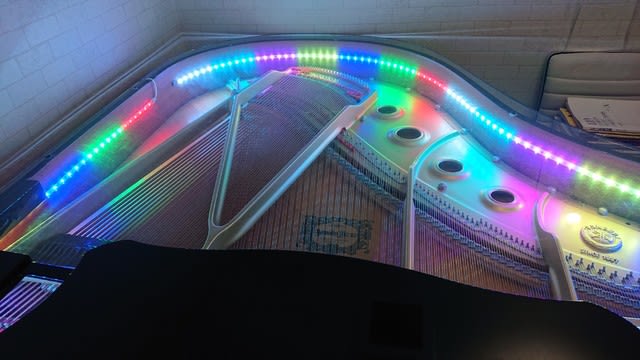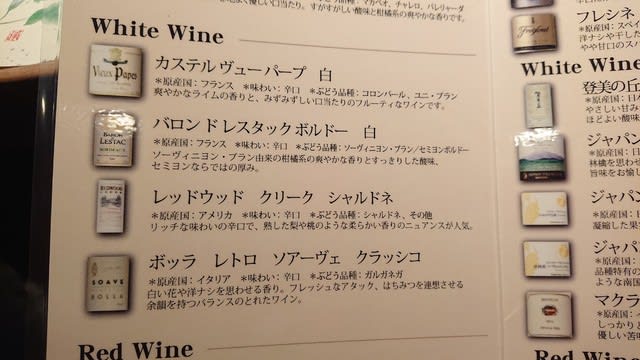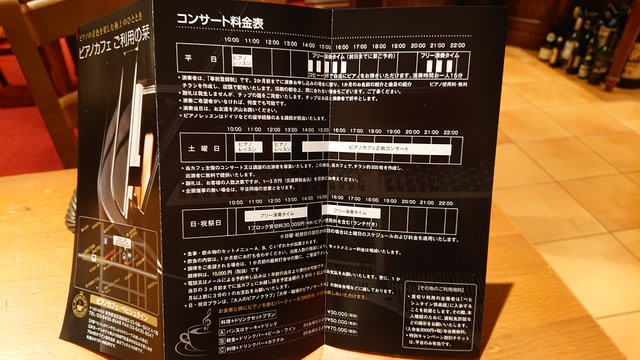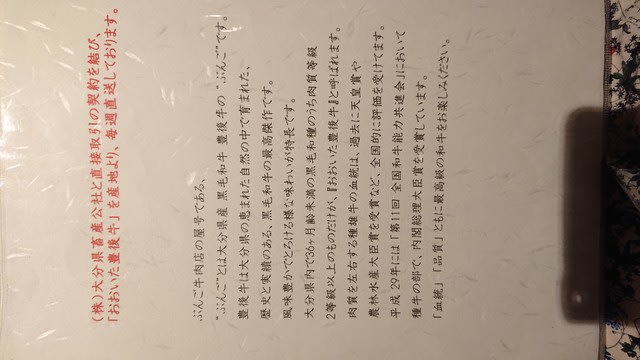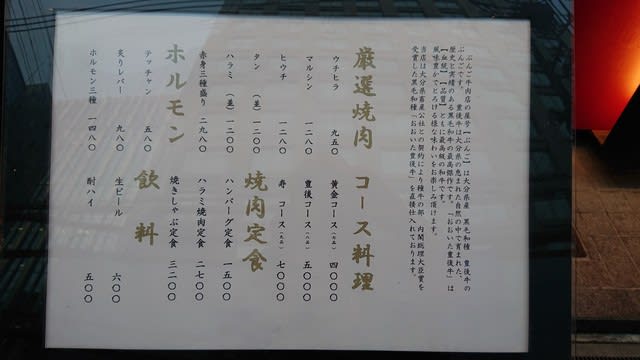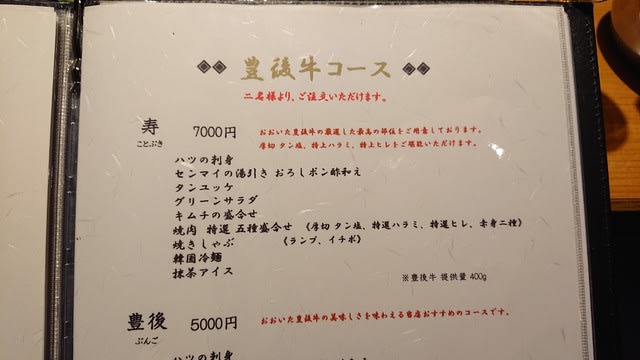「敗者の生命史38億年」という本は、地球の生物の長~い歴史を振り返れば、生き延びて新しい時代を作ってきたのは実は敗者の生物であり、その敗者たちが雌伏の時を耐え抜いて、大逆転劇を演じ続けてきたことについて分かりやすく説明したものです♪
目次を引用すると、以下の内容となっています♪
・競争から共生へ :22億年前(原核生物や真核生物)
・単細胞のチーム・ビルディング:10億~6億年前(多細胞生物)
・動く必要がなければ動かない :22億年前(植物)
・破壊者か創造者か :28億年前(酸素について)
・死の発明 :10億年前(オスとメス)
・逆境の後の飛躍 :7億年前(エディアカラ生物群)
・捲土重来の大爆発 :5億5千年前(カンブリア爆発)
・敗者たちの楽園 :4億年前(両生類等)
・フロンティアへの進出 :5億年前(植物の上陸)
・乾いた大地への挑戦 :5億年前(裸子植物)
・そして、恐竜は滅んだ :1億4千万年前(5度の大量絶滅等)
・恐竜を滅ぼした花 :2億年前(被子植物)
・花と虫との共生関係の出現 :2億年前(虫や鳥等)
・古いタイプの生きる道 :1億年前(針葉樹等)
・哺乳類のニッチ戦略 :1億年前(ニッチ戦略)
・大空というニッチ :2億年前(気のうや鳥等)
・サルのはじまり :2600万年前(サル)
・逆境で進化した草 :600万年前(草)
・ホモ・サピエンスは弱かった :400万年前(ネアンデルタール人等)
本書では特に以下についてはナルホドと思いましたね♪
・生物は共生
・植物は生産者、動物は消費者、菌類は分解者で、地球はそれぞれで循環する生態系
・生物の進化における性の発明は、もう一つ偉大な死の発明を行った
・被子植物は世代更新が早いから進化のスピードが速い
・哺乳類は大型恐竜から逃れるために夜間に活動し聴覚や嗅覚、俊敏性に優れる
・恐竜や鳥類は一方通行の「気のう」で呼吸のため低酸素濃度に適応
以下は本書のポイント等です♪
「敗者の生命史38億年」という本は、地球の生命史について非常に分かりやすく理解でき、とてもオススメです!
・細胞の中に、別のDNAを持つ生物が共生するとなると、自らのDNAをそこら中に散らかしておくわけにはいかない。そこで細胞は細胞核を作り、自らのDNAを格納した。それが真核生物である。もしかすると真核生物の祖先は、もともと核を持っていたことによって、DNAを持つ他の単細胞生物を無理なく取り込めたのかもしれない。いずれにしておm、原核生物から真核生物への進化は、核を持つことにあった。しかし、重要なのは、核を持つことではなく、そうすることによって、別の生き物を細胞内に取り込めたことにあったのだ。ちなみに、エネルギーを生むミトコンドリアは動物細胞にも植物細胞にもあるのに対して、葉緑体は植物細胞にしか存在しない。そのため、ミトコンドリアがより古い時代に取り込まれて先に共生するようになり、その後、動物の祖先となる単細胞生物と、植物の祖先となる単細胞生物とに別れた後に、葉緑体との共生が起こったと考えられている。
・私たちの体の中には腸内細菌がいる。腸内細菌は、私たちの胃腸の中に棲みついていて、病原菌の侵入を防いだり、分解しにくい食物繊維を分解したり、ビタミンなどの代謝物を生産したりと、さまざまな役割を果たしている。進化の頂点にいるかのような人間も、腸内細菌の働きがなければ、生きていくことはできないのだ。一人の人間の腸の中にいる腸内細菌は、100兆とも、1000兆とも呼ばれている。この腸内細菌は、もともとは外部から、やってきたものである。私たちは食べ物などを介して、口から体内に取り入れた大腸菌と共生しているのである。進化の頂点に立っているかのように偉そうにしている人間も、やっていることははるか昔の単細胞生物たちの共生と何ら変わらない。食べたものと共生するというのは、そんなに奇妙なことではないのだ。
・地球上が凍りついてしまうような劇的な全球凍結は、数度にわたって起こったと考えられている。最初のスノーボール・アースがおよそ23億年前のことである。すでに紹介したように、このスノーボール・アースの後、地球には真核生物が登場するのである。次に約7億2千万年前のスターシアン氷河期と約6億3千万年前のマリノアン氷河期の二度のスノーボール・アースに襲われる。そして、この直後の地層から多細胞生物の化石が生み出されていくのである。大きな変化と過酷な環境が生命を著しく進化させた。これだけは事実なのである。生命は、過酷な逆境でこそ進化を遂げるのである。
・葉緑体を手に入れた植物細胞は、太陽の光で光合成を行うことができるから、動く必要がない。光さえあれば良いのだから、動き回って無駄にエネルギーを使う寄りも、光が十分当たるところに腰を据えた方がいい。そして、光を浴びやすいように、細胞を並べて、構造物を作った方が良い。そこで、植物細胞はしっかりとした構造を築くために、細胞壁を作った。また植物は動かないので、病原菌から逃げることができない。細胞壁は、防御力を高めることにも貢献する。そのため動物細胞は細胞壁がないが、植物細胞は細胞壁を持つのである。もっとも、葉緑体を持たずに植物細胞と進化の別れを告げた生物の中にも、細胞壁を持つものが現れた。それが菌類である。菌類は動かない植物をエサにして、光合成で植物が作り出した栄養分を奪い取るという生活を発達させた。そして、動かない植物と共に動かない道を選んだ菌類の細胞をまた、細胞壁を持つようになるのである。こうして、動かない生活を送る生物が発達する一方で、菌類と袂を分かち合った生物は、動き回る積極的な戦略を選択した。つまり、防御するのではなく、まわりのものを積極的に取り入れて消化する。そして、有害なものがあれば、代謝・分解して、排出するのである。このように、まわりと積極的に物質をやり取りするのであれば、細胞壁はない方が良い。これが動物の祖先なのである。動物と菌類とは似ても似つかないような気がするが、自分で栄養を作り出すことができず、他の生物に依存して栄養を獲得している生き方は、まったく共通しているのである。
・動物も植物も菌類も元をたどれば、共通の祖先にたどりつく。真核生物の祖先は、自ら栄養を作り出すことはできず、もっぱら他の生物を食べては栄養を得る、従属栄養の生物であった。そして、ミトコンドリアを細胞内に捕らえて、共生生活を始めたのである。ここまでは、動物も植物も菌類も同じである。このうち、葉緑体と共生を始めたものが植物の祖先となった。そして葉緑体との共生を行わなかったもののうち、細胞壁を選択したものが菌類の祖先となった。そして、細胞壁を持たなかったものが動物の祖先となったのである。
・現代の生態系において、植物は光合成によって栄養分を作り出す「生産者」と呼ばれている。これに対して、植物を餌とする草食動物や、あるいは草食動物を餌にする肉食動物は、植物の作り出した栄養分に依存する「消費者」と呼ばれている。そして、菌類は植物や動物の死骸を分解して栄養を得る「分解者」と呼ばれている。この植物と動物と菌類の働きによって、有機物が循環する生態系が作られているのである。真核生物の登場と時をほぼ同じくして、現在の生態系を支える三者の祖先がすでに揃い踏みしていたというのは、何だか不思議である。
・光合成を行う生物たちは、酸素を放出し、それまでの地球環境を変貌させていく。シアノバクテリアによって産出された酸素は、海中に溶けていた鉄イオンと反応して酸化鉄を作る。そして酸化鉄は海中に沈んでいったのである。その後の地殻変動によって、酸化鉄の堆積によって作られた鉄鉱床は、後に地上に現れる。そして、はるか遠い未来に、地球の歴史に人類が出現すると、人類はこの鉄鉱床から鉄を得る技術を発達させるのである。人類は鉄を使って、農具を作り、農業生産力を高めた。やがて、鉄を使って武器を作り、争うようになった。すべてはシアノバクテリアのせいである。
・さらに大気中に放出された酸素は地球環境を大きく変貌させる結果を招いた。酸素は地球に降り注ぐ紫外線に当たるとオゾンという物質に変化する。シアノバクテリアによって排出された酸素は、やがてオゾンとなり、行き場のないオゾンは上空に吹き溜まりとなって充満した。こうして作られたのがオゾン層である。まさに地球環境を大改変してしまったのだ。ただしこのオゾン層は生命の進化にとって思いがけず重要な役割を果たした。かつて地球には大量の紫外線が降り注いでいた。この紫外線は、お肌の大敵といわれるがDNAを破壊し、生命を脅かすほど有害なものである。殺菌に紫外線ランプが使われるのもそのためだ。実はオゾンには紫外線を吸収する作用がある。そのため上空に作られたオゾン層は地上に降り注いでいた有害な紫外線を遮ってくれるようになったのである。これまで紫外線が降り注ぎ、生命が存在できなかった地上の環境は一変した。やがて海の中にいたシアノバクテリアは、植物の祖先と共生して植物となり、地上へと進出を果たすようになる。自ら吐き出した酸素によって、新たな住み場所を作った。そして、ますます酸素を放出し、植物たちの楽園を作ったのである。
・生物の進化における「性」の発明は、もう一つ偉大な発明を行った。それが「死」である。「死」は38億年に及ぶ生命の歴史の中で、もっとも偉大な発明の一つだろう。一つの命がコピーをして増えていくだけであれば、環境の変化に対応することができない。さらには、コピーミスによる劣化も起こる。そこで、生物はコピーをするのではなく、一度、壊して、新しく作り直すという方法を選ぶのである。しかし、まったく壊してしまえば、元に戻すことは大変である。そこで生命は二つの情報を合わせて新しいものを作るという方法を作り出した。これが「性」である。
・細菌やアメーバのような原始的な原核生物には、「性」はない。ただ細胞分裂をして増殖していく。細胞分裂を繰り返したからと言って、年老いて細胞が疲弊していくことはない。そして細胞は増えても死滅をするわけではないから、原核生物は永遠に死ぬことはないと言えるかもしれない。
・しかし同じ単細胞生物でもゾウリムシのような真核生物は違う。ゾウリムシには明確な「性」があるわけではないが、「性」の基礎となったと考えられるグループ分けがある。そしてグループ間で遺伝子を交換するのである。ゾウリムシは分裂回数が有限である。そして700回ほど分裂をすると、寿命が尽きたように死んでしまう。ただし死ぬまでに他のゾウリムシと接合をして、遺伝子を交換すると、新たなゾウリムシとなって生まれ変わる。すると分裂回数はリセットされて、再び700回の分裂ができるようになるのである。こうして生まれ変わったゾウリムシは、元のゾウリムシと違う個体である。だから、これは新たなゾウリムシを作り上げて、元の個体は死んでしまったと見ることができる。こうして真核生物は「死」と「再生」という仕組みを創り出したのである。
・遺伝子を交換することで新しいものを作り出す。そして新しいものができたのだから、古いものをなくしていく。それが「死」である。「死」もまた、生物の進化が生み出した発明である。「死」というシステムは「性」というシステムの発明によって、導き出されたものなのだ。「形あるものは、いつかは滅びる」と言われるように、この世に永遠にあり続けるものはない。何千年、何万年もの間、コピーをし続けるだけでは、永遠の時を生き抜くことは簡単ではない。そこで、生命は永遠であり続けるために、自らを壊し、新しく作り直すことを考えた。つまり、一つの生命は一定期間で死に、その代わりに新しい生命を宿すのである。新しい命を宿し、子孫を残せば、命のバトンを渡して自らは身を引いていく。この「死」の発明によって、生命は世代を超えて命のリレーをつなぎながら、永遠であり続けることが可能になったのである。永遠であり続けるために、生命は「限りある命」を作り出したのである。
・スノーボール・アースで閉ざされた環境にいた生物たちは、小さな集団の中で遺伝的な変異を蓄積していった。その変異の蓄積が、多細胞生物の急激な進化を推し進め、エディアカラ生物群を生み出した。そしてカンブリア爆発の新たな生物の出現につながっていったのである。やがて大繁栄をしたエディアカラ生物群も、5億4200万年まえから始まるカンブリア紀までに絶滅をしてしまう。
・カンブリア爆発による新たな生物の出現は、生物たちの世界の「捕食」という行動によって引き起こされたと考えられているのである。カンブリア爆発の中では、他の生物をエサにする捕食者が出現した。捕食者から身を守るために、生物はさまざまなアイデアで防御手段を発達させた。ある者は固い殻に身を包み、ある者は鋭いトゲで捕食者を威嚇する。すると、今度は捕食者が、それを打ち破るために強力な武器を手に入れる。そしてその捕食者から身を守るために、弱い生物はさらに防御手段を発達させる。この繰り返しによって、生物は急速に進化を遂げていったのだ。攻める者と、守る者のせめぎ合い。まさに軍拡競争である。軍拡競争による変化と淘汰の繰り返し。この変化のスピードに追いつけない者は滅んでいく。つまり、厳しい競争が進化を生んだのである。
・生物が最初に獲得したのは、小さな目だった。小さな目は視点を動かすことができない。そこで小さな目をたくさん並べることで視野を補った。これが、現代の昆虫などにも見られる「複眼」である。「目」は、生物にとって革新的な武器であった。「目」を持つ捕食者は、獲物を見つけて的確に襲うことができる。一方、防御側にとっても「目」は有効である。目を持っていれば、いち早く敵の襲来を察知して、逃げたり、隠れたり、防御態勢を取ることができる。戦いには敵を補足する情報収集が必要である。まさに「目」は情報収集に有効なレーダーなのだ。目を持たない捕食者は、獲物を取ることができず飢えてしまう。また目を持たない生物は捕食者に次々と食べられてしまう。この目の出現によって、生物の軍拡競争は、激しさを増していくのである。
・海での戦いに敗れ、追いやられた弱い魚たちは、過酷な環境である汽水域へ逃れ行く。しかし、そこは魚が生存することができない過酷な環境である。汽水域で最初に問題となるのは浸透圧である。塩分濃度の濃い海で進化を遂げた生物の細胞は、海の中の塩分濃度と同程度の浸透圧になっている。もし、細胞の外側が海水よりも濃い塩分濃度であれば、細胞の中の水は細胞の外へと溶け出してしまう。そしてもし細胞の外側が薄い塩分濃度であれば、その塩分濃度を薄めるために、水が細胞の中へと侵入してきてしまうのである。そこで魚たちは塩分濃度の薄い水が体内に入ってくることを防ぐために、うろこで身を守るようになった。さらには、外から入ってきた淡水を体外に排出し、体内の塩分濃度を一定にするために腎臓を発達させたのである。それだけではない。海の中には生命活動を維持するためのカルシウムなどのミネラル分が豊富にあるが、汽水域ではミネラル分が不足してしまう。そこで魚たちは体内にミネラルを蓄積するための貯蔵施設を設けた。それが「骨」である。骨は体を維持するだけでなく、ミネラル分を蓄積するための器官でもあるのである。こうして生まれたのが、骨の充実した「硬骨魚」である。
・迫害された弱い魚の中でも、さらに弱い魚は、より塩分濃度の薄い川の河口へと侵入を始める。もちろん、そこでも弱肉強食の世界は築かれる。弱い魚の中でも、さらに弱い弱者中の弱者は、逃れても逃れても現れる天敵に追われながら、川の上流へと新天地を求めていくのである。中には、同じ食われるのであれば、海も同じだとばかりに、再び海へと戻っていくものもあらわれた。サケやマスなどが、川を遡って産卵をするのは、彼らが淡水を起源とするからと考えられている。浅瀬で泳ぎ回る敏捷性を発達させていた魚たちは、海に戻ってからも、サメなどから身を守る泳力を身につけていた。そのため、海をすみかとすることができたのである。こうして汽水域に追いやられて進化を遂げた硬骨魚の中から、川や湖をすみかとする淡水魚と、海で暮らす海水魚とが分かれていくのである。
・陸上という新天地を求めた魚はどんな魚だっただろう。その祖先は海での生存競争に敗れ、汽水域へと進出した魚たちであった。そこで硬骨魚類へと進化を遂げた魚たちの中で、より弱いものは川へと侵入した。そして、その中でもさらに弱い魚たちは上流へと追いやられた。まさに最弱を決定するトーナメント戦のようなものである。その戦いに負け続けた魚が、川の上流をすみかとした。川をすみかとした魚たちの中で、小さな魚は俊敏な泳力を身につけた。一方、早く泳ぐことのできない、のろまな大型の魚類は水のない浅瀬へと追いやられていくのである。ところがである。このもっとも追いやられた魚が、ついに上陸を果たし、両生類へと進化を遂げる。そして爬虫類や恐竜、鳥類、哺乳類の祖先となるのだから、自然界というのは面白い。生命の歴史を振り返ってみれば、進化を作り出してきた者は、追いやられ、迫害された弱者たちであった。新しい時代は常に敗者によって作られるのである。
・海中にあった植物たちが放出する酸素によって、次第に上空にオゾン層が形成される。するとオゾン層が紫外線を吸収し、紫外線が陸上に降り注ぐのを防いでくれるようになったのである。準備は整った。満を持して植物は上陸を果たす。植物の上陸は、古生代シルル紀の4億7千万年前のことであるとされている。両生類の祖先となる魚類が上陸を果たすのがデボン紀の3億6千万年前だから、植物の方が1億年以上も早いのだ。
・最初に上陸をした植物はコケ植物に似た植物であったと考えられている。コケは体の表面から水分や養分を吸収する。これは水の中にいる緑藻類と同じである。そのため、コケは体のまわりが乾かないような水辺にしか生えることができない。その後、陸上生活に適するように、さらに進化をしたのが、シダ植物である。シダ植物は茎を発達させた。水の中では、体を支えるための仕組みは必要ない。しかし、陸上では体を支えるための頑丈な茎が必要となるのである。さらにシダ植物は、乾燥に耐えるために、体内の水分を守るための固い表皮を発達させた。もっ友表皮を発達させると、水分が体外に出ていくことを防ぐことができる代わりに、外から水分が入ってこない。そこで水分を吸収するための根を発達させ、仮導管という通水組織を発達させて、根で吸収した水分を体中に行き渡らせるための維管束を発達させたのである。維管束を発達させて効率よく体中に水を運ぶことにより、シダ植物は枝を茂らせることができるようになった。枝を増やせば、多くの葉をつけて、光合成をすることができる。こうしてシダ植物は巨大で、複雑な体を持つことができるようになったのである。
・シダ植物が根を発達させることができたのには理由がある。最初の植物が陸地に進出したとき、陸地には土はまったくなかった。ただ、砂と石の大地が広がっているのである。地球上に存在する土は有機物から作られている。つまり、生物の死骸などが分解して土になっていくのである。しかし、地上に進出した植物が生命活動を繰り返し、世代交代を繰り返す中で、枯死した植物が分解して、蓄積されていった。こうした有機物が風化した岩石と混ざって、植物が育つことができるような栄養分を含む土ができたのである。シダ植物は、その土を手掛かりにして、生息地を広げていった。そのためシダ植物は根を持っているのである。こうしてシダ植物の森が作られると、やがて昆虫が地上へと進出した。そしてついに魚類がドラマチックな上陸を果たすのである。
・地上に上陸を果たした脊椎動物が、両生類として繁栄している頃、森を形成していたのはシダ植物であった。シダ植物が水辺から分布を広げていくと、それまで水辺で暮らしていた両生類は恐竜の祖先となるような爬虫類に進化を遂げた。シダ植物が進化をしながら、分布を広げ、植物の量と種類が増えていくと、植物をエサにするさまざまな爬虫類もまた種類を増やしていった。そして草食の爬虫類をエサにして、肉食の爬虫類も発達を遂げた。こうしてシダ植物の繁栄によって陸上には、豊かな生態系が築かれていったのである。しかしシダ植物が陸上への進出を果たしたとはいっても、まだまだ水際から遠くへと離れることはできなかった。それは受精をして子孫を残すために水を必要としたからである。シダ植物は胞子で移動をする。そして、胞子が発芽して前葉体が形成されるのである。前葉体の上では、精子と卵子が作られ、精子が水の中を泳いで卵子に到達し、受精する。精子が泳いで卵子にたどり着く方法は、生命が海で誕生した名残である。進化を遂げた陸上植物にしてはずいぶんと古くさい方法と思うかもしれないが、人間も同じように精子が泳いで卵子と受精する。まったく同じなのだ。地上に進出を果たしたシダ植物も、精子が泳ぐ水が必要なために、水分のあるジメジメとした場所でないと増えることができなかった。その結果、大繁栄したシダ植物も勢力範囲は水辺に限られ、広大な未開の大地への進出は果たせなかったのである。
・その後、恐竜の時代に繁栄をしていたのはシダ植物から進化を遂げた裸子植物である。裸子植物が出現したのは、およそ5億年前の古生代ペルム紀のことである。裸子植物は内陸へと分布を広げ、地上に恐竜の楽園を作る基になったのである。
・裸子植物は、植物の進化の歴史の中で、ある偉大な発明を行った。それが「種子」である。種子を作る植物は「種子植物」と呼ばれる。裸子植物は「種子植物」の先駆けなのである。種子は固い皮で守られているため、シダ植物の胞子よりも乾燥に耐えることができる。さらに、この固い皮に守られて、植物の芽は、いつまでも発芽のタイミングを待ち続けることができるのである。植物が生存するには水が必要である。しかし種子は水がなくても、水のある場所まで移動することもできるし、水が得られるようになるまで、じっと待ち続けることが可能なのである。つまり、植物の種子は空間を移動し、時間を超えることができるのだ
・裸子植物の工夫は種子だけではない。もう一つの工夫が「花粉」である。シダ植物は胞子で増える。胞子は種子の代わりのような感じがするかもしれないが、胞子は種子植物の花粉に相当する。花粉は精子を作らない。ただ精細胞を作る。精細胞は精子と同じようなものだが、べん毛を持って泳ぐようなことをしないので、精細胞という別の名で呼ばれている。花粉が種子の元になる胚珠に着くと、花粉管という管を雌しべの中に伸ばしていく。そして、花粉管の中を精細胞が移動して、胚珠の中にある卵と受精するのである。この方法であれば、水はいあらない。そして種子植物は水のない乾燥地帯へと分布を広げていくのである。
・裸子植物の強みは単に乾燥に強いというだけではない。移動能力が高いということも、特徴の一つだ。シダ植物の場合は精子と卵子が受精してできた受精卵は、その場で大きくなり、シダ植物を形作る。ところが種子植物は、受精卵が種子となる。そしてさらに移動することができるのである。シダ植物は胞子で移動をするだけだが、種子植物は花粉と種子という二度の移動のチャンスを手に入れたのである。これは動けない植物にとっては、大きな飛躍だ。
・種子植物は胞子を進化させて花粉を作り出した。シダの胞子には雌雄の区別はないが、花粉は雄の配偶体である。そして花粉が遠くへ移動することによって、よりさまざまな個体と交配をすることができるようになったのである。そして多様な個体と交配することで、多様性のある子孫を残し、進化のスピードを早めることができる。こうして生まれた裸子植物は、シダ植物に比べて多様な進化を遂げて行ったのである。エサとなる植物が多様になると、それを食べる動物もまた進化を遂げる。こうした裸子植物の進化の結果、多様な恐竜が生み出された。
・スピーディな進化を可能にした裸子植物は、草食恐竜に食べられないように大型化を進めていく。そして、裸子植物が巨大化を進めていくと、それを食べるために、恐竜もまた大型化していった。こうして裸子植物と恐竜が巨大化競争を推し進め、巨大な裸子植物の森と巨大な恐竜を主役とした生態系が生まれたのである。
・最初の地球での大量絶滅は、古生代オルドビス紀末(約4億4千万年前)である。オルドビス紀は、オウムガイや三葉虫が活躍した時代である。また甲冑魚のような魚類が海を泳ぎまわっていた。そして地上には最初の原始的な植物が上陸を果たした時期である。古生代オルドビス紀の大量絶滅では地球上の種の84%が絶滅したとされている。恐竜の絶滅した白亜紀の大量絶滅が76%の種が絶滅したとされているから、その時期の大量絶滅よりも大規模だったのである。二度目は古生代デボン紀後期(約3億6千万年前)すぇう。この時期には陸上には既にシダ植物の森が形成され、昆虫が出現していた。そして両生類が上陸を果たしていた頃である。この大量絶滅では種の70%が絶滅したとされている。三度目が古生代ペルム紀末(2億5千万年前)である。この時期には既に巨大な両生類や爬虫類が絶滅した。古生代ペルム紀末の大量絶滅は驚くことに96%もの種が死滅した。地球史上最大の大量絶滅だったと言われている。古生代の海に出現した三葉虫は、オルドビス紀末の大量絶滅で壊滅的な打撃を受けたがわずかな種が生き残った。やがてデボン紀後期の大量絶滅でも大打撃を受けたが、いくつかの種が生存を果たした。しかしそんな三葉虫も三度目の大量絶滅であるペルム紀末を乗り越えることはできずについに絶滅したと考えられている。4度目の大量絶滅が中生代三畳紀(2億5千万年前から2億1千万年前)である。この時期には巨大な超大陸パンゲアが分裂し、地中から大量に吐き出された二酸化炭素とメタンによって気温の上昇と酸素濃度の著しい低下を引き起こした。これにより、それまで活躍していた種の79%が絶滅をしたとされている。そして低酸素環境に対する適応能力を身につけた爬虫類が繁栄をし、恐竜へと進化を遂げていくのである。そして5度目の大量絶滅が、恐竜を襲った白亜紀(1億4千万年~6500万年前)である。白亜紀末には70%もの種が滅んだと言われている。
・恐竜絶滅の引き金となったのは、はるか宇宙からやってきた隕石が地球に衝突したことにあると言われている。6550万年前のことである。現在のメキシコのユカタン半島沖に隕石が衝突した。その衝撃はすさまじく、広い地域が火球に包まれたとされている。高熱で巻き上げられた岩石は、落下して地球のあちらこちらで大規模な森林火災を起こした。そして、灼熱の炎は多くの生物を焼き尽くしたのである。この灼熱地獄を生き抜いても安心はできない。巨大な隕石が落ちてできた巨大な穴に海水が流れ込む。やがて猛烈な勢いで流れ込んだ海水は、穴がいっぱいになると今度はあふれ出して逆流した。そのあふれ出た海水が大地に向かってくる。大津波である。巨大津波は高さ100mを超えて内陸部への襲いかかり、地形によっては高さ200~300mに達することもあったと言われている。この津波は数日間にわたり、何度も襲ってきたと考えられている。未曾有の大災害によって多くの恐竜が滅んでしまったことだろう。しかし、それだけではない。隕石の衝突によって巻き上げられた粉じんが地球全体を覆ってしまったのである。太陽光は遮断され、地球の気候は寒冷化していった。太陽の光が当たらない大地では植物が枯れ果て、わずかに残った恐竜たちも飢えて死んでいったことだろう。こうしてついに楊柳は地球から絶滅してしまったのである。
・生き抜いた生物たちには共通点がある。それは恐竜たちに虐げられ、限られた生息場所を棲みかとしていた敗者たちであったということである。恐竜の時代、広大な大地と大海の多くは、さまざまな恐竜に支配されていた。そして、大型の恐竜が棲みかとしない「水辺」という生息地で暮らしていた生き物がいた。爬虫類である。限られた生息地である川を棲みかとする恐竜は少なかった。そのため爬虫類たちはそこを棲みかとし、巨大なワニのような大型の爬虫類も発達をしたのである。どうして爬虫類は生き残ることができたのだろうか。爬虫類のすむ水辺は生命に必要な水がある。また高熱を避けることができ、保温効果のある水は「衝突の冬」と呼ばれる厳しい環境を乗り越えることにも役立ったかもしれない。また、恐竜は体温を保つことができる恒温動物であるのに対して、爬虫類は体温を維持することが出来ない変温動物という古いタイプであったことも幸いしたのかもしれない。体温を保つためには大量のエサを必要とする。しかし、ヘビやカメなどの爬虫類が冬眠をするように、変温動物である爬虫類は気温が低くなると代謝活動が低下するのである。
・鳥もまた、この大災害を乗り越えた。鳥は恐竜から進化したとされている。しかし大型の恐竜が大地を支配する中で、鳥となった恐竜は、他の恐竜の支配が及ばない空を自分たちの生息場所としていた。そして、地上では弱者であった鳥たちは、穴の中や木の洞の中に巣を作っていた。こうした隠れ家を持っていたことから、災害を逃れることができたのではないかと考えられているのである。あるいは翼を持つ鳥は遠くに移動することができることも功を奏した要因かもしれない。
・哺乳類たちは、恐竜たちの目を逃れて新たな生活場所を見つけた。それが「夜」である。昼間は活動している恐竜が多いから、安心して活動することができない。そこで、恐竜たちの眠っている夜の間に、ひっそりと活動をするようになったのである。とはいえ、あらゆる種類に進化をした恐竜でさえも活動しない「夜」に行動することは簡単ではない。哺乳類たちは、暗い闇の中でもエサを探すことのできる嗅覚と、聴覚を発達させた。そして感覚器官を司る脳を発達させていくのである。この逆境の中で身につけた感覚器官と脳が、後にほ乳水の繁栄の武器となるのである。恐竜が繁栄した1億2千万年もの間、哺乳類たちは恐竜の目から逃れてひっそりと暮らしていた。虐げられた敗者だったのである。しかし、ひっそりと隠れていたことが幸いして、哺乳類たちは未曾有の大災害を生き残り、小さな体が、その後のエサが少なく寒冷な環境を生き抜くことに役立ったのである。
・裸子植物として進化を遂げてきたマツでさえも、花粉が到達してから受精するまでに、およそ1年を要するのである。一方の被子植物はどうだろう。被子植物は、安全な植物の子房の内部で受精することができる。そのため、被子植物は花粉がやってくる前から、胚を成熟させた状態で準備しておくことができるのである。そして花粉がやってくるとすぐに受粉を行うのである。花粉が雌しべについてから受精が完了するまでの時間は数日。早いものでは数時間で完了してしまう。それまでは1年かかっていたものが、あっという間に受精が完了するのである。何という劇的なスピードアップだろう。受精までの期間の短縮は、植物にいったい何をもたらすだろうか。それまで、種子を作るのに、長い年月を要していたものが、わずか数時間から数日中にできるようになれば、次々に種子を作り、世代を早く更新することができる。世代更新が進むということは、それだけ進化を進められるということだ。こうして植物の進化のスピードが高まっていったのである。
・進化のスピードが速まる中で、被子植物が手に入れたものが「美しい花」である。植物が美しい花を咲かせるのは、昆虫を呼び寄せて受粉させるためである。裸子植物は、風に乗せて花粉を運ぶ風媒花である。そのため、裸子植物の花は美しく装飾する必要がない。むしろ、風まかせで花粉を運ぶ方法は、雄花から雌花に花粉が届く確率は低いから、花びらを飾るようなことにエネルギーを使うよりも、少しでも多くの花粉を作った方が良い。裸子植物は花粉を大量に生産するのはそのためなのだ。現代でもスギやヒノキなどの裸子植物が、大量の花粉をまき散らして、花粉症の原因として問題になるのは、裸子植物が風媒花だからなのである。
・昆虫は花粉を食べる害虫ではあるが、花から花へと移動するから、昆虫の体に花粉を付着させれば、効率よく花粉を運ぶことができる。少しぐらい昆虫に花粉を食べられたとしても、どこへ飛んでいくか分からない風まかせの送粉方法に比べれば、ずっと確実である。こうして、昆虫に運ばせることによって、植物は生産する花粉の量を減らすことに成功した。そして節約したエネルギーを使って、昆虫を呼び集めるために花を目立たせる花びらを発達させたのである。
・水中に上陸を果たしたのは、草とは呼べないようなコケのような小さな植物だった。そして、その植物からシダ植物が進化したとき、シダ植物は頑強な茎と仮導管という通水組織を利用して巨大な木を作り上げた。こうして地上には、シダ植物の森ができたのである。その後、シダ植物から、裸子植物、被子植物への植物は進化を遂げたが、植物は常に大きな木となり、巨木の森を作っていたのである。草というスタイルが出現したのは、白亜紀の終わり頃であるといわれている。
・世代更新を早めることによって、環境の変化にいち早く適応して、劇的に進化を遂げる被子植物。やがてこの被子植物が恐竜たちを追い詰めた。進化のスピードを高めた被子植物に、恐竜の進化が追いついていくことができなかったのではないかと考えられているのである。もちろん、恐竜もまったく進化をしなかったわけではない。たとえば、子どもたちに人気のトリケラトプスは、花が咲く被子植物を食べるように進化をしたとされる恐竜の一つである。それまでの草食恐竜たちは、裸子植物と競って巨大化し、高い木の葉が食べられるように、首を長くしていった。しかしトリケラトプスは違う。トリケラトプスは足が短く、背も低い。しかも頭は下向きについている。その姿はまるで草食動物のウシやサイのようだ。これは地面から生える小さな草を食べるのに適したスタイルである。
・しかし被子植物の進化の速度は、恐竜の進化を確実に上回っていたことだろう。トリケラトプスでさえも、植物の進化についていくことは難しかったはずである。被子植物は短いサイクルでさまざまな工夫を試みて、変化を遂げていく。植物を食べる草食恐竜に食べられないように身を守るための工夫もあっただろう。たとえば植物は、アルカロイドなどの毒性のある化学物質を次々に身につけた。そして恐竜は、植物が作り出すそれらの物質に対応することが出来ずに、消化不良を起こしたり中毒死したのではないかと推察されている。実際に白亜紀末期の恐竜の化石を見ると、器官が異常に肥大したり、卵の殻が薄くなるなど、中毒を思わせるような深刻な生理障害が見られるという。そういえば恐竜が現代に蘇るSF映画「ジュラシックパーク」でもトリケラトプスが有毒植物による中毒で横たわっているシーンがあった。
・カナダ・アルバータ州のドラムヘラーからは、恐竜時代末期の化石が多く見つかっている。この地域の7500万年前の地層からは、トリケラトプスなど角竜が8種類も見つかっているのに対してその1千万年後には角竜の仲間はわずか1種類に減少してしまっている。一方、この間に哺乳類の化石は、10種類から20種類に増加している。
・世代更新を早め、進化のスピードアップに成功した被子植物が発明したものは、昆虫と共生する「花」だけではない。「果実」もまた、劇的な進化の中で、植物を発達させた「共生するためのもの」である。被子植物は大切な胚珠を守るために胚珠のまわりを子房でくるんだのである。子房で守ることによって、胚珠はさらに乾燥条件にも耐えられるようになった。また、子房には大切な種子を害虫や動物の食害から守るための役割もあったことだろう。ところが、やがて子房を食べた哺乳類が、一緒に食べた種子を糞として体外に排出することで、結果的に種子が移動することが可能となった。そして、植物は果実を作ることで種子を散布させるという方法を発達させるのである。動物や鳥が植物の果実を食べると、果実と一緒に種子も食べられる。そして、動物や鳥の消化管を種子が通り抜けて糞と一緒に種が排出される頃には、動物や鳥も移動し、種子が見事に移動することが出来るのである。
・花が進化することによって、蜜をエサにして花粉を運ぶ鳥が現れた。そして、花の形に合わせてさまざまな鳥が進化していったのである。また、さまざまな植物をエサにするために、さまざまな昆虫が発達する。さらに、植物はさまざまな果実をつける。こうして、エサが多様化することによって、鳥もまた多様な進化を遂げて行ったのである。現在では、植物の果実をエサにして種子を運ぶ役割は、哺乳類よりも、むしろ鳥類が担っている。哺乳類は歯が発達しているので、果実だけでなく種子をかみ砕いてしまう恐れがある。それに対して鳥は、歯がないので、種子を丸呑みする。また、消化管が短いので、種子は消化されずに無事に体内を通り抜けることができる。さらに、鳥は大空を飛び回るので哺乳動物に比べると移動する距離が大きい。そのため、植物にとっては、鳥こそが種子を運んでもらう最良のパートナーなのである。植物は、効率よく種子を運んでもらうために、あるサインを作り出した。それが果実の色である。果実は熟すと赤く色づいてくる。これは赤く色づいて果実を目立たせているのである。一方、種子が成熟する前に食べられてしまうと困るので、未熟な果実は葉っぱと同じ緑色をして、目立たなくしている。また、苦みを持って食べられないように守っているのである。赤色は「食べてほしい」、緑色は「食べないでほしい」、これが植物と鳥との間で交わされたサインなのである。
・落葉樹が誕生したのは、白亜紀の終わり頃であると考えられている。恐竜を絶滅させた隕石が地球に衝突した後、地球の気候は寒冷化していった。こうした中で、寒さに耐えるための「落葉」という仕組みが作られたのである。「落葉」は極めて優れた仕組みである。植物にとって葉は、光合成をするために不可欠な器官である。しかし同時に、葉からは蒸散によって水分が失われるという欠点がある。隕石の衝突によって巻き上げられた粉塵は、太陽の光を遮る。すると光合成の能力は低下してしまうのである。気温が冷え込めば、根の動きも鈍り、水の量も不足する。光合成能力は低下していくのに、貴重な水分は浪費する。こうなると、植物の葉はお荷物になってしまう。このような状態では、ぐんぐん伸びるよりも、ずっと堪え忍ぶことが大切になる。そこで植物は、光合成はできなくなっても、水分を節約することを選択する。そして、自ら葉を落とすのである。いわばリストラのようなものだ。落葉樹は、こうして厳しい低温条件を乗り越える術を身につけた。
・被子植物の木の中に、葉を落とす落葉樹と常緑の照葉樹があるのに対して、遅れたタイプである裸子植物は、針葉樹と言われている。裸子植物もまた低温に耐えるために進化を遂げた。それが、葉をコーティングするとともに、光合成能力を犠牲にしても葉を細くすることだったのである。これらの木は、葉が針のように細くなっているため、「針葉樹」と呼ばれている。寒さに適応して進化をした落葉樹に比べると、裸子植物である針葉樹はずいぶんと古いタイプの植物である。ところがである。シベリアやカナダの北方地帯に分布するタイガや、北海道のトドマツ林やエゾマツ林のように、遅れた植物である針葉樹が、もっとも寒さの厳しい極地に広大な森を作っているのである。
・裸子植物の仮導管は、細胞と細胞の間に小さな穴があいていて、この穴を通して細胞から細胞へと順番に水を伝えていく仮導管という方法で水を運んでいる。これは水を一気に通す被子植物の導管に比べると、効率がすこぶる悪い。いかにも古くさいシステムである。しかし、バケツリレーのように細胞から細胞へと確実に水を伝えるので、導管のように凍結によって水を吸い上げることができなくなることは起きにくい。そのため、裸子植物は、凍てつくような場所でも水を吸い上げて生き残ることができるのである。こうして、裸子植物は凍結に強いという優位性を生かして極寒の地に広がって生き延びたのだ。
・地球に被子植物が出現し、分布を広げていく中で、末期の恐竜たちは追いやられた裸子植物とともに見つかるという。被子植物をエサにできなかった恐竜たちは、裸子植物とともに棲みかを奪われていったのである。そして、生育に適した温暖な地域に被子植物が広がると、裸子植物は寒冷な土地へと分布を移動させていった。現在、北の大地に見られる裸子植物の針葉樹林は、被子植物の迫害を受けた裸子植物の末裔たちである。
・哺乳類は大型恐竜から逃げるかのように、恐竜の活動が少ない夜間に活動する夜行性の生物として進化を遂げていくのである。しかし弱い存在であった哺乳類は、弱い存在だったがゆえに身につけたものがある。それが敵から身を隠し、暗闇の中でエサを探すための優れた聴覚や嗅覚である。そして狭い場所で活動する俊敏性も身につけた。そして哺乳類が身につけたもう一つの武器が「胎生」である。卵を産んで、どんなに卵を守ろうとしても、弱い存在である哺乳類に卵を守るだけの力はない。泣く泣く卵を諦めて命からがら逃げたこともあったろう。必死に守ろうとした卵を奪われて食べられてしまうこともあったろう。そこで哺乳類は卵を産むのではなく、お腹の中で子どもを育ててから産み落とすという胎生を身につけたのである。
・地球の歴史上、最初に空を飛んだ生物は昆虫である。およそ3億年前のことである。両生類がやっと陸上に進出しようかという頃、すでに昆虫たちは、今とあまり変わらない姿で空を飛んでいたのである。大空を支配していたのは、メガネウラという70cmを超える巨大なトンボのような姿をした昆虫である。現在では、昆虫といえば、どれも小型でメガネウラのような巨大なものを見ることができない。古生代に巨大な昆虫が活躍できた背景には、酸素濃度があると言われている。当時は陸上に進出したシダ植物が盛んに光合成を行い、盛んに酸素を放出していた。そのため、現在の酸素濃度が21%であるのに対して、当時は35%と高かったのである。昆虫などの節足動物の呼吸は、気門から取り入れた酸素をそのまま体内に拡散させるという単純な仕組みである。そのため、酸素濃度が高くないと、体の隅々にまで酸素を行き渡らせることができないのである。しかし、やがて酸素濃度が低下する。この原因はわからない。火山の噴火による植物の減少や、火災による植物の焼失が挙げられている。また気候変動により雨が多く降るようになると、植物を分解する菌類が発達をしたことも要因の一つとして考えられている。
・メガネウラなどの巨大昆虫が活躍をしたのは古生代の石炭紀と呼ばれる時代である。石炭紀は、植物が枯れてもそれを分解する菌類があまり活発ではなかった。そのため、植物は旺盛に生育して枯れても、分解されることなく、そのまま捨て置かれたのである。こうして樹木が化石化したものが「石炭」である。石炭紀は、この石炭が作られた時代であることからそう呼ばれているのだ。しかし、菌類が活発に働くようになると、植物を分解するときに酸素を消費する。そのため、酸素濃度が低下していったと考えられるのである。
・酸素濃度が低下すると、昆虫たちは呼吸ができるサイズに小型化していった。体が小さければ、酸素濃度が低くでも、体内に十分に酸素を行き渡らせることができるのである。小型化したとは言っても、空を飛ぶ生物は昆虫だけであった。この石炭紀に繁栄をしていたのは、私たち哺乳類の祖先にあたる哺乳類型爬虫類と呼ばれるものであった。しかし哺乳類型爬虫類もまた、低酸素の中で衰退し、わずかに小型のものだけが生き残るようになる。その一方で、訪れた低酸素時代に適応し、繁栄した生き物がいる。それが恐竜である。低い酸素濃度の条件下で恐竜は「気のう」という器官を発達させた。気のうは、肺の前後についていて、空気を送るポンプのような役割をしている。私たち人間は呼吸をするときに、息を吸って肺の中に空気を入れる。そして、肺で酸素を取り込み、息を吐いて二酸化炭素を出すのである。つまり、空気は肺まで行って帰ってくるのである。電車の単線のように、吸う息と吐く息は順番交代に肺を行ったり来たりするのである。これに対して、気のうは違う。空気は肺に入る前に気のうに入り、気のうから胚へと送り出される。そして、肺から別の気のうを通って排出されるのである。つまり、一方通行である。そのため息を吸うときにも肺の中に気のうから新鮮な空気が送り込まれて、息を吐くときにも、気のうから空気が送り込まれることになる。極めて効率の良い呼吸システムなのだ。この気のうを発達させることによって恐竜は、低酸素という環境に適応して、繁栄を遂げたのである。
・今や大空は鳥たちのものだ。中には、1万メートルを超える高さを飛ぶものもいるという。これは、もうジェット機と変わらない高度である。鳥がこんなにも高い空までを飛ぶことが出来るのには理由がある。それが、鳥が持つ気のうである。気のうのおかげで、鳥たちは空気が薄い上空を飛ぶことができるのだ。この気のうこそが、低酸素時代に恐竜が手に入れたものである。鳥たちは、恐竜が手に入れた気のうを上手に応用して、空を手に入れた。そして、地球のあらゆるところへと分布を広げていったのである。
・空への進出を企てた哺乳類がいる。コウモリである。コウモリの進化も謎に満ちている。空へと進出したコウモリだが、制空権争いは、鳥たちの方が勝っている。そこで、コウモリは鳥のいない空を選択した。それが夜の空だったのである。鳥たちが寝静まる頃になると、コウモリたちは飛び始める。コウモリは今や980種が知られている。驚くことにこの数は地球上の全哺乳類の4分の1を占める数である。日本でも、日本に生息する哺乳類のうち、3分の1の35種がコウモリである。私たちの目につきにくいコウモリではあるが、実はもっとも繁栄している哺乳類なのである。それにしても空を飛ぶ生物の進化は謎が多い。
・恐竜が闊歩していた時代、哺乳動物の祖先は恐竜の目を逃れて夜行性の生活を送っていた。夜の闇の中で、もっとも見えにくい色は赤色である。そのため、夜行性の哺乳動物は赤色を識別する能力を失ってしまったのである。ところが、哺乳動物の中で、唯一、赤色を見ることができる動物がいる。それがサルの仲間である。サルの仲間の一部は、赤色を見ることができる。私たち人類の祖先は、哺乳類が一旦は失ってしまった赤色を識別する能力を取り戻したのだ。果実をエサにするために、熟した果実の色を認識することができるようになったのか、あるいは、赤色が見ることができるようになったから、果実をエサにするようになったのかは明確ではないが、こうして私たちの祖先は、鳥と同じように熟した赤い果実を認識して、果実をエサにするようになったのである。
・イネ科植物は、食べにくくて、固い葉を発達させた。イネ科植物は、葉が固い。イネ科植物は、葉を食べにくくするために、ケイ素で葉を固くしているのである。ケイ素はガラスの原料にもなるような固い物質だ。また、野原でススキの葉で指を切ってしまった経験をもつ方もおられることだろう。ススキの葉のまわりは、のこぎりの刃のようにガラス質が並んでいる。これはなんとも食べにくい。食べにくくするのであれば、トゲで身を守っても良さそうだが、トゲを作ることは、余分に葉を作ることと同じだから、コストが掛かる。一方、ケイ素は土の中に豊富にあるので、いくらでも利用することができるのだ。それだけではない。さらに、イネ科植物は葉の繊維質が多く消化しにくくなっている。こうしてイネ科植物は、葉を食べられないようにして身を守っているのである。イネ科の植物がガラス質を体内に蓄えるようになったのは、600万年ほど前のことであると考えられている。これは、動物にとっては劇的な大事件であった。驚くことにイネ科植物の出現によってエサを食べることのできなくなった草食動物の多くが絶滅したと考えられているのだ。
・イネ科植物の防御策に対応して、進化を遂げたのが、ウシやウマなどの草食動物である。たとえば、ウシは胃が4つあることが知られている。この4つの胃で繊維質が多く、固くて栄養価の少ない葉を消化していくのである。
・ウシだけでなく、ヤギやヒツジ、シカ、キリンなども反芻によって植物を消化する反芻動物である。ウマは、胃を一つしか持たないが、発達した盲腸の中で、微生物が植物の繊維分を分解するようになっている。こうして、自ら栄養分を作り出しているのである。また、ウサギもウマと同じように、盲腸を発達させている。このようにして、草食動物は、さまざまな工夫をしながら、固くて栄養価のないイネ科植物を消化吸収し、栄養を得ているのである。